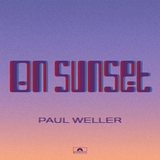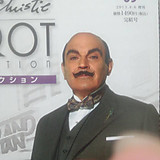幸せなひとりぼっちのレビュー・感想・評価
全134件中、101~120件目を表示
存在の意味に気付くこと、気付かせてあげること
心温まるで賞
長屋の口うるさい頑固爺。
オーヴェの頑固爺っぷりは、江戸の長屋の小言ばっかり言ってる大家みたいだ。めんどくさいし、いちいち癪に障る。
だけど、言ってることは真っ当なことばかり。
理不尽でないことには、子供は敏感なものだ。だから懐く。猫まで懐く。
キツメの性格ながらも、それが表現の下手な思いやりだと気付くと、向かいの妊婦(名前はなんだったか?)も頼りだす。贔屓もしないかわりに偏見も持たない公平な考え方をするのだと知ればなおさらだ。
したいこと(言わないでおくけど)にも毎度毎度邪魔が入り、ドタバタを繰り返すうちに、周りが幸せになっていくストーリーはこちらまでほっこりさせられた。
要所要所で過去を振り返るシーンを差し込むのもタイミングが抜群だ。なによりも、死んだ妻ソーニャがかわいい。容姿はもとより、性格までも。ああ、この人が惚れたのだから、この頑固爺だっていい人なのだと、お墨付きがあるような気分で観ていられた。
ラストがまたいい。無理なく、背伸びなく、一人の老人の最期として穏やかな死に様に、拍手。
この映画や「シンプル・シモン」のように、スウェーデン映画には良作があるようだ。
アウディはダメなのか
凄くよかった!
妙好人
こんな頑固爺さんになりたいもんだ
日本版タイトルは、内容とちょっと違う感じがするけれど、原題は「EN MAN SOM HETER OVE」(オーヴェという名の男)。
本国で大ヒットした映画だということですが・・・
半年ほど前に愛する妻ソーニャ(イーダ・エングヴォル)に先立たれたオーヴェ(ロルフ・ラッスゴード)。
郊外の集合住宅に住み、近くの鉄道の操車場に長年勤めている。
が、その仕事場もリストラされてしまう。
妻を亡くしてからのオーヴェは、頑固というよりも偏屈なジジイになってしまった。
もう、生き甲斐もなくなってしまい、首吊り自殺を図ろうとした矢先に、隣に越してきたペルシャ人一家(夫はスウェーデン人で再婚、妻は妊娠中)に邪魔されてしまう・・・
というところから始まる映画は、自殺直前に走馬燈のように頭をよぎるオーヴェの過去と、自殺に失敗した後のオーヴェの様子が交互に描かれていく。
何度も自殺を図ろうとするが、その都度、横槍が入って失敗するあたりは、まさしくコメディだし、オーヴェに心を開く隣人たちが徐々に増え、オーヴェの心が開かれていくのも、笑いながら心温まる。
しかし、この映画、そんなに笑ってばかりいられない。
走馬燈のように少しずつ描かれるオーヴェとソーニャの物語が美しく切ない。
貧しいながら前向きな鉄道掃除夫のオーヴェと、インテリで文学を勉強して教師になろうとするソーニャ。
そんなふたりの姿も美しいが、切なくなるのは、後半。
オーヴェがどれほどソーニャを大切にし、常に傍にいたか、そして、オーヴェとソーニャに子供がなく、ソーニャが亡くなったときに「ひとりぼっち」になったかが描かれる後半は、実に切ない。
前半、チラリと写される、オーヴェの家の低いキッチンなどの伏線が上手い。
周りのみんなを助け、助けられたオーヴェは、隣のペルシャ人の妻が出産を機に、生きることに前向きになる。
が・・・、という終わりも切ない。
でも、幸せな感じがする。
傑作ではないけれど、「心温まる」という言葉が相応しい秀作でした。
妻に先立たれ、後を追うつもりで自殺を試みる偏屈爺さん。しかし、引っ...
妻に先立たれ、後を追うつもりで自殺を試みる偏屈爺さん。しかし、引っ越してきた隣人家族や町の住人のタイミングの良い干渉により、実行は何度も阻止されてしまう。
笑いと涙で溢れ、ペーソスの漂う暖かい人情劇。爺さんが自殺を試みる度に生きてきた人生が走馬灯のように蘇る。親試練と苦難の人生の中で、親との生活、妻との馴れ初め、数少ない友人との交流などが語られる。偏屈爺さんは本当は心優しい。引っ越してきた隣人一家も付き合ううちに理解し、お互い無くてはならない存在になる。新年にふさわしい心温まるストーリー。
偏屈爺さんといえば、すぐ思いつくだけでも、
『グラン・トリノ』
『ヴィンセントが教えてくれたこと』
『カールじいさんの空飛ぶ家』
などの映画が思いつく。
どの作品も、独り身になった生きる意味を失いつつある老人が、他人との触れ合いにより生きる意味を見出す秀作ばかりですね。本作は北欧スウェーデンで国民的な大ヒットを収めた作品であり、上記作品に一歩も引けを取らない素晴らしい秀作でした
今年の3月にイギリスの名匠ケン・ローチ監督の『わたしは、ダニエル・クレイグ』という孤独な老人と隣人家族との交流を描いた作品も公開されます。本作と比べて見るのも良いかもしれません(^-^)
人間味のあるドラマ
ヨーロッパから渡ってくる映画でよく観てるのは、気難しいお爺さんが、周りの人との交流を経て徐々に心を開いていく、という系統のものが多い気がする。
そんな中でもこの映画は、若い頃の回顧シーンがタイミング良く挿入され、気難しくなっていく老人オーヴェを良く理解出来ながら話が進んでいく。親友と疎遠になっていく過程も、くだらないエピソードなのだが、さもありなんというような現実味があって物語に感情移入出来る。
北欧ならではの、色鮮やかながらどこか侘しさのある映像も含めて、とても味のある、秀逸な作品だった。
最後の猫のシーンは、「そこにいてくれたら、猫のことよく分かってる人が撮ってるなー」と思いながら観てたが、ドンピシャそこに居てくれた(笑)
またまた涙腺が
見当違いの感想ですが…
この邦題を採用したのは、今の日本には、リタイア後の人生や配偶者に先立たれた後の人生を、現実的に切迫感を持って考えている人が団塊世代を中心にたくさんいるからなのでしょうね。
ささやかながらも、一定のコミュニティーの中で相応の責任感を持って取り組める仕事(無報酬でも)があるのは、幸せなことだと思いました。オーヴェだって文句を言いながらも墓前であれこれ報告するのが(たぶん)楽しかったはずです。
普段は誰も気付いてくれないけれど、たまには、やっぱり俺でなきゃダメなんだなと、たとえ独りよがりだとしても思えることがあるのは、その人にとっての支えになります。
この映画の主題は、今述べたようなことではなくて、本当はもっとオーヴェ個人の人生にスポットを当てているのだと思いますが、個人的には人生における黄昏時(君の名は。の誰そ彼時のような哀切とは程遠い平凡な人生の黄昏時)以降をどう生きていくか、考えるヒントとなる作品でした。
※車を巡るこだわりが、とても愉快でした。
私の場合はビールですね。
晩酌は、専ら首の長い動物か、ふくよかな太鼓腹です。
幸せな気分になれるはず
全134件中、101~120件目を表示