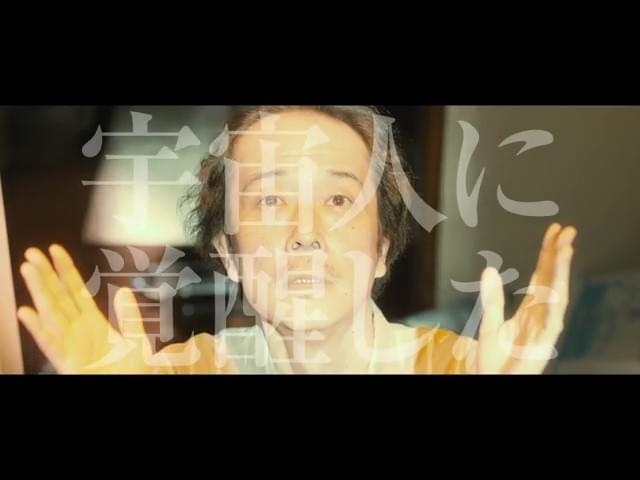美しい星 : インタビュー

三島由紀夫に「ロックを感じた世代」リリー・フランキー&吉田大八が挑んだ異色SF
三島由紀夫の異色SF作を、「桐島、部活やめるってよ」「紙の月」の吉田大八監督が大胆な脚色で映画化した「美しい星」が公開中だ。火星人であると覚醒し、狂気の中に哀愁とおかしみを漂わせる主人公の大杉重一郎をリリー・フランキーが好演した。撮影当時の吉田監督とリリーはともに重一郎の設定と同じ52歳。三島の生きざまに「ロックを感じた世代」で、50代は「開き直って自由になれた」と言うふたりが対談した。(取材・文/編集部、撮影/間庭裕基 撮影協力/明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン)
——今回のキャスティングについて
吉田 リリーさんといつかご一緒したいと思っていたところに、ちょうど重一郎と同じ年齢だということも重なって、最初からリリーさんが演じることをイメージしてシナリオを書き始めました。
リリー 僕も、吉田さんの作品は本当に好きで。お仕事したいなという以前に、似たようなものが好きなんだなということは感じていました。こういう映画で、何かできると思っていなかったのでうれしかったです。しかも三島の作品で。
——ふたりにとって三島由紀夫とは?

リリー 大八さんや僕の世代のサブカル祭り。「美しい星」が映画になって、僕らが原体験している好きなものがちりばめられてる感じ。特に当時の美術系の学生にとって、三島はポップスターでしたね。文学者以上のいろんな顔を持っていて。それで美しい文章を書く。
吉田 多面的ですよね。多くの作家が小説だけに専念していた時代に、確信犯的にいろんなことをやっていくかっこよさ。三島さんが亡くなったのは僕らが小1くらいのときなので完全なリアルタイムではないんですが、三島由紀夫という名前にどこか特別な雰囲気を感じていました。
リリー 小学生だったけれど、三島由紀夫が自決したってことはなんとなく認識していた。だから、最初からショッキングな出会いだった。
吉田 いろんなアーティストがいるけれど、自分の死に様まで演出した人はなかなかいない。そんな三島さんの小説の中でも、「美しい星」は異色。どこに連れて行かれるかわからないまま、呆然と置き去りにされて終わる、そんな読後のインパクトが当時の自分に強烈に刻まれてしまって。あれだけ丁寧に積み上げてきたものを、最後に全部ひっくり返す感じが鮮やかで、まず単純に「かっこいい!」と思いました。そのうち人に勧めるだけでは物足りなくなって、自分もこの作品にかかわりたい、この作品の一部になりたいという思いが強くなっていって。
リリー 僕らの世代にとっての三島って、その活動や存在がロックスターのよう。ロックを感じているから、自然とこの映画も音楽的になったと思います。
吉田 現場でもリリーさんと音楽の話をすることが多かったですよね。もしかすると映画より音楽で持てた共通項が多くて、感覚が共有しやすかった。
リリー 多分、僕らのもうちょっと上の世代だと、ハードロックだとかプログレだとか、音楽にロックの質実さを求められていたと思うけど、僕らの時代は、ニューウェーブ、パンク、テクノの頃。解放されたというか、多面的に音楽を取り入れていいという時代の最初の子供たちだったのでは。
吉田 自由になっていった時代ですよね。いいな、と思ったら、楽器弾けなくてもすぐにギター買って鳴らすんだ、っていう世代。「美しい星」を映画にしたい、って思ったのもそれに近い衝動だったのかも。
——50代になって映画化が実現しました

吉田 振り返ってみると、30代、40代のほうが不自由だった気がします。でも50代になると、それほど周りの目を気にしなくてもよくなってくるんです。だから、このタイミングでよかったなと。
リリー 若い時はなにかをやることに、どこかでものすごく個を出そうとして、そしてその同じ力で、自分が否定しているポピュラリティを持とうとしてたのかも。でも50代になると、ポピュラリティをあきらめることができるようになれた。それは、元来そうじゃない、という更なる気付きが起こるということ。
吉田 僕もそうです。やっぱり、自分が好きだった音楽はクラスで一人か二人くらいしか聴いてなかったな、とか思い出すんです(笑)。30、40代は多分、求められていることと、自分が好きなこと、できることのズレを埋めようとしてがんばったり、苦しんだりすると思うんですが、50代になると「もういいや、元々こういうのが好きだったし」って開き直り始める(笑)。
リリー 自分に対してのあきらめがついている。俺の心の根っこの腐ってるところは治らないとかね……(笑)。
吉田 もう取り返しのつかないことも多いから(笑)。逆に開き直って自由になれた気がする。迷いがなくなった気がします。
——その振り切った感じで、あの火星人が誕生したんですね

リリー 試写を見て、自分が大げさなことしてるんだなと気付気ましたが、ああいうやり方でないと、言葉がお芝居にならなかった。スタジオのシーンは4日連続の撮影で、毎日の空気の重さといったら(笑)。本編は音楽でポップに盛り上げられてますが、現場はそんなに楽しいものではなかったんですよ。でも、客観的に見て、すごくかっこいい映画になったと思う。かっこいいという言葉は軽くてあまり好きじゃないけど、ほかに言いようがない。
——あるシーンで、唐突に牛が登場します
吉田 牛はCMの撮影で何回か使ったことがあるんですが……動かないんです(笑)。だから、牛に乗るという演出は最初はあきらめていました。
リリー 台本読んだときに、そうはいかないよ! って笑いましたもん。乗れましたけど、意外と歩くスピードが早かったです。牛に宇宙を感じてるのも、ピンクフロイドっぽい(笑)。
吉田 「原子心母」のようなホルスタインは見つかりませんでしたけど(笑)。
リリー 思っていたより、牛はしっかり芝居していましたよね。
吉田 今まで出会った牛の中で、最高の牛でした。
リリー 公開後忙しくなるでしょうね(笑)。
——三島由紀夫が生きていたら、楽しんで見てくれる作品になったのでは?

リリー こうやって、次の世代の人がリミックスしてくれるほうが、原作のまま映画化されるより作家としてはうれしいでしょうね。
——またふたりでなにか生み出せそうですね
リリー 映画という形じゃなくても、何か作りたいですね。二人でコンピレーションCD出したりね。
吉田 (笑)。同じものを好きだった人と、この歳で、このタイミングで、出会えた。何かに導かれたような気がします。ラッキーでした。
——三島のおかげで、同じ星の仲間と出会えたようですね
吉田 同じ星……九州ですけどね(笑)。