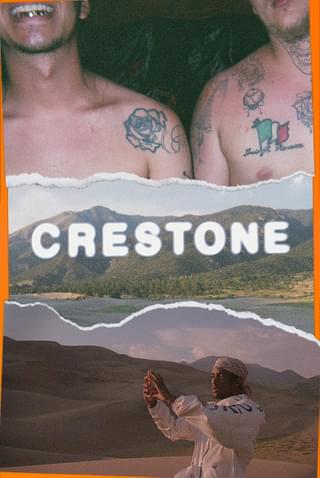ヴィクトリア(2015) : 映画評論・批評
2016年4月26日更新
2016年5月7日よりシアター・イメージフォーラムほかにてロードショー
2時間越えのワンショットが垣間見せる、映画の麻薬性
何の落ち度もない女性が、アウェイの地で一夜のうちに犯罪に巻き込まれ、共犯者の一人となっていく。そんな予想だにせぬ転落のプロセスを、133分ワンショット(クレジット除く)で捉えた野心的な作品だ。
かつて映画がフィルムを媒体とした頃、カメラに装填できる撮影用フィルムの尺には限度があり、長時間のワンショット技法には物理的な不可能があった。よしんばその制限内でおこなったとしても、カメラの機動性は限られ、また状況の推移に応じて照明や絞りを変化させねばならず、撮影自体の難易度もべらぼうに高い。ゆえにヒッチコックやウェルズ、アルトマンやデ・パルマといった、腕に覚えのある監督がこの至難の技に挑んだのである。
しかし、デジタル媒体への移行により、映画は先述の制限から解放され、長時間切れ目のない撮像を生み出すことが可能となった。さらにはカメラの高性能化、小型化が進み、どこまでも被写体を追える機動性をも得ている。そのため、こうしたアプローチは今や珍しいものではない。現に昨年の米アカデミー作品賞を受賞した「バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)」(14)は、長時間ワンショットのスタイルをとった作品として周知されているし、身近な例としては三谷幸喜が「short cut」(11)「大空港2013」(13)というテレビムービーでそれを実践している。

しかし「バードマン」はショットとショットの切れ目をデジタル処理でつないでシームレスを装い、三谷作品は両作とも限定空間、ランニングタイムは110分前後だ(それでも偉業は偉業だが)。「ヴィクトリア」はそれらを凌駕する2時間越え、ベルリン市街を大移動するワンショットなのだ。クライマックス直前でNGを出そうものならば、全てが水泡に帰す。その緊張だけで観る者の背筋は伸び、対峙の姿勢はおのずと正される。
実際、ワンショットが2時間の壁を突き破ったとき、何が観客にもたらされるのか? まずは劇映画を観ているという意識を、極限まで薄れさせる。編集や加工を極力施していないリアルタイムな映像は、観客の体感時間と意識を作品に同期させ、3Dよりも深い没入の域へと観る者をトリップさせるのだ。
そんな密着した意識を引っぺがすかのごとく、劇中では主人公ヴィクトリア(ライア・コスタ)が難易度の高いピアノ曲を弾いたり、現地点から屋外階段やエレベーター、あるいは車を用いて別の場所へと移るアクロバティックな移動など、NGを誘発しかねない演出がときおり顔を覗かせる。こうした観る側と作り手との「受け」「攻め」のSMチックな行為を構築している点で、ワンショットの趣向は作り手の純真な野心を超え、倒錯と悪趣味さを発散する。ヴィクトリアが悪の轍に踏みはまり、良くも悪くも自己を解放していくように。
2時間越えのワンショットが垣間見せる、映画の麻薬性。技法を極めた成果にしてはいささかデンジャラスだが、「興味本位」でも「物珍しさ」からでも構わない、その驚異にはオンタイムで接するべきだ。
(尾﨑一男)