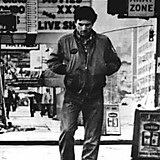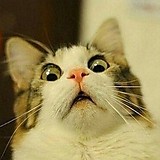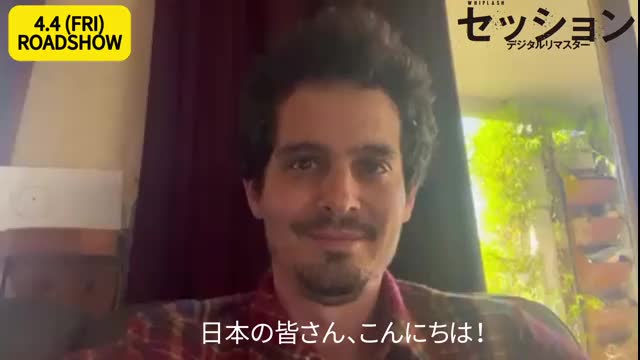セッションのレビュー・感想・評価
全191件中、161~180件目を表示
ハゲの活力ハンパなし。
空飛ぶハゲにドラムのハゲ(誉めてます)と、ハゲの活力がハンパない。
数々の賞を総なめにしたおっさん(好きです)ハゲ、J・K・シモンズ。
いや~いいわ、このホラー(爆)、スリラーだし、スポ根にもなってる。
あまり見たことない恐ろしさにド嵌りした人も多いんではないかしら。
今じゃこんなシゴキをやろうもんなら、DV!モラハラ!で訴えられて
(まぁ今作の場合、訴えられても仕方ないが)家族は一丸となって子供を
その選択から遠ざけようとするわね。だって殺されちゃうかも?だもん。
しかしそこへ喰らいついて離れないピラニアのような弟子をこの師匠は
心から欲しているんだよね。たぶん自身が叶えられなかった夢を弟子に
見出そうとしてるんだけど、それが狂気を帯びて常軌逸脱、果ては鬱病
になってしまう弟子が続出、っていうちゃんと巧い教え方が出来ない人。
でもこの鬼に目をつけられたってことは、育てる才能があった訳でしょ。
主人公ニーマンだって相当の食わせ者だと最初からちゃんと描かれてる。
あの家族(親類)に囲まれてたら、そりゃ上昇志向も高まるってものだし。
結局この師弟はよく似ているから理解も衝突も生まれる。一度は辞めた
ニーマンが意気揚々とまた加わるところなんかホラやっぱり!てな感じ。
自分から好きになっといて彼女に別れ話をきり出すニーマンを見た時、
(思わずソーシャルネットワークか?なんて思ったけど)コイツ何様!?
と思ったけど、その何様感が師匠フレッチャーとソックリで。たかが
音楽院の一教師がどれだけの権力を握ってる?と私なんかは思っちゃう。
(つまり音楽が分からないニーマン父と同類ね)でもニーマンには、もう
やっぱりドラムしかないわけで。それを教えたのも鬼ハゲ野郎ときてる。
切っても切れない間柄の二人は、最後の最後でまた対決!するんだけど、
この裏切りが何を齎したか…ここが最高潮興奮度MAX。でもこの作品、
最初から最後までずっと周囲の楽団員が迷惑かけられっぱなしなのね^^;
(緊張感と高揚感と戦慄。映画もテンポは大事です。ふぁっきんてんぽー!)
アドレナリンが放出させるような映画。
予告編からずっと気になっていて、アカデミー賞をたくさん授賞したと聞いたので、観に行きました。
この映画、一言で言うとヤバイ。自分は音楽には全く興味がなかったのですが、すごかったですね~w
あのドラムさばき!見たこともない速さでした!
物語は以下の通り(細かい部分は省略。)
主人公ニーマンは、偉大な音楽家になる為、日々、ドラムの練習していた。
そんな時、鬼教官のテレンス・フレッチャーが現れる。ニーマンのドラムをダメ出しされ、フレッチャーがニーマンに自分が指揮するバンドに招待されるが、大声でめちゃくちゃ怒鳴られ、暴力に耐えながら指導を受け続ける。
そこでニーマンは、偉大な音楽家になる為、付き合ってた彼女と別れ、必死でドラムの練習を受け、やがて鬼指導者フレッチャーから認められ、主奏者になれると思いきや、ライバルに奪われてしまう。
そして、ニーマンはフレッチャーに認めてもらおうと会場へ向かうのだが、乗っていたバスがパンクし、仕方なくレンタカーに乗り、急いで会場へ向かい、到着するが、ドラムのステッキを忘れてしまう。フレッチャーをなんとか説得し、10分で戻ると言い、ステッキを忘れたレンタカー屋へ。そして帰り道に悲劇が起こる。
まさかの交通事故!Σ(゜Д゜)
あれにはビクッとなりました!
しかし、ニーマンは諦めず、血だらけのまま這い上がり、徒歩で会場へ到着。
だが、フレッチャーはニーマンの姿を見て呆然…。ニーマンを即辞退させる。ニーマンは今までのうっぷんを晴らすかのように暴言を吐き、追い出されてしまう。
そして、夏…フレッチャーと再会したニーマンは、フレッチャーから学校を辞めさせられたと知る。それで新たなバンドのドラムを招待されたニーマンはドラムをすることを決意する。
そして、いざ!本番という時にフレッチャーから「俺をハメたな。俺を甘くみるな」と言い、急に曲を変えてしまう。突然の変更に戸惑うニーマン。そして知らない曲が流れ、うまく演奏することができないニーマン。
ステージの裏で待っていた父親とハグをしたあと、ニーマンは再びステージへ戻り、いきなり、ドラムを演奏をし始める。突然の行動に困惑するフレッチャー。構わず激しくドラムを叩くニーマン。師匠と弟子の激しい攻防を繰り広げ、最終的にはドラムのフィニッシュで幕を閉じました。
おおざっぱで説明しましたが、この映画は本当に激しい。役者が素晴らしかったですね~あのリアルなドラムの叩くシーンや、師匠の激しいスパルタ教育がやばかったです!(>_<)
観て良かったです!(^o^)
長文失礼しましたm(__)m
圧巻の対決。
思わず息を飲みながら画面に釘付けになった107分であった。
名門音楽学校に入学した主人公の青年ドラマーを待ち受けていたのは鬼教官、フレッチャーによる容赦ないスパルタ教育。
本作を鑑賞中、中盤ごろまでは「ブラックスワン」あたりを彷彿とさせる心理スリラーのような印象を受けていたが、それ以降は映画はガラリと様相を変える。
特に終盤における最大の目玉、演奏シーンの演出はもはやアクション映画のそれである。
「ボーン」シリーズのようなめまぐるしいカット割、息をつかせぬテンポ、フレッチャーとの駆け引き等、これは音楽映画の皮を被った格闘アクションだと個人的に感じた。
ラストの最高のセッションを演奏し切った後の二人の表情が本作を象徴している。
ラスト、フレッチャーが口を動かしていたように見えたがなんと言っていたのか気になる所。やはり「Good job」だろうか。
本作は一部、音楽関係者からの批判を受けているそうだが、この映画にそこまでの音楽的リアリティを求めるのは野暮である。
なぜなら、リアリティばかりを重視していては本作のカタルシスを味わえないからだ。
JKシモンズは地味な俳優というイメージしかなかったが本作で一躍ブレイクを果たした。本作は彼のキャリアを代表する作品になったと思う。
私個人の話だが本作を観るため、他府県まで出かけて行ったのだが、その甲斐はあった。映画館でなければ本作の魅力を髄まで味わえないだろう。
迷っている方がおられたら是非とも遠出してでも本作を劇場で鑑賞して欲しい。
その価値はある映画だと思う。
てっぺんを目指すことの苦さ
今現在、何かを目指して
苦戦してる人が見ると共感する部分も多いんじゃないでしょうか。
- - -
嫌なやつも苦い体験も
格好悪い自分も、全て自分の糧にする。
最後にとった主人公の行動からは、昔の彼はどこにも感じられなくて、青くて苦くて、そんな成長に励まされました。
最後のシーン前、
父親のハグに沈まずに本当に良かった。立ち向かってくれて本当に良かった。
あそこで立ち向かわなければ、一生傷になって、もう立ち向かえなくなってしまうので、、
自分はかなり共感してしまい、涙腺ゆるかった、、オススメです。
凄い。
これは、所謂、根性物の映画ではないと思います。そういった映画を観た後のカタルシスが、まったくありません。芸術=音楽の為なら自分の生徒を自殺に追い込んでも、なんとも思わない人間と、芸術=音楽の為なら、死んでも構わないと思っている人間。この2人の気狂いの物語だと思います。
最後のシーン、二人はお互いに笑顔を交わしますが、それは二人が心を交わしたわけでは決してなく、そこに立ち現われた芸術=音楽に心酔していただけです。
自分を含め、殆んどの人にとっては、疎外感を感じさせる映画だと思います。
あの様な人間でなければ、あの様な場所には行けないのではないのでしょうか。
とても凄い映画だと思いますが、正直、観なければよかったと感じてます。
面白い
ただ訓練して大会に出る話だけど、フレッチャーの何を考えているのか分からない魅力に引っ張られてあっという間の2時間だった。
甘い父親を捨て、厳しい父親も乗り越えて一人前になった最後のドラムソロは圧倒的!
独りよがり
ジャズドラマーとして成功を夢見る青年と、その才能を開花させるべく執拗なまでのシゴキを繰り返し追い詰めていく名指導者?鬼教授?とのやり取りなのだが・・・。
青年の生き様も、ドラムプレイも独りよがりで共感できないし、教授の指導ももっと狂気に満ちたものを想像していたので期待はずれ。
評価の高さと宣伝文句にやられてしまった。ドラム版「フルメタル・ジャケット」なんて記事まであったけれど程遠い内容です。
映画は不満でも、TOHOシネマズ新宿はいい映画館でした。
歌舞伎町の雰囲気も変わりそう。
おっさんと青年の喧嘩
技術と精神論で極めていく系かと思いきや
おっさんと青年の意固地な殴り合い。
予想の斜め上を行く内容だった。
事故るシーンから血だらけで演奏するまでわくわくする、いい意味でギャグ。
終始笑い転げる。
観てるこっちが汗掻いた!
素晴らしいの一言。
強烈な師弟関係。裏切り、そして逆襲。
張り詰めた緊張感が最後の最後まで続く。観終わった、主人公と同期したように汗掻いた。
これは鬼教官とそこに入部した青年の血殴りの葛藤を描いた師弟関係の人間ドラマだ。
名門楽団に入部し、主ドラマーになった主人公だったが、重要な発表の場に行く途中、乗っていたバスがパンクするという事故に始まり、到着するがステッキを忘れ戻りに帰るが、そこで衝突事故に合う。血まみれで現れるが、演奏が出来ずにクビに。
鬼教官の指導で鬱になり自殺した生徒のため、罵らてきたことを密告する主人公。
鬼教官への復讐のいみもあった。
鬼教官はそのことが原因でクビに。
街のJAZZでピアノを弾く鬼教官とたまたま出会う。
戻ってきてほしい。お前が必要だ。
主人公、楽団に戻り。コンサートの日。
そこには有名なスカウトマンが沢山きていた。ここで失敗したらドラマー人生の終わりだ。
曲が始まる直前に、主人公に向って一言。
密告者はお前だ!
曲が始まった。それは主人公が知らない曲。裏切られた、、スカウトマンが見ている中、その場を去る主人公。
父と舞台袖で抱き合う。
しかし、主人公は立ち上がる。再び舞台に戻る。
鬼教官の指揮を無視!
いきなり激しく叩き始める主人公。
威圧感に押され、皆もセッションする。
呆然となる鬼教官。
完全に立場が逆転した。
俺の指示通りに動けという鬼教官に反発し、指揮権を奪ったのだ。
猛烈なドラム。とてつもない速さ。
鬼教官も次第にその中に、
最後は鬼教官も取り込み、
皆でセッションして終わる。
手に汗握る映像だ。
最高!
ニーマンのドラムのテンポが凄くはやくなっていくシーンが最高!
マイルズ・テイラーも良く演じきってくれた。
終盤は、観ている人達をのりのりにさしてくれた感じだった。となりの席の人をちらっと見ましたが、目が輝いて見えた。僕自身ものりのりで、気分最高!
これは、ジャズ好きの人はもちろん、映画好きの人は、観て損なし。
最後のニーマンとフレッチャーの掛け合いがとても良く、微笑ましい。
観ていてあっという間に時間が過ぎていた。
ストーリーも抜群。良いもの観させていただいた。
肩透かし
菊地氏と町山氏の対決を見て見に行ってきました。
率直な感想としては、菊地氏の言う「カタルシスがない」というのに同感です。
主人公が教授を訴える→教授が主人公を騙す→主人公がコンサートをぶち壊す
とただの負の感情連鎖のように感じてしまいました。
観客を置き去りにした冗長なドラムソロの中でお互いに何か通じ合うものがあったんだろうけど、
それだけ?って感じの終わり方に感じました。
そしてこの物語で誰か救われたのだろうかと。
音楽的にもとにかく、テンポテンポテンポで、
手数とかひたすらジャストのタイミングを要求する音楽はうんざりです。
全体的にはスパルタ教育VSゆとり教育(が理想としたもの)と、
負の連鎖というところが気になりました。
厳しくしないとスターや有能な人材が生まれないのか、
厳しくしたら潰されるのか。
欧米では体罰はあり得ないという話を聞くので、
この話(というか、こんな状況がまかり通るジャズ業界)は前時代的ということでしょうかね。
またイスラム教を嫌っときながら、報復してるのはキリスト教徒も一緒だよね。
キリストの言ってることと違うじゃんか。
そんな映画がアカデミー賞を取るほどいいのだろうか?
それとも好敵手と書いて「とも」と呼ぶジャンプ的な何かだろうか?
全編通して飽きずに見れましたし、
できが悪いということはないですが、
最後の終わり方が肩透かしで、もやっとしたままでした。
ドラムはかっこいい。
アンドリュー(マイルズ・テラー)は、胸に希望を抱いて音楽大学の門を叩く。厳しいコーチ フレッチャー(J.K.シモンズ)の目に留まり、彼の率いるバンドの一員になる。
スパルタ的な指導に違和感はなく、一流になるためにはこれくらいのことはありかと。
リズム、テンポを習得するためのビンタは、まさにスパルタなのだが、叩かれているほうが何も言わなければ何の問題もない。
フレッチャーに追い出されるのも、ほぼ自分の不注意で、教師としては、時間にルーズなヤツは使えないというところだ。
だからこそ、カーネギーホールで仕返しみたいなことを企てたフレッチャーは少し残念であった。
が、アンドリューの演奏が、フレッチャーの器の小さい思いを吹っ飛ばすラストは見応えがあった。
デイミアン・チャゼル監督のビートの効いた演出もかなりよかった。
素晴らしいが、音楽の魅力からは外れる
感情と台詞を音で表現したラストシーンは圧巻だが、ステージの上で敢えて恥をかかせるというフレッチャーの行動は音楽家としてあり得ない。ただの狂った奴だ。
そんな狂った奴へ向けて狂気的に叩くドラムが偶然に素晴らしいものになってしまう、それも音楽の一つだが、本来あるべき身震いする程の音楽による感動は得られなかった。
その為「セッション」という邦題はズレている。
卓越してた
J・K・シモンズの演技が評価されているけども、主人公も含めてキャストは良かったと思う。
ただ、それだけでなくストーリーも良かった。
とてつもない逆境をねじ伏せるほどの圧倒的な努力と決意ってものをみせてくれる映画。"普通の"努力家だったら、最後にハメられた場面でそのまま去るのみで一生戻ってこれなくなるとこだったと思うけど、そこをゴリ押しして自分で主導権を握ってしまうなんて考えられない。そういう理不尽な状況は世間ではよくあるので、「敗者はただ去るのみ」というのが正しいとは限らないことを教えられた気がした。
長生きよりも、名を残して早世
マイルズ・テラーとJ・K・シモンズの好演によるところも大きいのだろうが、終始流れているぴりっとした真剣な雰囲気に釘付けになる。
最も恐ろしい言葉は「グッド・ジョブ」だとして、現状で満足させないように、あえて厳しい指導をするテレンス・フレッチャー。
その様が逐一自分の仕事と重なり、共感と考えさせられることの連続だった。
敵が多くなることを自覚しつつ、育てるためと割り切る指導者側の苦悩も垣間見えるようだった。
最後のステージでの、マイルズ・テラーの密告に端を発する互いの復讐のやり合いも面白かった。
ただ、その後の止まらないドラムがやや冗長かつ分からないのが、唯一残念。
ニコルとのやり取りも、もうひとつあっても良かったかもしれない。
最後の9分にむかう映画。
この映画は最後の9分間に全てが詰まってるといっても過言ではないと思います。
それほどに濃い9分間です。
最後への盛り上がりかたが半端なく、息をのんで釘付けになりました。そして期待を上回るラストに感動しました。
フレッチャーがアンドリューの「合図を出す。」と聞いた時にうなずくシーンは感動し、ドラムソロでは鳥肌が立ちました。
そして何と言ってもフレッチャーの演技です。すごかったです、アカデミー賞獲得もうなずけます。
この映画があまり劇場でやってないことが不思議でなりません。
絶対見るべきだと思います!
理路整然とはいかないか
「なんか、はっきりとした言葉で感想が出来ないな」これが見終わった後の素直な感想です。ラスト10分(長さは適当)の音で闘う場面は確かに熱量半端ないし、暗転のタイミングも初監督では思い切ったものだった。でも、でもである。それ以上の何かがあるのかと言われたら「どうだっけ?よく考えたらそんなになかったかもね」と言いたくなるのが本作。一番の引っかかり、もしくは矛盾点と感じたのはラストの舞台へあがる動機だ。基本構図として、音楽狂い、芸術狂いの「音楽の為」なら暴力でもイジメ、パワハラ、何でもする独裁者的講師と誰からか認められたいトップジャズドラマーを目指す主人公の激しい邂逅、緊張、対立、挫折、対決、共有を描いているんだけども、この肝になる音楽講師が理路整然としてない。体罰とかパワハラ、イジメとかは別にいいんだけど(実体験組としてはふーん位の描写だと思う)、ラストの場面前で挫折した主人公を自身が指揮するプロ楽団に誘うんだけども、その動機が復讐なんだよね。音楽狂いが音楽を復讐のアイテムに使っちゃいけないでしょ。こうなってくると音楽狂いでも何でもなく、ただの権力をもったイヤなヤツでしかない。こうなると、主人公を見いだした動機すらも怪しくなってきて判然としなくなってくる。そして、音楽狂いじゃなくて音楽好き程度なヤツって考えるとラスト2人の「音の闘い」も薄味になってくる。ただ、考察に足る映画だし、誰かと話したくなる伝えたくなる映画だということは間違いない。
殺し合いだろ?
一応、この物語はハッピーエンドなんだろうな…。
彼は伝説を手に入れ。
彼は伝説を育てた。
だが、順風満帆とは、真逆…エンドロールの為にブラックアウトするまで、この二人は演奏途中だろうが何だろうが、つぎに何かが起これば、もしくは起こせば、間違いなく殺しあうと思ってた。
俺的、編集賞をあげたい!
世間のモラルのなんとチープなことか。
なんとかハラスメントとか、勝手にやってろ風な暴力の嵐だ。
相手の為に厳しくとかいうレベルじゃない。
俺にやられるようでは、所詮そこまでの器だと断言し、徹底的に追い込む…いや、むしろ、潰しにかかってる。
それを受けた主人公。
彼のサクセサストーリーは、危ういなんてもんじゃない。
神さえ裏切られたと思う。
まるで100mの高さから水面めがけて飛込むかのようだ。
勝算なんてない。
破れかぶれだ。
でも、彼は問うた。
自分の価値を問い続けた。大声で。
最初と最後、到底、同一人物に見えない程、彼の中身は変貌してた。
とんでもないアクション映画だった。
劇場が明るくなった頃、拍手がパラパラと起こった。
納得だ。
俺も微力ではあるが、喝采を送りました。
神々の戦い
噂に違わぬ素晴らしい映画でした。「持ってるヤツに持ってないヤツがたまには勝つと思ってたいヤツ」人にとってはこれ以上ない映画なのではないでしょうか。勿論、話の舞台がアメリカ最高の音楽学校の最高のバンドですから、上の上の下ぐらいのものなのでしょうが…笑
やはりあのラストが好きです。フレッチャーに音楽の楽しさを奪われ、音楽以外のものを全て捨てざるを得なくなり、最後には音楽すら失くしてしまった。それでも尚襲い来るフレッチャーに「音」で対抗し、最後には奪われた「音楽」を取り戻す。僕はこの映画を「音楽を取り戻す」映画として素晴らしいと思います。
不満点としては主人公もフレッチャーもバックボーンがほぼほぼ描かれず肩入れしづらいことなのですが、最早僕とは違う世界の神々の戦いとして眺めているだけで楽しかったので、やはりあまり気になりません。こんなに口あんぐりで観続けた映画は初めてです。傑作!
全191件中、161~180件目を表示