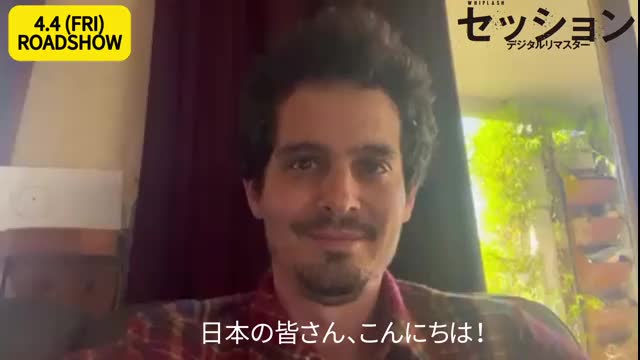セッションのレビュー・感想・評価
全191件中、141~160件目を表示
もうやめてー!精神的なヒリヒリ感
酸欠になりそうでした。師匠と師弟の成長ものかと思って見ていましから、主人公と同じ軸でコノヤローと爆発するタイミングは同じでした(笑)
ただ、DV夫婦の顛末を見せられている気分になったのは私だけでしょうか?
怖い映画です。
迸る狂気と狂気のセッション
最初は鬼教官の狂気に引きずり込まれる話なのかと思ったが、実際には主人公も狂気を秘めていてそれが次第に表面化してきたように感じた。自分から口説いた彼女に暴言を吐いて別れるところは変化の象徴として分かりやすいが実家での親戚との会話などで既に誇大妄想的な片鱗は見えている。歴史に名を残せない人生に価値などないと純粋に信じられるのは若さの特権だし、そのような道の先に幸福が訪れないことに気付く頃にはもう取り返しがつかないと悟るのも人生だ。ただそれでも熱狂する情熱から逃れられないのならば後はどこまでも修羅の道を突き進むしかない。終盤、二転三転するどんでん返しの果てにようやく絡み合い一瞬の奇跡を見せた二つの狂気。これから始まる更なる地獄の予感を感じつつも彼らの魂が一瞬でも至福の時を迎えたであろうことを祈りたい。
胸くそ悪い
『狂気』という一言で片付けているけど、
アンドリューが日に日に高慢になってライバルを罵る様は見ていて気持ちいいものじゃなかった。
女の子をデートに誘うのもあんなにたどたどしかったのに…
加えてフレッチャーはドがつくクソ教師。
化けの皮が剥がれた瞬間は驚き以上に呆れて開いた口が塞がらなかった。
こいつはステージを本当に自分の私物だと思っている…。
『最後の演奏に乞うご期待!』というような予告で、本当にアンドリューの『才能』が開花した瞬間だったと思うけど、その直前のフレッチャーのクズさが尾を引いてあまり感情移入できなかった。
人間ってこんなに早くドラムを叩けるのか、という感動はもちろんあったけれど、予告のような「師弟関係」や「感動の音楽サクセスストーリー」を期待していくと大きく裏切られる。
それがいい人もいるかもしれないが。
「永遠の一本」とは、まさにコレ!
アカデミー賞の頃から期待していたんだけど、期待どおり...いや、期待以上のデキだったわ。10点満点の「アメリカン・スナイパー」には届かなかったけどな。
カメラ・ワークは荒々しく、短いカットが実に多かった。だがコレがかえってこの作品の凄さを引き立たせたな。
それにしても、あの交通事故のシーン。よくあんなのをクルマの中から撮影したな。
そして、最後のあのシーン。ダマされて一旦引き下がって、戻って逆襲。コレ本当に「してやったり!」だわ。そしてあの演奏(ドラム・ソロ)。コレ本当に映画史に残るわ。
狂気のラスト15分
ラスト15分のために残りがあると言って良いぐらいの映画でした。映画を観終わったあとで頭の中で反芻したくなる様な映画が好きな方ですが、映画が終わった瞬間に全てを消化できるスッキリ感とラストの狂気に満ちた演奏からのエンドロールには鳥肌が立ちました。DVDが出た際はヘッドホンの大音量で観直そうと思います。
してやったりな笑顔と、やるやん!こいつな笑顔
テンポが速い!遅い!言われても素人には何のことやら。そんな理不尽とも思える強烈な指導を行う鬼教官とプロのドラマーを目指す青年のやりとりを描いた映画。
スポ根的な要素は満載で、実は学生思いのいい先生だった!みたいな展開と思いきや、若造にそんな復讐するかーというラスト。と思いきや、さらにもう一手隠されていた。
ラストのその一手がこの映画の評価を高めているはず。なんだかんだいって自分の求めている演奏に出会うと体が動いちゃうよねって感じの鬼教官と、してやったりな主人公の笑顔が最高。エンドロールが流れる中、しばらくにやけ顔がおさまらなかった。教育とは…、ドラムの技術が…、なんてのは気にせず楽しめばいいのだ。
パンチ効いてる作品
終始力が入る映画って戦争映画くらいかと思ってたら、非常に疲れた。
速さとリズムがすべて、的な追いこみ方とか、それについていこうとする異常なストイックさとか完全に狂気の沙汰としか思えないやり取りだけど、うっかりのめり込んでる自分がいた。
確かに最後の件は凄い!
信頼と復讐と血と汗と涙と酒と音楽と親子と恋愛と狂気のど根性映画でした。
個人的には邦題で良かったと思う。
先生と学生の駆け引きに興奮する
フレッチャーの暴力的行動、アンドリューのフレッチャーへの態度に常にドキドキさせられた。
ジャズに限ったことではないが、スパルタ的教育の中で、潰されてしまう人もいれば、反抗して逆に力を伸ばす人もいるということだろう。
フレッチャーはアンドリューに「学生の力が伸びることを期待した」と言っているが、その時点でフレッチャーはアンドリューに対して反感を持っていた。今まで理不尽でスパルタ的な教育を続けていて、潰れた学生がいなかったわけがないし、先生自身、いたことを認識していなかったわけがない。単に技術の低い人を罵倒することによって自分の立ち位置を確保していたのだろう。
しかし終盤、アンドリューが逆に力を伸ばしたことで、フレッチャーはアンドリューを認めざるを得なくなったのだと思う。
魅了された!
偉大なジャズドラマーになるべく音大に進み、そこで出会った超スパルタ教師の狂気に満ちたレッスンにより挫折、努力しながら自身を高め成長していく話。
最初から最後まで目が離せない、映画に魅了されるとはこういう事だと感じる作品。
シモンズの無茶な要求に応えようと努力する姿はスポーツさながらの熱さを感じ、また、狂気を孕んだ暴力的な指導はサスペンス、ホラー映画の恐怖感をも感じさせる。
だからといってどっちつかずではなく、作品の流れ、場面に応じて変化し感じさせてくるので本当にシーン毎の衝撃が凄い。
ラストのシーンはニーマンが怒りと情熱を身体と音で表現し、シモンズはニーマンの力を引き出そうと舞台上で二人だけの世界に入っていく。両者共に破天荒な行動をするが、それすらも魅力と感じさせ、客を魅了していくシーンは圧巻だった。
もはや作品が圧巻の完成度だ。
映画の完成度は素晴らしいが、お客としての立場ではこの映画を好み、観れる人は少し人を選ぶかもしれません。ですが、興味があるのであれば一度は観たほうが良いとオススメできる作品です。
親子の話だと思う。
母親がいない、主人公は、
父親が母親がわりである。
父親と、主人公は一緒に
映画に行くのが日課で、
普通の10代の男であれば、
気持ちが悪いほど、
ファザコンである。
そこへ出てきたのが、
スパルタ教師フレッシャーであるが、
彼の絶対的な支配は、
古き「父性」であると思う。
実の父親と、スパルタ教師を
対象的に描いている。
クライマックス。
まんまとフレッシャーにしてやられた、
主人公は、一度はステージを後にするが、
出口に迎える母親のような父親を、
背にして、もう一度フレッシャーと
対決する。
これはファザコンを断ち切り、
大人への成長を意味すると思った。
超絶技巧を堪能。
演奏のシーンはどれも圧巻。ドラムの事は何も知らない私が観てもすごいのがわかる。
息をのむとはまさにこの事。途中、本当に呼吸するのを忘れてたくらい。
終始、緊張感が半端ない。
あと、先生の鬼教官ぶりには私が怒られてる訳ではないけど、怖くて、悔しくて、涙が出た。
ただ、
現役鬼教官時代の先生の本当は優しい人エピソードをちょいちょい挟むのは要らない気がする。
人間的にはまあまあ大丈夫よって事だろうけど、最後に復讐を仕掛けるくらいのクズな訳だし。
あと、主人公のドラム狂いっぷりもベタだなーと思った。
叩きすぎて流血とか。
事故って血だらけで大事な演奏会に駆け付けるとか…
ラストシーンでこの映画のタイトルである「セッション」の本当の意味が分かる瞬間、鳥肌が立った。魂の共鳴とはまさにこの事だ。
音楽家同士の黒い部分
この映画は、音楽家を描いています。
常に周りと協調を求めようとする人には、とんでもないくず二人の意地の張り合いの映画に見えると思います。
ジャズとか、ロックとかクラシックとか関係なく、常に自分のアイデンティティを求める性
観客に夢をとか感動とか、言いながら自分を表現することで自分の存在価値を他人に認めさせようとする演奏家の暗い部分を描き出した。初めての映画だと思います。
最後の演奏の時、観客の姿は全く出てきません、観客は映画を見ている自分たちなのだと思います。
最後の壮大な意趣返しと、意地の張り合い。それを見せられる観客。
でも、息をするのを忘れるぐらい見入りませんでしたか?
これこそが、この映画の描く音楽家の正体。感動をあたえる音楽家のエゴイズム。
大事なのは自己のアイデンティティであり、そのためには周りのことは二の次
そして自己の鍛錬などはやって当然、自身が楽をして周りを利用するのではなく。
周りのことなど考えていないという音楽家の本音を描いていると思います。
この映画は、ジャズを50年聞いていても、聞く側だったらわからない。
演奏家、パフォーマーとして人前に出れば気がつく部分が多いと思う。
最後がアツイ
結構CMとかであらすじだいたい把握できるけど、最後あたりで色々内容が盛り上がってくる。
オーケストラの面々がかっこいい。
海外の人がやると様になるなーと思った!
最後のなめんなよ感がよかった。
自分にはあんなことできないからスカッとした。
パフォーマンス自体も良かったな。
見終わった後にもう一回最後の部分だけみたいと思った。
音楽に詳しい人が観たら、批判とか出るのかもしれないけど、自分は良かった。
主人公はなーんか好きなタイプじゃないけど(笑)
教官の演技うますぎ。
しわ一つが演技の一部に感じた。
年齢もあると思うけど、人間的に深い演技。
すごかった
大学の教授のジャズの先生が海兵隊の新兵訓練の教官のような恐ろしいスパルタ教師で、先生のバンドの練習はトラウマレベルのしごきであった。「速い!」「遅い!」と超微妙なズレを指摘しているようなのだが、聴いているこっちはどう違うのか全く分からなくて単に難癖をつけているようにしか見えなかった。答えのない問いを延々突き付けられているようで主人公が気の毒だった。
しかしそんな主人公もかなり思い上がりの強い人物で、似た者同士ではあった。音楽やその他の表現などはそのような強い自我がなければ魅力的なものにはならないと常々思っている。魅力的な作品や演奏などパフォーマンスは、しかしそれだけでもダメで、他者からの共感を得られる何かや暖かいオーラのようなものもあった方がいい。一体作品や演奏は誰のためのものなのか。
主人公の演奏は彼自身だけの冷たい世界で、先生の指揮する音楽も彼自身のためだけ徹底的に意図以外を排除した冷たいものに見える。パソコンでプログラムして再生すればいいんじゃないかな。
主人公は最初は、先生に認められようと必死に食らいついて懸命に演奏する。その時は先生のための演奏だ。
いろいろあって学校をやめて、先生も学校をやめてお互いプロとしてバンドを一緒にやることになる。そのバンドで出場したコンテストで彼は先生に怒りを爆発させて勝手に演奏をし始める。その時は自分のために演奏する。先生に対して自分の凄まじい技量を見せつける演奏で、それにつられて先生やバンドメンバーは息を合わせていく。大変な迫力のパフォーマンスだった。
オレ凄いだろ!という圧倒的な演奏だった。見ているオレもすごく圧倒された。そこにあるのは純粋にオレすげえだけだったと思う。演奏している音楽はスタンダードな曲だそうで、楽曲にある元々の作者の意図はどれほど汲まれていたのだろう。またお客に対してなにかを伝えようと言う意図も全くないように見えた。ただ純粋に、特に先生に対して凄さを見せつけていた。
敢えて言えば社会や世界に対してクソをぶっかけるような表現だったと思う。それもありだと思う。学校の標語で「ロックは才能のない者の音楽」というような貼り紙があったけど、ロックでありパンクなのだと思う。超ハイレベルな世界のことは分からないけど、オレにはとんでもなく才能に恵まれた人にしか見えない。
この映画を見た日は、オレも友達との約束に遅刻して迷惑を掛けてしまったため、主人公が発表会に遅刻して、遅刻しただけでなく交通事故に合って演奏を台無しにしてしまった事がとても胸にしみた。オレの場合は友達がとても優しく許してもらえて有難かった。
主人公は本当に学校に先生のパワハラをチクったのだろうか、それが疑問として残った。また演奏の直前にそんな疑惑を主人公に対して先生が告げるのだが、その後演奏が滅茶苦茶になるに決まっている。どんな意図だったのだろう。
ちょっと言い過ぎだけど、途中まで
激鬱なえなえ丸 なしごき。
私個人がクビにさせられた会社の社長を思い出すほど(°_°)
ストイックに技術を磨いてくストーリーだけど、信じる力を感じる映画だった。
師匠に社会的仕打ちで返されても自分の力を信じる。社会的仕打ちをされたなんて考えてもなさそうで、ただドラムたたきたい、もう一回フレッチャーと自分の力を信じてみたい、それだけだった気もするが。
天才をつくるために、側からの評価や管理を気にしない師匠も、それを信じる弟子もすごい
師匠はほんとに恨んでる心だけだったのかもしれないが、その心を自分の才能を信じてくれてる、試されてると信じてステージに戻る。ただ単にフレッチャーがムカついて見返す ただそれだけだったかもしれない いがみ合ってる関係があとからみたら師弟関係だった。そんな感じだった。
ただそれでも天才はうまれた。そんななかでしか天才はうまれないのかもしれない。
あの社長さんに自分は応えられなかっただけなのかなぁ
新宿で見ましたが、その映画館に着くまでにクビにさせられた会社の営業でいった街並みを3ヶ所くらいとおって思い出してからこの映画を鑑賞。不思議な日でした。
あと、今日は母の日だけど、パパの愛情を感じられます。パパの愛情に支えられた天才、師弟関係でもあると思います。
母と死別してる僕はなんか応援されてる気持ちでした。
ちなみに僕がまだ天才認定されてないので星0.5マイナスです
後味悪い現実離れした映画
この映画の評価がいいのが判らない
映画.com4.2、Yahoo!映画4.3…
『1930年代、カウント・ベイシーのバンドでミスをしたチャーリー・パーカーの頭にジョー・ジョーンズがシンバルを投げつけた。その後二度と笑い者になりたくないチャーリー・パーカーは練習を重ね偉大なサックス奏者になった』この逸話を信じている完璧主義の指導者フレッチャーはネイマンに対し、テンポがずれてる事を理由に①椅子を投げつけ②皆の前で事前に聞いた母親が出て行った事をわざと言い③頬を何度も叩く、といった理不尽な暴力をする
≫≫自分に酔った子供じみた芸術家気取りしか
思えない。
理不尽な暴力を受けた後、練習の時間の無駄との理由で(チャーリ ー・パーカーの逸話を聞かされた事もあって)、大学生のニコルとも別れる
≫≫独りよがりも甚だしい
重要なコンペティション当日、バスが遅れレンタカーで行くが事故ってしまう。その事故の影響でまともに演奏も出来ずフレッチャーから『お前は終わりだ』と言われる
≫≫フレッチャーは血だらけのネイマンを見て、それでも最後通告をするのだろうか?指導者たる態度だろうか?
他にも、
フレッチャーが納得するまでドラマー3人に数時間も血まみれになるまで演奏させる
≫≫血まみれになるまでの練習が上達に繋がるはずがない
JVC音楽祭でフレッチャーに誘われネイマンは参加するが、ネイマンの知らない楽曲を指揮する
≫≫フレッチャーは自分の評価も下げてしまう
あまりにも現実離れとしか思えない
そもそもドラマーは力一杯、何時間も演奏する事が上達になるのだろうか!
題名も『セッション』は違うだろう!セッションが無いのでは?原題の『Whiplash』のほうがいい
JVC音楽祭でフレッチャーに嵌められた後のネイマンの長演奏!唯一、そこが見所か!!
また、マイルズ・テラー、J・K・シモンズの演技は良かった!
全191件中、141~160件目を表示