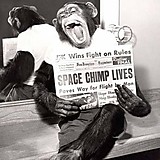チョコレートドーナツのレビュー・感想・評価
全244件中、1~20件目を表示
ゲイカップルと母に捨てられたダウン症児が差別的な社会にめげずに生き...
ゲイカップルと母に捨てられたダウン症児が差別的な社会にめげずに生きていく話。女装シンガーの熱唱にはじまり熱唱におわる。お涙頂戴ものなのに、一生懸命な自分と悪い社会という露骨で単純なつくりに、一粒も泣けなかった。これに感動した人がたくさんいるなんて、世の中は広いな。2点
何食べのケンジとシロさんに会いたくなった
1970年から50年以上経った今も彼等のような社会不適合者と思われてしまう事実はまだありますが、昔と違い大分犯罪として扱われることはなくなった。
ゲイカップルのルディとポールは育児放棄されたダウン症の少年マルコと本物以上に家庭的な家族となり無性の愛を捧げるようになる。
一人の少年を救いたいと躊躇なくマルコの手を取るルディの温かさに心震えた。しかし彼の笑顔を守りたいという気持ちが膨れ上がりその愛情が暴走し、茨の闘いに挑んでしまったのでないか。
後半はずっと裁判シーンが続き重い。マルコ少年が通う学校の女性教師だけが、ありのままの彼等を慕っていたのが救い。ただ意固地にマルコの親権を争うのではなく賢く寄り添える術を模索すべきだったのではと難しい問いに頭を巡らせる。
とにかく衝撃的な最後に心が苦しくて涙が止まらなかった。
昔々ある所に魔法の少年マルコがいました。そのマルコは、ハッピーエンドが大好きです
どれだけたくさんの人が死んで、どれだけの時を積み重ねていったら、誰もが自由に幸せに生きる時代が来るんだろう?望んで生まれてきた訳ではない、何も悪いことをしていない、命には限りがある。なぜこんなに苦しまなければいけない社会で世界なんだ?
ルディの歌、歌詞、笑顔、涙。マルコの好きなお話をするルディ。マルコの頷き、笑顔、マルコの最初の言葉:"Excuse me, I'm hungry"。幸せいっぱいのホームビデオ。小さい小さい新聞記事を手紙と共に関係者に送るポール。自分を隠し料理が上手く弁護士でハンサムなポールと、カミングアウトして自由な仕事をしている優しいルディから、日本のTVドラマ「きのう何食べた?」を思い出した。この映画と原作がヒントになったのだろうか?
キャスティング、衣装にヘアメイク、音楽、脚本、セリフ、全てがよかった。新聞記事の内容とポールの手紙に涙が止まらなかった。
かなしい
人類は少しずつではあるが成長している
救いの手を差し伸べられるか?
本当にきつい現実がここにはあって、誰が悪いとかそういう話じゃないような気もして、、、
時代が追いついてなかったような気がする。
同性愛者のカップルが薬物中毒者の息子に愛を注ぐ話です。映画にハッピーエンドを求めてしまうが故にバスタオル一枚ぐらい必要な量の涙が出ます。
誰かを助けてあげられるような心に余裕を持っていたら、助けてあげられなくても認める言葉をかけてあげていたら報われたかもしれない。
もっともっと寄り添ってほしかった!!!
やるせ無い気持ちがどんどん溢れてきます。
ルールは大事だけどそれが全てではないと思うのに譲れない気持ちを持つ人はたくさんいますよね、、
でもその気持ちもわかる気がするし、、
んー、、、とにかくみんなに観てほしい!
人生で一度は観ておいて損はない作品だと心から思いますので是非観てみてください!
(もし心無い表現をしていたらすみません💦映画の内容にを完結にまとめるのは難しいですね、、)
お涙頂戴と侮るなかれ
年のせいか涙腺が緩んで困る(笑)。
本作は、ヤク中の母親が逮捕されて天涯孤独の身になってしまったダウン症の少年と、たまたまアパートの隣に住んでいたという縁で彼を仕方なく引き取ることになった中年のゲイカップルの間に本当の家族のような愛情が芽生えるのだが周囲は理解してくれず…という物語である。
これが泣かずにおられようか。涙腺決壊である(笑)。
特にダウン症の少年マルコが涙を誘う。
マルコのポツンと寂しそうな背中が映るたびに涙腺が刺激されるのだけれど、物語もさることながらマルコ役を演じたダウン症の少年が撮影現場という緊張を強いられる場所で頑張って演技をしたことを想像してウルウルしてしまうのである。
ある意味ちょっとあざとい映画だとも言える。
ベースとなる実話はあるのだけれど、あくまでベースであって、少年の監護権を巡る裁判沙汰や、ラストに少年の身に起こる事件などは全て創作である。
物語のかなりの部分が創作だからといってこの作品の価値が減じるわけではないけれど、人によっては創作と知って興醒めしたと感じるだろうし、LGBTQに対する世間の差別的態度を強調するために話を盛っていると感じるかもしれない。
確かに本作はLGBTQに対する差別をなくそうという一種の啓蒙映画であって、物語自体はそんなに意外性はなくけっこう先が読めてしまうし、主人公たちの前に立ち塞がる保守的な人たちもかなりステレオタイプな描かれ方をしている。
一歩間違えばLGBTQのためのプロパガンダ映画になりかねないのであり、事実そう感じて拒絶反応を示す人もいるかもしれない。
でもこの作品はLGBTQのための政治的映画という枠を超えて自分の心に深く突き刺さってきた。
それはもちろん劇中のマルコ少年の健気な姿に涙腺を刺激されたというのもあるのだけれど、それよりも主演のアラン・カミングが体当たりで演じてみせたゲイの中年男性の生々しい姿に感銘を受けたというのが一番大きい。
アラン・カミングはバイセクシャルであることを公言しており、一度女性と結婚したが離婚して、その後男性と結婚している。
こういう言い方が適切かどうか分からないけれどアラン・カミングは「本物」であり、この映画には「本物」が持つ生々しい迫力が感じられるのである。
アラン・カミングは確かな演技力を持つ一流の俳優だけれど、とりたててイケメンというわけではない。もちろん顔立ちは整っているし華のある俳優なのだけれど、いわゆるハリウッド的な美男子ではない。しかも撮影当時アラン・カミングは四十代後半である。
うっすら髭の生えた中年のアラン・カミングがゲイバーで女装して歌う姿や裸で彼氏とイチャつく姿など、こう言ってはなんだけれど美しくもないし格好良くもない。
この、美しくもないし格好良くもないゲイの中年男性の生々しい姿を堂々と演じ切った「本物」のアラン・カミングの姿を見て、たとえ周りや世間から嘲笑されようと毛嫌いされようと自分自身のセクシャリティに正直に生きることの大切さ、いや、セクシャリティに限定しなくても自分自身に正直に生きることの大切さを教わったような気がして自分は震えるほどの感銘を受けたのである。
この作品は、自分に自信があって世間を堂々と渡っていける強い人たちから見れば、LGBTQの政治的主張が鼻につくあざといお涙頂戴映画ということで片付けられてしまうのかもしれない。
でも、さまざまなコンプレックスを抱えて世間の中で生きづらい思い、肩身の狭い思いをしている人たち、かく言う自分もそういうコンプレックスだらけの一人なのだけれど、そういう人たちにほんの少し顔を上げ、ほんの少し胸を張って生きる勇気を与えてくれる、そんな稀有な映画でもあるのだ。
お涙頂戴と侮るなかれ。
自分は本作の製作に携わった全ての人に、よくぞこの作品を世に送り出してくれたと最大級の感謝を捧げたい。
すごく考えさせられる作品
合同会社everfreeの代表、梶清智志です。
TikTokのお薦めで上がっていたので鑑賞してみたのですが、すごく考えさせられました。
深く胸に刺さる作品でした。
偏見や制度に翻弄されながらも、「愛すること」「守ること」に誠実であろうとする主人公たちの姿が印象的で、何度も心を揺さぶられました。
小さな行動が社会を変えていく、その連鎖の力を信じたくなる物語。
悲しみも希望もリアルに描かれ、「本当に大切なこととは何か?」と静かに問いかけてくるようでした。
ラストには言葉が出ませんでした。
ものすごく衝撃を受けるとともに、深く深く心に刻まれるものになりました。
経営者として、会社を、事業を営む者として、自分の行動を見直すきっかけになりました。
今を生きるすべての人に観てほしい、魂に触れる作品です。
大学進学も、独り暮らしも、就職も望めない
ハッピーエンドが好き
昨今のポリコレは・・・
「ハッピーエンドがいい」の言葉が・・・
作り手側の熱量と優しさを感じる
素晴らしい
差別・偏見と闘う、真実の家族愛!
初めて鑑賞し観終わった時は、しばらく動けずに感傷に浸るしかなかったことを覚えています。本当の家族とは本当の愛とは何なんだろう。ラストの結末には、胸が締め付けられる思い出いっぱいになりました。なぜ、こんなにも優しいく温かい人たちが幸せになれないのだろう…、なぜ幸せな家族になれないのだろう…。悔しさすら覚えてしまいます。
マルコの事なんかどうでもいい大人たちの、偏見と差別はいったい何なのだろうか。本当の親でない同性愛者ということだけで、なぜ裁判でそこまでする必要があるのだろうか。特にポールの上司の行動の意味が分からなかったです。
ルディが言いました。
「一人の人生の話だぞ、あんたらが気にも留めない人生だ!」
ポールも言いました。
「この世界中で誰も彼を求めていない、私たち以外は。私たちは彼が欲しいんです。彼を愛しているんです。」
言葉が深く響きます。ほんとです、なんでマルコの幸せを第一に考えてあげ無いのだろうか…。本当の母親の元に戻されるマルコは何度も言うんですよ!
「ここは、おうちでない。」
と。。。なのに、なぜ…。
本作は、このように胸に刺さる名言が本当に多かったと思います。1つ1つの言葉が深く全てに意味があります。ルディが歌う歌詞ですらも。
本当に心に残る映画でした。何度みても涙がこぼれます。ただ、本作を観て思ったのは、現代社会でも問題となっている子供への虐待から守ってあげれないのと一緒ですよね。結局、昔も今も変わっていないのかもしれないと、思わせてくれる映画でもありました。
泣きそう
全244件中、1~20件目を表示