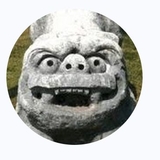愛、アムールのレビュー・感想・評価
全54件中、41~54件目を表示
老いは日に日にやってくる。
老いた2人の愛とは?と問われる作品でした。
四六時中の献身的な介護はしかも(老老介護)は、精神も肉体も疲れ果ててしまうのでしょう。
病状が進み、夫が懸命に飲ませた水妻が吐き出すでしょ。
介護している方は一生懸命なのですが、もう水分もいらないと訴えているのよ。きっと
食べる事も飲むものも欲しない、無理にそれを与えようとすると苦痛に感じる。
判断は本当に難しいけれど、そして夫が妻を叩くでしょ。ここは泣けてきましたよ。
しかし結末はあの老人のエゴのように映りました。
奥さんは若い頃は美しく、ピアノ教師で教養あり素敵な女性だった。
それは元気だった頃の老夫婦の食卓の風景で解る。
夫もそんな彼女を愛し、誇りに思い生きて来てからこそ、
徐々に崩れていく妻の容姿、混沌とした意識の状態で生きている彼女を
みるのは自分だけでいい。
でも人間は何時か老いて行く、それを誰も止める事は出来ない。まして病に倒れれば尚更に。
病院には二度と入れないでという妻の願いには誠実でしたが、これでいいわけないでしょ。
私は枕を顔の上に置いた時その気持ち解らないでもないと、
でも途中ではっと気づき枕をどかすと思っていました。
最後まで抑えたままで、ここでテンション一気に下がりましたよ。
なぜ自然に逝かせて上げなかったのか?他に方法は無かったのかと・・・。
夫も妻と共に病んで行ったのですよね。きっと。これも愛アムール。
最後に老夫婦を演じた2人素晴らしかった。
初めてハネケ作品に好印象を持ったのは持ったのだが…
昨年のカンヌ国際映画祭パルムドール、本年度アカデミー賞外国語映画賞を受賞したミヒャエル・ハネケ監督作。
正直、ハネケ作品は苦手。本作同様、カンヌでパルムドールに輝いた前作「白いリボン」も生理的に駄目だった。唯一印象に残ってるのは、「ファニーゲーム」くらい。
話題作なので、覚悟を決めて鑑賞。
共に音楽家のジョルジュとアンヌの老夫婦。ある日、アンヌを病が襲い、入院を拒むアンヌをジョルジュは献身的に介護する…。
これまでのトゲトゲしい作風が消え、ハネケ作品で初めて好印象。
老夫婦の姿を、淡々と静かに見つめる。
決して万人受けする感動作やハートフルな作品ではない。老いや死、老人が老人を介護する現実を痛々しいまでに描いたハネケの演出は深い。
ジャン=ルイ・トランティニャンとエマニュエル・リヴァは誰にも真似出来ぬ名演。
リヴァはオスカーを受賞すべきだった。受賞した「世界にひとつのプレイブック」のジェニファー・ローレンスの魅力的な演技も、強力ライバルだった「ゼロ・ダーク・サーティ」のジェシカ・チャスティンのパワフルな演技も素晴らしいが、やはりリヴァが受賞すべきだったと思う。
トランティニャンもノミネートされるべきだった。
高齢化社会の日本において、本作の題材は無視出来ない。
老人が老人を介護する。もし、二人同時に倒れてしまったら、どうすればいいのか。
映画では、二人は上流階級で、周りに娘や音楽家の弟子が居るとは言え、やがて孤立していき、その厳しい現実は変わらない。
そして、行く末に出した決断は…。
崇高な愛、深い愛などと言われているが、とてもじゃないけど美談では済まされない。
初めてハネケ作品に好印象を持ったのは確かだが、やはりこれまで同様、残酷な面も突き付けられた。
ある愛の物語
ジョルジュとアンヌの愛の物語。平穏な老夫婦に病魔が襲い、老老介護の夫婦になる。きっと、現実を見据えれば、悲壮感に包まれた作品になる。しかし、この作品では、最後に輝く二人だけの愛の世界を描いていく。子供も、友達もいない二人だけの世界。当然辛いことが全くないわけではないが、二人は幸せそうに映る。
二人の名優、シャン・ルイ・トランティニャンとエマニュエル・リバの演技が秀逸。撮影は、パリのアパートメントのみ、そこでアップを多用した撮影で、まるで二人を見守る、もう一人の家族のような錯覚を起こす。一つ一つの動作が、丁寧に細やかに描かれ、二人の積み重ねられた長い人生の思い出が刻まれていくような気がしてくる。
小品だが、忘れられない作品になりそうだ。
愛が崩れ逝く姿に人は耐え切れるのか
ミヒャエル・ハネケ監督作品は今回が初鑑賞。
この方の映画は精神的にキツイと聞いてたので今まで観るのを躊躇してました。
飛行機の機内上映で鑑賞したので削除されたシーンもあるかもだが、
(英語字幕のみだったのでまず話を理解できてるかが怪しいが(笑))
ま、とにかく初ハネケ。
感想。確かに、キツい。キッツい。
老人による老人介護という重苦しいテーマを、重苦しいまま淡々と、リアルに描写する。
リアルに描写、と簡単に書くが、映画というのは奇妙なもので、
リアルをそのまま撮ればリアリティが生じる訳じゃない。
現実と同じ表情・風景を撮ればリアルに見えるものじゃない。
その点、この映画からは物凄い生々しさを感じる。
明け方の陽光のような、白みの強い、ひんやりとした映像。
定点もしくは低速の、静かな緊張感漂うカメラ。
顕微鏡を覗き込む学者のような低い体温を感じる。
音楽を排す一方、効果音への配慮は非常に細やかでもある。
本編。
身も心も衰えてゆく妻が、誰に対しても意固地になってゆく姿が悲しい。
ピアニストという過去を持つだけに、妻は“人からどう見られるか”により敏感だったのだろうか。
過去や他人の憐みを忌み嫌うように「CDを止めて」と頼むシーンが印象的だった。
そうでなくても食事・歩行あげくは排泄まで人の手が必要になるのは誰の自尊心にも堪える。
世話をする相手と親しければ親しいほど、感謝の気持ちよりも
申し訳ない、自分が不甲斐ないという後ろめたさが勝ってしまうものだと思う。
そんな妻を介護する夫も若くはない。
不審な物音を確認しようとしてもじれったいほどの速度
でしか動けないし、妻を抱き抱える姿も危なかっしい。
彼の閉塞感が投影されたかのような、窒息の悪夢。
ピアノの録音再生を止めた時の、言い様の無い喪失感。
妻の頬をはたいた時の、後悔と疲労の入り雑じった表情。
終盤の妻の姿は見るのが辛かった。
傲慢な介護士に任せるよりは、彼女の意思をそれでも汲もうとする
夫に世話してもらう方がずっと幸せだったと思う。
けれど、夫の最後の選択は果たして純粋に妻への『愛』と括って良いものなのか。
崩れゆく妻の姿に、彼自身が堪えられなくなったのも理由のひとつではないのか。
そうだとしても、僕は彼を責める気には全然なれないのだけれど。
評価が高いのは頷けるし、良い映画だと思う。けれど……しんどい映画。
<2013/3/27鑑賞>
愛、アムール
ピンピン…コロリ、それは叶わない願い
3月28日、銀座テアトルで鑑賞。
近い将来、介護状態になりそうな人、すでに介護をした経験のある人…そんな感じのお客さんがほとんど。平均年齢は70歳くらい。
51歳の僕なんかは、小僧っこみたいな感じ。
それはともかく。
フランスにおける老老介護の現実をある意味で描ききったのだろう。
ハリウッドでは絶対できないようなアンハッピーエンドが重い。
そこに突きつけられている、現実、どう受け止めるべきなのか?
しかし、「その現実」を見る、想像することは大切だと思う。
基本的に、重くて暗い作品だが、痴呆が進むヒロインが、写真のアルバムを見ながら、「人生!」とつぶやく、あの場面にはぐっと来た。
2年半前に、85歳で亡くなった僕の父親も、母親が介護していた。
ぼけて、おむつをあてて…。風呂に入れるのも並大抵のことじゃない。
実にたいへん…。
エマニュエル・リバの熱演は賞賛したい。
包み隠すことなく描かれた「愛」
ミヒャエル・ハネケと聞くと、暴力をテーマとした映画ばかり思いつく。「ファニーゲーム」はその代表格だが、ぶっちゃけすべての映画が何らかの形で、人間の潜在的な暴力を描いていると言っても良い。一応ラブストーリーの「ピアニスト」だってアレなんだし…。
だから今回の「愛、アムール」はちょっと意外だった。そういったシーンは一切なく、むしろあまりにも閑静だから逆に怖いくらいだ。だが見ていくうちに、これは紛れもなく彼の監督作であることが分かってくる。
この映画では冒頭のシーン以外、すべて老夫婦のアパルトマンでストーリーが展開される。そのストーリーも一見ありがちなものだ。病に冒された老婆とそれを支える夫の姿を追い続けるだけ。これだけ無駄がなく、シンプルな映画なのに非常に力強いテーマを感じることができる。
一つ目の理由として挙げられるのは、ジョルジュとアンヌの老夫婦を演じたジャン=ルイ・トラティニャン、エマニュエル・リヴァの存在だ。彼らもまた映画と同じく、繊細だが芯のある演技を見せてくれる。
エマニュエル・リヴァは少しずつ衰えていくアンヌに完璧になり切っている。外面的な部分では、右半身付随の状態を演じなければならないのに、それがまったく不自然でない。少し回復したり、逆にさらに衰えを見せるときも、非常に微妙な違いを出すことで、精神的に弱っていく様をも見せている。
また静かな語り口でも、心の奥底には一人の人間としての確固たるプライドを抱えていることがはっきりと分かる。病人として扱われることを嫌がるシーンでも、ありがちな頑固者の老人ではない。夫に負担をかけているのではないかと負安易思い、衰弱していく自分の体が(言い方は良くないが)惨めで、怖いのだ。それぞれの行動から表面的ではない、深層心理が見えてくるのが彼女の演技の素晴らしい点だ。
そのアンヌの夫ジョルジュを演じたトラティニャンの演技にも脱帽した。お世辞にも「穏やかな老人」とは言えないジョルジュだが、彼の言動からいかにアンヌを大事に思っているかが伝わってくる。ジョルジュとアンヌがする日常的会話の場面はお気に入りだ。直接的なことは話さずに至って普通のことしか口にしないのに、一つ一つに愛情が感じられて微笑ましい。
だからこそ、生きることを拒否するようになるアンヌを必死で支えようとするジョルジュの姿は何とも痛ましいのだ。彼女の回復を心から願っているにもかかわらず、その瞳には常に絶望が漂っている。彼にはアンヌの行く末がはっきりと分かっているのだ。かろうじて生きてはいるものの、衰弱し切ったアンヌの姿に呆然とし、顔には疲労感と哀しみが浮かぶ。誰よりも愛しているが故に、自分以外の人には衰えたアンヌを見せようとしない。彼女に惨めな思いをさせたくないからだ。
彼のこういった矛盾した感情が映画の根幹になっていると言っても良い。題名が愛(アムールはフランス語で「愛」)とついているが、ストレートにその愛情を示すことはないのだ。あえて間接的、時には真逆の行動がジョルジュとアンヌの間の本当の愛を示してくれる。
終盤でジョルジュが取った行動はある意味で矛盾を孕んでいない。夫婦どちらの望みも叶えた形だからだ。だがミヒャエル・ハネケはその「究極の愛」を美しい演出でカモフラージュなどしない。ジョルジュの行動を美化することなく描いているから、あまりのストレートさに衝撃を覚えた。私個人は彼の心情に同調するが、監督は誰の肩を持つこともなく、かなり突き放した描き方をしている。なぜなら、感動を煽るようなことをしなくても十分感動的だからだ。むしろわざとらしい部分がないから、夫婦の感情をダイレクトに受けることになる。
エンディングは曖昧な描かれ方をしているから、人によっては釈然としないだろう。だが監督が見せたかったのは「2人がどうなったのか」という事件の顛末ではない。ジョルジュとアンヌは最後まで愛し合っていたことを描きたかったのだ。そう考えると、あれこそが最もふさわしいエンディングではないだろうか。
今回はしつこいほど「愛」という言葉を使ったが、「愛、アムール」ほどこの言葉を実感できた映画は今までにない。唯一無二の傑作である。
(13年3月28日鑑賞)
死生観を共有する相手。
またもM・ハネケの新作がカンヌでパルムドールを受賞した。
アカデミー賞では数々のノミネートと、外国語映画賞を受賞。
さぞかし残酷レベルも高いんだろうなと勝手に想像し^^;
主演のE・リヴァの演技に、冒頭から観入ってしまったけれど…
しかしすごいね~フランス人女優って。80代でも威風堂々。
夫役のJ=ルイにしたって若い頃のあの美貌(何たって男と女!)
A・エーメでなくても惚れちゃうくらいだった。
名優二人がこんなに歳をとって、愛し合う夫婦役を演じると
いうのも(しかも難役だし)とことん魅せますよ!の筋金入りだ。
だけど監督がハネケとくれば^^;
どんだけ残酷で嫌悪感を残すラストを持ってくるかと、ついつい
考えてしまうところなんだけど、それ以前にこの話はとことん重い。
老人介護問題、という部分にだけ焦点を当てて観ると、
うちもそうなんです。とか、我が家もじきに両親が…。などと
心配&懸念ばかりが浮かんでくる作りになっているのが結構辛い。
だがおそらく、妻の病を献身的に介護する夫の姿を、ハネケは
観せたかったんじゃなくて、いかにあんな姿になろうとも抵抗し、
早く死なせて。なんて必死に訴える妻の気高さ(プライド)が齎す
周囲との軋轢にどこまでこの夫が耐えていけるか、悪くいえば、
妻からの災難をこの夫に与え、傍で眺めている気がしてならない。
音楽家の娘は忙しいが、それでも父親に何度も意見をしに来る。
「なにか他にいい方法はないの?」
父親は首を振る。
「どうせホスピスに入れたって同じだ。それくらいなら俺にできる」
子供が思う親への愛情と、夫婦が背負う互いへの愛は似て非なる
ものかもしれないが、私も母の看病をする父に同じ想いを抱いた。
最近ことに身体が弱くなり始めた母は、何度も病院に行くのだが、
家のことは母に任せきりの父が、なぜか献身的に母を支えている。
やはり先立たれたくはないのだろうが、
いや、それだけでもないのだろうか?(愛、アムール)なんて思える。
老人が老人を介護せねばならない時代になった。
決して金銭に不自由のない音楽家夫婦でありながら、他人を拒み、
同情を拒み、(特に妻は)気高い自分のまま死んでいくことを望む。
妻の意志を汲んだ夫は、妻の言いつけどおり他人にひれ伏さない。
プロの介護士のお姉ちゃんに、お前は使えない女だと言い放ち、
「何このクソジジイ!くたばっちまえ!」なんて吐き捨てられても。
窓から入り込んでくる鳩は何を象徴してるんだろう、やはり自由か?
幾度も入りこんでくる鳩をついに夫は捕まえるが、すぐ放してやる。
日に日に記憶も精神も退行し、赤ちゃん返りを繰り返す妻。
泣き叫び、唸り、食事を拒否し、痛みを訴える毎日。やがて夫は…
名作「カッコーの巣の上で」と、やや被るシーンがある。
何を以て人は幸せに旅立てるのか、自分がその人の立場にならねば
永遠に理解できないことだが、私とて遺された者を苦しませたくない。
生きている歓びは、自分が自分だと分かるうちに味わえれば十分だ。
夫婦はその人の死生観にまで精通する必要があることを告げる作品。
(エンドの静寂がまたハネケ。観客も皆さん静かに出て行きました^^;)
フランス映画だなぁ。
見たくない現実をみる
ハイネ監督は僕らが見たくない現実を描く。
でも、それは決してネガティブな行為ではなく、
ポジティブな意味を込めて・・・。
そうですよね。
「ファニーゲーム」ではわけもわからないまま、不条理な暴力に蹂躙される
夫婦を。「白いリボン」では、わけもわからない出来事によってナチスドイツをおびき出してしまう悲劇を、描いていたと思う。
そして、今度はわけがわからないということはない。
誰でも経験しなくてはならない問題を提起している。
「老い」「死」そして「愛」。
突然、襲ってくる出来事にどう対処するべきなのか?
正解もないだろう。何が倫理的なのかもないのだ。
かっこよく言えば「尊厳死」なのかもしれないけれど、
夫はそのとき、深く考えていなかった。
そう考えたときはもちろん、あったろう。
でも、そのときは夢中になっていたというべきだろう。
それは衝動的なものだったと思う。
そう、人間の考えなんて、行き着くところ、計算なんてないのだ。
でも、映画としての画面は極めて計算されている。
構図はおそろしくストイックだし、音は細部に渡っている。
蛇口から流れる水の音。ページをめくる紙のおと。
夫婦の息づかいもリアルである。
そんな静謐な世界に内なる激しい息遣い。
「老い」「死」そして「愛」
僕はこんな作家を支持します。
日本でどう評価されるかは微妙
逃げないでください、ハネケさん。
老老介護の末に起こる悲劇を描いた映画ですが、他のハネケ映画同様、突然、終わります。いや、終わるというよりは、作品を作る事を放棄してしまいます。さあ、これから先は、あなたたち観客の判断に委ねられているのです。ハネケはこう云い訳しているかのようです。しかし、この監督、毎回、云い訳していますね。これで、カンヌのパルム・ドールですか。いやあ、ハネケさん、楽していますね。内容については、とにかく、痛々しい映画、この一言に尽きます。特に、二度目の発作を起こした後の、エマニュエル・リバは正視できませんでした。鳩が二回、家の中に迷い込んできますが、それが何の暗喩なのか、私には、全然、判りませんでした。もしかしたら、監督本人も判っていないのかもしれません。ここで、鳩を適当に登場させておけば、批評家の連中が勝手に深読みして、何とか云い繕ってくれるだろう。ハネケはこう高を括っていたのかもしれません。
とにかく、ミヒャエル・ハネケは現在、世界で、最も過大評価されている監督でしょう。オペラを作曲した作曲家が長大な序曲だけを作っておいて、いざ、幕が上がると、楽団員も歌手もトンズラしている。勿論、指揮者も作曲家も逃げている。
ハネケさん、そろそろ、逃げるのは止めて、本気で勝負して下さい!
全54件中、41~54件目を表示