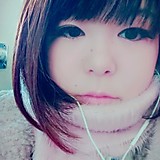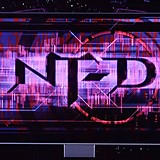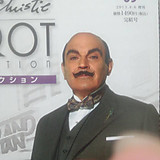インフェルノのレビュー・感想・評価
全327件中、161~180件目を表示
Not so complicated as Da Vinci Code luckily
Inferno directed by Ron Howard who also directed the other two Da Vinci Code and Angels&Demons. I couldn't really understand Da Vinci Code when watched for the first time, for I was not good at solving riddles or deciphering codes even in films, whereas my mother really enjoyed it though. And then Angels&Demons was not so difficult to follow the story that was great. This time when Inferno was released, I just hoped that I could understand as much as I did with Angels&Demons. Hopefully it was not really complicated just Tom Hanks tries to find out some clues from Dante's death mask. Although there are so many world history words that I learned when I was a student in world history classes, you don't have to know much of them cos Tom Hanks explains them a bit. Hope you all won't fall asleep in the cinema. Have fun
シリーズって大変
もう謎解きよりもアクションメインの映画に…
冒頭からノンストップ、
駆け足海外パック旅行、添乗員トム・ハンクス
なんだかドタバタした映画です
Minute to midnight. ラングドン教授のヨーロッパ紀行第三弾
原作は未読で鑑賞。前二作は先に小説読んじゃってて映画を観てすっごいガックリした経験があるので今回はあえて原作を読まずに鑑賞してみました。うん!普通に面白いじゃないですか!!
しかし、ダンテって正直ピンと来ません。前二作のキリスト教関連よりも自分とは縁遠いかも?単に自分が教養ないだけ?今だかって「ダンテっていいよね~。神曲の地獄篇マジパネェ!」なんて話を人としたことがないのですが、一般の方はやっているものなのでしょうか?ま、今回も映画の内容とはあまりダンテ関係ないですけどね。
トム・ハンクスもすっかりラングドン教授が板についてきたのですが、今回はいきなり記憶喪失!知識が売りだったラングドン教授が頭が働かないなんて!っと最初っからピンチで映画に引き込まれます。
そのピンチを助けてくれるシエナ役のフェリシティ・ジョーンズ。スター・ウォーズにも出演し、今注目されている女優さんですね。シエナが「人口増加大問題!人類滅ぼさなきゃ」って発想に影響を受けてしまうのは、一時期流行ったシー⚫ズにハマった若者を思い出しました。どちらも本人は良いことやってるつもりなんですよねー。
実際問題ちょこっと映画でも言われていたのですが、現在は6回目の大量絶滅期と言われています(ちなみに5回目の時に恐竜が絶滅してます)。地球上に生命が誕生してから生物が大量に絶滅した事件が過去に5回あって、今が6回目の真っ最中。でも、6回目がこれまでの大量絶滅と違うのは、この6回目は人間という単一の生物が原因となって引き起こしている点にあるそうです。
勿論今日明日どうこうなるという話ではないのですし、何百年のスパンの話なので実際に人類滅びる時には個人的に生きていないんですが。しかし、そんな現状を考えると変に意識高い系の人が「人類は地球にとって癌だ!地球の為に人類滅ぼさなきゃ」ってなっちゃうのもわかんなくもないです・・・なんて事を考えると、この映画のように現実に行動する人が出てきてもおかしくないのかなっと思いました。
そう難しい事を言わなくても単純に楽しめるエンタメ作品。小説とは随分違っているみたいなので、これから本を読を読むのが楽しみになるような面白い作品でした。
ハングオーバー系鬼ごっこ
エンドロールが流れるや否や本当にロンハワード監督作品なのか?と調べ直した。
トンネルを通過する辺りまで劇場内には大量の「?」マークが漂っていたし、右後ろからはイビキが聞こえてきた。何故追いかけられているか、何が目的なのかが判明する頃には、正直くたびれていた。構成が悪い。フィレンツェやイスタンブールの街並みが美しいからまだ観ていられたが、これと同じことを都会でやってたらきっと僕も寝てしまったと思う。
テンポよく進む
じっくり考えるすきも与えず次々と物語は進む。
懐かしい、美しいイタリアの風景も駆け抜ける
記憶を失っているラングトン教授同様 何が何だかわからないうちに物語は進む。
細菌の恐怖もあまり現実実がないまま 教授の活躍により世界は救われた。
よかった、よかった。
面白かったです
早い段階でぐっとのめり込んでから終わるまでずっと前のめりになってみ...
世界の人口問題について
おなじみのトム・ハンクス演じるラングドン教授シリーズだ。ミッキーマウスの腕時計も健在。となると、困難な状況に陥った教授が、持ち前の宗教学の知識と頭の回転の速さで次々にパズルを解いていくストーリーになるのは必須だし、お約束だ。そういう意味では安心感のある映画である。
とはいえ、今回はいきなり教授が怪我をしているシーンからスタートする。いったいどういう状況なのか、教授にもわからないが、観客にもわからない。そこに危険が迫り、記憶がはっきりしないままに追われて逃げることになる。教授は超物知りというだけで、特殊な能力を何も持たない普通の人間であり、暴力には極端に弱い。しかし時には蛮勇を発揮することもある。観客は教授とともに謎解きと逃避行の旅に向かうが、誰を信用していいのかもわからず、極めて心もとない心情を共有することになる。感情移入せずにいられない展開だ。
フィレンツェから始まり、ヴェニスのサンマルコ広場、そしてイスタンブールと、誰もが行きたい観光名所が舞台であるところも感覚的になじみやすい。どこも観光客で一杯だ。みんなが見ているはずの観光地に、みんなの気づかない秘密があるところがこの映画シリーズの一番の魅力である。
映画のタイトルはダンテの「神曲」の地獄篇を意味するが、ダンテのことを知らなくても、映画は十分に楽しめるようになっている。むしろ知らない方が一層面白いかもしれない。
そもそものきっかけを作った大金持ちの男性の、人類が地球上に増えすぎているという思想は、あながち間違っているわけではない。生物兵器を用いて人類の半分を減らそうという目論見は、手段として否定されるが、ラングドン教授はその思想自体を否定してはいないのだ。
地球の人口は80億に達しようとしていて、地球温暖化その他が齎す天災地変は人口増加が原因のひとつであることは誰もが認めざるを得ないところだ。「人口論」のマルサスが警告したのは食糧危機だったが、飽食の日本では、実感に乏しい。世界各地では貧困と飢餓にあえぐ地域があるのは情報として得られるし、それらの地域ではまぎれもなく食糧危機が現実である。だがそれは地球全体の問題というよりも、格差の問題であるように思われる。飽食の地域と飢餓の地域の格差だ。むしろ人口問題は、人口の増加が格差を生み出したというところに本質があるのだ。
映画はスリリングで息もつかせぬ面白いストーリーだったが、人口問題は映画で解決されはしない。戦争で人口が減るのが人間の自然淘汰だと主張する学者がかつていたが、人類は戦争を減らす方向で努力している。戦争をしないで人口問題を解決するには、子供を産まない選択をするしかない。そして高齢化が世界で最も進んでいる日本では、すでに国民がその選択をしはじめている。少子化は政策で解決できる問題ではない。人類にとってもっと根本的な、構造的な問題だ。人口増加が格差を生み、その格差が少子化を齎しているのだ。世界の人口減少の最先端に日本がある。
世界の人口増加はいつかは止まるだろう。そして減少がはじまる。そのときにたくさんの問題が次々に湧き上り、たくさんの人々が苦痛を味わうことになる。それはまさに現実のインフェルノとなるだろう。日本ではそれがもうはじまっている。
全327件中、161~180件目を表示