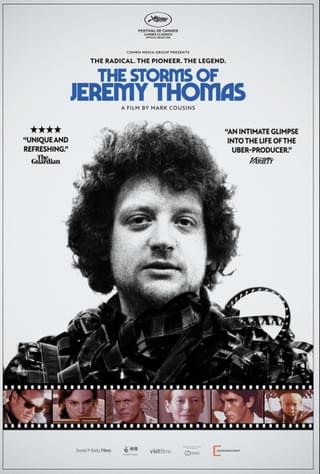十三人の刺客 : 映画評論・批評
2010年9月14日更新
2010年9月25日よりTOHOシネマズ日劇ほかにてロードショー
凄絶な命懸けの戦いにリアリティを与える「悪」の造形

何かとラスト50分のバトルばかりに注目が集まりがちだが、本作の真価はそこではない。確かに13人対300人という荒唐無稽に思える集団抗争は、単なる斬り合いを超え、仕掛けあり肉弾戦ありで娯楽マインドが炸裂する。あくまでも今風の芝居を貫く役所広司や山田孝之。東映時代劇の型を継承し流麗な殺陣で魅せる松方弘樹。脚本担当の天願大介の父・今村昌平作品を彷彿とさせる土着性を感じさせ、侍という特権階級を対象化する“山の民”伊勢谷友介。多様なキャラクターが入り乱れ、カオス状態によってこそ三池ワールドは生彩を放つ。惜しむらくは13人のうち5、6人の彫り込みは浅く、長丁場を一気に運ぶ生理も希薄だが、名誉の戦は阿鼻叫喚の図に到り、武士の矜恃に向ける冷ややかな視線は興味深い。
では肝は何か。傑作の誉れ高いオリジナル版を蘇生させ、凄絶な命懸けの戦いにリアリティを与えたもの、それは「悪」の造形に他ならない。稲垣吾郎扮する権力者は、現代の病が結晶化した姿だ。庶民を捕まえては無表情に繰り返す陵辱と殺戮。誰でもよかったと言わんばかりに残虐非道の限りを尽くし、太平の世に生の証しを求める。虚無の果てに到達する狂気。討たねばならぬ存在として、国民的アイドルのメンバーの一員を抜擢したことは快挙といえる。これは決して“時代劇版「クローズZERO」”ではない。原作ファンやティーンへの媚びへつらいが常態化した日本映画の製作環境にあって、仄かな希望を抱かせる事件をゆめゆめ見逃してはならない。
(清水節)