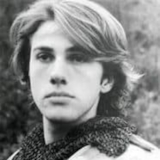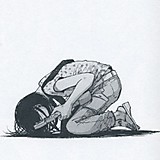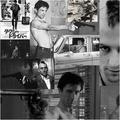インビクタス 負けざる者たちのレビュー・感想・評価
全20件を表示
負の連鎖を止める人
オープニングからエンドロールまで最高
なぜ今まで見てこなかったのか、、
ネルソンマンデラは本当に偉大、やられたらやり返すの精神では平和は訪れない。誰かが止めなければならない負の連鎖を止めた。
自分の魂の指導者指揮官は自分という言葉は自省する上でも自分を奮い立たせる意味でも本当に力がある言葉だと思った。
がんばれ!ではなく、○○がんばれ!
ただの横断幕じゃなく、飛行機に書いてあるメッセージ。アンセムは試合前だけじゃなくて試合中の方が力になるかもしれない。メッセージは言葉だけじゃなく伝え方も大丈夫なんだと思った。人の熱意をコントロールすることが指導者の重要な資質でこのあたりのセンスもすごく感じた
負ける時とは自分の本意でない行動を自分が取ってしまった時なのかなあと思った。
ナショナルスポーツを戦争の代わりに行うのはやはり一つの解決策だと思う、国家間で競うことはやはり無くならないから。
ラグビーに根付くノーサイドの精神とスポーツの持つチーム、国としての一蓮托生の性質に目をつけたのはすごい。ましてや白人のスポーツを黒人の大統領が尊重する姿勢を最初に見せることによる効果は絶大。決勝の相手がオールブラックスなのも出来すぎ
クリントイーストウッド、モーガンフリーマンにはずれなし
素晴らしい大統領
................................................................................................
南アで黒人勢力が白人勢力を逆転しネルソンマンデラが大統領になった頃の話。
黒人勢力から、ラグビーナショナルチームの改名案が出た。
チームの応援主体は白人で、黒人の白人に対する憎しみはすさまじかったのだ。
しかしそれをすると憎しみの連鎖になる、チームを存続させると説くネルソン。
最も大事なのは白人に復讐することでなく、歩み寄って共に国を発展させること。
そしてチームは存続し、何とW杯でオールブラックスを破り優勝。
大統領府で最初はいがみあってた白人と黒人もラグビーを通じて仲良くなった。
................................................................................................
脚色はされてると思うが、ネルソンマンデラってすごい人やなと思った。
そのことにチームのキャプテンのである白人のマットも感銘を受けてた。
白人に30年も投獄された過去があるのに、何故許すことができるのか、と。
人として深いものがある。モーガンフリーマンは適役だと思った。
当時の南アの人達は大統領やラグビーチームに酔いしれたことだろう。
優勝直後の大統領とマットの会話がいい。
「優勝で国に誇りをもたらしてくれてありがとう」
「誇りを持てる国にしてくれてありがとうございます」
この映画を見た影響で、2019W杯は南アを応援してた。
そしたら見事優勝!同時に、ラグビーが面白いってことを知ったわ。
俺軍、暁の出撃! くたばりません勝つまでは。
1995年ラグビーワールドカップの顛末を、南アフリカ共和国大統領ネルソン・マンデラの視点から描いた、史実を基にした人間ドラマ。
監督/製作は「硫黄島2部作」や『グラン・トリノ』の、言わずと知れたレジェンド映画人クリント・イーストウッド。
主人公ネルソン・マンデラを演じるのは『ショーシャンクの空に』「ダークナイト・トリロジー」の、レジェンド俳優モーガン・フリーマン。なお、フリーマンは製作総指揮も担当している。
南アフリカのラグビー代表チーム「スプリングボクス」のキャプテン、フランソワ・ピナールを演じるのは『オーシャンズ』シリーズや『ボーン』シリーズの、名優マット・デイモン。
南アフリカ🇿🇦の政治状況は言わずもがな、ネルソン・マンデラ大統領のことすらほとんど知らない状態で観賞。
この映画の非常に優れている点は、その情報整理力。
90年代の南アフリカがどういう状況だったのか、ネルソン・マンデラがどういう人物でどのような人生を送ってきたのか、南アにおけるラグビーの立ち位置がどのようなものなのか。
このような要点が纏まっており、なおかつ説明的でなく描写されているので、非常に観やすい。
政治劇は事前の知識が無いとよくわからんということになりがちだが、本作はほぼ知識0の状態でもちゃんと理解出来るように構成されている。
この辺りはさすが名匠クリント・イーストウッドといったところでしょうか。
スポーツを取り扱っている作品ではあるが、決してスポ根映画ではない。
友情・努力・勝利が描かれていない訳ではないが、そこはあくまでもサラッと流される。
また、BGMやサントラで一気に盛り上げるというような演出もほとんど無い。
ラグビーというハードなスポーツを描いた映画でありながら、全体の温度は驚くほどにクールで淡々としている。
ラグビーワールドカップの優勝。
これがこの物語の目的である。
結果として南アはワールドカップを優勝する訳だが、実は大会の結果とかこの映画においてはどうでも良い。
この映画のメッセージは「インビクタス」=「不屈」。
勝てなくても良い。しかし、屈服だけはするな。屈服しさえしなければ、今は無理でもいずれ強大な壁に風穴を開けることができるかもね、ということが主題な訳なので、無理にラグビーの描写を増やしたり、過剰に盛り上げようとしたりしなくても良いのです。
むしろ淡々と描写を積み上げていくという本作の作風とネルソン・マンデラの人間性はピッタリ。
この静かな作風により、マンデラという人間の生き様がより克明に浮かび上がってきているように思います。
間違いなく良く出来た映画。まぁちょっと思ったのは、あまりにも楽観的に過ぎるかもなぁ、ということ。
アパルトヘイトの撤廃は、新たな差別と格差を呼び起こし、今やネルソン・マンデラの掲げた「虹の国」は崩れさり、新しい人種分離の問題が噴出している。
映画の中だけでも…という思いもわかるのだが、ちょいと安易な解決を提示しすぎている気もする。
ウェルメイドな映画だとは思いますが、めちゃくちゃ面白い!とか、燃える!とかそういう感じではない。
言い方は悪いが、いかにも老人の撮った映画という感じ。
テンポがゆったりとしており、ダッシュッ!💨というより散歩〜🚶って感じの映画。
しっかりと腰を据え、ネルソン・マンデラの人生に思いを馳せながら観賞しましょう😄
※この映画の解説をライムスターの宇多丸さんがしており、それが某映像サイトに転載されていたんだけど、宇多さんの読み解きが凄い!👏
言葉、詩、歌、舞踊…etc。そういった「表現」がいかに人間を鼓舞し、持ち得る力以上の実力を発揮させるのか。この映画ではそれが一貫して描かれている…。なるほどなぁ。
横と後ろにしかパスを出せないラグビーというスポーツが、南アという複雑すぎる国家の政治の比喩として作用している。横と後ろにパスを出しながら、少しずつ前進していけば、いずれは勝利を手にすることが出来るかもしれないのです。なるほどなぁ。
※※日本が産んだ最高の詩人、「マーシー」こと真島昌利。私が最も尊敬する人物です🎸
彼の楽曲に「俺軍、暁の出撃」(1996)というものがあるんだけど、その中にこういう一節がある。
俺は俺軍の大将
俺は俺軍の兵隊
俺は一人でも軍隊
最強無敵だ
この歌詞、ウィリアム・アーネスト・ヘイリーの「インビクタス」から拝借していたのか!
とこの映画を観ていてピン💡ときました。
まぁ偶然の一致かも知れんが、マーシーならこの詩を知っていてもおかしくはない。
流石マーシー、文学の素養半端ねぇっすわ…。
タイトルなし
当時の南アフリカの状況をよく描き出している。想像を絶する差別社会と推測されるが、それを色濃く扱う訳ではなく、マンデラの大らかさ、赦しの心がドラマに爽やかさを与える。モーガン・フリーマンはハマり役。実話ということで、ラグビーW杯優勝は国を一つにまとめるのにこれ以上ない大きなインパクトを与えたのだと映画からわかった。
大統領の詩
クリント・イーストウッドさんの映画なので安心して鑑賞。
観る時のこういう心理状況が評価につながる、ってこともあるけど、やっぱり良かった。
でも、頭悪い私は、肝心なとこに気づけなかったです、、
大統領と主将のお茶会で、
「バスの中では無言です。それぞれが気持ちを作って、
できたところで曲を流す。
みんなで歌詞を聞いていると高揚する」
という話が。。
その後、大統領が「インビクタス」という詩を書いて渡すシーンがあり...
ここで普通の人はピンとくるんですかね!?
特に英語圏の方は多くの方が知ってるんですかね、、
邦題にご丁寧に「負けざる者たち」と説明書きまであるのにそういう内容の詩だと気付きませんでしたorz
この詩がウイリアム・アーネスト・ヘンリーさんの詩で有名な物には気づけなかったけど、
ただ、、
バス車中のエピソードの「振り」があっただけに、詩を受け取った主将がバスの中でこれを読みあげるか、チームのみんなに回して読ませるかして士気を上げるシーンがくるに違いない、と思ってしまった。
決勝の相手がニュージーランドで、相手の強さの秘密は「ハカ」である、というのも振りのひとつだと思って、ハカ対策としても期待しちゃったんですよね...
実際には、そんな捏造シーンにカタルシスを求めなくても、詩「インビクタス」とその内容を知っていればさらに感動出来たわけで。
また忘れた頃に鑑賞してリベンジしよう。。
マンデラとラグビー
ネルソンマンデラの話というより、ラグビーワールドカップの話。
南ア初の黒人大統領誕生、それだけでもすごい事なのに、同時期に南アでワールドカップが開催され、しかも地元南アが優勝という、事実は小説よりも奇なり、をそのまま準えた出来事。
ラグビーワールドカップはかなり無知な自分は、前回大会に日本が南アを撃破した感動に鈍く、ていうか日本以外はラグビーとかサッカーもそうだけど大体強いから勝つのは大変だよね、くらいにしか思ってなかったけど、この作品でその事がどれだけすごい事かよく分かった。
サッカーで言えば、今年のベルギー戦で勝っちゃうくらいすごい事だ。
この作品見終わって、当時のラグビー記事を探しまくったくらい、これホント?、と驚いた事が嬉しかった。
メインはマンデラのアパルトヘイトとの闘いなので、彼の不屈の心が、南アラグビー代表に伝わるという盛り上げ方も良かった。
こーゆー話を観たら、ラグビーにしろサッカーにしろ、日本がワールドカップで優勝するとか、絶対考えられないとも思ってしまった。
マンデラ程ハングリーな首長は不世出。
タイトルなし(ネタバレ)
ウッドくんの映画にはやっぱりやられました。
黒人のマンデラが南アフリカの大統領になった直後~ラグビーのワールドカップ優勝までの話。
白人の象徴のチームだから黒人からしたら、憎むべきチームのはず。それを排除するのではなく、それを認めてもらおうとする態度。白人からも黒人からも認められる。
30年も刑務所にいたのに、それを赦すココロ。それは誰にでもできることではない。そのココロが、南アのラグビーチームを強くしていったと言っても過言ではない。
マットデイモンが窓に向って30年間の牢獄人生を思うシーン。
「動」が多い中で、「静」だけど力強さがあふれていて、それが試合につながっていく。
ただ練習して強くなっていくのが真の強さではない。チームとして、いや国の代表として1つにまとまっていく。肌の色とかが問題ではなく、お互いラグビーを愛する仲間としてまとまっていく。それこそチームが強くなる秘訣なのだろう。
試合終了間近で涙腺刺激されました。
人種を越えて
人種を越えて国が1つになり、世界に誇れる国へ…。
スポーツを政治的に利用した例は過去にも多い。
最も痛ましい例は、1980年と1984年のモスクワとロス五輪だろう。
但し五輪に関して言えば、ヒットラーを始めとして、国威発揚・経済発展を筆頭に民族統一等。五輪の理念であるアマチュアリズムとはかけ離れた。開催国が世界に対して示す《思惑》が、先ず第一に目立つ大会として進化を遂げて来た。
1990年代に、《アパルトヘイト》により、国際的に孤立した南アフリカ共和国からは、毎日の様に国中で暴動が起きていたのを報道していた。
冒頭にて、代表選手がラグビーをしているが、道路を隔てて黒人の少年達はサッカーに興じている。その間を行くネルソン・マンデラ。
「この屈辱を忘れるな!」と語る男。
しばしばスポーツに於いては“奇跡”が起きる。
ちょっと場違いな例えかも知れないが、以前『元気が出るテレビ』で放送された、アイスホッケーのエピソードは良い例かも知れない。
一度も勝った事が無いライバル高校(相手はライバルと思っていない)に勝つ事を目標に番組で追い掛け、その結果奇跡的な勝利を収める。
まさにスポーツは“筋書きの無いドラマ”だと言う事を、実感した企画だった。
敢えて理由を考えれば、その場の異様な雰囲気に、相手が飲まれ込まれた結果と言える様な出来事だった。
テレビ放送によって人気となり、物凄い応援で個人のスキル以上の力が発揮されたとも言える。
その場の応援によるエネルギーのパワーとゆう奴は馬鹿に出来ない。
そんな例えとして、YOU TUBEでじっくりと見られるが、数年前の近鉄バッファローズが優勝した試合に於ける、近鉄北川のサヨナラ満塁ホームランが良い例だ。
始めは観客も諦めムードだったのだが、徐々にボルテージが上がり、最後の盛り上がりの物凄さたるや凄まじい。
おそらく、1995年のラグビーワールドカップに於ける決勝戦での盛り上がりも、この様な観客のパワーが後押しをしたからだと思う。
ネルソン・マンデラは、ラグビーとゆうスポーツを通して、人種を超え民族が1つになる事を願った。
決して“政治的”にスポーツを利用した訳では無い。
27年間投獄されながらも、人を赦す気持ち。
主将役のマット・ディモンが、マンデラが実際に投獄されていた房を自分の目で見て、その想いの凄さを実感する場面こそが、この映画に於ける一番重要な場面と言える。
その想いが、試合後に交わす2人の会話に表れる。
我々が、世界に誇れる民族で有る事を宣言する如くに…。
今、新国歌を白人と黒人が一緒に歌い、試合展開には一喜一憂する。
ラストシーンはファーストシーンとは違い、みんながボールを手を使いパスする。
代表選手の活躍が国民全員の意識を変え、やがては人種の壁も取り除かれるであろうとゆう希望に溢れている。
ところで、監督クリント・イーストウッドは、今回いつにも増して。《ちょちょい》と言った感じでこの映画を作ってしまっている。一体どうなっているんだ…。映画ってそんなに簡単に製作出来てしまうモノなのか…。
この作品の後で、既に2本作ってるって情報も有るし※1…。そのフットワークたるや、我々がどんなにタックルしたところで、いともたやすくスルリと交わされてしまう。
全く恐ろしい爺様だ!
※1 ご存知の様に『チェンジリング』と『グラントリノ』の超ド級傑作。
その後も製作意欲に全く衰えを見せない。
(2010年2月16日新宿ピカデリー/スクリーン6)
心が洗われる
良い指導者・リーダーの、あるべき姿とは。ネルソン・マンデラの、人を赦す心の広さ、自分の信念をブレずに周りに示せる強さに、心を打たれる。
そして、そんな彼に感化され、変わっていく人々が描かれる。
黒人と白人のボディガード達の壁がなくなっていく様子や、ピナールがチームを良くまとめていく様子に感動した。
観終わったとき、心が洗われる様な気分になる映画だ。
いつのまにか応援してました
ハッピーエンドの作品でしたが久々に良作でした。
クリントイーストウッドの作品はいつも日々の生活や生き方を考えさせてくれますね。本当に感謝です。
マットデイモンは周りのラガーマンより小さかったですが彼らに負けない肉体美ですごかった。いつもと違ってスポーツマンでもうまく演じてますね。
モーガンフリーマンはネルソンマンデラ役は適役でしたね。ショーシャンク同様失礼ですが囚人似合いますね。ゆっくりとはっきりと人に語りかけるように話す姿はまさにプレシデントでした。
アパルトヘイト後の世界ということでアパルトヘイト時代のマンデラを回想とかで長くやると思いきやほとんどしなかった。それが良かったと思う。しかし,その後ということで歴史上の差別に苦しむ人々の生き方が描写されてた。国の機関から民衆の家まで長く続いていたアパルトヘイトが残したものの大きさを痛感しました。やはりアメリカの黒人差別より後なので現代の差別に対して考えさせられるものでした。ラグビーというスポーツを通して人は変わっていけるものなんですね。感動しました。
ありがとうございました。
今年一番の傑作!これを見ずして傑作というなかれ!
はっきりいってさほど期待はしていなかった。しかし観終わった際に私の両眼からあふれる涙が止まらなかった。久しぶりに感じた作り手のメッセージ。実話を元にしたというだけでなく、モーガンフリーマン=ネルソン・マンデラそっくり感がこの映画を傑作にしています。最後に実在のシーンがありますが本当に似ている、今や彼以外にネルソン・マンデラは演じきれないと断言してもいいくらい。ストーリーも秀逸(って実話を元にしていてもやっぱり脚本家が良かったのでしょう)最期まで飽きずに観ることができました。30年近く牢獄に閉じ込められても国の事を考え、復讐は国の為にならないと私情を捨て発展に尽力する。国の大きな問題アパルトヘイト本当に素晴らしい人物に描かれていますがモーガン・フリーマンの演技故でしょう。マット・デイモン扮するラグビーチームの主将も本当に良かった(少し背が低すぎますが)絶対に打ち解けるはずのない黒人と白人がスポーツ(ラグビー)の元に一つの国家として打ち解ける。分かっていても最期のシーンは鳥肌が立ち涙が止まりませんでした。最後にもう一度言いますが絶対に観た方がいい。感動します。いやー久しぶりに泣いたわ・・・。
良い!の一言!
南アフリカ初の黒人大統領、ネルソン・マンデラ。
彼のことをそんなに知らずにこの映画を観て、色んなことを考えました。
ずっと迫害され続け、30年近くも牢屋に入れられ、それでも尚、白人は憎むべき相手ではないと国民に諭すマンデラ大統領。
誰かがこういう行動を取らなければ、負の連鎖がこの先何世代も続いてしまう。
白人を許そう、アパルトヘイトを許そう、許すことで自分達の強さを見せる。
そんなこと言ったら、同胞からさえも見放されるかもしれないのに。
マンデラ大統領は、全ての南アフリカ国民を信じていたんだなー。
その気持ちが白人にも黒人にも伝わったことが、観ていてとても嬉しかった!
彼が大統領に選ばれて、その次の年の自国開催のラグビーのワールドカップで優勝するなんて、なんてドラマティックなんだろう。
彼が選手を奮い立たせたというのもあるだろうけど、こういう波を引いてくる彼の運気というか、カリスマ性の証明というか、やっぱりマンデラ大統領は偉大な人だなって思いました。
英語のアクセントはキツイけれど、最初から最後まで中だるみすることもなく、一気に最後まで集中して観れました。
本当に良い映画。南アフリカのこと、もっと知りたくなりました。
カッコいい男の友情に感動
ここ最近のクリント・イーストウッドの作品は、
どこか暗い業のような翳をまとうものが多かったように思うのですが、
これはめずらしく明るく爽快な作品です。
とはいえ、もちろんイーストウッドなので、
単細胞に「勝利」に向かって突き進む、ありがちなスポーツものではありません。
ここで描かれているの「勝利」は、単にラグビーワールドカップの勝利ではなく、「人種差別」への勝利。
そしてその方法は、力ずくで相手をねじ伏せるのではなく、
とことん赦し、認めていくというものです。
27年の投獄生活から解放されたマンデラ(モーガン・フリーマン)は
94年に南ア初の黒人大統領となる。
アパルトヘイトが撤廃されたとはいっても、まだまだ人種差別が根強く残る同国で、
ラグビーチーム「スプリングボグス」は、白人優位主義の象徴だった。
翌年、ラグビーワールドカップが同国で開催されるにもかかわらず、
国際試合で負け続きのチームに、
黒人勢からは「チーム名とチームカラーを変えろ」との声が高まる。
しかし、そのチームが同国白人の宝であることを理解していたマンデラは
チームをそのまま存続させることを宣言。
そのかわり、キャプテンのピナールを呼んで
「ワールドカップで優勝してほしい」と告げる。
実際に会ったマンデラに深い感銘を受けたピナールは、
一致団結して優勝を目指すことを誓う…。
マンデラが偉大であることは言わずもがななのですが、
典型的な白人家庭(父親はかなりの差別主義者)に育ったのに、
素直な心でマンデラに共感し、不思議な信頼と友情を築いていくピナール、
素晴らしいです。
まさにスポーツマンの鑑☆
このお話は実話なので、結果はわかっているので、
イーストウッド監督のこれまでの作品のような
「この先どうなるんだろう」というハラハラはありません。
でも、人種差別は必ずしも、白人⇒黒人だけではなく、
黒人⇒白人もあるのだということ、
そして、どちらにしても力で対抗することは悲劇の連鎖を生むだけで、
その先にある「赦し」を描いたこの作品は、
色合いは違っても、やはり「グラン・トリノ」のような作品の
延長線にあるのではないかな、、、と思いました。
と、そんなコムズカシイこと考えなくても、
“カッコいい男”を堪能するだけでも十分すぎるくらいですが♪
無臭のイーストウッド。
あのイーストウッド卿が描いた作品にしては、
まったく彼の臭いが(すいません、こっちの字で^^;)
漂ってこないストレートで爽快な作品だった。
私もそうだけど彼のファンからすれば、
お~そうきましたか。という印象を持った気がする。
いや~別に彼がひねくれ爺とかそういうことでなくて、
(言ってますけども^^;)
今回はマンデラという偉大人物を掘り下げるにあたり、
自らがへりくだって演出してみました…という感じか。
よく纏まっているし、本当に爽やかなラストを迎える。
第一こんなラストが珍しい(実話なんだから当然です)
というわけで、あのグラン・トリノから一転、
何でもこなしてしまう卿が、また佳作を撮ってしまった。
自分の身内に銃を突きつけていた人間を警護に付け、
国家の恥とまで言われた差別象徴チームを援護する。
マンデラという人は、どれだけ器が大きいんだとまで
思えるが裏を返せば根っからの政治家。目先の利益
より将来を見据えた展望策を練るような人物だった。
これだけ国民のことを考えていても、自身の家族
問題は解決できないまま…という部分がとても切ない。
そんな彼の信念を知れば、フランソワも共感するはず。
今までこんな人物に逢ったことがない。と語るシーン、
本当にその通りだと思った。だから国が変わったのだ。
マンデラとは私生活でも交流のあるM・フリーマンは
彼がのり移ったかのような会心の演技。素晴らしい!
フランソワ役のM・デイモンは身体から作り込んで、
こちらもまた素晴らしい演技。文句のつけようがない。
たった二時間で全てを描くのは難しいところだが、
そつなく纏めたイーストウッド卿のお手並みも鮮やか。
彼の臭いがした部分といえば(こだわってるな~私も)
冒頭の不穏なワゴン車の猛走シーンと、
ラストの黒人少年と白人警官がにじり寄るシーン。
ドキドキさせといて、スパッと落とす、遊び心?のある
演出手段がやはり巧い(そこが好き)と思わせてくれた。
ただ好き好きでいえば、私は「グラン・トリノ」のが好き。
(加齢に負けざる卿でいて下さい。臭いはいいですから)
最近のイーストウッドらしい作品
この作品、大変面白かった。
学がない私はこのストーリーがフィクションかノンフィクションかなどどうでもよい事です。
要は面白いか否か…。
レビューすら書く気がしなかった『アバター』よりも(ジャンルは全く違うと思いますが…)よっぽど優れた作品だと感じました。
最近の作品でしょうかはストーリーは二の次、CGの映像技術を観に行っているかの様な作品全盛の中にあってこのような作品があることに『ほっ…』とした次第です。
監督が何を言わんとするか判る…ような気持ちになります。
追伸
ボーイング747があのような形で絡んでくるとは…。
イーストウッド恐るべし…。
熱い男達の映画でした
予告から気になっていて今日観てきました☺
人種を越えて国を一つにしたい、一人の男のその思いが人の心を変えていく。。。そんな実話をもとにしたストーリー🌀
最初は反発していた人々も次第にラクビーを通じてひとつになっていく感動のストーリーです。
ええ、感動のストーリーのはずなんですけど、熱い試合に熱中しすぎてついつい感動するのも忘れ応援してました😅
しかしなんでしょうね。。。いまいち誰に感情移入したらいいのか最後までわからなくて泣けなかったんですかね?まぁ泣いてる人もいませんでしたけど🌀隣の夫婦の旦那さんはイビキをかいて寝てるし、後ろのおじさんは座席を蹴ってくるしでイライラしてたのもあるんですけどね😅関係ないけどマナーは大切にしてほしいです💨
てかサントラが平原綾香さんのジュピターに似てるなと思ったのは私だけでしょうか⁉気になって気になって仕方なかったです。ちょくちょく日本語?みたいな言葉も聞こえてきて気になりました🌀耳の錯覚ですかね?
インヴィクタス 負けざる者たち
映画「インヴィクタス・負けざる者たち」
ネルソン マンデラが27年間捕らわれていた獄中から出所した日から20年たった。この記念すべき日、2月11日 南アフリカでは 大規模な祝典と人々のマーチが行われた。マンデラとともに出所した かつてのANC闘士は マンデラの護衛官になったが、晴れ晴れした顔で、ニュースのインタビューに答えていた。
南アフリカ、この国の国歌は 3つの言語で歌われる。はじめに黒人の間で使われているBANTOUという先住民族の言葉で、次に 白人アフリカーナが使っているドイツ語をベースにした古いダッチの言語で、そして、最後に英語で同じメロデイーを歌う。黒人も白人もなく、マンデラのいう虹色のネーションが、声を合わせて 3つの言語で国歌を歌うのだ。
映画「インヴィクタス・負けざる者たち」(原題 INVCTUS)を観た。
79歳のクリントイーストウッドが監督、制作した30作目の作品。ネルソン マンデラが アパルトヘイトの南アフリカで大統領に選出され、それまでバラバラだった国民を一つにまとめる感動的な実話だ。原作は、ジョン カーリンの「PLAYING THE ENEMY」。
キャスト:ネルソン マンデラ:モーガン フリーマン
フランソワ ピナール:マット デーモン
ストーリー
1990年 ネルソン マンデラが27年ぶりに刑務所から出所するところから 映画は始まる。国民大多数の黒人が熱狂してマンデラの出所を祝う一方で、白人達は、テロリスト マンデラが出てきやがった、、、と舌打ちする。彼の出所は 長年の黒人達ANC主導の公民権獲得運動や、国際社会によるアパルトヘイトに対する嵐のような激しい非難と経済封鎖の結果だった。その後 事実上、アパルトヘイトは廃止され、初めて黒人に投票権が与えられ、民主選挙が行われる。圧倒的な支持によって、ネルソン マンデラが大統領に選出される。
マンデラはユニオンビル 大統領官邸に初出勤した朝、大慌てでデスクを片付けで出て行こうとする白人官邸職員たちを引き止めて、君達の能力と経験を新しい国作りのために、協力して欲しいといって、おしとどめる。白人の大統領護衛官たちも留まる。それには黒人護衛官たちは、納得がいかない。昨日まで自分達を拘束し、拷問し、獄中に送り込んでいた連中が マンデラを守れるわけがない。大統領の命を危険に曝すのか。怒る黒人護衛官を前に、マンデラは 懸命に説得をする。国を変えていくには、まず 憎しみを捨て、自分達が変わらなければならない のだと。
スポーツ協議会は 今まで事実上黒人に道を閉ざしていた 南アフリカ代表のラグビーチーム スプリングボックの廃止を決議するが、マンデラは それを覆す。スポーツを通じてこそ人々の心は ひとつに結ばれる。南アフリカはアパルトヘイトのために、長いこと国際試合から締め出されていた。マンデラは スプリングボックを1995年のワールドカップに参加させ、公式会場を南アフリカに招聘することで アパルトヘイトで病んだ国民の心をひとつに結び付けたいと考えていた。
まずスプリングボックの主将、フランソワ ピナールを官邸に呼んで話し合う。当時、スプリングボックは 国外試合に出てられるようになっても 惨敗を繰り返していた。また、フランソワ ピナールには はじめ、マンデラのラグビーで国民の心を統合するという夢が 理解できなかった。何故 ラグビーか。半信半疑のピナールはマンデラから手渡された イギリス詩人ウィリアム アーネスト ヘンリーの「インヴクタス=征服されない」という詩を読む。
やがてピナールは マンデラが収容されていたロヘ島の監獄を訪ね マンデラが27年間すごした監房を訪れる。そして、小さな監房でインヴィクタスの詩に支えられ気高い精神を維持し続けたマンデラの偉大さと彼のラグビーにかけた夢に、心をうたれる。
マンデラの 黒人でも白人でもない、虹色の国民が心を一つにして新しい国造りをするという信念にインスパイヤーされたピナールは 黒人のBANTOU語で歌われる「南アフリカに神の祝福あれ」という歌をチームの全員に手渡す。
1995年ワールドカップに向けて強化訓練が始まる。ゲームを南アフリカで、というマンデラの熱心な招聘要請の結果、ワールドカップの決勝戦は南アフリカで行われることになった。
チームはまず、オーストラリアを破り、遂に 決勝戦で、ニュージーランドのオールブラックとの最終決勝戦で勝ち抜き優勝する。熱狂するに虹色の国民たち。
と、いうストーリー。
本当にあったことで、本当に感動的な決勝戦だった。
この映画を観なければならない理由が3つある。
ひとつは
ネルソン マンデラの偉大さを改めて映像をと歴史的事実をとおして確認する、ということ。マンデラの自分が受けた弾圧や差別を憎まず、人種に拘らず 暴力に頼らず 差別を乗り越え国を造った という偉業に心打たれない人はないだろう。昨日2月11日のニュースで ノーベル平和賞のツツ司教が、「すべての国がマンデラをもっているわけではない。南アフリカはラッキーだった。」と述べている。本当にそうだ。
マンデラの精神の高さと、それに伴う実行力は、となりのジンバブエに比較すると よくわかる。ムガベ大統領とジンバブエ国民の悲惨な状況が悲しい。
またマンデラあとを引き継いだ、このあとの大統領でさえも、この悪名高いジンバブエに癒着して 腐敗が進んでいる。4人の妻を持つ現大統領の醜悪な姿、、、。暴力が 日常茶飯事で、ヨハネスブルグはいま、世界で一番治安の悪い土地だ。エイズの広がりも止められない。そんな時だからこそ、過去を振り返り マンデラの歩んだ道を明らかにすることに意味がある。
2つ目には、
この映画はクリント イーストウッドが79歳で30作目の作品だということ。イーストウッド すごい。
イーストウッドが「ローハイド」で ちょいワルのカーボーイだったころからのファンだ。「ダ-テイーハリー」に胸ときめかせ、「マデイソン橋」でよろめき、「ミリオンダラーベイビー」や「ミステイックリバー」で 監督としての彼を見直した。昨年の「グラントリノ」はいまだに私のなかで一番好きな映画のひとつだ。
彼は偉大だ。おもしろい話がある。
彼はワーナーブラザースに、もう40年も自分のオフィスを持っている。数年前、新しく社長に就任した男が イーストウッドに電話してきて、「挨拶にいって、僕から君にちょっとした注文をしたいんだけど、何時が良いかね?」と聞いたら、イーストウッドは、「いいよ。何時来ても パラマウントのオフィスにいるからね。」と答えたという。新社長の「ご注文」や「ご意見」など聞くつもりはない。社長に従わなければならないなら、さっさと辞めてパラマウント社に移るゼーィ というわけだ。製作者として 自信に満ちた 権威をきらうイーストウッドの姿勢をよく表したエピソードだ。かっこいい。
3つ目は
この映画がラグビーの映画だということ。
ラグビーは良い。最高のスポーツだ。子供の時から大好きだった。
正月の早慶戦は必ず見ていた。慶応が力をなくしてからは 早明戦が、全国一の勝者決定戦だった。早稲田の藤原、明治の松尾兄弟。忘れられない顔がつぎつぎとよみがえってくる。
ラグビーは肉弾戦で、格闘技に近い。それでいて走るのも早くないといけない。ニュージーランドのオールブラックでは 体重が100キロ以上なのに、100メートルを10秒で走るマオリの選手がぞろぞろいる。オーストラリアのワラビーズも同様だ。
この映画では ラグビー戦闘シーンの迫力がすごい。ラグビー好きな人は絶対観るべきだ。よく観客席でみていると、ボールを持った選手が わざわざ敵が待ち構えるところに突っ込んでいくのが、不思議に思えるが このフィルムを観て フィールドに、選手と共に立ってみると デイフェンスの壁を破るのがどんなに 難しいかがわかる。何と広いフィールド。固いデイフェンス。ボールをどこに渡したら前に進めるのか、、、。もう自分がラグビーをやっているような臨場感だ。カメラワークが素晴らしい。スクラムを直下から見た映像の迫力にゾクゾクする。後半戦のスクラムの繰り返し。選手達の背骨のきしむ音がする。荒い息、声にならない呻き。肩と肩がぶつかり合う鈍い音。まさに、これがラグビーだ。これほどラグビー選手に密着してフィルムを回せる人は他にないのではないだろうか。さすがに、これがイーストウッドなのだ。すばらしい。
現代史の奇跡みたいな人、人類の宝、ネルソン マンデラが ラグビーに夢をつないだ映画を イーストウッドが撮ったなんて、こんな ザ ベストがそろった映画を観ないで済ませる人がいるなんてもったいない。俳優のマット デーモンがよくチームで泥だらけになって 実際スクラムも組んでパスもしていた。オールブラックもワラビーズも出ていた。
フィルムの最後に本当の1995年に優勝したときの選手が出てきて それも良かった。というわけで、この映画は絶対お勧めなのだ。
何事にも征服されない心。
1987年制作の「遠い夜明け」は、まだアパルトヘイト政策下の南アフリカだったけれど、
この「インビクタス」は、ネルソン・マンデラ大統領に代わった直後からの物語。
1995年のラグビーワールドカップで、弱小だった南アフリカのチームが、優勝を成し遂げた実話だ。
スポーツドラマではなく、マンデラ大統領を軸においた、社会性ある素晴らしい実話。
「実話」であることの、重みがヒシヒシと伝わってくる。
黒人はサッカー。
白人はラグビー。
スポーツの世界にも、アパルトヘイトは存在した。
27年間も刑務所に収容されていたネルソン・マンデラ。
両手を広げて伸ばせば、部屋の壁に当たってしまうような、日本で言えば畳2枚分の広さ、そんな狭い空間に押し込められながらも、ほんの少しの復讐心も持たない。
変えなくては、ならないもの。
変えては、いけないもの。
変わらなくては、いけないもの。
すべての人に、分け隔てなく接する大統領の話は、人種を超えて、人々を惹きつけて魅了していく。
国の指導者とは。
上に立つ者の技量とは。
また、その気持ちに応えようとする喜び。
オールブラックスとの決勝戦は、その場にいる観客になったかのように、応援してしまった。
黒人も白人も関係ない、民主主義国家の誕生だ。
場外の警備に当たっていて、試合を楽しみにしている白人と、その車から聞こえてくるラジオを聞きたい黒人の少年。
その距離が、少しずつ少しずつ、縮まっていく過程が、実に微笑ましい。
ネルソン・マンデラになりきった、モーガン・フリーマンはとても素晴らしい。
決勝戦の観客の中に、クリント・イーストウッド監督の姿を、チラッと見たような気がするのですが、見間違いかな~。
我が魂の指揮官が全力でオススメすます!
単刀直入に素晴らしい映画です!
流石はクリント・イーストウッド!何故に2010年第82回アカデミー賞のノミネートの作品賞とか監督賞から外れたのか、その意味がわからないくらいに素晴らしい映画です!
真に素晴らしい映画であると、私勝手に確信しました。
それくらい私にとっては素晴らしい映画でございます。映画好きでよかったなと。
至ってシンプルなヒューマンドラマです。
ネルソン・マンデラ大統領を演じるモーガン・フリーマンが、一人奮起して、国民を立ち上がらせ、ラグビーのワールドカップで優勝させる。という単純なヒーローもののスポーツドラマというわけでもありません。
とくに目立ってカッコイイとか凄まじいとかいうことはないんですれども、この抑制された映画の中でも、幾つかの山場と言いますか、抑揚させるようなシーンは、やはり存在するわけです。
私は、『頑張れ』という言葉が大嫌いです。
そもそも無理することが嫌いなのですが、十分頑張ってるつもりなのに、なんでこれ以上頑張らないかんねん?とか思うからです。
少なくともここ日本においては、頑張るという言葉は、間違った解釈で使われがちなんじゃないかなと思います。
頑張るって、読んだまんま、頑なを張るってことですやん?
要するに信念を貫くとか、自分らしくあるって意味じゃないんですかね?
と私は昔からそぉいう意識で生きてきているのですが、これが言葉で説明すると中々難しいのですが、兎に角、信念を貫くとか、他に流されず、自分らしくあるって意味での『頑張る』とか『頑張れ』という自分の解釈の中での言葉の意味は好きです。
しかし、軽々しく頑張れだのなんだの言うのも言われるのも大嫌い。
ですが、この映画の中においては、その『頑張れ』という言葉が頻繁に出てきます。
しかし、他人に軽々しく言われるのが嫌いなハズのこの言葉が、この映画の中においては、物凄く心地良くて、その言葉についての自分の気持ちや思いを、クリント・イーストウッド、そしてネルソン・マンデラが代弁してくれているように感じました。
イーストウッドも、そういうことをわかってて(勿論私個人に向けたものではないですが)、今の世情を理解して伝えるために、この頑張れという言葉を多様したんじゃないかと、勝手に思った次第なのですが、その頑張れの真意は、ネルソン・マンデラ大統領(=クリント・イーストウッド)から、『インビクタス』という詩に載せて南アフリカ共和国ラグビー代表チーム(=私たち観客)に伝えられます。
私を覆う漆黒の闇
鉄格子にひそむ奈落の闇
私はあらゆる神に感謝する
我が魂が征服されぬことを
無惨な状況においてさえ
私はひるみも叫びもしなかった
運命に打ちのめされ血を流しても
決して屈服しない
激しい怒りと涙の彼方に
恐ろしい死が浮かび上がる
だが長きにわたる脅しを受けてなお
私は何ひとつ恐れはしない
門がいかに狭かろうと
いかなる罰に苦しめられようと
私が我が運命の支配者
私が魂の指揮官
もぉ、この時点で鳥肌、そして思わず涙が溢れました。
私個人のことは置いておいて、これはもぉ、今のアメリカどころか世界中を駆け巡る大恐慌の嵐で、人々の心が荒みかけ、自尊心を傷つけられ失いかけている中で、イーストウッドが神、ないし世界の父として、世界中の人々に向けた重大なメッセージであり、頑張ることの真意なんではなかろうかと思いました。
『インビクタス(Invictus)』の意味は、ラテン語で『征服されない』とか『不屈』という意味だそうです。
つまり、世界の恐慌にも不幸にも、そして自分自身にも、負けることなかれと、そういうメッセージが篭められているんじゃないかと思いました。
そして、私の中の『頑張れ』という言葉の意味を、優しく、そして強く代弁してくれたようで、涙が溢れた次第でございます。
最後に重なる二つの「ノーサイド」
印象に残る予告編のワンシーン
専門家の予想では勝ち目がない と伝えた側近に
「専門家の予想通りなら私はまだ獄中にいる」とマンデラ氏
見た瞬間に必ず見ようと心に決めた
結果や過程に大きな意外性はない
事実どおりのお話がなぜこうも胸に刺さるのだろう
高い期待をさらに超えるいい話だった
本作のつくりには特徴的がある
その工夫が 単なるスポーツ青春映画にも
政治的な説教映画にもさせていない
■回想シーンを描かない
話をマディバ(劇中のマンデラ氏の呼称を拝借)の
大統領就任以降に終始し 27年間の収監生活は見せない
苦しく悲惨な負を堀り下げず あえてこれからのみを描く
負の暗い歴史は 明るい未来を強調し
払拭の喜びを引き立てることができるがそれをしない
だが、なんとなくその理由が感じられる
事実以上に話がドラマチックに写るのを嫌ったのではないだろうか
大統領になるまでの道のりが険しくないはずがない
判りきった過去の描写をあえて廃し
その後の人生を描く中に過去をじんわりとにじませる
だから過度な演出による政治的なメッセージを纏わせず
曲解されないありのままを観客は目にする
■話の「芯」を最後の試合以外描かない
マディバが大統領になり
世界や国内にどのような政治を行ったのか
国連演説シーンもあるが具体的なことは描かれない
が、アパルトヘイトの歴史がありきたりの努力で変わるはずがない
ラグビーナショナルチーム:スプリングボクス
彼らがどんな練習をして力をつけたのか
その進化の過程もやはり描かれない
お荷物と呼ばれたチームがハードな練習無しに勝利するはずがない
そんな「芯」は言わずとも判る
だからスポットを当てることはしない
むしろサイドエピソードを丹念に繰り返す
深みが足りないと感じるかもしれないが
エピソードの積み重ねが「芯」の輪郭を構成し、判りにくくはならない
この抑えた表現が個人的には好きだ
肌の色が違う大統領警護たち
「ヨーロッパ系のラグビー」と「アフリカ系のサッカー」
「ヨーロッパ系家族」と「アフリカ系メイド」
「欧風の邸宅」と「スラム街」
「仕事中にラジオを聴く男たち」と「少年」
目指す「和解」への変化は これら相対する要素に現れ
描かれていない 「芯」が真っ直ぐブレずに伝わってくる
If you want to make peace with your enemy,
you have to work with your enemy.
Then he becomes your partner.
もし敵と平和を築きたいなら
敵と共に働かなければならない
そうすれば敵は仲間になる
主将ピナールを演じたマット・デイモン
前作「インフォーマント!」の弛んだ身体をジェイソン・ボーンに仕上げていた
勝てないことに苦悩をし、マディバの期待にとまどい、それを力に変えて皆を導く
強さと苦悩を併せ持った役を好演していた
マディバ役のモーガン・フリーマンは圧巻
まるでマンデラ本人と違うと思っていたのだが
落ち着きと思慮深さを感じさせる振る舞いに、彼はマンデラだと脳が理解した
ホンモノの役者は言葉よりも雄弁に演技で説明するなとつくづく再認識
彼らが一丸となり目指したのは最高の「ノーサイド」
ラグビーにおいての試合終了を意味する言葉であり
これはサイドがないこと=敵味方がなくなったことを表す
「和解の過程」の象徴は 「スプリングボクスの快進撃」
最終関門はニュージーランド代表オールブラックスとの戦いだ
スポーツも人生も同じ、完璧な状態で戦えることはない
それでも負けられない戦いをじっくりこってり描ききる
クライマックスで迎えたスプリングボクスの「ノーサイド」
4200万人の国民の熱狂がスクリーンからこちらにビリビリと伝播する
それは紛れもないマンデラの望んだ和解=アパルトヘイトの「ノーサイド」の瞬間
泥にまみれ困難を極めた戦いの結果
この二つの 「ノーサイド」 が重なるウマさに酔いしれる
その興奮覚めやらぬ中、流れはじめるエンドロールには
実際のマンデラ氏やピナールをはじめスプリングボクスの姿が映し出される
「奇跡」ではなく 意を持って成された「意思」
貫いた彼らに思いを馳せ じっと心地よい余韻に浸る
もうすぐ始まるサッカーワールドカップ南アフリカ大会
ラグビーと違いアフリカ系選手中心の南アフリカサッカーチーム
彼らがどのような戦いをするのかも楽しみになった
きっとその姿にスプリングボクスを重ね
また同時に観戦しているであろうマディバを思い出すだろう
全20件を表示