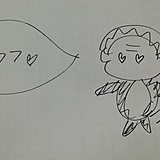クライマーズ・ハイのレビュー・感想・評価
全93件中、41~60件目を表示
ニュースを聞いた時の衝撃を思い出す
日航機墜落事故。
今でも墜落原因について陰謀説やら色々と様々な意見があって、本当のところは謎に包まれている。
墜落前の機長達の会話をネットで聞いた事があるが、聞いた後数日は何も手に付かなかった。
この映画では事故当日からの数日間の北関東新聞社を描いているから事故の描写はあまり出てこない。
でも、凄惨な事故現場を見た記者が気がふれてしまうシーンで滝藤賢一の凄さが現場の悲惨さを伝えている。
親友の病気の話や元社長秘書のセクハラのくだりは正直必要ないと思った。
昭和の時代・・
ロクヨンと撮り方が一緒
ラストは飛行機墜落原因の裏取り情報を全権デスクへ電話連絡で伝える社会部記者が自身の直感を交えて報告した為、全権デスクがそれを信じてスクープネタを記事にせず、社主からお咎めを受けるお話し。
ラストシーンが主人公である全権デスクが恐怖心で冷静さを失う「クライマーズハイ」状態?でのタイトルなのかは意味不明。
豪華俳優人で構成され、展開も良い作品です。
●昭和の熱さよ。
昔見た作品
混乱、そして失望。
日本人なら誰もが真摯に向き合わずにいられない惨劇の状況、その原因の追求、緊迫し混乱した報道の現場、複雑な人間関係、そして親子の和解……
日航機事故を依り代に様々なドラマが複雑に絡み合い、そしてほどけていく。
しかしあまりにも多くの要素で構成されるがあまり、ひとつひとつの描写が上っ面を撫でただけ。どこに感情を任せて良いかわからず、混乱させられた。
時折インサートされるPOV的なカットなど演出手法にも、なんら意味を見出せなかった。
なにより、苦楽を共にした同僚1人の死すら悼めない者達が、見知らぬ520人の死に向きあうことが出来るのだろうか。違和感を禁じえなかった。
役者の演技は素晴らしく、また題材が題材なだけに、残念な気持ちになりました。
一生懸命の大切さ
『クライマーズ・ハイ』
原作を超える
今日、第2次大戦の映画「レイルウェイ」を見て、原作と映画との関係を考えた。「レイルウェイ」は原作よりも映画が面白いかどうかということを考えたわけではない(そもそも原作を読んでない)。個人としての戦争責任を問題にしている映画なので、その点に関する映画製作者の意識を問題視した。その時、実際の事件をどのように映画製作に取り込むかという意識の問題として、想起したのが「クライマーズ・ハイ」である。
日航機墜落事件を原作とした映画としては「沈まぬ太陽」とこの「クライマーズ・ハイ」が思い浮かぶ。「沈まぬ太陽」は日航という組織内の個人の問題が原作の主題で、映画もこれを踏襲している。「クライマーズ・ハイ」は新聞記者という斜めの角度からこの大事件を見ている点、原作・NHKドラマ・映画の三者に共通する。この視点は横山秀夫の原作に負う。しかし、映画は原作を超えた。しかも、映画は「新聞記者からみた」という原作の視点を愚直に維持して、そこを超えた。
最初に見たのはNHKドラマで、このドラマは登山場面が最も印象に残った。崖登りの途中で悠木が恐怖感に襲われる場面が強調して描かれていた。次に見たのが映画で、この映画は登山場面と新聞社での記事編集場面との切り替えが見事だった。NHKドラマで悠木が恐怖に身をすくめる崖登りの場面は、映画では悠木が新聞社内で「チェック、ダブルチェック」とつぶやきながら、特ダネ出稿を逡巡する場面と重ね合わせて描写されるのである。この「チェック、ダブルチェック」は原作にはない。映画での創作、おそらく監督、脚本双方を担当した原田真人の創作である。
しかも、この「チェック、ダブルチェック」は幼少期の悠木がパンパンの母親と進駐軍兵士がデートする場に連れられて行った映画館で放映されていた映画での新聞記者のセリフで、それが悠木の新聞記者として誇り、記事校閲の正確さに対する自戒のより所になっている。アメリカに負けて、アメリカに助けられて、ここまでやってきた日本の現実が悠木個人の人生の縮図と重なる場面である。このことは原作にない。映画では、日航機墜落の原因究明がアメリカの圧力に阻まれたことを暗示する描写が続くが、そのことを終戦直後の悠木の映画館での記憶や首相の靖国神社参拝(敗戦の記憶。原作にも出てくるが、原作では敗戦の記憶と有機的に関係させていない)まで関連させて描写した上、悠木の息子が白人と結婚する結末を用意して、ストーリー救済の出口を用意するなど、「クライマーズ・ハイ」は映画の社会的影響を考慮していたことを、「レイルウェイ」を見た後、思い起こした。
記者魂
総合75点 ( ストーリー:70点|キャスト:80点|演出:75点|ビジュアル:70点|音楽:65点 )
事件を追いかける新聞社の記者の意地や誇りのぶつかり合いや社内の派閥や権力構造の問題や、特ダネを追いかけつつも事実を裏付けようとする現場の緊迫感があって、全体としては楽しめた。
しかしその反面、やたらと登場人物が多くて、映画では複雑な人物の相関関係を把握するのにやたらと苦労する。会社の組織図を把握するだけでも苦労するのに、それぞれに人間関係があるし事情もあって、一回観てどれだけの視聴者がそれを理解出来ただろうかと疑問に思う。それと主人公をはじめとして登場人物が上司を含めて相手かまわずやたらと喧嘩腰で怒鳴って主張の仕合ばかりしていて、私は新聞社に勤めたことがないのでよくわからないが、常識的に考えて民間企業でこれはないのではないか。
それと日航機墜落事故を追う地方新聞社を取り上げながら、その大事件を追求するというよりも、事件を追求する新聞社の記者を追いかける。それで観終った時に、映画の主題は何なのか、ただ新聞社の当時の現場を見せるだけでいいのかという点で肩透かしを感じた。主人公自身の話や山登りの話も中途半端だし、物語がすっきりと終わっていない気がする。
聞屋精神と人間模様を綺麗に描く
j普段何気なく読む新聞報道の裏で起きる群像劇の怖さがひしひしと!
私は、こう言うテーマの映画が大好きで、個人的に文句無く高得点を付けてしまいたくなる。
もともとこの映画の原作者は、ミステリー作家の横山秀夫氏の作品である。この横山氏の作家デビュー前の職は、本当の新聞記者だから、あの1985年に起きた我が国の最悪にして、最大の惨事となった飛行機事故をも実際に取材した経験があるのだろう。
新聞記者の内部事情に精通している彼ならではの、迫力のあるストーリー展開のお話だ。
事件を追う文屋さんの取材を進める過程で次第に明らかになる事件の真相。その真相を巡る過程で起こる記者たちの報道に対する真実を伝える事への正義と現実の社会の壁。どこまで自分達記者の記者魂を貫く事が出来るのか?もうワクワク、ドキドキ引き込まれる。
事件の追究と、報道の自由、マスコミの正義とマスコミ取材の限界・実際の事件を絡めたフィクション仕立ての社会派ミステリーに仕上げるのは、今回の作品は特に作家の記者としての実体験をふまえて描かれるストーリーであるだけに、しっかりとした細かい部分も描かれていて、リアリティー満点で、最もこの作家の得意とする部類の世界なのだろう。
そしてこの映画の監督も原田真人と言えば社会派の映画ではド迫力のパンチの効く監督だから、これで面白くない訳がない。
俳優陣も、堤真一・堺雅人・山崎努・みんな芝居達者で個性派揃いなこの映画、やっぱり観終わって、ハズレ無しの大満足でした!!
今から4半世紀も前の時代の地方新聞社、携帯電話も無ければ、メールも無いし、そんな時代でありながらも、時間が総ての勝負の勝敗を左右する事になる新聞業界での記者同志の取材合戦の闘いはいかに・・・!友情と対立、そして記者は何故命がけで真実を追求するのか?一人の人間として何故生きるのかと言う、生きる目的、価値、取材を通して体験する記者の生き様は、平凡な私にも、共感できる共通するテーマ。
「クライマーズハイ」とは山岳者の限界に挑戦する事で得られる自然な高揚感と言う、ナチュラルハイの状態の事だったのだと。どこまでも、ハードで限界を感じれば感じる程にチャレンジしてしまうと言う山男の生き方と記者の生き様が徐々に一つに重なっていく。
都会育ちの、甘ちゃんである自分には、限界に挑戦する事もそれ程無く、ユルユル生活体験者なだけに、この世界観には、魅了された。
しかし山に登るのは、時に降りるために登るというのも意味深なセリフだった。
どんなに上へ上へと頂上を目指し、より高い山を目指して登りつめても、必ずその上にはその上を征服している者が常にいると言うのも、上を極めた人だからこそ、リアルに伝わって来るセリフだった。
しかし、そんなに高く無くても、景色をゆるゆると楽しみながら生きていく道もあるのになあと考えてしまう私は、何処までのゆるゆるの人生だけど、この飛行機事故で本当に亡くなられた歌手の坂本九氏のヒット曲が「上を向いてあるこう」だったが、そこからこの物語は生れたのだろうか???
この物語の中心は、この航空機事故の取材をする記者側に特化した話で展開するので、あまり当時の現実の事故被害者の様子に意識が向かずに観てしまったけれど、実際には524名の方々が搭乗した飛行機の墜落事故で、これほどまでの大惨事は、日本ではそれまで無かった史上最悪のケースだろう。
犠牲者の方々のご冥福をお祈りし、人生は1度と言う事実を肝に銘じ、やはり私も日々を大切に、そして「上を向いてあるこう」と気持ちを改めて、我が人生の教訓としたい。
最後に、新聞記者のミステリー物語として興味深かった作品を記しておきます
「消されたヘッドライン」「大統領の陰謀」この2本は面白い!!うーんおまけで、「ザ・ペーパー」って言うロン・ハワード監督の映画も確かありましたが、これはコミカルな映画だったような印象しか残っていない気がする。
全93件中、41~60件目を表示