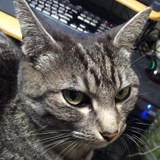東京物語のレビュー・感想・評価
全77件中、21~40件目を表示
喪服どうなさる?
原節子さんの優しさに感動❗
エゴイズムとヒューマニズム
時の流れ。大河のごとく。
「家族を描いた映画」と聞いていた。ほのぼの系の家族称賛の映画かと思っていた。
いや、シビア、シビア。
昨今のいろいろな家族を見ていると、これが「家族崩壊」と言われると「甘い」と思ってしまうが、確かに”大家族”が崩壊し、核家族に移行していく時代を切り取っている。
人によっては家族とは何なのだろう、自己実現との兼ね合いを考えさせられる。
郷愁を誘う。
この映画では、両親が子どもたちの住む東京を訪ねる顛末から始まるが、私は小学生から中学生にかけて、父の田舎に帰省した日々を思い出してしまった。
小学生から中学生になると、周りの大人が忙しそうにしていることにも気づき、いとこ達も部活や自分の友達と遊ぶことが優先になって、一人ぽつねんと居場所を見つけられなかったあの時間。田舎の親戚も、せっかく帰省した私たちを気遣って、近くの行楽地等に連れて行ってくれるものの、お盆休みのない職業に従事していた人々も多く、日常の近所付き合いもあり、帰省期間、毎日がお祭りだったわけでもない。勝手知ったる土地でもなし、親戚の家からそう離れることもできず、この映画の老夫婦みたいに、家の中に居場所を見つけられず、わずかにわかる場所をふらふらと。”嫁”の立場の母は、この映画の長男の嫁のように、親戚の手前、「いい子にしていないさい」とヒステリックになり、次男の嫁のごとく、田舎の舅・姑に尽くす。父といえば、久しぶりの実家なので、トドのように動かず。母をかばいもせず。親戚同士の歯に衣着せぬ物言いを聞き。
そんな居心地の悪さを思い出した。
そして、今。
どの方も指摘なさっているが、鑑賞する年代によって、老両親に感情移入したり、子ども世代に感情移入したり。
親が来てそれなりのことをしてあげたい気持ちはあるものの、日常との兼ね合いが優先されてしまう子どもたち。
特に長男は町医者で、今のような診療時間などなく、患者がいれば、往診に行く。その犠牲になっているのは、老両親だけでなく、長男の子どもたち(孫)。夜間・休日診療とか、救急車も今のようには整っておらず、町医者が頼り。
長男の嫁は、舅・姑のために尽くしたい気持ちはあるが、夫に止められる。アテンドしようかと提案した時に、「いいよ。お前が(家に)いなけりゃ困るだろ」との言葉。夫の意思を無視して動かない当時の理想の嫁。夫に頼りにされているととるか、舅・姑や子どもたちの喜ぶ顔が見たいのにわかってくれないととるか。複雑だが、最後の老夫婦の言葉を聞くと、長男の嫁って損だなあと思ってしまう。
長女も美容室の経営者。店だけでなく、寄り合いに忙しい。商店街の寄り合いか、技術向上の同業者同士の寄り合いか。どちらにしても、その土地で生きていくためには邪険にできないつきあい。
長女の婿は、寄席のようなところに連れていく、銭湯に付き合う等、おもてなしをしているが、妻である長女と喧嘩してまで、舅・姑のためには動かない。老両親には悪いが、妻を立てるあたり、家庭円満の秘訣である。
電話でもあれば、お互いの都合をつけて上京できたのであろうが、尾道と東京のやり取りは電報のみ。突然上京されて困った面々の動きが丁寧に率直に描かれる。田舎のように、部屋が有り余っているわけではないのも混乱に拍車をかける。
会社勤めの次男の嫁が、自分に任された仕事の都合をつけて(この頃有休ってあったのか?)、老夫婦の相手をする。上司に、仕事の進捗状況を確認されるあたりがリアル。まだ、結婚とは”家”に嫁ぐという意識が濃厚な時代。そういう親戚づきあいをきちんとできるのが女性の嗜みとされた時代。事業主とサラリーマンと言う働き方の違いもはっきりくっきり。
大阪にいる三男は、列車の中で具合の悪くなった母と、付き添っている父のために、仕事中抜け出して手当できるが、出張で大切な電報を受け取れず、後手後手になってしまう。
老両親と同居している次女は、勤務中に、両親の様子を見に来れているおおらかな時代。今なら、介護申請とか、有休を使ってと手続きを踏まなければ大問題となるだろう。時間の流れが、この時代でも東京と尾道では違う。
そんな登場人物のやり取りが、必要最低限に切り取られて、映画が進んでいく。
人物造形はある一種の典型。
おっとりとした長男。独楽鼠のように動く長女。理想的な嫁として描かれる次男の嫁。長男の嫁がしっかりして隙がないのとの対比も際立つ。一人大阪にいる糸の切れたような三男。まだ世間を知らぬ甘さを持つ末っ子次女。
それぞれ子どもたちの配偶者との出会い等は想像がつかぬが、尾道で家族7人で暮らしていたころがしのばれる。教育関係の役職等にもついていたが、若いころにはお酒の失敗もあった父のフォローや、幼い弟妹の世話を、母を助けて長女がしていたのであろう。そのそばで、一家の跡取りである長男は勉強に励んでいたのか。農業・漁業等、家を”継ぐ”職業ではなかったから、東京に出て大学で勉強してそのまま医院を開いたのか。医者として従軍して、そのまま東京にいついたのか。
まだ、兄弟の序列がはっきりしている。一番しっかりしてそうな長女は、常に長男に相談し、了承を得る。次女は兄姉に文句があっても面と向かっては文句を言えない。両親を見ているのだから一番強くたっていいのに。
反対に、次男の嫁の背景は見えない。尾道には行ったことがない様子なので、次男とは東京で知り合ったのか。東京空襲で親族が亡くなって天涯孤独?親戚や近所の人の口利きで縁談が来るケースが多かったと聞く時代に、そういう世話を焼いてくれる人は身近にいない?一人で暮らしていくより二人の方が経済的だからという理由で結婚する人が多かった頃と聞くが、一人で自活できるキャリアウーマン。そんな風に考えると、紀子のこの先の不安と期待や、舅・姑への思いも身に迫ってくる。
映画は、ひと夏の思い出として尾道の情景を描いて幕を閉じるのかと思えば、急展開。前振りはあったが。
この時のやり取りも、あるあるが満載。移動時間だけでなく、帰省にかかる費用も、自営業者の長男・長女は頭の中で算盤をはじいているに違いない。(21時発の列車で翌日の昼過ぎに着くって、今ならエジプトやブラジルの距離感?)とはいえ、親の一大事。結局、親をとる。たかが、されど”喪服”。世間の手前、役職者だった父の顔をつぶすような真似もできない。喪主としてみっともないものは着られない。ファストファッションの店なんて論外だし、そもそも店がない。レンタル業者もおらず、借りるとなったら、近所の方のをしかない。画上の都合か、長男の嫁・孫、長女の婿は来ず。
不思議なのは、東京訪問時の次男の嫁の有様からすれば、「危篤」の電話を受けた後、すぐに帰省するための行動に移すのかと思えば、紀子はいったん机に戻って、思案する。何を思案していたのだろうか。母の東京ラストでのやりとりや、映画最後の方の父とのやり取りが頭をかすめてしまう。
昨日と明日が同じで、今の生活を続けることに余念のない長男・長女・三男・次女。
同じく独り身となった次男の嫁と、父。同じ境遇ながら、二人の思いは分かれる。若い次男の嫁は未来を見つめだし、それゆえの不安・捨てがたい情・自分に張られた過度な評価の中で葛藤する。父は過去の中に置き去りにされる。映画ラストの言葉が身に染みる。
そんな人生の一コマを淡々と描いた映画。”死”さえも、特別なことではなく、日常の通過儀礼のごとく。けっしてドラマチックに描かない。
なのに、この家族のこれまでと、これからが大河ドラマのように浮かび出てくる。”ある”家族の”ある”が”The”でもあり、”a”でもあり。
戦争未亡人に、過去にとらわれるんじゃなく、新しい人生をつかむように背中を押す言葉。それだけでも、心をわしづかみにされる。日本だけでなく、各国にいる未亡人や未亡人にかかわる人はどんな思いで、このやり取りを聞いたのだろう。
その言葉だけでなく、親の有様。東野氏演じる沼田とのやり取りで、親にも親のうっぷんはあれど、それは直接子どもたちには伝えない。熱海の出来事でさえ「よかった」のみ。子どもたちが子どもたちなりに考えて、親である老両親のためにしてくれたことへの感謝ゆえ。
文句はあれど、子どもたちのすべてを包み込むような両親の存在が、ファンタジーで癒される。
一つ一つのシーンを見ていると、かなりシビアなのだが。
特筆すべきは、こんなスローテンポで物語が進むと、途中で眠くなってしまうのだが、この映画ではそうならない。
緩やかに始まるが、どんどん出てくる毒。次に長女が何をしてくれるのか待ってしまう自分がいる。血がつながり、家を出るまでは良いことも悪いことも共にしていた気の置けなさ。そんなきつさだけだと飽きてしまうが、嫁の立場を守り、清涼剤のような次男の嫁。両親のおおようさ。暖簾に腕押しの長男と長女の婿。舞台は下町。どことなく気ぜわしさも漂う。凝縮された、光と影、長男家の炊事場がその雰囲気を表す。
熱海の昼と夜の落差。今ならある程度遮音の個室だが、当時は襖一枚。外には流しの音楽隊。夫唱婦随を地で行く夫婦。だからこそ、その動きがシンクロして、コントのような笑いを誘う。
原さんのたおやかさ・控えめな上品さがよく取りざたされるが、いろいろなタイプの女性も出てくる。おっとりとした母。眉間に皺寄せた長男の嫁。世話焼きの長女。世間知らずな次女。酔客のあしらいのうまい女将。腕まくりして、頭にカーラーをつけ、女性も麻雀に参戦。他にもいろいろ。
映像の美しさも際立つ。よくローアングルとか解説にある。正直よくわからないが、ある場面ー例えば長男の家の炊事場。人を追いかけるのではなく、その画面に次から次に人が入り、出てとまるで舞台を見ているよう。かえってダイナミックに感じ、次何が起こるのか、わくわくさせられる。
解説にも、計算しつくされた映像とよく読むが確かに。
なのに、”淡々と”映画は進む。
主役は、笠さんと原さんと紹介される。
確かに、前述のように、未来を見つめる紀子と枯れていくだけの周吉の対比とすれば、老親と嫁の心の交流だけに焦点を当てれば、この二人が主役なのだろうけれど。
この映画の世界観を作っているのは、周吉ととみ。登場人物総てを包み込む、この二人の雰囲気がなかったら、観賞後感が全く異なってくる。おっとりとした夫唱婦随がなかったら、最後の言葉は響いてこない。
シビアすぎるほどにリアルに描きながら、どこか生だけでなく死でさえも、どんな思いも包み込んでしまう映画。
魔法にかけられたようだ。
鑑賞すればするほど、いろいろな思いが頭と心を駆け巡る。
なんて、映画だ。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
風俗にも目を見張る。
赤ちゃんが食卓カバーのような蚊帳の中で寝ている。動いている。
紀子の家の共同炊事場。
浴衣の寝巻のままで、ドアを開けてしまうんだ…。
他にも、音声解説を聞くと、今はすたれてしまったが、昔はどの家でも持っていた、玄関に提灯とか、こだわった意匠があるという。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
DVDには音声解説がついていたが、本編と解説の声がごっちゃになって聞き取りづらかった。笠さんも出席されていたが、ほとんど発言なく…。損した気分…。
だから-0.5しているわけではないが。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
≪2024年11月15日追記≫
『麦秋』鑑賞。 『東京物語』『晩春』と合わせて『紀子三部作』と言われる映画。
ほとんど、演じる役者が同じなのに、まったく異なるテイスト。
同じように、家族のドタバタが描かれるのだが、違う人物造形。例えば、『東京物語』では長男の嫁と次男の嫁として、比較対象されてしまう三宅さんと原さんだが、『麦秋』では、長男の嫁と、小姑という関係なのだが、姉妹のように仲が良く、一緒に高価なケーキを隠し食いしたりする。『東京物語』での三宅さんは眉間に皺寄せ硬いが、『麦秋』では人妻の美しさが際立つ。
他にもと上げていくとキリがない。
改めて小津監督のすごさを感じた。
私ずるいんです
私個人の話になってしまいますが、出身地方が尾道と同じ方言のため、老夫婦が私の祖父母に重なって見えてしまい客観的にレビューできません。
2023年になっても1953年に公開されたこの映画で描かれている家族の在り方が、そっくりそのまま通用するのは、この映画がいかに普遍的なテーマを描き切ることに成功しているか示しています。
年を取ると家族がどんどん離れ離れになっていって自分の生活が大切になっていく。
老いていき孤独になって、人生って家族って何なんだろうか。
この映画が描いているテーマは、恐らく今後も変わることがない平凡なテーマです。
家族の在り方をテーマにした映画は多くありますが、この映画にハッピーエンドはありません。
ただそれがバッドエンドだったかと言われるとそうでもありません。
よく言えばトゥルーエンドとでもいうべきか、人の一生は多かれ少なかれ恐らくみんながこの映画のような結末を迎えるのでしょう。
我が生涯シネマベストテンの一作に再び…
私にとっては、
小津映画のベストワン作品でもあるし、
生涯の映画ベストテンの一作でもある。
新聞紙上で、
小津監督に関する新刊書の紹介があり、
「紀子三部作」に触れていたので、
「晩春」「麦秋」に続いて何度目かの再鑑賞。
「紀子三部作」の前二作では、
離れがたい家族の絆を描いていたように
感じたが、
この作品では血縁だけに留まらない、
一見、新しい絆の形を先取りしているように
見えて、実は、
紀子が再婚しない姿を通じ、
義理の関係ではあるものの、
やはり、その関係から抜け出せないでいる
同じような印象がある。
また、今回、改めて感じたのは、
都会に出て
子供達に邪険にされる老夫婦の姿は、
「リア王」やその翻訳版の黒澤「乱」の
小津バージョンにも思えると共に、
都会生活で人間性を見失う
「ニュー・シネマ・パラダイス」との
共通点だった。
だから、この「東京物語」の“東京”は、
むしろ否定的意味合いにも感じたが、
小津作品の多くに見られる、
鎌倉に住み、東京へ通勤する設定も、
そんな大都市への嫌悪感の一貫
なのだろうか。
幾度となく観てきたこの映画、
終盤の感動の場面を思い浮かべながらの
この度の鑑賞でも、
たくさんの伏線のシーンに更に涙し、
そして作品の最後に配された
人間の優しさを凝縮したかのような
父と義理の娘の会話のシーンには
改めて号泣させられるばかりだった。
どこを切り取っても凄い画像
淡々と、ただ淡々と
人生において何度目かの鑑賞時、
「長男長女の気持ちもわかる!彼らに共感できる」と感じた時に「自分も大人になったものだなぁ」と思った。
長男長女は決して薄情なわけではない。ただ、両親をもてなす事より先にどうしても優先せねばならない事があるだけなのだ。
子供達の学習、目の前の仕事。顧客との信頼関係。
それらには「今、その時にせねばならないタイミング」というものがどうしてもある。違う選択をしてしまったらえらく遠回りになるか最悪は望む未来を断念せねばならないかもしれない。
長男長女も決して両親を疎んじたり蔑ろにしているわけではない。
ただ、どうしてもそれ以上に大切な事が1つ2つあるだけなのだ。
母、とみが倒れた時、長女が「喪服を持っていくか悩み、結局持っていく」という選択をするシーン。
これは本当に身につまされた。
心情的には「絶対、助かって欲しい!」と強く願うならば喪服を持参するのは言語道断かもしれない。
しかし、もし「万が一」の事態があった場合には、東京に喪服を取りに戻る金銭的余裕も時間的余裕もないのだ。
有り余る財力があるならば、飛行機で取りに戻る事も現地で調達する事も出来るだろう。だが、そんな事が出来るのは一部の富裕層だけだ。
医師だろうが美容室経営だろうが、子供達に充分な教育を与えたいと思ったら生活費にゆとりなんかない。
長男長女も、日々精一杯の努力を重ねて家族を守り育てているのだ。紀子が甲斐甲斐しく老父母に尽くせるのは、彼女にはそれら(守るべき城)が無いからだとも言える。老父母に尽くす事が今は亡き最愛の夫との絆を保つことでもある。
「私もやっぱり、喪服を持っていくだろうな」と思ってしまった時、「東京物語」という名作の凄さに近づけた気がした。
笠智衆演じる父・周吉もそれを充分に理解してくれていると思う。「子供達の現在」は、かつて自分も通ってきた道に違いないからだ。
子供達がきちんと巣立ち、彼ら自身の城を築いている事は、親として最大の幸せだと思う。
今、自分が人の親となった時、自分自身は子供達に何も求めない。
子供達に様々な経験や学びを(情・知・体すべて含め)与えてあげられることこそが最高に幸せだと思う。
巣立ちの日、繋いできた手を離すために。
当時の背景を思えば、大家族から東京に象徴される核家族化によって失われるものへの哀惜も描かれてはいるだろう。その一抹の寂しさはあれど、周吉もとみも子供達の現在に対して肯定的だと思う。
すべてを達観した周吉の眼差しに、観客は古今東西、人類が繰り返してきた日々の営みを見るのだろう。
悠久の歴史の中で幾億幾兆と繰り返されてきた家族の姿。生きるという事。
大空や大地、満天の星々を眺める時のような不思議な感覚に身を任せ、時間の海を揺蕩う。そんな感情を抱かせてくれる本作なのである。
いやはやとてつもない名作だ。
家族の喜びと寂しさの交差する物語
笠智衆さんの演技を引き出した演出
「PERFECT DAYS」の主人公「平山さん」からの連想で再び見ることにしました。
前に見たことがあったはずなのに、東京旅行のところしか覚えていませんでした。同じ映画でも、見る時期によって感動も受け取り方も変わるものですね。
息子さんがお父さんに病状を告げるシーンの笠さんの演技は、ほんとに心に染みました。
お母さん役の女優さんもよかったです。
もしも、この映画を見て、笠智衆さんに興味を持たれた方は、ぜひ、ドラマ「ながらえば」を見てください。NHKオンデマンドで見ることができます。DVDもあるので、レンタル等にも、まだあるかもしれません。映画ではありませんが、この「東京物語」と同じように、笠さんの演技に胸を打たれます。
尾道も東京も変わったが、尾道は僕の世代でも見たことのある風景だった...
変化する其々の内面を描写した映画。
内容は、上京した老夫婦と家族達の姿を通して、家族の絆、親と子、老いと死、人の一生等々を冷徹な客観的視点で表現した作品。小津安二郎の畳の目が見える様な畳上30cmの煽り撮影は物憂げで生活感のある表現に親近感を覚える。印象に残った言葉は『東京はのう、人が多過ぎるんぢゃ』正直な感想が人が変わってしまう根本的な生活の変化に違和感なく感じてしまう恐ろしさであったり。『親孝行したい時に親は無し、せれとて墓に蒲団も着せられず』分かるけど行動に移さず結果後悔してから気付く人の業みたいなモノが心象のスケッチとして描かれて素晴らしいと思うばかりです。最後の紀子の台詞『私ずるいんです。ずるいんです』は主観的ではなく客観的で観客其々が相剋する矛盾に静かに光を当てられた様でドキッとします。静かな物語の中にも其々のキャラクターの作り込みがしっかりしているので、メリハリがついて共感も誘う様で素晴らしいと感じます。戦後間も無く訪れた変化に翻弄される人々と社会の移り変わりと共に心模様の移り変わりの対比は、全く時代が変わった今でも胸に詰り言葉にならない物語です。正に名作と言われる所以です。
共感する引き出しがあまりに多くて,これは自分の家族を描いた映画では...
歴史的名作であり歴史的偉業なのだと思います。
これまでちゃんと見たことがなかったのですが、初めて通しで鑑賞。
どうしても、世界的名作という評価と、どこかで読んだり聞いたりした著名人の推しコメントがこびりついているので、何らかのバイアスゼロというわけにはいきません。
今見て面白いか?
と問われたら正直、うーむ、と唸るしかありません。
でも凄さは十分に伝わってきます。
この映画で描かれているテーマはすべて、今作られているたくさんの映画たちも、色々と設定や形を変えて懸命に描こうとしている普遍的なものです。
太平洋戦争で日本が降伏したのが1945年8月。
この映画が作られたのが1953年。
戦後復興と生きることに必死になっている時代にですよ、日常生活の中にふと訪れる虚無感とか焦燥感とかを、実に鋭く切り取って、映像に落としているのです。
登場人物の中で一番成熟した大人のように感じる紀子ですら(というより紀子だからかもしれません)、日常が日常として何事もなく過ぎていくことに、時として耐え切れずに泣いてしまうわけです。
『私、歳を取らないことに決めたのです』なんてセリフから窺える〝無理してる感〟が終盤になって明らかになってくる展開はサスペンスと言っても過言ではないほどです。
戦後の変わっていく家族関係
1953年頃、尾道で暮らす周吉(笠智衆)ととみ(東山千栄子)の老夫婦は、東京で暮らす子どもたちを訪ねるため上京した。しかし医者の長男・幸一(山村聰)と美容院を営む長女・志げ(杉村春子)は自分の生活が忙しく、両親の相手が出来なかった。戦死した次男の妻・紀子(原節子)だけが優しい心遣いを見せ東京の観光案内までしてくれた。そして、東京から帰る途中とみの具合が悪くなり大阪の三男・敬三の所に寄ってから尾道に帰ったが、帰宅後に体調が急変した。危篤の電報を受け帰省した息子と娘も、とみが亡くなり、葬儀が終わるとさっさと東京や大阪に帰ってしまい、次女京子(香川京子)と暮らす父のもとに残ったのは我が子ではない紀子だけだった。そんな親、実子、嫁といった家族関係を描いた話。
戦後の日本の家族関係が戦前とは変わっていった様子を描きたかったんだろうと思った。それまでは「家長が」とか、「長男が」とかだったのが、戦後は平等というある意味無責任な親子関係になっていったのだろうと思った。
原節子を初めてスクリーンで観たが、鼻は大きいし、美人というほどじゃないと思った。香川京子や三宅邦子の方が綺麗かも。
戦後たったの8年後に撮影された東京の復興がすごくて驚いた。尾道は現在ともあまり変わらない感じだった。
なんとも言えずほのぼのとした良い作品だった。
全77件中、21~40件目を表示