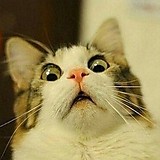浮雲のレビュー・感想・評価
全38件中、21~38件目を表示
とても面白かった
冒頭の引き揚げシーンからラストまで、どのくらいの年月を描いた話なのか、思い返しても判然としない。とにかく最初から最後まで、ひと組の男女がひたすらお互いを行ったり来たりする様子だけ。他には劇中一切、全く何も描かれない。
1955年に公開された映画なので当然ながら、人間の等身大をはるかに超えたバカでかいスクリーンで見られることしか想定されていない。そういう風に設計された映像を現代でも映画館で見られる贅沢。
富岡の、女に対してのみ威力が発揮される超絶クズ仕草。ゆき子(雪子?由希子?)はわかっていながらそれでも食らいついていく。その気持ちの強さを表現する高峰秀子の表情と言葉と佇まいに、見ているこちらの心が全部持っていかれる。
日本映画オールタイムベスト第3位。
成瀬巳喜男監督の戦後の日本映画を代表する作品。
林芙美子の原作。
大変な波瀾万丈の恋愛映画である。
仏領インドシナ(現在のベトナム)に始まり、東京、
そして日本の南の果ての屋久島へと転々と舞台が
移る。
戦後最大の流行作家・林芙美子のストーリーテリングは、
悲劇を喜劇のようにアップダウンさせて、
人間の好奇心を痛く刺激する。
これでもか、これでもか、女を不幸のドン底に突き落とす。
《ストーリー》
戦時中の1943年、農林省のタイピストとしてインドシナに
渡ったゆき子(高峰秀子)は、農林省の技師・富岡(森雅之)と出会う。
冨岡は妻帯者と知りながらも2人は恋仲になる。
冨岡は妻と離婚すると約束するが、戦後東京に戻ったゆき子が、
冨岡宅を訪ねると、妻が応対。
妻とは別れていないと分かる。
失意のゆき子は米兵の情婦になる。
しかし冨岡と再会したゆき子は、またも簡単によりを戻す。
妊娠したゆき子はかつて貞操を奪われた義兄(伊藤雄之助)から、
金を借りて中絶をする。
冨岡とゆき子の腐れ縁。
側から見ると、賢い上に生活力もあるゆき子が、
女にダラシない富岡に
何故惹かれるのか?とても不思議に思う。
観客は馬鹿なゆき子に、ヤキモキして、
同情したり怒ったり忙しい。
これが流行作家と映画監督の手練手管か。
大体に冨岡は妻の葬式代を愛人に借りるような男。
ちょっと子綺麗な女(岡田茉莉子)を見ると、眼が爛々と輝く。
そんな身持ちの悪い男(森)を忘れられない女・ゆき子。
この「浮雲」は日本映画を代表する映画だという。
(日本映画のベストテンの上位に必ず入っている)
高峰秀子さんは、週刊朝日に連載していた「わたしの渡世日記」を読んでいたのと、
2010年没ですので、それなりに知っています。
(本当に賢い信念の人という印象)
成瀬巳喜男監督は殆ど知らず、この映画で作品を初めて観ました。
森雅之も生存中は殆ど知らず、最近観た「羅生門」の武家、「白痴」の主役。
今作と幅広い役を演じる演技派ですね。
戦前戦後の世相も珍しい。
ゆき子の元軍人の義兄は「踊る宗教」を主宰してボロ儲けをしている。
(踊る宗教?って何?
………………これ、本当にあったらしい)
森雅之はゲスな上に、付き合う女が3人とも不幸になる・・・
という凶運の持ち主。
なんと夫(金子信雄)を捨てて森を追って上京した岡田茉莉子は
金子信雄に嫉妬から刺殺されてしまう。
森雅之の妻は病死する。
ゆき子(高嶺)も、また・・・。
…………肺結核に罹患します…………
そして屋久島ではもう起き上がることも出来ず、
病いに臥せってしまう。
屋久島は雨の多い事では有数の土地。
寝床の外はウンザリする程の、雨また雨。
原作者の林芙美子について触れます。
芙美子は行動力のある女性で、戦時中にはボルネオや中国へ慰問に行くやら、
パリ留学するやら、ロンドン滞在歴もあるのです。
男と女の腐れ縁をただただ追っている本作品。
なぜか微妙に面白いのです。
演歌の世界の暗い情念・・・と同じに惹かれるのでしょうか。
日本人の私小説のルーツでしょうか。
《花の命は短くて苦しきことのみ多かりき》
林芙美子が好んだこの言葉。
映画のラストに大きく書かれて、終わります。
自分を「花」に喩える度胸。
大した女性です。
ゆき子も林芙美子も、花の命は短かったです。
林芙美子のこの原作。
芸術性もヘッタクレもあったもんじゃないです。
林芙美子は大変な流行作家で仕事を抱え込みすぎて、
働き過ぎ・・・過労で亡くなったようなものです。
ウィキペディアを読むと実生活の森雅之も
大変な女たらし・・だったらしい。
当時の庶民の楽しみが林芙美子のリアルな小説。
翻って考えても、なぜこの映画が凄い名作なのだろうか!?
ゆき子の男運の悪さ、
こんな男を愛さなければ・・・
理性で解決出来ない男女の仲。
確かに面白いけれど、
日本映画を代表する一本・・・
そう言われるとちょっと首を傾げてしまいますね。
花の命は短くて
南国で出会い、雨降る島で永久の別れ
高峰秀子と脚本の力がとにかく素晴らしかった。ゆき子=高峰秀子のセリフの一つ一つが最初から最後までリアルでシャープで男全般に対する皮肉と本心、普遍的。一方の富岡もゆき子に嫌みばかり言うクズ男だがどこまでも優しい。第一印象だって悪かったのに二人は出会ってしまった。子鹿のバンビのようにかわいらしいゆき子。一人で生きていける強さを持っているのにゆき子はひたすら富岡を追う。富岡もむげにしない。ゆき子がどんな男とつきあおうとどんな暮らしをしていても、ゆき子を拒むことは一切ない。優しさと腐れ縁の連続。二人は離れない。
高峰秀子、本当に凄い。娘時代の彼女はおんなじような役(親思いの健気な娘)ばっかりやらされていて本当に気の毒で可哀想だと思った。だからこのような作品にオファーされ堂々と演技するチャンスを与えられたのは女優として最高の幸せで彼女も肝が据わっていたんだと思う。この役をできる女優は今の日本にはいないでしょう。
むしろ憎しみ合っているかの男女。
とにかく高峰秀子と森雅之の演技力は半端ない
男が女を愛するには責任と義務が生じる
それは頭では分かってる
けれども、成り行きで気がつけば深い仲になってしまっている
女だってこんな男と付き合ってもどうにもならない
それは分かっているのに逃げない
気がつけば追いかけている
浮雲のようにあてどもなく漂い流されていく
千切れて別れてはまたくっついていく
理屈でない、だらしなく生きる楽さが互いに欲しいのだ
いつしかそこに強烈なリアリティーを感じるようになった、自分も大人のはしくれになったということか
幸子が富岡をなじる言葉のひとつひとつにリアルで聞き覚えのある男性も多いはずと思う
とにかく幸子は何度も泣く
しかし富岡は泣くことはない
そんな真面目な男ではない
だがラストシーンで初めて泣くのだ
浮雲は流れ流れて行き着いた最果ての地で山にぶつかり雨となったのだ
とにかく高峰秀子の演技力は半端ない
仏印での清純な女性からやさぐれたパンパンまで見事に演じてみせている
森雅之もまた彼が演じる富岡兼吾という男が漂よわせる空気をこれ以上ないリアリティーで感じさせる名演技だった
監督の演出も的確で過剰ではなく流麗なほどにスムーズに物語が進行する
日本映画の傑作のひとつ
恋の道行き
離れられない男女の成れ果て
成瀬巳喜男監督による、終戦前から直後の混乱期、男女の不倫の哀しさと成れ果てを描いた映画。林芙美子原作。予備知識があまりなく、観るまで、二葉亭四迷の「浮雲」だと思っておりました。
成瀬巳喜男氏、2作目の観賞でした。初見は『歌行燈』でした。こちらに比べると、ずいぶん重くて心にのしかかるストーリーでした。森雅之氏は以前、『白痴』(黒澤明)で観てすごく印象的でしたが、この人って「目」で演技しているような気がします。
観ていて腹が立つほど、ええ加減な口先だけの無責任男に何故、惹かれるんだろう? でも、女性の方がゾッコンという気がしますし、悲しいかな、「この男に惚れる」のも、理屈抜きで、わかってしまうところが怖かったです。ずるいのも卑怯なところも女好きでどうしようもないところ……すべてを知っているのに、離れられない、離れてもまた巡り会って追い掛けてしまう、結びついてしまう、女のサガなのか。ダメ男なのに、女をぱっと引き寄せてしまうところなどは、うまく描かれていました。(富岡とおせいの目が合い、ねんごろになる予感など)性描写はないのに、身体でつながっている男女であるのは明白だったし。温泉宿で、入浴中に、脱衣籠だけが映し出されるところなどの演出もよかったです。
雨が降り続ける、湿った屋敷、屋久島で、ゆき子が病に伏してしまい、最期を迎えるシーンは本当に哀しいですが、ゆき子の死に顔が美しく、くちびるに紅を差して、むせび泣く富岡の姿にある種のカタルシスがあったかのかもしれません。
現代風にリメイクしたら、きっと、この作品の良さは出ないでしょう。
男と女。50年生きてきたからわかる何か
映画の世界に呑まれる
息つく間もない2時間という上映時間。どこまでもすっきりしない腐れ縁の男と女が出てくる。ただそれだけの物語なのだが、最後まで映画の中に埋もれる感覚。少し鼻にかかった声の高峰秀子の色香と倦怠感がスクリーンいっぱいに満ち溢れている。屋久島で最後のときを迎える高峰の美しさにも感動。
僕には早かった
宿命なるくされ縁によって繋がれた男女の至高のラブ・ストーリー
「くされ縁」とは「運命」以上の「宿命」のようなもので、切りたいと思った時に切ることができず、自然と切れそうな時は、自らそれを繋ぎとめてしまう。
本作は感傷的なメロドラマだが、その感傷を閉口ものにせずに、情感豊かに描きあげた成瀬演出は見事だ。戦中、外地の異国情緒の影響もあってか、ロマンティックな恋を初めた2人は、戦後の混乱と同時に、愛の行方を見失う。どうしようもない男に執着したがために、時代に流され最後には、故郷から遠くはなれた屋久島で病死する薄幸のヒロインの悲恋物語・・・否、そうではない。これは自分を一途に想ってくれる女の心を尊重し、いかに幸福にしてやれるかという、「男の優しさ」を描いた物語だ。このラブ・ストーリーが、特異な形をなしている最大のポイントは、戦後の時代でありながら、男がとてつもなく現代的(平成的)であることだ。この男の優柔不断さ、芯の無さは、公開当時ではどうしようもないダメ男と思われただろう。しかし、この男の優柔不断さ、芯の無さは、今現在の若者の典型であり、今現在の女性が求める理想の男性像(それが虚像であろうと)そのものなのだ。つまりは、ヒロインが彼と別れられない唯一の理由は、幸せにはなれないことがわかっていても、抗えない理想の男の魅力に他ならない。たとえ優柔不断であろうと、甲斐性がなかろうと、いつでも自分を受け入れてくれる男を、何時の時代も女は求めるのだから。
富岡は、ゆき子と初めてあった時、わざと冷たい態度をとる。故郷から離れた外地では、当然、日本の若く美しい女性はチヤホヤされるはずのところを、そのような接し方をされたため、ゆき子は急激に富岡に関心を持つ。ここですでに女は、女使いのうまい男の罠にはまってしまった。富岡には、故国に妻がいることを知りながら、彼女の方から彼の部屋へ行ってしまう大胆さ。勝気だが、マジメな女をこの行動に走らせる男の魅力は、まだこの時点ではわからない。それは、外地でのほんの火遊びで終わらせることのできない「運命の力」だ。ここから2人の流転の人生がスタートする。
戦後、外地から引き上げて来たゆき子は、富岡の実家を訪ねる。そこには男の妻の姿があった。頭では解っていながらも、現実に見る彼の妻にショックを受ける女を、男は妻の見ている前で連れ立って外へ出る。妻の姿を見ても、「俺と一緒になっても不幸になるだけだ」と男が言っても、今、自分のすぐ横にいる男の「大きな存在」をあっさり捨てることはできない。ゆき子の数奇な人生のスタートだ。彼女は生きるため、ある時はアメリカ兵相手に娼婦まがいの生活をしたり、昔馴染みの金貸しの情婦になったりと、女としては最低の生活を送る。ここまで身を落とせば普通なら、身も心もすさんで自暴自棄になるものだ。しかし、彼女には「人生をやり直して幸福になる」という強い希望を実現させようとする不屈のパワーがある。そしてその「幸せ」には「富岡の愛」がセットになっているのだ。たとえ1人の力で成功したとしても、富岡のいない人生は意味がない。しかし富岡との生活は、必ず不幸が付いてくるのだ。
さて、富岡は「優しい男」だと前に述べた。何故優しいのか?それは、「来る者をこばまず」という姿勢だ。一見これは、節操のないことのようにも思えるが、ゆき子のような女にはとても大切なことだ。この時代で、娼婦まで身を落とした女を受け入れてくれる男がどれだけいるだろうか?いや、この時代だけでなく、「女の貞操」など死語となったフリー・セックスの現代でも、男性はえてして、不特定多数の男と交渉を持つ女を嫌うものだ。ましてや男尊女卑の時代では、たとえ自分がその原因となっていようと、他の男に抱かれた女を、男は決して受け入れないものなのに。しかし、富岡は、女の身の上全てを承知していながら、久しぶりに逢った時でも、「やあ、どうしたの?」と、つい昨日別れたばかりのような、さりげない挨拶のできる男なのだ。女が言いたくないことは何も聞かず、当たり前の笑顔を返してくれる男の温かさ。どんな犠牲を払ってでも、それは繋ぎ止めておかなくてはならないものだ。ただ、富岡の場合、その「優しさ」はゆき子だけに向けられているのではないということが玉にきずなのだが・・・。そのよい例が岡田茉莉子演じるおせいの存在である。富岡はこともあろうにゆき子との旅先で、知り合った男の若い妻、おせいに好意を持ち、同棲するに至る。しかもゆき子は富岡の子供を妊娠していたのだ。この行為、富岡が極悪非道のようにも思えるが、私の「富岡=優しい男」の法則から考えると、いたしかたないことなのだ。富岡が一目でおせいに興味を持ったのは、もちろん彼女が若くて美人なこともあるが、「ここから逃げたい」と思っていることを感じ取ったからなのだ。その強烈なSOSサインを、優しい富岡にはとうてい無視できるものではなかったのだ。富岡はおせいを捨てることはなかった。富岡には、「遊び」という付き合い方はできない。その証拠に、おせいの夫は、富岡ではなくおせいのほうに制裁を加えたのだから。そう、「優しさ」というものはこの世で最も恐ろしい行為なのである。
さて、ゆき子はおせいとは違い、富岡に助けを求めたことはない。彼女は決して従属型の女性ではないのだ。彼女は自分の行動には全て自分で責任を持っている。富岡の子供を墜ろす決心をしたのも彼女1人でであった。基本的に彼女は1人で生きていける強い女性だ。だからこそ、富岡のように、ふと気弱になった時に、黙って受け入れてくれる男性が必要なのだ。自分をひっぱっていってくれる強い男でも、始終べったり一緒にいてくれる甘い男でもなく、富岡のような優しさの男でなければならないのだ。
皮肉なことに2人が真の幸福を掴んだのは、ゆき子が病で世を去る時だった。ここまで、一方的にゆき子の富岡へ対する激しい想いしか表立って描かれていなかったが、2人が新たな人生をスタートさせるべく選んだ屋久島への道中で、富岡のゆき子へ対する深い愛がはっきりと感じられるようになる。重い病にかかり、動けなくなったゆき子を献身的に介抱する富岡。ゆき子を置いて、先に島へ渡ろうと思えばできた富岡だったが、彼は彼女を置き去りにすることはなかった。港を出てゆく船を見送り、ゆき子のためにみかんを買う富岡の複雑な心中は察するにあまりある。ようやく2人で島での生活をスタートするも、湿気の多いこの地では、ゆき子の病状は悪化するばかりだ。それでも、2人は絶望することはなかった。最後の朝、軽口を叩き合う2人。そう、このシーンが私はとてもとても好きだ。表面的にはふざけたような軽い会話だが、その中に秘められた2人の深い愛が、たとえ死を目前にしていようとも、幸福であることを物語っているからだ。富岡はゆき子の死に目は会えなかったが、最後に安らかなゆき子の唇に口紅を塗ってやる。そして、それまで飄々としていた彼が、ここで初めて声をあげて泣くのである。この涙、悲しみか?哀れみか?絶望か?それとも安堵か?何であろうとゆき子の前では決して涙を見せなかった彼は、やはり優しい男なのだと私は思う。
これは宿命なるくされ縁によって、愛に流されたのではなく、愛を貫いた男女の至高のラブ・ストーリーだ。
全38件中、21~38件目を表示