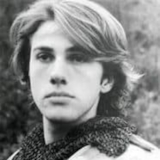硫黄島からの手紙のレビュー・感想・評価
全106件中、41~60件目を表示
やっぱり戦争なんてするべきじゃない
クリント・イーストウッドが、ほぼ全編日本語で映画を一本撮ったことは、素直にすごいと思う。
ただ、その日本語が聞き取りづらい…。
私の耳が悪いのかもしれないけど、1割くらい何言ってるかわからないところがあった。
二宮くん演じる西郷が、ほぼ現代日本語でしゃべってるのは正解だった気がする。
彼の、反抗的で正直なキャラクターが際立ってた。
日本軍が米軍に投降した時に、一瞬米軍を天使のように描くのかと思ってがっかりしたら、そうではなかった。
父親たちの星条旗と同様、戦争は一方が善で一方が悪なわけではないこと、現場の兵士たちは、心身ともに極限状態まで疲弊しながら、自分の信じるもののために、大切な人のために、ただ必死だったのだと伝えたかったのだろう。
日本人が見ても違和感が少ない、日本が舞台の映画。
でも、日本人には作れないだろう感覚が混ざってる。
2つはあまりつながらない
賛美せず、いたずらに英雄を作らないという点では、そうあるべきだと思います。映画として2部作とするのであれば、あえての仕掛けがあってもよかったのではとも思ってしまいますが、それは素人考えなんでしょうね。きっとそういう声がありながらも抑制をきかせたことに価値があるのかもしれません。
硫黄島の激闘(日本目線)
演技が軽くリアリティに欠ける
アメリカ人が撮った純ジャパンな映画
戦争の真実に誠実なイーストウッド監督
日本の敗戦が濃厚だった頃の、南洋の最前線で最後まで諦めず敵と戦う日本兵の姿を、クリント・イーストウッド監督が紳士的に描く。本来、この脚本ならば日本人監督が撮るべきものを、全編日本語の台詞にも関わらず遣り遂げたことが意味することは、イーストウッド監督の懐の深さであり、戦争に対する見識の高さであろう。モノトーンに近いカラーの色彩が代表するように、内容も演出も編集も冷静な視点が行き届いた生真面目さが特長になっている。戦後も60年以上経つと、これまでの一方的な反戦思想だけでは全てを語ることが出来ない。戦死していったひとりひとりの事情に配慮した客観的な再考が必要とされる。日本映画の欠陥を指摘されたようで、映画を離れて考えなくてはいけない作品だ。
俳優では、唯一加瀬亮の演技に感銘を受ける。
圧倒的リアリティ。
観なくてはいけない映画
アメリカ人とこの映画について語り合いたい
ドキュメンタリー風。目の前で爆破して血や肉片がこっちまで飛び散ってくるような臨場感がある。
『父親達の~』を観ていると「あ、この場面」と二重の楽しみも。
日本制作にありがちの「それ泣け〜!!」とか教訓的な盛り上がりには欠ける。
ただ淡々と綴られる。
役者の熱演で感情移入して盛り上がれるけれど、演出として、音楽とか総動員して盛り上がらせようとはしていない。
それだけに、考えさせられる。この戦争ってなんだったのだろうと。特に二部作両方見て、両方の事情知ってしまうと、なんだったのだろうと。
あの時代の人々が何故あのように、一つの価値観に追い込まれていってしまったのか、よくわからない。教育制度や、非国民にされないためという人もいる。
でも、それよりも何よりも、あの極限状況に置かれて、自分がやっていることの意義を妄信しないと心が折れちゃうと、この映画を観ていて思った。自決も視野狭窄。
しかも考えてしまったのが「家族を守るために自分の命を投げ出す」「困難なミッションと知りつつも、あえて挑戦する」姿に憧れを感じるのは、あの時代特有なものではない。『宇宙戦艦ヤマト』『ガッチャマン』その他たくさんの映画にも流れている主題。
あの時代特有の狂気としてしまうだけでいいのだろうか?
とてもたくさんのことを考え、感じさせられた。泣いて、感動して、なんていう言葉が薄っぺらに思えるほど。
観て、そして多くの人と語り合いたい。
戦争の恐ろしさ
この映画は数ある戦争映画の中でも有名な作品であり、人生で1度は見ておきたい作品である。
今の私たちにとって戦争というものがどれほど恐ろしく、残酷で悲しいものであることは想像でしか感じることが出来ない。目の前で味方がやられていく辛さ、勝ち目がないとわかっていても自分の命をかけてまで国を守ること、戦争というものは決してあってはならないものだと思う。
私も学校で硫黄島の戦いを勉強する機会があったが栗林閣下は兵士のことを考え、しっかり向き合うかなりいい方だと学んだ。そのこともこの作品では描かれていた。
西郷役の二宮の演技もかなりすばらしかった。
今の世界でも戦争している国はある。私たちは戦争についてもっと深く考えていくべきではないだろうか。
数奇な運命
イーストウッド監督は公開に際して「勝ち負けを描く戦闘映画ではなく生身の人間を描きたかった、どちらの側であっても、命を落とした人々は敬意を受けるに余りある存在であるということ、映画は彼らに対する私のトリビュートなのです」と語っている。馬術のバロン西は有名だが栗林中将がハーバードに学んでいたとは知らなかった、米国にも知人の多い二人が硫黄島で散って行ったという運命の数奇さも製作の動機になったのだろう。
清水上等兵(加瀬亮)が米国人捕虜の母からの手紙の内容が自分の母からのものと同じだったことに衝撃を受ける、鬼畜米英と習ってきたのに彼らもまた自分と同じ人間であると気づくのだった、しかし投降するも米兵に射殺されてしまう戦争の現実。いたずらに感傷に走らず淡々と戦場を描いていく群像劇の傑作、民間人の視点で描いた硫黄島の死闘の裏側は脚本家のアイリス・ヤマシタさんの着想、謙さんのアドバイスも相当あったらしいがハリウッドが日本映画より日本映画らしい力作を作ってしまったことに驚きを隠せない、クリント・イーストウッド監督は日本人の心を鷲掴みにしてしまったことでしょう。
葛藤抱える兵士の信念、胸締め付けられる
戦況分析続け斬新な戦略練る上官の、部下を見守る優しい眼差しや相手の立場に立って敵味方関係なく状況判断下す姿に胸打たれる
戦地へ配属された兵士の過去が描かれ、大切な人への切ない思いが綴られた手紙や、難航極めながらも攻め続け、信念持った兵士の無念にじませる心情が胸に突き刺さる
アカデミー賞サウンド編集賞・ゴールデングローブ賞外国語映画賞受賞作
日本軍側に焦点当て戦時下の緊迫した情勢や人間関係を考えさせられる、クリント・イーストウッド渾身の一作
今平和に生きれていることに感謝
涙は流しても、笑顔は作らない。戦争がどれだけ愚かで卑劣な行為かが分かる。
1945年2月、日本本土を守る最重要拠点となった硫黄島で起きた戦争を
描いた「硫黄島からの手紙」を観ました。
日本兵 2万2786名に対し、アメリカ軍の兵士は11万名。
圧倒的な戦力差にも関わらず栗林中将(渡辺謙)を中心に驚異の粘りを見せ、
36日間の猛攻の末、日本兵が壊滅するまでが描かれています。
硫黄島の戦いと呼ばれ、アメリカ兵の死傷者が日本兵の死傷者数を
上回る稀有な戦いとなりました。
映画は彩度を落とし、戦場の重苦しさや命の儚さを表しています。
アメリカ軍が上陸してくるシーンにただならぬ恐怖を感じました。
大量の戦艦・戦闘機が押し寄せ、兵器の恐ろしさに圧倒されました。
日本兵は、銃弾・火炎放射・爆撃など陸・海・空のあらゆるところからの集中砲火を
受けることになります。
とてもじゃないが勝てる見込みはありません。
人が物のように吹っ飛び、命を失っていきます。
それでも圧倒的戦力の前に立ちふさがったのです。
その時の心境なんて戦後に生まれた僕には想像もつきません。
ただ、戦場がどれほど恐ろしい場所か、
戦争がどれほど卑劣な行為なのかは分かりました。
そもそも硫黄島自体が過酷な場所でした。
その名の通り硫黄が立ち込め、地下道を掘ると有毒ガスが充満していたそうです。
飲み水も自力で確保できず、本土からの物資と雨水に頼っていたとのこと。
さらに上官が目を光らせ、下手な発言もできない超体育会系な社会だったのです。
こんな場所でいつ死ぬかもわからない行為をしていたのですから、
戦争って誰にとって得なのか疑問に感じました。
ストーリーは現代に戻り、兵士たちが立て籠もっていた洞窟から
多数の手紙を発見します。
その内容のほとんどが本土に残した家族の心配でした。
どんな心境だったのでしょう。
もう二度と会うことができないと確信し、それでも家族のことを思い、
届くかどうかも分からない手紙を書き残す。
手紙を書くことが心の支えになっていたのでしょうか。
書かずにはいられなかったのでしょうか。
手紙の内容がナレーションのように読まれ、映画は終わります。
戦争で涙を流すことはあっても、笑顔を作ることはありません。
戦争の恐ろしさが、ずしりと心にのしかかる映画でした。
作品としての素晴らしさは色々あると思う。 これが戦争というもので、...
作品としての素晴らしさは色々あると思う。
これが戦争というもので、きちんと観なければいけないとは思うのだけど、とにかくむごい。むごすぎる。
他の方のレビューに「人が虫けらのように死ぬ」とあったが、ほんとその通り。様々な死に方で、バタバタ死んでゆく。
2時間半つらかったーーーー
呼吸が浅くなる映画。精神的にとか表現上とかじゃなく、本当に息が苦しくなった作品。
基本的に、何言ってるか聞こえないシーンが多い。それがまたストレスとなるので、ただただ辛い。
全106件中、41~60件目を表示