ネタバレ! クリックして本文を読む
山本周五郎の原作小説を映画化した黒澤明監督の珠玉の名作。
長崎留学中に許嫁に裏切られ蹉跌を経験した青年が、名医のもとで「何のための医学か」を見つめ直すことにより再生する姿を軸に描かれるヒューマンドラマ。
本作が黒澤作品最後の出演となった三船敏郎をはじめ、青年医役の加山雄三や『天国と地獄』(1963)で演じた冷淡な犯罪者とは正反対の善良な職人を演じた山崎努、黒澤作品では姑息な小人役が多い藤原鎌足らが密度の濃い演技を見せている。
狂女役の香川京子は出番少ないながら怖いぐらいの迫真の演技。
中でも、公開時15、6歳だった二木てるみはメイクやライティングの力を借りているとはいえ、特筆ものの熱演。天才子役と評されたというのも納得。
物語の後半は、彼女が演じるおとよが病だけでなく人間性を回復する様子に付随して保本が成長する姿が丹念に描かれる。
ところが、原作のおとよはそんな重要な人物ではなく、ほんの一瞬登場するだけの役回り。そして映画では彼女と心を通わせる長次は一家心中を図ったのち、魂(たま)呼びの甲斐もなく命を落とす。
そのため、大筋で原作に沿っているうえラストもほぼ同じなのに、映画と原作では印象が大きく異なる。
個人的な見解になるが、光の射さない絶望的な世界にも一条の光が射し込むような印象の映画に対し、原作の読後感は希望の光が射し込む余地のない絶望的な世界を救うには、覚悟を決めた人間がより必要とのシビアな余韻が残る。
戦前から活躍した原作者の山本周五郎は大衆的な娯楽作品が多いなか、武士の矜持や侍の誇りといった美徳が通底していたが、戦争を挟んだのちの作品では本作の原作『赤ひげ診療譚』や『人情裏長屋』のように社会的弱者に焦点を当てた作風が主流になり、『よじょう』や『日々平安』(『椿三十郎』〈1962〉の原作)のような形骸化した武家社会の欺瞞性を揶揄する作品も目立つようになる。
直木賞をボイコットするなど、やや偏屈な人物としても知られるが、当時存命だった山本は本作を観て絶賛したといわれている。
モノクロ映像に拘った黒澤監督の到達点ともいえる本作。
明るさや光の表現を強調した演出は陰影というより「陰映」。人生のほとんどをカラー化の時代に過ごしてきたので、『銀嶺の果て』(1947)や『生きる』(1952)では作中のセリフほど白黒の画面を美しいと思えなかったが、本作は心から賞賛できる映像美といえる。
初のシネスコ作品だった『隠し砦の三悪人』(1958)では画面構成に苦闘して『用心棒』(1961)で宮川一夫の手を借りざるを得なかった黒澤監督が「ミヤガワの呪縛」から解き放たれた作品のような気もする。
NHK-BSにて鑑賞。




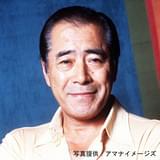





 七人の侍
七人の侍 用心棒
用心棒 天国と地獄
天国と地獄 椿三十郎
椿三十郎 隠し砦の三悪人
隠し砦の三悪人 無法松の一生
無法松の一生 竹取物語
竹取物語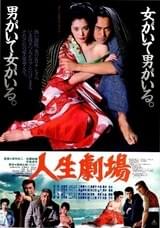 人生劇場
人生劇場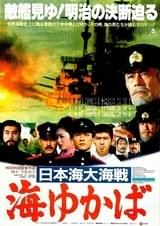 日本海大海戦 海ゆかば
日本海大海戦 海ゆかば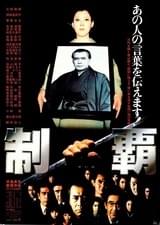 制覇
制覇











