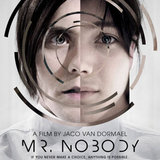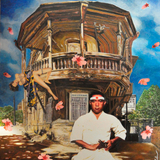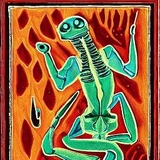時計じかけのオレンジのレビュー・感想・評価
全200件中、41~60件目を表示
悪いことしたらあかんのです...
私がこの作品を初めて観たのは30数年前、二十歳前後のことだったと思います。
相当ショッキングな内容で気分が悪くなった覚えがあります。
50歳を過ぎ人生経験もそれなりにこなしてきた今、改めて観なおしてみましたが・・・・
やっぱりとってもショッキングでシーンによっては目を覆ってしまった場面もいくつか。
1971年の作品で近未来の退廃した都会を描いたわけだけど、50年以上経った今もこの映画を観るとこの先世の中どうなっていってしまうのかという強烈な不安感を抱いてしまう。いつまでたっても追いつけない感覚。キューブリックの異次元的な頭の構造のなせる業なんでしょう。
今も巷ではいじめ、迷惑動画、盗撮から強盗殺人、銃乱射大量殺人に至るまでいまだ毎日世界中で犯罪が横行しています。悪いことしたらこうなっちゃうんですよってこの恐ろしい映画を観せたら抑制になるんでしょうか。それとも報復による刑罰は時代錯誤とネガティブな印象受けるだけなんでしょうか。是非とも若い人たちにこの映画を観てもらって感想を聞かせて欲しいものです。
暴力とはなにか?
見るに耐えない、目に見える暴力
そして見えない暴力(親切な顔をした思惑や…)
はじめ老人のリンチや女性のレイプなどの過激な暴力シーンに目を薄めていたが、青年が更生される過程、その後にも暴力は続く。
目に見える暴力から解放されたが、実際のところ、その暴力の種類が移り変わっただけなのかもしれない。
暴力へ嫌悪感を感じながらも、暴力を振るってきた青年が暴力を振るわれる姿に、どこか快感を感じている私の中にも。
見ている者を聖者では居させてくれない、鋭い問いのある映画だった。
ほんとに面白いのは後半のどんでん返し!
過去鑑賞
独特な世界観だったけど
普通に最後まで楽しめた
目をガン開きにする“治療”という名の拷問とか、因果応報なところとか、いろいろな要素があった作品だったけど、特に気が散ることなく楽しめた。
因果は巡る
もう一つの未来
近未来の都市、非行少年も多く犯罪率の上昇や刑務所の敷地不足が問題となる
グループで軽犯罪を繰り返すアレックスは仲間の裏切りにあい刑務所行きになってしまう
そんな中特殊な治療を受ければすぐに釈放になるという話が
洗脳まがいの治療を受け、自由のみになるも過去の自分に復習され続ける
最後には自身を洗脳した政府のイメージキャラクターとして洗脳による報酬を与えられながら映画は終わる
形として犯罪がなくなれば人権など意にも介さない政府、犯罪者に対する復讐を糧とする刑務所
悪しき風習が過激に描かれている
〝レイプ〟と〝超暴力〟と〝ベートーベン〟を、悪趣味とする青年の冒険を描く。
私の知る限り、『時計じかけのオレンジ』は史上最高の映画のひとつである。この「芸術作品」によって、スタンリー・キューブリックは、映画をミケランジェロの芸術のレベルにまで高めた。
ポルノと芸術の境界で、映画の評価を妨げたり複雑にしたりするのは、いわゆる「性的描写」である。
この点、『時計じかけのオレンジ』は、『愛のコリーダ』とは異なり、一見して著しく性的に露骨であるようには見えない。
しかし、ハイパーセクシャルで煽情的なイメージの連合体であるにもかかわらず、脚本、メイクアップ、ベートーベンの音楽、インテリアや調度品、未来的な家具、プロダクションデザインの完璧さによって、映画そのものはエレガントに見える。そしてそれは、撮影スタッフ全員のテクニックと想像力によって完璧に造形されている。これは、ズームアウトや過激な撮影技術にも起因している。
『時計じかけのオレンジ』は、ポルノ的であり芸術的でもあるが、決して下品ではない。
それにもかかわらず、チャールズ・チャップリンやジャン=リュック・ゴダールの作品と比較すると、この映画は著しく過小評価されているように思える。
しかも、映画は出演者の名演技なくして名作とは言えないにもかかわらず、この映画には「泣き虫」や「感傷的な出演者」がほとんどいない。
これは、「映画は監督のもの」という固定観念を作り出したキューブリックの完璧な自己防衛である。
ため息が出るほど鮮やかで美しく、時に暴力的で、時に狂気に満ちたこの136分の映画は、まるで写真展に足を踏み入れたような気分になる。
キューブリックの優れた写真センスを視覚的に示すものである。すべてのシーン、すべての静止画が、A級写真の集合体である。このような映画は他にない。
未だ時代が追い付いていない
いやぁな気持ちになれます
部屋とか衣装はおしゃれだけど、描写が見るに堪えない サイコパス
始めっから、気分が悪くなる映像です。
レイプのシーンや性描写ばっかりで、そういうような描写に触れたくない人は絶対に見ない方がいい!
そして、もちろん子どもは見てはダメだし、青年や若者は思考に影響を与える可能性があるので、みない方が良いと思います。上映禁止になった理由もよくわかります。
私も大人ですし、一線を置いて一つの作品として鑑賞できるくらい客観的に見れるようであれば良いのかも知れませんが、また私の脳みそに余計な画像がインプットされてしまったという気持ちがあります。
暴力が面白いとか言っている人は本当にやばいと思う。
ただ、スタンリーキューブリックの作品は、とにかくサイケでおしゃれ。
非日常の雰囲気を漂わせて、精神世界の話しのような感じにさせますよね。
あと、重厚感のあるBGMもキューブリックだなって思いますし、一つ一つの描写に妥協がないというのが素晴らしいなと思います。
そこが評価が高いポイントかも知れません。
50年も前の作品なのに、全然色褪せないし、斬新で新しいです。
評価が高い作品なので、頑張ってみました。
あんまり繰り返し見ると、精神病になってしまいそうです。
そこまで影響力のある映画だと思います。
精神力が落ちている時や、疲れている時はみない方が良いと思います。
映画に引きずられて病になってしまうと思います。
衝撃
これまた解釈が難しい。
まさにキューブリック作品で解釈の難しい映画だけど、その雰囲気だけでも楽しめる良作。ところどころ挟まれるナッドサット言葉が妙に癖になり、中盤からは理解できるのがまた不思議。
欲望に忠実すぎる主人公たちに共感はできないが、二転三転するアレックスの人生模様が面白かった。
人間の持つ欲望に兎に角忠実なアレックスは友人の中でもリーダーでいたがり、徐々に亀裂が膨らみ、ある夜強盗に入る家で裏切られ、警察に捕らえられる。それまでの行いから当然なのだが、そこからのアレックスは少し可哀想。好きだった音楽すらトラウマになるほど過激な治療を受け、暴力などに吐き気を催すなど、強制的に非行に走れない身体にされる。しかしそれを利用した反政府の圧があり、結局は欲望に忠実なアレックスに逆戻りというバッドエンド。原作はハッピーエンドらしく、そっちも見てみたくなった。
人によって感性は異なるとしても人生最高の一本にはなり得ないし、オススメしづらい映画だが、映画好きなら一度は見ておきたい作品だし、好きな作品の1つにならなり得る、そんな映画。
ヒューマニズムの偽善批判と英国病理への風刺
この映画でキューブリックは二つのことを描いている。
一つは世界を覆うヒューマニズムはウソで、人間は他者に対する攻撃本能があり、バイオレンスは快楽である、ということ。
二つ目は、揺り籠から墓場まで個人の生活に介入し、英国病をもたらした英国福祉政策に対する風刺である。
1)ヒューマニズムのウソについて
一つ目のヒューマニズムのウソという点は、社会のタブーに挑むキューブリックの面目躍如たるところ。
主人公たちが悪ガキグループや安穏に暮らす人々を襲い、破壊し殴り蹴り斬りつけレイプするシーンは、人間にとって暴力がいかに快感かを、これでもかと言わんばかりに観客に見せつけた。
対立する悪ガキグループのリーダーは、主人公からの悪口雑言をニヤニヤ聞き、嬉しそうに飛び出しナイフを取り出して、グループ全員が闘いに突入していく。
今ならヘビメタコンサート会場で、聴衆が喜び勇んでモッシュ(押しくら饅頭)に突入するするさまに似ている。
バイオレンス映画といえばペキンパー監督作品がその代名詞であり、すでにこの頃、「ワイルド・バンチ」などが公開されている。
しかし、そこには暴力は人間にとって快楽であるという自覚的な思想は伺えず、そのような自覚的、思想的「バイオレンス映画」は、この作品から誕生したのだと思われる。
2)英国の社会国家政策の愚かさについて
次に、こうしたバイオレンス男を英国社会は、どのように扱うか。
英国の社会国家政策は「揺り籠から墓場まで」と揶揄されたように、個人の生活に過度に関与し、その財源を国民、企業から重い税負担で徴収したことから景気が低迷。そのさまが英国病と呼ばれたことは有名である。
重い税負担については、ビートルズの「タックスマン」やキンクス「サニーアフタヌーン」などが批判や揶揄をこめて歌っている。
本作の後半は、「揺り籠から墓場まで」への風刺と言え、犯罪者の教育、矯正、果ては人格改造にまで乗り出す、個人への国家の過度な関与への風刺となっている。
多数の専門家と物量と時間で、主人公はバイオレンス男から、見事に暴力のぼの字さえ恐れる哀れな少年に変身してしまう。
しかし、それは逆に本人に対する暴力を呼び込み、その果てに自殺にまで至らせる。
そのドタバタが終わった時、人格改造の呪いが解けると、何が現れるのか…もとのバイオレンス男である。
こんなバカな個人への干渉をやるのは愚の骨頂だ。何故なら暴力は本能なんだから…というのがラストシーンの意味だろう。
3)評価
社会のタブーに対するキューブリックのバイオレンスが、全面的に解放された見事な映画だ。
さらに英国的形式主義を揶揄したシーンもたっぷり盛り込まれ、例えば主人公が刑務所に収監されるとき、白線の前に踏み出さないよう脅されるところなど、「ああ、英国病だなw」と感じる。
自業自得
全200件中、41~60件目を表示