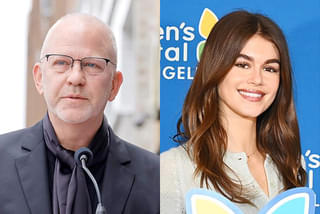ネタバレ! クリックして本文を読む
イカのラビオリ、チーズパイ、ルッコラのサラダ、メカジキのミートローフ、ラズベリーソースを添えたウズラのロースト、ウサギ肉のグリル――オープニングで映し出されていくのは、“美”と“味”の両方が追求された、獣や魚、植物たちの殺害現場。スノッブな人々の欲を満たすべく、シェフは“遺体”を華麗に処理していく。そんなスマートさと対照的なものが、主人公・パトリック・ベイトマンによるアッパーな殺人だ。
ベイトマンは、81丁目ウエストサイドに住む27歳のエリートサラリーマン(=ヤッピー)。自分のケアも、決して欠かさない(ボディスクラブ、ジェル、ノンアルコールのローション、ミントのパック――朝の身支度の流れが最高のテンポ感)。完璧な肉体を高級スーツで包み、一流の同僚たちと最高のレストランで会話(中身は空虚で下世話)。仕事は、誰かと会食をしていれば万事OK。でも、名刺の質だけは、誰にも負けたくはない。そんな彼には“快楽殺人者”としての裏の顔があった、というのが本筋だ。
顔立ち、身だしなみ、学歴――全て非の打ち所がないライバルの出現から、ベイトマンの殺人行為は加速していくのだが、どれもこれもずさんものばかり。殺した遺体を詰めた袋から血が滴り、通りすがりの者を躊躇なく殺害。警察に発砲、遺体は隠れ家へ隠してしまう……まるで現実味がない。印象的だったのは、遺体を運んでいる時、知り合いに遭遇するパートでの「パトリックか?」「いいや“俺”じゃない。間違いだ」というセリフ。ジャンルとしてはサイコホラーに属しているが、本作はブラックコメディの側面の方が強い。
クライマックスに訪れるのは、解釈の分岐だ。真実と虚構、どちらをとっても良いように描かれているので、他人との議論が捗るはず。こんなことも考えられる。ベイトマンは、生気のない目でエリート社会の鉄則「中身なんて関係ない(外見だけでいい)」と語っている。ベイトマンの殺人行為も、中身(=理由)はなく、外見(=結果)だけだった。しかし、その外見すらも消え失せたことで、全ての“意味”を失った……「何もない」という断定は、彼にとって最も耐え難いものだろう。ラストの“顔”は、あまり空虚だった。
余談:なんといっても、クリスチャン・ベール!濃ゆい芝居がしっかりと堪能できます。“鏡の中の自分を愛でるSEX”はかなり笑えますし、「悪魔のいけにえ」の亜種ともいえる“血まみれ全裸チェーンソー男(スニーカーを履いているのがミソ)”はやっぱり衝撃的。











 ダークナイト
ダークナイト ダークナイト ライジング
ダークナイト ライジング マネー・ショート 華麗なる大逆転
マネー・ショート 華麗なる大逆転 バイス
バイス バットマン ビギンズ
バットマン ビギンズ フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法
フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法 スパイダーマン
スパイダーマン アムステルダム
アムステルダム アメリカン・ハッスル
アメリカン・ハッスル 永遠の門 ゴッホの見た未来
永遠の門 ゴッホの見た未来