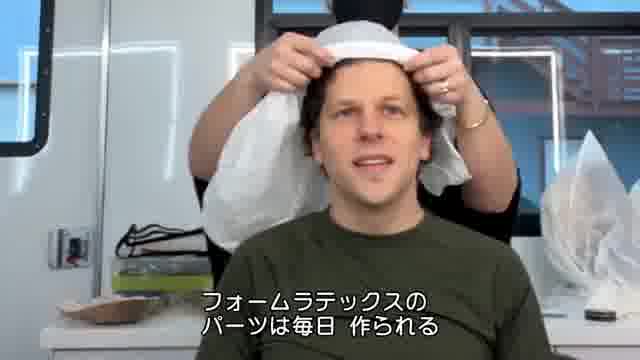サスカッチ・サンセット : インタビュー
生き残りをかけた「生存」の物語だからこそ人類も共感できる――ゼルナー兄弟が語るサスカッチ(=ビッグフット)への愛

Copyright 2023 Cos Mor IV, LLC. All rights reserved
ネッシー、ツチノコ、チュパカブラ……世界中の人々が魅了され続けてきたUMA(未確認動物)。そんなUMAの代表的存在、「毛深い巨人」ことサスカッチ(別名:ビッグフット)の生態に迫るかつてないネイチャー・アドベンチャー映画が誕生した。それが5月23日に公開となる「サスカッチ・サンセット」。サスカッチ目線で生き残りをかけた激動の1年を台詞なしで描く異色作だ。
心優しいオスのサスカッチを演じたのは「リアル・ペイン 心の旅」で監督・脚本・主演を務め、多彩な才能を発揮しているジェシー・アイゼンバーグ。ボディスーツと特殊メイクで身体と顔を覆い隠しながらも、完璧な動作で見事にサスカッチを体現する。またメスのサスカッチを演じるのは「マッドマックス 怒りのデス・ロード」のライリー・キーオ。鬼才アリ・アスターが製作総指揮として参加する本作のメガホンをとったのは、菊地凛子主演映画「トレジャーハンター・クミコ」やテレビドラマ「THE CURSE ザ・カース」などで知られるゼルナー兄弟ことデビッド・ゼルナー&ネイサン・ゼルナー。彼らが10年以上の歳月をかけて完成させたという「サスカッチ・サンセット」にはどのような思いが込められているのか、ゼルナー兄弟に語ってもらった。(取材・文/ISO)
【「サスカッチ・サンセット」あらすじ】

Copyright 2023 Cos Mor IV, LLC. All rights reserved
北米の霧深い森に生きる4頭のサスカッチ。アルファオス(※)が率いるその群れにいるのは、 つがいのメスとその子ども、そしてもう1頭のオス。彼らは寝床をつくり、食料を探し、交尾 をするいつもの営みを繰り返しながら、どこかにいると信じる仲間探しの旅を続けていた——。
※アルファオス…群れのトップに君臨するオスのこと

Copyright 2023 Cos Mor IV, LLC. All rights reserved
●何故「サスカッチ」に心惹かれた?「ある意味で自然と人間のつながりの象徴とも言える」
――子どもの頃にパターソン・ギムリン・フィルム(※)を観て以来、サスカッチに魅了され続けてきたと伺いました。2010年にはサスカッチを描いた短編映画「Sasquatch Birth Journal 2」も製作されていますが、サスカッチのどういう部分に惹かれ、映画の題材にしたいと感じたのでしょうか?
デビッド・ゼルナー(以下、デビッド):おっしゃるとおり、我々は子どもの頃からサスカッチ(=ビッグフット)の伝説に魅了されてきました。それはきっと、サスカッチが自然界や動物界と人間の狭間にいるような存在だからでしょう。ある意味で自然と人間のつながりの象徴とも言えるかもしれません。日本には妖怪のような我々も大好きな民話や伝説がたくさんありますが、アメリカにはそういったものが数えるくらいしかなく、サスカッチほど広く知られた存在は他にいません。だからこそ我々はサスカッチに惹かれ続けているのだと思います・
ネイサン・ゼルナー(以下、ネイサン):パターソン・ギムリン・フィルムをテレビで観た子どもの頃は、今のようにスマホで撮影された不思議な動画がたくさん流れてくるような時代ではありませんでした。当時の我々からすると、パターソン・ギムリン・フィルムは本当に珍しく日常とはかけ離れたものだったからこそ、不思議な興奮を覚えて深く記憶に刻まれたのでしょうね。それは我々が映画業界を目指すうえでも影響を与えたと思いますし、監督として成長するなかで初期衝動をもらった存在に改めて立ち返りたいという気持ちから自然とサスカッチを題材にしたのだと思います。人間目線ではなく、サスカッチ目線で物語を描こうというのはその当初から考えていたことでした。
※パターソン・ギムリン・フィルム…1967年10月に撮られた「サスカッチ(=ビッグフット)」らしき生物が映った短い動画のこと。未だその真偽は明らかでないという。

Copyright 2023 Cos Mor IV, LLC. All rights reserved
●「サスカッチ」を徹底リサーチ!世界中に“バージョン違い”がいるという事実に魅了される
――ネイサンさんが語られたとおり、本作はサスカッチ目線のネイチャードキュメンタリーのような仕上がりとなっていますね。これまで映画におけるサスカッチといえば人間を襲うモンスター的存在として描かれてきましたが、「サスカッチ・サンセット」をまったく異なる独自のアプローチでつくった理由を教えてもらえますか?
デビッド:サスカッチをモンスターのような存在ではなく現実的な存在として描きたかったのです。だからこそ、我々はサスカッチのなかに観客が共感できる人間的な部分を見出しつつ、彼らを動物界の一員として自然主義的に映し出すことを選択しました。

Copyright 2023 Cos Mor IV, LLC. All rights reserved
――サスカッチの生態、食事、日々の行動を構築していくうえでたくさんリサーチを行ったと思いますが、その過程で興味深いと感じたことはありましたか?
ネイサン:アメリカにはサスカッチに関する様々な伝承がありますが、サスカッチと同じく「森のなかに暮らす人間に似た毛深い獣」の伝承は世界各地の様々な文化圏にあります。たとえばネパールのイエティやオーストラリアのヨーウィーなどですね。そういうサスカッチのバージョン違いが世界中にいるという事実は、我々をさらに魅了していきました。
またアメリカには、サスカッチの断片的な証拠を解明するためにたくさんの時間を費やす疑似科学的な研究者や自称科学者たちによる大きなコミュニティが存在します。そのコミュニティが面白いのは、メンバー間でサスカッチに対する見解が一致している部分もあれば、基本的に確証がないため各自見解が異なる部分も多く、頻繁に議論が行われているということ。そのコミュニティの人々に話を聞いたり独自のリサーチをしながら、皆の意見が一致している部分を抽出し、サスカッチの物語として構成していく作業はとても楽しかったですね。たとえば劇中でサスカッチたちが木を叩いて音を出しますが、あの行動はサスカッチが互いにコミュニケーションを取る方法だと言われています。また仲間を埋葬した場所に木の飾りを置くというのも実際にある説として聞きました。とはいえ未知の部分がかなり多い生物なので、いろんな要素をつなげて物語を構築していくうえで独自の解釈やアイデアも入れていきました。

Copyright 2023 Cos Mor IV, LLC. All rights reserved
●「サスカッチ」研究者たちの反応はどうだった? 一番苦言を呈されたのは……
――サスカッチの生態は定説に沿って描かれているとのことですが、本作に対するサスカッチ研究者たちの反応はいかがでしたか?
デビッド:反応は人それぞれでしたね。というのもサスカッチの伝承や定説には多くのバリエーションが存在し、皆が独自のサスカッチ像を持っていますから。しかもサスカッチを研究しているのは文化人類学者から愛好家までいろんなタイプの人がいるので、見解が非常に幅広いんです。なので本作のサスカッチ描写に納得してくれる人もいれば、自分のサスカッチ像と齟齬があるため受け入れられない人もいました。本作のサスカッチ描写は事実と異なると主張する人もいましたが、それを証明する証拠もありませんからね。要はかなり賛否両論でしたが、我々にとって大切だったのはそういったコミュニティの人々が本作に対し感情的な反応を示してくれたことでした。
ネイサン:一番苦言を呈されたのは、サスカッチに生殖器があるという点でした。我々はサスカッチを人間やその他の動物たちと同じく、生殖器があり、交尾し、子どもを産んで育てる生物として描きたかったんです。ペットとして飼っている犬も動物園の動物たちもみんな裸で生殖器が見えていますよね。本作のサスカッチはその延長線上として描写したのですが、一部の人たちは「サスカッチはもっと神聖な生き物だ」と否定していました。

Copyright 2023 Cos Mor IV, LLC. All rights reserved

Copyright 2023 Cos Mor IV, LLC. All rights reserved
●不条理で悲劇的な死が描くことで「生存」の物語を紡ぎ出す
――日常のなかで突然「死」が描かれることも本作の特色ですね。タイトルの「サンセット=日没」という言葉に込められているとおり、終わりに向かう種族の物語でもあると思いますが、あえて愛するサスカッチをそのように描いた理由は何なのでしょうか?
ネイサン:サスカッチたちの未来が不確実であり、人類が開発などで自然界に及ぼす影響もテーマとして含まれていることから、少しメランコリックなトーンと「サンセット」という表現が相応しいと考えました。おっしゃるとおり本作では突然「死」が降りかかりますが、そのなかでサスカッチたちがいかに生き残るために奮闘するかという「生存」についての物語です。この世界でどのようにして生き残るかというのは人類にとっても遥か昔から語られてきたテーマであり、歴史のなかでも語られてきたような人間的な苦悩が本作に含まれているからこそ、サスカッチが題材ながら多くの人々の共感を呼ぶのではないかと思います。
デビッド:一部のシーンは荒唐無稽で笑えるように描いていますが、その一方で突然不条理で悲劇的な死が襲いかかります。観客は突然の死に驚くかもしれませんが、ネイチャードキュメンタリーを観ていても動物の死は予想していないタイミングで訪れますよね。それと同じ感覚で描きたかったんです。

Copyright 2023 Cos Mor IV, LLC. All rights reserved
●セリフ“ゼロ”というチャレンジングな試み プロジェクトの要は俳優陣の挑戦的な姿勢
――台詞が一切ないなかで4匹のサスカッチの内面やキャラクター性、関係を表現することは非常にチャレンジングだったと思いますが、どのようなことを意識しながら脚本を描き進めていったのでしょうか?
デビッド:脚本を書くうえで、ドラマチックな展開やコメディのタイミング、視覚的な要素についてはかなり細かく書き記すようにはしました。そのなかで感じたのは、これはサイレント映画をつくるようなものだということでした。普通の映画であれば多くの情報は台詞を介して伝えられますが、本作にはそれがありません。なのでサスカッチの肉体的な表現や顔の表情であらゆることを表現する必要がありました。本作の撮影ではサスカッチのボディスーツで俳優の全身を隠してしまいますが、目だけは覆わずそのままにしたんです。なぜなら目を人間のままにすることで、観客にサスカッチの魂と繋がってほしかったから。俳優陣は目でいろんな演技をする必要があったので大変だったと思いますが。

Copyright 2023 Cos Mor IV, LLC. All rights reserved
――ジェシー・アイゼンバーグをはじめ、俳優陣にとって顔も身体も隠して演技することは初めての経験だったと思います。彼らをディレクション・撮影した監督にとっても、改めて俳優の技術を感じる体験だったのではないでしょうか。
ネイサン:何より本作に出演してくれたことが純粋にすごいと思いました(笑)。
デビッド:ボディスーツを着て、サスカッチに扮するだけであれば俳優でなくともできます。でも我々はサスカッチたちからあらゆる感情を引き出したいという気持ちが強かったからこそ、スタントマンではなく俳優に演じてもらいたいと考えました。ただ本作では全編にわたり顔も映らないボディスーツを着て演じる必要があるので、俳優の皆さんは俳優として普段とはまったく異なる演技を学び、自身を表現するという覚悟が必要だったと思います。これまで培ってきた技術やツールを使わずに、新しいことに挑戦するわけですからね。でもジェシーとライリーは特にそんな挑戦に興奮していたように思います。我々だけでなく俳優陣の挑戦的な姿勢こそが、このプロジェクトにとってとても重要だったと思いますね。

Copyright 2023 Cos Mor IV, LLC. All rights reserved
――製作総指揮のアリ・アスターとのお仕事はいかがでしたか?
ネイサン:我々が主にやりとりしていたのはアスターのビジネスパートナーであり、長年の知り合いでもあるラース・クヌードセンでした。想像していたことではありますが、本作の企画を実現させるのはとても大変な道のりだったんです。でも彼もアスターも、この企画を誰にも見向きされない段階から信じてくれて応援してくれました。二人が早い段階からこのプロジェクトに携わってくれたからこそ、本作をつくることができたのだと思っています。
●参考にした作品は? 次回作SFコメディ「Alpha Gang」はどうなってる?
――本作を製作するうえで影響を受けたと感じる作品はありますか?
ネイサン:いろんな作品から影響されたと思います。たとえば「2001年宇宙の旅」。とりわけ冒頭の猿が骨を拾い道具として使用する“進化”を描いたシークエンスは深く心に刻まれていました。1968年の「猿の惑星」も大好きなので、少なからず影響を受けたのではないかと思います。またそれと同じくらい本作のインスピレーション元となったのは、動物たちを追ったネイチャードキュメンタリーや実際の動物たちですね。特に猿やゴリラなどの類人猿の行動はとても参考になりました。また作中の動物的な行動に関しては、我々が子どもの頃から飼っていたペットの犬や猫の行動も参考にしました。

Copyright 2023 Cos Mor IV, LLC. All rights reserved
――最後に、次回作のSFコメディ「Alpha Gang」(原題)について教えてください。ケイト・ブランシェットが主演・製作するほか、デイブ・バウティスタ、レア・セドゥ、スティーブン・ユァン、ゾーイ・クラビッツ、チャニング・テイタム、ライリー・キーオという錚々たるキャストが揃っていますね。間もなく撮影が始まるそうですが、可能な範囲でどんな魅力を持った作品になりそうか伺えますか?
ネイサン:まだ撮影前なのであまり言えることはないのですが、素晴らしいキャストにスタッフが集結してくれたのできっとすごい作品になるんじゃないかと我々もワクワクしています。撮影が始まるのが待ちきれないですね。
デビッド:以前監督した「トレジャーハンター・クミコ」は日本で撮影したのですが、とても素晴らしい経験として記憶に残っています。なのでまたいつか日本で映画を撮りたいですね。そのときは怪獣映画にトライするかもしれません(笑)。
――日本が舞台の怪獣映画、ぜひ観てみたいですね。その時が来ることを楽しみにしています!