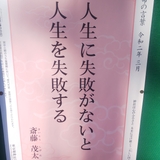52ヘルツのクジラたちのレビュー・感想・評価
全286件中、101~120件目を表示
飲酒シーンが宣伝に見える
映画としては最後まで飽きることなく観れました。しかし飲酒シーンがサントリーの宣伝に思えてしょうがなかったです。虐待やトランスジェンダーの苦悩と同じにはできないですが、アルコール依存症に悩む人もいる中で違和感しかなかったです。特にこの映画のストーリー的には。それがなければ5にしました。
誰かを救う事ができる映画
魂のつがい
52ヘルツって高いの?低いの?と調べてみると、
楽器だとチューバの一番低い音らしい。
でも、他のクジラたちはもっと低く、
シロナガスクジラで10~39ヘルツ、とか。
となると、52ヘルツは確かに高く、
他のクジラたちには聞こえない、ということになる。
観た感想は、というと・・・
児童虐待、ヤングケアラーという重いテーマ、
それを背負った、主人公きなこ(きこ)。
でもそんな苦しい状況にいた、きなこ(きこ)を救ってくれた、
心の声をキャッチしてくれたのは、通りすがりのあんご(あん)。
「家族の呪い」から、きなこ(きこ)を解放してくれた。
そんなあんご(あん)を「魂のつがい」かと思ったが、
実はあんご(あん)は性別不合、そしてトランスジェンダーであり、
きなこ(きこ)の幸せを祈りつつも、自身の苦しんでいる心の声は
残念ながら届かなかった。
そして、それは実の母親にも。。
その後、自身と同じように虐待に苦しむ少年と出会い、
その少年の心の声を聴き、守ろうとする、きなこ(きこ)。
そして、ラストは・・・
かなり心が苦しくなる、重いテーマ連発のストーリー、
でも、明るい未来がやってくるよう、前を向いていこう、
って思えると良いな。
ワンピースのルフィがビビに言う
「お前の声ならおれ達に聞こえてる」
を思い出してしまった。
(シチュエーションとか全然違うけど)
きなこ(きこ)を演じた、杉咲花さん、よかった~、うまかった。
虐待のシーンは可哀そうだったけど。。。
あんさんの志尊淳さん、あごひげを生やしている時点で珍しいな、
と思ったけど、そこで逆に違和感をおぼえ、すぐわかってしまった。
ぼっちゃん専務の宮沢氷魚さん、狂気入ってくると怖い。
昨年観たレジェンド&バタフライの光秀を思い出した笑
心に傷を抱える孤独な人々
彼らの声が誰かに届くことはない。
ごく一部の例外を除いては。
母親に虐待されて声を失った少年と出会ったキコ(杉咲花さん) 。彼女は少年のSOSに気づいた。
キコにも虐待を受けた過去があった。
母親の暴力に支配されてきたキコ。親友のミハル(小野花梨さん)やその友人のアンさん(志尊淳くん)のサポートを受け母親から逃れた。
そう、キコの声はミハルやアンさんに届いた。
それにしてもアンさん。悟ったような前半とボロボロの後半のギャップはいったい?
アンさんが理解できなかった。
あの流れで何故閉じたのか理解できなかった。
そう、アンさんの声は誰にも届かなかった。
アンさんこそが52ヘルツのクジラだった。
ちなみに演出過多か感情が入り過ぎたのか、志尊くんと宮沢くんはエモーショナル過ぎやしないか。
孤独と絶望
原作がかなり話題になって、自分がリスペクトする方々がことごとく傑作と言っておられたので、ずっと気になってて、読もう読もうと思っている内に、先に映画が公開になった。
公開一週間で上映時間がグンと減り、見逃していけないと慌てて劇場へ。
くらった。
素晴らしい映画だった。
どんなに孤独を感じても、絶望しようとも、逃げても良い、生きる事を諦めてはいけない、と訴えてくる。
主演の杉咲花さん、「市子」に続き、素晴らしかった。他の演者の方々も、脇に至るまで素晴らしい。
多少、映画ならではの過剰な部分はあれど、ラストに向かう為に必要であり、気にならなくなる。
見終わって、益々原作が読みたくなった。
余談ですが、エンディングは原作にインスパイアされてつくられた、うぴ子さんの「52ヘルツの唄」なら完璧だったなぁ。
原作もキャストもいいのに...
久々に、心が震えました。
観終わった今は、現代的な課題をよくあれだけ入れて、お話をまとめたなあと、感心しています。
イヤフォンで52ヘルツのクジラの声を聴くだけで、脳内にクジラが雄大に泳ぐ姿がイメージできたので、最後の迷いクジラの出現は不要だったかな。
今作で一番不思議な人物、あんさん。
きこさんへの接し方や、紡ぐ言葉は、すごく優しい。
きっと壮絶な人生を過ごしたんだろうなとは想像できました。
反面、なぜこんな中途半端かつ似合わないひげを生やしているのか、あんさんの表情や言葉、態度に強い違和感を抱くのか、分からなくてもやもやしました。
きこさんの過去の話の方に強く惹かれてどんどん映画の中に没入していきました。
中盤、あんさんの過去が分かった時のカタルシス。
中学生の時に、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」で体験した初カタルシス以来のスッキリでした。
なるほど、だからかと、非常に納得しました。
この部分だけでも、ホントに観てよかったと心から思いました。
本当に欲しいものを手に入れたいなら、失うかもしれないというリスクを冒す必要がある。
きこさんもあんさんも、本心を伝えあっていたら、ハッピーエンドになっていたかもね。
「女でも男でも、生きていて欲しかった」
「心からあなたの幸せを祈ります」
まさしくこれらは、子を持つ親の気持ちです。
私も、生きているわが子に、ちゃんと直接伝えなきゃ。
実の親から、こういう言葉をもらえない子どもたちの支援をしている身の上としては、気が引き締まる思いです。
この気持ちを忘れないように、ブルーレイを買って、何度も何度も、この映画を観賞しようと思いました。
要素過多なのに内容散らかってなく見やすい
ステレオタイプをなぞらせる理由は何なのか
杉咲花の熱演、志尊淳の支え、小野花梨の友情、子役の子のたたずまい、西野七瀬の豹変、池谷のぶえや倍賞美津子の味わい等々、トンデモ男の宮澤氷魚であっても、アパート玄関口でのシーンなど、良いところは山ほどあり、語りたいところもいっぱいあった。
なのに、トータルで自分はのれなかった。
なぜなのかを考えると、「演出が自分には合わなかった」というところに尽きる。
<以下はグチなので、読みたくない方はスルーして下さい>
一つは、様々な場面で「ほら、ここは感情を昂らせるところですよ」とささやいてくる(叫んでくる)かのような、大げさなストリングスがやたらと耳についたこと。
二つ目は、ラスト近くの杉咲花と少年の場面のように胸を打つセリフがあってグッときているところで、まさかの過剰演出でアレが登場…。盛り上げようとされればされるほど、気持ちが冷めてしまった。
そして三つ目は、登場人物の抱えている問題が、とことんステレオタイプにわかりやすく処理されていて、薄っぺらく見えてしまったこと。
原作は未読なのだが、その世界観を大事にした演出だったのだろうかと疑問に思った。
虐待やDVや性自認の問題に対して、観る側のステレオタイプな見方をなぞるかのような演出は、前日に観た「アメリカンフィクション」の中に出てくる、主人公モンクがヤケになって書いた小説と重なるが、それをよしと考えてわざわざやっているように見えるところが、自分には受け入れがたいのだと思う。
志尊淳演じる安吾は、杉咲花演じる貴瑚を救うにあたって、単に言葉だけでなく具体的な支援プランを探るところを丁寧に描くなど、雰囲気だけの話とは一線を画していてハッとさせられるし、虐待している母にかける言葉なども、本当に深い。
それらを、過剰な演出なしに、淡々と描き重ねるのは、日本の商業映画としては成立しないのだろうか。
と書いて投稿し、読み返してみたら、そここそが「夜明けのすべて」との違いなんだとわかった気がした。ちゃんと商業映画として、成立している作品もあるのにな。
(追記)
原作を読んだところ、52の支援について納得できる形で具体的に描かれているし、映画ではカットされているが、支援者の距離感についての重要な人物(美音子)も登場している。映画の尺や登場人物の精選という事情もあったのだろうが、そのせいもあって情緒的な押し出しが強く、違和感を感じてしまった面があるなと思った。
アレも、原作では大げさではなかったし…。
家族という呪いからの解放
非常に濃密で悲哀に満ちた物語。最後は少し希望の持てる終わり方
小説は未読です。序盤から児童虐待、ヤングケアラー、DV、性同一性障害など悲しく重苦しい展開が続きます。2時間30分の映画ですが、すごく濃密でまったく長さを感じさせません。メッセージ性含め改めて邦画の力を感じた映画でした。また、非常に難しい役どころを演じ切った杉咲花さんの演技力も素晴らしかったです。
タイトルの『52ヘルツのクジラ』とは、声をあげても届かない人々を比喩したものですが、劇中にはそんな声を上げられず苦しんでいる人々の姿が描かれています。この映画では声を出すことで救われた人、声を出したけど受け入れられず自死を選んだ人などが描かれており『声に耳を傾けることの大切さ』について改めて考えさせられる良作でした。
ひとつ難点を挙げるなら、連ドラでもいいくらいの内容を2時間30分にギュッと凝縮して詰め込んだため、ひとつひとつの掘り下げが浅く、行間を自分で埋めないとなかなか理解や感情移入が難しかった点については惜しまれます。
ここからはあらすじ
杉咲花演じる貴湖は幼少期から日常的に母親の虐待を受け、ネグレクトの状態にありました。さらに高校卒業後は家から一歩も出ず、継父の介護に追われる日々を送っていました。
そんなある日、介護中に継父が誤嚥性肺炎を起こします。母親はそれを貴湖の責任だと咎め『おまえが死ねばいいのに!』と罵倒し、暴行した挙句、首を絞めて殺そうとします。その場にいた医者に止められ、辛うじて命は取り留めましたが、貴湖は深く傷つき自殺を図ります。
間一髪のところで志尊淳演じるアンに救われますが、アンは抜け殻のような貴湖の精神状態を心配し、美晴(貴湖の元同級生)と共に貴湖に寄り添い、必死に心の声に耳を傾けます。
その後、貴湖は母親と距離を置くため、美晴の家で生活することとなり、徐々に母親からの精神的呪縛が解かれて自我を取り戻していきます。そして、意を決した貴湖はアンを伴い、直談判して母親と絶縁することに成功します。
そんななか貴湖は次第にアンに好意を寄せるようになり、告白します。しかし、アンは(本当は両想いだったのにもかかわらず)『貴湖は心の友だよ』と言って告白を断り、貴湖も落胆はしながらもそれを受け入れます。
そんな貴湖ですが、しばらくして職場の上司である新名に見初められ、恋人関係になります。新名は会社の重役であり、いずれ会社を引き継ぐ社長の跡取り息子というエリートの大金持ち。貴湖と新名は何度も男女の関係を持ち、同棲を始めます。
そして、貴湖はアンと美晴を新名に紹介します。しかし、新名は貴湖とアンとの関係にただならぬ雰囲気を感じたのか、アンに対し強烈な嫉妬心を抱き、それを露骨に顕します。そのことでアンと新名は険悪の仲となります。
そんななか新名には貴湖とは別に婚約者がいたことが発覚します。ショックを受ける貴湖。しかし、新名は貴湖に『これは父親にごり押しされた政略結婚で、本意ではないし愛もない。愛してるのは貴湖だけだ』と言って、貴湖もそれを受け入れ同棲を続けます。
しかし、しばらくして新名の婚約者宛てに、貴湖と新名の同棲を告げ口する手紙が届きます。それにより新名の婚約は破談となり、新名は両親の怒りを買って職も失います。新名は自暴自棄となり、酒浸りの日々を送り、さらには貴湖に暴力まで振るうようになります。
そして、その手紙は貴湖と新名の仲を引き裂くためにアンが送ったものでした。
すべてをぶち壊された新名はアンへの復讐を企てます。新名はアンの身辺調査を行い、アンがトランスジェンダー(心と見た目は男性だが、戸籍上の性別は女性)という事実を突き止めます。
新名はその事実をまずアンの母親に告げます。アンは自身がトランスジェンダーであることを母親に知られ、深く傷つき泣き崩れます。その後、アンは母親と話し合いの場を持ちますが、母親はその現実を受け止めきれません。さらに新名は貴湖にもアンがトランスジェンダーであることを告げます。
数日後、貴湖が母親とともにアンの自宅に入ると、アンは浴槽で自殺していました。母親はアンがトランスジェンダーであることを受け入れなかったために自殺したと自責の念に駆られます。
貴湖は新名にアンの自殺を告げ、新名の目の前で自ら腹に包丁を刺して自殺を図ります。幸い一命は取り留めたものの、傷心の貴湖は新名に別れを告げ、東京を離れて地方の静かな海辺の街の一軒家に移り住みます。
その街で貴湖はとある少年と出会います。その少年もまた貴湖と同様、母親に疎まれ、日常的に虐待され、ネグレクトされていました。貴湖は自分と同じ道を歩ませまいとその少年を保護し、同居生活を始めます。
そこにアンの自殺後、消息不明となった貴湖を案じ、家を訪れた美晴も加わり3人での共同生活が始まります。少年は生活を共にするなか、次第に貴湖と美晴に心を開いていきます。
そんななか少年の行方不明届けが出されていることを知ります。このまま少年を母親の元に返さなければ、貴湖と美晴は誘拐犯となってしまう。それを知った少年は家を飛び出し、自殺を図ろうとします。
しかし、その寸前で貴湖が自殺を止め、事なきを得ます。貴湖と美晴は母親による虐待の事実を訴えることで、役所に少年の保護についての理解を求めます。こうして3人はようやく平穏な暮らしを取り戻すこととなりました。
ちょっと欲張りすぎだが、印象深い作品
問題を絞り込み、深掘り、考察して欲しかった
本屋大賞受賞作が原作ということなので、期待して鑑賞したのだが・・・。本作は、幼児虐待、ネグレクト、ヤングケアラー、トランスジェンダーなどの現代社会が抱える問題に真摯に迫った良作である。しかし、それぞれの問題を網羅的に一つの作品に纏めようとする作り手の意欲は買うが、それぞれの問題の闇は深く一筋縄ではいかない。網羅的にまとめるには無理があると感じた。
本作の主人公は、三島貴湖(杉咲花)。彼女は、家族に振り回されて生きてきた。心の痛みを癒す為、東京から海辺の町の一軒家に引っ越してきた彼女は、そこで、母親からムシと呼ばれて虐待される、声の出せない少年に出会う。彼女は少年との交流を通して、かつて、彼女の声なき叫びを受け止め救い出してくれたアンさん=岡田安吾(志尊淳)と過ごした日々が蘇ってくる・・・。
起点として、それぞれの問題を纏めて提起するのは構わない。しかし、その後は、問題を絞り込み、その問題に丁寧に寄り添って、深掘りし希望ある解決の糸口を示すべきだろう。その問題解決までのプロセスが他の問題のケーススタディーになるだろう。
但し、本作で取り上げた問題は家族の問題が殆どであるが、一つだけ異質な問題がある。それはトランスジェンダー問題である。演じる志尊淳は健闘しているが、問題の掘り下げが浅く、当事者の心情が理解できない。寄り添えない。感情移入出来ない。また、他の問題は家族の問題としての共通性があるが、この問題は、性別の問題であり、家族の問題と同時に描くには無理がある。原作未読なので、原作がどうなっているかは分からないが、思い切ってカットした方が、作品としての安定感は増すと推察する。
現代社会が抱える問題に網羅的に迫るのではなく、問題を整理、分析し主軸となる問題を選択し、その問題を集中的に深掘りし考察していくという手法で問題に迫って欲しかった。そうすれば、より重厚で感動的な作品になったのではないだろうか。
やはり安定感が凄い
髭の理由
脇役でも存在感ある金子大地くん
痛みを感じ取れる存在でありたい
多くの人に読まれ、また支持された原作を映画化することは大変なことであるけれども、この原作にある人の優しさや、共感する、認められる存在に自らもなりたいと多くの読者は思ったことだろう 虐待を受ける、無視をされる、そういった日常が続くと、人間は意欲を失い、言葉も表情も失っていく 従順であるということは「あきらめ」の裏返しでもあるし、従順な「よい子」を作り上げていく恐ろしさ、危うい「親」がきっと私たちの周りにもたくさんいることだろう そんな子どもを救い出せる「おとな」と出会わなければ、子どもたちはどうなっていくのか、「通報して児童相談所につなぐ」ことが、救い出せる「おとな」と出会える方法なのか 自らその痛みを訴える術をもたない人の声を、痛みを感じ取れる存在になりたい、と思う
「市子」と共に杉咲さんの演技は、普段のインタビューの表情とはまったく異なり、この人しかいない、と思わせるものであったし、志尊さんは同年齢の俳優さんにはない穏やかさと安心感を備えられているが、このむずかしい役をやりきったと思える 小野さんは一昨年「ほどけそうな、息」で虐待児を救えなかった児童相談所の新人ケースワーカーを主役で演じられていて、本作で子どもを支えようとする演技と重なった ムシは「虫」だけど「無視」でもあり、気づかれない、わざと気づかない、そんな存在にはなりたくない
(3月7日 イオンシネマりんくう泉南 にて鑑賞)
杉の花ふんで目がウルウル、鼻がグシュグシュになってるところに杉咲花にトドメを刺された。
原作読んでないならよかったかも
ブログ書きました
ラストは
バーベキューシーン
解決してない
親の親が出てこない
きなこはあんに告白してる
トランジェスターのネタバレはや
注射うってる
母が、理解ある?
なんで自殺した
主税、婚約者に振られ会社もクビかわいそうすぎる。
マンションのお金どうしてるの?
きこ、最初の引っ越しも金どうした?
親が貯金させててくれたとは思えない
自分でお腹指した
主税から手切れ金?もらってないのにどうして祖母の家で無職
ちほちゃんて、だれだっけ?
“52”て、変て思ってくれてよかった。
52、何歳?
キナコ小さすぎて微妙。子供みたい。
女にみえない。
殴りたくなる顔
アンもむかつく
話せよ
全286件中、101~120件目を表示