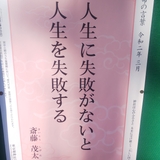悪は存在しないのレビュー・感想・評価
全252件中、101~120件目を表示
人間は悪には足りえない
冒頭の1時間半、私はなんでもないものをみていたのだろうか
巧さんは自分そして親、祖父の生きてきた自然に与えた影響をグランピング計画で起きる、山そのものとも言える自分自身における変化の中で知りたくなってしまったのだろうか
解釈を観ている私達にさせてくれる濱口監督の作家性に優しさとそれ以上の狂気を覚えました
そんな狂気に触れた自宅で待つ黛さんが人間界の狭い場所へ逃げるように急ぐような数秒のカットが1番印象に残っている
ドライブマイカーを観させてもらったときも感じたのだが濱口監督とハイパーボイルドグルメリポートの上出さんとかダブり、そして真逆におられると感じる
私は勝手に考え、個性豊な人間って好きだな。めんどくさいけど。
みな死ぬまで生きていく
とても面白かったです
問題のラストをどう捉えるか、人それぞれ違っているでしょう。
私は、希望が欲しい気もしつつ、感じ方としては『怪物』と同じで悲しい最後です。
淡々として見えていましたが、巧の抱えていた闇は想像以上に大きかったのではないかな、と思いました。
衝撃!、どっちなの?
まず、間が長すぎる。
オープニングから15分くらいは結構睡魔地獄。
何も無いシーンが何度か続きます。初めのうちは、何かあるのかな?と集中しようとしますが、そのうち、帰りなんか食べていこうかな、、、とか他のこと考えてしまいます。間や行間や余韻とか、映画にとって大切だと思いますが、さすがに無意味に長すぎる。
オープニングに余韻はいらないでしょう。
逆にエンドロールは余韻が欲しいけど、バッサリ。
斬新な演習ですね。
ようやく、役者がしべり出して話が展開していくと、キャラクターに没入する感じがあります。日常を普通に見ている感じ。この辺りがとても特長的な監督なのだろうと思います。ドライブマイカーもそうでしたが。
グランピング施設を作るか、自然を守るか、、、というテーマは目新しいものでもなく、特にドラマもありません。
その後ろの人間のドラマの映画だと思いますが、私には難解過ぎたようです。
最後は、、、え!?終わり?、どういうこと?となってしまい、即ネタバレサイトを探しますが、、、答えは自分で考える必要があるようです。
私にはラストは、「助けた」のか「殺した」のかさえ分かりません。ハッピーエンドなのかバットエンドなのかさえ分かりませんでした。
「鹿」=「お父さん」
で、普段は襲わないけど、手負いや家族に危険がある時は大切な家族を守る、お父さんは変人で、善悪の区別がつかないのか、、、
そもそもお父さんは変人(ここは確定だと思いますが)で、娘に興味が無い様子。娘がジャマで、、、もしかしたら奥さんも、、、とも思えます。
まさに難解な映画です。
せめて、答えが知りたい、、、監督の解説や原作があれば良いのですが。私にはとても気持ちの悪い映画でした。
映画の中で答えがわかる必要はありませんが。いつまでも答えが分からないのは不快ですね。
けっこうよかった
ある意味田舎ホラーだ。グランピングを進めようとして歩み寄る社員の二人が、素の人柄を見せるようになるのに、主人公はずっと裏表なくそのままだ。露骨に反発する金髪の若者は礼節を欠いているものの、正直だ。なんで主人公は社員の男を絞め落としたのか、殺意があったのか、鹿に感化されたのか全然意味が分からない。ただの変わり者だと思ったらヤバい奴だった。何を考えているか分からなくて、突然牙をむく自然みたいな存在なのだろう。
コンサルタントと社長がクソだ。グランピングの用地を下流にすればいいのだろうけど、用地の買収をし直すのも難しいのだろう。
行方不明になる女の子が、大人みたいな顔立ちで、カメラが寄っていると子どもに見えない。
どんより残る
結末(答え)は存在しない
ネタバレなのかどうかは分かりませんが、自己解釈はあるので鑑賞前情報を入れたくない人はご注意を
濱口監督作品なのに大阪ではナナゲイとシネヌーヴォしか上映していないのでちょっと出遅れての鑑賞でした。
相変わらず予備知識は全く無し(強いて言えばタイトルが先入観になっていたかも知れない)で鑑賞しましたが、面白いというよりメチャクチャ引き込まれました。
でラスト、ひょっとしたらこれで終わるのか?と予感した途端にエンドクレジットが流れ出しました。
見ていた誰しもが突然に家から放り出された様な、そんな茫然とした感覚になったと思います。特に、映画には起・承・転・結があるものだと疑わない一般観客は目が点になって劇場を後にしたのでしょうね。
まあ、起承転結は有るには有ったのだけど、見方を変えると起・起・起・結だったかも知れないし、起・起・起・起だったのかも知れない様な構成でもありました。
本作は見ていて大雑把に四部構成だったので、その切り替えが非常にトリッキーでもあり、自分が何を見せられているのか分からなくなりつつ、何処に向って行くのかの興味だけは肥大して行く感じですかね。
あと台詞の全てが伏線の様な役割があり、前の台詞の一言一言を思い出させるシーンが次にちゃんと用意され緊張感を煽っていました。この辺りも非常に技巧的だと思え、ある意味サスペンス映画の様な錯覚に陥るのですが、それがこの物語のテーマと嚙み合っていない様にも感じられて、作り手に翻弄されている様な気分にもなりました。
でも、シンプルに見ると本作は“自然対人間”のお話であって、タイトルも厳密に言うと『自然には悪は存在しない。悪は人間だけの概念である』という事だと思います。
四部構成と言いましたが、起の一部がプロローグで“自然vsそこに生きる人”(自然と人との共生)を描き、承の二部がグランピング説明会で“そこに生きる人vs侵入者”(正vs否又は善意vs悪意)を描き、転の三部ではいよいよ善悪の闘いかと思いきや説明者の本音が語られることにより善VS悪の予想が裏切られ(理解VS非理解)という展開にとなり、結の四部では今までの二部・三部の展開が無かったかのように、一番自然に近い人である娘の迷子からの結末に至る。そして、最後のシーンが何だったのか?という謎を残した(説明を拒否した)まま映画を終わらせている。
早い話、最後は観客である貴方自身で考えて(感じて)下さいという事である。
面白い面白くない・好き嫌いは別にして、これが濱口竜介監督の映画なのだという事が理解出来たらそれで良いのだと思います。
で、私の感想は非常に面白かったがテーマ(自然と人間の関係性)やポスターにあるコピーの「これは、君の話になる-」に対しての答えを見つけたいとは思わなかったかな。
追記.
家に帰ってから感想を書き始めて思い出したのですが、この子役の写真が誰かに似ているのを思い出した結果、ロシア映画『草原の実験』('14)の少女でした。(フォトギャラー参照)
そこで、更にあの映画のラストと本作のラストって、ひょっとして似ているのかも知れないという気もしてきました。
片や“自然”片や“核爆弾”の違いはありましたが、人間が相手にできないモノに対して同じ運命を辿った様な気がしてきました。
難解
最初は
自然の中に人間のegoのため、グランピングを作る計画で地元民とその企業が揉める話から
芸能事務所のスタッフである二人の心の揺れ
不思議な親子、父と娘
奥さんは亡くなった?
娘が行方不明になり
捜索
その後、あのシーン
鹿に向けられた銃声がハナに当たった?
難解。
真実は人の数だけ存在する
「ドライブ・マイ・カー」を、そんなに好きではないけれど、終始退屈せず集中して鑑賞して観た者です。話題になっているけど解説やレビューではどうにもイメージが湧かず、自分の目で観に行くことにしました。
環境問題が題材かと思えばそうでもなく、誰かの立場に立って反対勢力を糾弾するものでもなく、淡々とした雰囲気がリアルだなと思いました。でも大音量のBGMが急に消えたり、効果音がバーンと始まったりと場面の切り替えが派手で、自然や田舎暮らしの情景の映像がやたらと美しかったりするので、静かでも退屈せず集中できます。
悪は存在しない、というタイトルのとおり、絶対悪や絶対善などというものはなく、みんな自分の都合で自分で優先順位をつけて生きていくしかないなぁと思いました。自分で決めるのが怖いという人が、なんやかんやと後付けで理由(言い訳?)をつけて後ろ盾にするんだろうなと。
ラストはある程度想像していましたが、想像を超えるレベルでした。監督に「あとは自分で考えてね」と言われたような気分です。
何事も白黒はっきりさせたい方はイライラするかもしれませんが、人間の不条理を面白がれる方には一見の価値あり!の作品です。
映画館で見て良かった
あまり、良い意味ではない。家で見ていたら、チャンネルを変えるか早送りしてしまっただろう
いわゆる悪の裏にもある事情や立場があり、悪が存在しない事を、表現したかったのだろうか?
だとしたら、世の中にまみれてしまった身として、個々のキャラクターが抱える事情や立場に感情移入してしまえるものの、その時感じた自身の悪意を
思い出してしまい、悪は存在しないとは思えなかった。
監督が意図しているのは、そんな簡単な事で無く、一周回って、その悪すら許されるべきで、存在しないといいたいのだろうか?
いろいろ、考える作品は好きだけれど、自身が答えにたどりつけなかった自分の力不足を棚に上げ、答えにたどりつけなかった作品の評価を低くするのは、お金払って映画館にいたのだから、悪では無いと思う。
"悪があるから善がある"と言うならば
あっ…!上から下へ流れる
東京組にキャラクター性を持たせることで、現代社会に生きる私たちの相手への配慮に欠けた無関心な言動=他ならぬ暴力を浮き彫りにしているようだった(そこの社長やコンサルが如何にもな権化だったが自分は"普通"と思っても)。そして、やはりそれらも個人の気付き次第で、"100も1から"といずれより多数へ流れていくのだろうか?
リアウィンドウから撮られた映像。そして、劇伴が途中でブツ切りされるのは勿論、様々な"音"も印象に残った。
あまり進んで喋るタイプでない、濱口監督らしい淡々飄々とした感じの主人公に、説明会シーンから東京組が入ってきて喋り会話量がどっと増える印象。飾られた写真でしか出てこない主人公の奥さんや明かされないバックグラウンド然り曖昧さがある一方で、東京組は車中シーンでベラベラと喋るし、何なら(少なくとも表面的には)主人公たちより彼らの方が共感性が高い描写がされていた。それはまるで自然と現代社会に汚染された個人(観客)という縮図のようだった。
あらすじになるようなメインのストーリーライン以外にも色々な要素を盛り込みながら、最後は観客に解釈を委ねるような曖昧なラストへと流れていく。例えば、この導入プロットで自分が作ったら、あのまま東京組が乗り込んできた当初の目的は果たされて、地元が大変なことになる…なんて表面をなぞっただけの薄っぺらなものになっていたかもしれない。けど、無論そんな想像からは違った。その中で、皆知らず知らずの内に暴力を振るっているということを考えさせられた。
思ったより断然笑えたし、自分の中でまだ咀嚼しきれておらず考える時間が必要だけど、すごい作品だなと感じる。
このなんとも言えない濱口的後味(笑)
不安をあおってくる劇伴
さて、渋谷に行くのが嫌すぎて(苦笑)見て見ぬふりをしていたわけですが、やはり濱口監督作品を無視することはできずに公開からようやくの3週目、サービスデイにBunkamuraル・シネマ渋谷宮下へ。このシアターは初来館の私、渋谷TOEI時代も入ったことがなかったので、ちょっとドキドキですwなお、公開から時間が空きましたが、毎度の如く前情報なしで挑みます。いつも聴くラジオ番組の映画評も、このレビューをアップするまではオアズケです。
で、始まって早々に気が付く「何、この劇伴。。」何となくですが不安をあおってきます。なるほど、このレビューを書くのに読んだ情報でようやく気付いたのですが、この映画、音楽を担当する石橋英子さんとの共同企画だったのですね。兎に角、音楽が鳴り始めると「何か起こるのでは?」と不安を感じます。そもそも題名がこれですから何も起きないわけがないだろうと想像の相乗効果で最後まで目が離せません。そして後半に案の定「事」が起きるのですが、起きる少し前、物語り中でも一番緩くちょっと可笑しく劇場からも笑いが起きていたのに、、という意地悪な展開により一層のショックを感じます。
観終わって誰しもが考察したくなる終盤に起きるそのことは、その少し前の会話に鍵があることは誰しもが気づくと思いますが、考えれば考えるほど実はあれもこれもが伏線に思えてきます。どんな質問にも簡潔に答える巧(大美賀均)が明言しないことにどんな意味があるのか、しっかり鑑賞者に考えさせる余韻を残してくれています。そして、何といっても作品のベースになる話(グランピング場建設計画)自体が興味深く面白いし、思いのほか為になることも重要な点だと思います。これも後で知ったことですが、銀獅子賞以外に受賞している賞の種類・幅にもなるほど納得です。
キャストの何人かは「見たことあるけどお名前は…」という方もいらっしゃいますが(衝撃の最後でクレジットを確認できませんでしたが、丘みつ子さんがいらしたと思います)、いわゆる「有名な方」が出演されていません。そんな中でも高橋を演じる小坂竜士さん、滑稽で最高です。状況に応じて器用そうに振舞っていますが、実は往々にして脊髄反射している部分など案外身につまされますし、ついつい苦笑します。
かなり好みの作品で、踏ん切りをつけて渋谷に来た甲斐がありました。何ならもう一度観たいくらい。満足です。
鹿の通り道
濱口竜介監督はやはりリアルな現実を切り取るのと、ライブ感を演出するのが上手い。
緩慢なカメラの動きに、演者のなるべく抑揚を抑えたような淡々とした台詞回しが、これが特別な非日常ではなく、あくまでも日常の延長線上にあることを観る者に意識させる。
舞台は長野県の自然が豊かな高原の町。特に沢の水が直接飲めるぐらいに綺麗で、都会からの移住者も増えているらしい。
代々この地で暮らす巧は、薪を割ったり水を汲んだりしながら便利屋として生きる物知りな男だ。
ただ物忘れが激しい。
娘の花は好奇心旺盛、巧の迎えが遅いと一人で森に踏み入り探索をする。
ある日、彼らの住む近くにグランピング場を作る計画が持ち上がる。
しかも計画を進めるのは畑違いの芸能事務所であり、町の一番の誇りである水源を汚染しかねない杜撰な計画でもあった。
まずこの住民説明会のシーンに引き込まれる。
計画の担当者である高橋と黛相手に住民が様々に異を唱えるのだが、まさにドキュメンタリーのようにリアルな対立を観ているように感じた。
巧たちはただ闇雲に反対するのではなく、しっかりと町にとっても財産となるような計画を立てるように彼らを促す。
しかし住民の意見をすべて聞き入れる余裕があるほど、芸能事務所側にも予算と時間があるわけではなかった。
しかもコロナ禍による行政からの補助金を得ているだけに、何としても計画を実行に移さなければいけない。
高橋と黛は社長に説得されて、再び巧のもとへ赴くことになる。
確かに住民を半分馬鹿にしたようなコンサルタントや社長の姿には悪意を感じる部分もある。
しかしこの映画のタイトルにもあるように、この作品には明確な悪は存在しない。
高橋と黛が移動中に仕事への不満や結婚観などを話すシーンが続くが、次第に観ているこちら側も彼らに共感を覚えるように誘導されているようだ。
彼らにも人生があり、信念があるのだ。
どうしても人間の目線で見ると、善であるとか悪であるとかを分けてしまいたくなるが、もっと大きな自然の流れの前ではどちらも些細な問題なのかもしれない。
手負いの鹿はやがて息絶えるように、自然の前では善も悪も関係ない。
ただそこに自然の流れに沿って生きる。
淡々と巧が薪を割るシーンが印象的だった。
簡単なようで薪割りは慣れない者には難しい。
そして巧が花を肩車しながら森の木々を説明する姿、そしてグランピング場の建設地が鹿の通り道であると淡々と話す姿が印象的だった。
通り道がなくなったら鹿はどこへ行けばいいのだろうか。
いつの間にか高橋と黛が巧の生活に取り込まれていく様もおかしかった。
さて、本来なら物語はグランピング場の計画についてどうお互いが歩み寄るのかを描きそうなものだが、事態は思わぬ展開を見せる。
花が下校中に行方不明になってしまったのだ。
冒頭にもあったが、狩猟による銃声が不穏な空気を感じさせる。
そして観る者を動揺させるような唐突で衝撃的なクライマックス。
なぜ花が倒れていたのか、説明はされない。
誤って銃に撃たれてしまったのか、それとも手負いの鹿に攻撃されてしまったのか。
それともすべては幻だったのか。
そして巧が思わず高橋の首を絞めてしまう理由も分からない。
これも何か大きな力によって導き出された結果なのだろう。
様々な疑問は残るものの、観終わった後の余韻が長く、カメラワークの秀逸さもあり、まるで大巨匠の作品を鑑賞したような充足感があった。
拓は、鹿だった。
自然な風と川のせせらぎ。
自然豊な高原に位置する長野県水挽町に住む住人達と、その高原にグランピング場を建設しようとする芸能事務所の話。
コロナ禍の影響で経営難になった芸能事務所が政府からの補助金を得ての計画…、住民説明会になるもグランピング施設内にある浄化槽位置が悪く、町の水源に汚水が流れるのではないかと問題に…。
分かりやすく書けば「マンション建設反対」、「太陽を奪うな!」的な、本作は町の水源を汚すな、施設を造っても管理体制が整ってない、20年に1度は起こる山火事が人の出入りが多くなるから頻度が上がるのでは?と問題が色々と、リアルでもある問題だけど私自身こういった問題に直面した事なくて、町の住人達の気持ちも分かるし、事務所側の言ってる都合のいい理由、人の出入りが多くなれば町も活性化しますよ!も何か分かるしで、こういった問題ってリアルでも「なるようにしかならない」と思う。
本作のストーリーは関係なしにあの高原、自然が良かったな~なんて、山道歩いて食べ歩き(陸ワサビ)とか、自然の水を生かしたうどん、薪割りとか、そんな描写が観てて少し癒されました。がっ!ラストの終わり方は何すか!?娘の花といい、事務所の高橋といい、どう解釈したら…。
花役の子は可愛くて将来有望、だから目の下の涙ボクロはズルいんだって!(笑)
ラスト不明の名作
わかるところとわからないところ
全252件中、101~120件目を表示