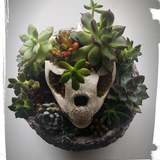悪は存在しないのレビュー・感想・評価
全252件中、1~20件目を表示
侵入者≒「他者」の受容と拒絶
石橋英子さんから濱口監督へライブパフォーマンス用映像の制作依頼がきっかけでつくられた本作。映像イメージの使用のみを想定してか、1ショットでのカメラワークや劇が実験/挑戦的で面白くて凄い。1ショットでの長回しは『親密さ』での明けの散歩シーンなどで印象的だが、強度がさらに強まっている。学童からの車の移動のショットとか、巧と花の山を歩くショットとか、巧と高橋の薪を割るショットとか凄すぎでしょ!!!本当にみているだけであっと驚かされる。役の練度がそのままカメラに撮られーつまり準備が凄いー、それをみるだけで十分面白いと思えるんです。
さて、本作は自然と人間の二項対立による濱口監督のエコロジー論が語られるのかと勝手に予測していたが全然違った。どのように〈私〉は侵入者≒「他者」を拒絶し、受け入れられるのかが主題系をなしているように思われる。菊池葉月さんや渋谷采郁さんがキャスティングされていることもあり、『ハッピーアワー』の主題系がリフレインされている印象だ。
その他者とは、まず主人公の巧らが生活する長野県・水挽町にグランピングを建設しようしている高橋と黛だ。二人は地域住民に対して説明会を開き、事業の推進を目指して説明をする。しかしその説明は、事業の正当化と利益のためであることが透けてみえて、地域住民の生活を考慮していない杜撰なものだ。地域住民は反発する。巧も計画の見直しを求める。しかしこの町も開拓地であり、地域住民も元はよそ者≒他者だ。もちろんこの計画に賛成の住民もいる。それなら解決は他者の拒絶ではない。拒絶と受容のバランスが問題なのだ。
バランスを失うと崩れる。崩れる運動の描写が『ハッピーアワー』でもされていることを指摘するのは蛇足であるが、高橋と黛はバランスを崩さないために、巧や水挽町の生活を知ろうとする。
他者の理解だ。巧の生活の一部となっている薪割りを高橋はしてみる。峰村夫妻が切り盛りしているうどん屋でご飯を食べてみる。うどんに使われる湧き水を汲んでみる。山に分け入ってみる。
高橋と黛は他者をさらに理解したように思える。それならば理解したものを東京に持ち帰って、グランピングの計画は改善されていくに違いない。地域住民も計画に納得して、「ハッピーアワー」が訪れる。
と、ならないのが本作の特異点である。濱口監督と石橋英子さんの二人が好きな映画がファスビンダーであることはパンフレットをみて知ったのだが、本作にはファスビンダー同様に不条理さがつきまとっている。
そんな数日の出来事で他者は理解できないし、グランピングの計画は社長とコンサル事業者といったさらなる他者によって問題は複雑であり、解決は困難だーさらに社会経済的な時間の有限さもあるー。〈私〉と他者が言葉を交わし合い、反省し合い、啓蒙されたら万事解決になるわけではない。理性的コミュニケーションの限界。徹底的な本読みによって、〈声〉を重視する濱口監督の作家性とは思えない展開だ。
さらに他者とは、〈私〉以外の誰かであると共に〈私〉の中にも他者性として存在するのではないか。そんな他者性の発露が巧にとって花の失踪事件だろう。
この事件は巧が迎えを忘れることが一つの原因ではあるが、彼の意志を超えた偶発的な出来事である。高橋も黛も原因には全く関係ない。しかし事件は起こってしまう。
花はみつかる。住民の必死な捜索が全く無意味で、巧が勝手にみつけたこともまた不条理極まりないのだがそれでもみつかる。しかし花はバランスを崩して死んでいるように思える。さらにそこから高橋への殺意と暴力に転化するのは全く理解不能だ。Quoi??? でもそれが他者性なんだと思う。巧は事件以前は殺意なんて全くなかったはずだ。けれど殺意は顕れた。行動に移された。他者とはそれだけ理解不能で不気味なものだ。
ではどのように〈私〉は侵入者≒「他者」を拒絶し、受け入れられるのか。その問いの答えは霧の靄へと姿を消す。グランピングの建設が進められるのかも分からない。花の死が事件か事故なのかも分からない。彼らの結末がどうなるのかも分からない。そもそもラストシーンは、物語世界で本当に起こったことかも分からない。全てが「判断不可能性」に開かれていて、悪の存在も判断がつかない。
つまりは私たち観賞者に問いが突きつけられているのだ。映されたイメージは何なのかと。「悪は存在しない」。このタイトルは結局のところ何なのだろう。思考が循環する。不気味な何かが私の中に澱んでいるのだけは分かる。
気づきや思索をもたらすストーリーテリング
人間とは不可思議な存在だ。こういう人物だろうと把握した次の瞬間、全く違う顔を覗かせることも多い。判で押したような悪人や善人は少なくとも本作には存在しないのだ。そもそもメインの父娘からして、どんな過去を持ってこの地へやってきたのか曖昧で、だからこそ我々は表情や言葉、調度品から懸命に理解しようとする。と同時に、グランピング場建設のためにやってきた男女にしても、車内のダイアローグで切々と胸の内を語り、最初の印象は刻々と覆っていく。人間とはかくも面白い生き物であり、変容の中にこそ本質があるのかもしれない。一方で、本作には自然環境や未来への視座も盛り込まれている。上から下へ流れるのは、水のみならず、時間も同じ。子供ら世代に豊かな環境を残せるか否かは今を生きる大人たちに委ねられた課題でもある。斬新なストーリーテリングでナチュラルな気づきや思索をもたらす作品として、ラストの謎も含めて、胸に深く刻まれた。
悪意はなくとも、悪いことは起こる
自然環境と開発、地元民とよそ者、野生動物と人間、消える子と探す親といった題材は、最近日本で公開されたものでは「ヨーロッパ新世紀」「理想郷」、少し前では「ラブレス」など外国映画でも時折描かれてきたものであり、問題意識と物語類型が国境を越えて共有されていることの表れだろうか。
映像は美しい。が、いくつかの長回しは冗長に感じられた。音楽家の石橋英子からライブ演奏時に流す映像を依頼されて企画が始まった映画であることと関係があるかもしれない。
ラスト近く、娘が置かれた状況を目にして、父親はある行動に出る。あの展開は、保護者としてのリアリティーよりも劇的効果が優先された純然たるフィクションだと感じた。ラストのインパクトを高く評価する向きも当然あるだろう。だが評者は、グランピング場計画をめぐるリアルな対立を興味深く追っていただけに、「えっ、それで終わらせちゃうの」と、何やら梯子を外されたような思いがしたのだった。
正直なところ見る人を選ぶ作品。ただ、流石のリアリティーで、ベネチア国際映画祭の銀獅子賞(審査員大賞)受賞は納得の佳作。
ベネチア国際映画祭やカンヌ国際映画、ベルリン国際映画祭の世界3大映画祭の受賞作は、見てみると割と「?」な映画が多い印象です。
本作も正直なところ、冒頭からイメージビデオのようで、「うわ~、これハズレの作品か」と思いながら見ていました。
ただ、濱口竜介監督の前作「偶然と想像」は脚本が面白く、本作をスルーするわけにもいかず見ていましたが、まさに会話劇となる説明会のシーンで盛り上がり、その後の展開も興味深く見ることができました。
セリフも素人のような感じが多く有名俳優もいない状態で、よくぞここまで作り込んだリアリティーを構築できたなと感心しました。
そもそもが音楽ライブ用の映像を制作するだけのはずが、緻密な構成によって106分の長編映画になったのも興味深いです。
まさに脚本と映像の両面で存在感を放ち、2023年・第80回ベネチア国際映画祭で銀獅子賞(審査員大賞)を受賞したのも納得できる作品です。
ラストの解釈
会話劇がものすごく面白い。
レビュー書き始める前にミニシアターで拝見
したので日にちは適当。
結構、苦手な人も多い様子。
私といえば、集会や車内の会話が
面白かったです。
それぞれの視点から見たときに
皆それぞれ、事情や考えがあり。
自分では何ともできない状況がある、
そこに悪なんていない。
それがわかりやすい、日常の会話劇が
面白いと見てたらあっという間にエンディング。
あのエンディングは好き嫌いわかれる
だろうな、と思いました。
色々考えられるけど、主人公は鹿に娘が
殺されることを容認したわけじゃなく。
娘を助けるためにあの男性が鹿を殺して
しまうのを防いだのだと感じてました。
何故なら鹿はあくまで身を守ろうと
してるだけだから。
主人公はあくまで物語全体を
通して自然とともにいる、
偏らないけど自然に抗う事は違うと感じ
てる印象だったので個人的に
伏線のように感じました。
今までが日常の人々の会話劇だったから
油断してました。
主人公の精神自体は自然に寄り添ってる、
倒すべき悪はいないから
運悪く手負の鹿にあった娘を
助けるために手を出そうとはしなかったし、
娘を助けなかったように見える
主人公も言ってみたら悪ではない。
色々と思考の迷宮に迷い込む映画で
良い映画だと思いました。
最後はどういうことなのかしら
水の美味しい田舎の村にグランピングの施設を建てたいという芸能事務所が現れる。その時点でマユツバの事業計画。舐めてかかっていた住民にコンテパンにされる。
この住民説明会は結構見応えあった。
後半に向けて芸能事務所の担当が、このグランピングの運営に興味を持ち始める。その発言がなんとも薄っぺらな感じなのだ。通り道にグランピングができて柵を作られてしまったら鹿はどこに行けばいいのか、どこか他の所へ行ってもらいましょう。そういえ問題か??
クライマックスが1番難解だ。鹿は誰に撃たれたのか、娘はなぜ鹿に近づいていったのか、止めに行こうとした男を締め殺す必要があったのか、娘を抱いてどこに行くのか。
不思議な世界の中で,終わってみると確かに悪はいなかったなぁ。
くだらない映画。長ーく感じます。
この監督の作品を観たのは3度目だが、最後になりそうだ。"寝ても覚めても"がそれなりに良かったのは唐田えりかが良かったからだったのだろう。前回観た"偶然と想像"も評価出来なかったが今回の作品は最悪だった。スタートからイメージビデオのような代物を見せられて、時計を見ながら視聴していたがとにかく長い、そしてつまらない。役者さんは全員素人っぽく(子役が例外かも)、後から考えれば唯一記憶に残ったのは芸能事務所の社員の車内での会話。ラストシーンは無責任。こんなに長々とくだらない映画を見せた上に結末をどう考えるかは視聴者に任せる、とはふざけている。鹿の親子は匠の幻想で娘さんはもう死んでいるのか、それとも娘さんはまだ生きているのに匠が親子心中を計ったのか、どちらでもない解釈もあるのかもしれないが、まあそんな事はどうでもいい、早く観たことを忘れたい。まあ、ベネチア映画祭なんてこんなものではないだろうか?
わからないですね
あのコンサルタント会社の人が怖いなぁ、と感じました。
生業である仕事先のことをあんなに適当に考えているのだろうか、と。もちろん依頼主の社長も悪いですが、コイツにええように踊らされていく予感。手に入れた補助金から支払い、当然のごとく事業は失敗の憂き目に遭うでしょう。
完璧を求めてはいけない、って⁉️
それで金貰うの❓
現実もこんなんでしょうか。
汲んでいた水をうどん屋さんで使うのですね。
陸ワサビでうどんや素麺食べたいな。
子鹿の死骸は生々しい。
鳥の羽根🪶の利用法を知りました。
[説明会]ええ加減過ぎて腹立ちます。😤
読まなくていいです、ムカっとしますから。
浄化槽の規模、→検討する、毎日5人分濾過されず流される。
浄化槽の位置、井戸の汚染→公共施設、専門家に相談している、
清い水でうどん屋経営→汚染水となれば、死活問題、
この土地の人にとって水は大事、位置の変更必ず→
貴重なご意見、、社長の決裁を仰ぐ、
専門ではなくコンサルタント会社に教えてもらっている。
なぜ社長やコンサルタント会社が来ないか?
この土地に金が落ちる、→共存共栄、
ここは住宅地、ホテルみたい、焚き火が怖い→24時間体制じゃない、←絶対24hの管理体制必要、
問題はバランスだ。
水は低いところに流れる、から、
上の方であったことが下に流れる、
上に住む人には義務がある、わかって欲しい、
とてもよくわかる説明。
巧さん、薪割りうまい。
うどん食べて水汲み体験、までは良かったですが。
花ちゃん帰らない、一人で歩くシーンがよくあり、
駿河のオッチャンにもあまり行くな、と言われていたのに。
父親巧はなぜ忘れるのでしょうか?
普通なら、迎えに行く時間だ、と所用を切り上げるでしょうに。
黛のケガは何を表し、巧は高橋をどうしたのでしょう?
花ちゃんの体が見つかるまで手負いのシカと対峙のシーン
シカ🫎にやられたのでしょうか。
“悪”は存在しない、の”悪”はやはり人間でしょうか。
入って来た人間には自然の制裁があり、存在できないからでしょうか。たとえ花ちゃんであっても。
「謎」を作ればいいわけじゃない、と思うのだが
後は各々で考えてください的な映画は、嫌いではないが、この映画はダメだった。
なぜなら、ラストシーンは作者(監督)の恣意が強すぎて、「謎のための謎」のような気がしてならないからだ。
私としては、普通に考えると、こういう理由なんだろうと思いつつ、他の要素(伏線)によって、違う理由も考えられるなぁ、くらいの「謎」がちょうどいい。
あくまで、いくつかの合理性を推理させる、考えさせる、くらいの謎。
この映画は、ラストに唐突な謎をぶっこみ過ぎる。
もうね、ドラえもんのラストシーンに、川辺に浮かんだ死体が出てくるくらいの謎レベルだと思って、楽しんでいただくのが良いかも
『悪は存在しない』は自分の中で存在し続けていく
濱口竜介はつくづくアートの監督だ。
その評価を決定的にした『ドライブ・マイ・カー』も難解と言われたが、まだ物語性や巧みな構成や最後はポジティブなメッセージも感じられた。
しかし、本作はどうだ。難題を突き出し、問い、明確な答えは描かない。見た人に委ね、見た人それぞれの解釈。
自分の解釈が当たっているのか、見当外れなのかすら分からない。
それも含め、試されているのだろう。いや、信じられているのだろう。
見た人一人一人が何かを見つけてくれる。絶賛でも酷評でも。
はっきりと意見は分かれる。ダメな人にはとことん合わず、好きな人はその深淵に誘われていく。開幕、森林木々の中に奥深く入り込んで行くかのように。
私も入りは迷ったが、気付いたら引き込まれていた。
長野県山奥の集落・水挽町。
豊かな自然と澄んだ雪解け水が自慢のこの高原地方は今、東京からのアクセスも良く、観光客も増えている。
この地で娘・花と暮らす巧は、自然と調和した慎ましい生活を送っていた。
序盤はこの父娘や住人たちの日々の営み。
薪割り、水汲み…。巧は寡黙ながら実直に日々の仕事をする。
花は元気に森の中を駆ける。
住人たちの交流。長年暮らす年長者の知恵、教え。
質素ながらも穏やかな町と暮らし…が今、大きな局面を向かえている。
巧の家の近くで、キャンプとホテルを備えた“グランピング”のオープン計画が上がる。
計画した企業による住民説明会が開かれる。
企業側は利便性と町の更なる活性化に繋がると自信満々に話すが、コロナの煽りで経営難に陥った芸能事務所が補助金と別企業からの提案で楽観的に推し進めた計画。
自然水が汚染される事、ホテルの管理体制やキャンプの火の問題など住民から不満疑問が続出。ずさん過ぎる計画に怒りの声も。
担当の高橋と黛は田舎人を簡単に言いくるめる事が出来るとタカを括っていたが、鋭い視点や意見、地元愛に完全にKO。
水は上から下へ。上でやった事は必ず下に影響する。…この区長の言葉は響いた。
社長や推進してきた企業を招いて改めて説明会を開く事に。高橋と黛はそう会社に伝えるが、社長も企業も条件は受け入れず、変わらず楽観的意見。
地元住民たちはバカじゃない。いい加減な計画、口だけの上役、それに振り回される自分たち。その愚かさに気付く。
最初はヤな連中と思った高橋と黛だが、彼らにも徐々に感情移入。再び水挽町へ向かう車内での会話が平社員の苦労が感じられ、何か気に入った。
二人は再び水挽町へ。会社の(バカみたいな)名案故。
町の便利屋のような仕事をしている巧にホテルの管理人を。どうせ暇だろう。←こんな言い方をする会社側にイラッと。
善は急げ。あまり気乗りしない二人。
巧の元を訪れ、薪割り中。薪割りをしてみる高橋。
管理人の話を伝えるが、暇ではないと鈍い反応。
巧にはもう一つ、気に掛けている事が。グランピングが建つ辺りはちょうど鹿の通り道。
鹿は滅多に人を襲わない。グランピングが出来、人も増えたらそこを通らなくなるだろう。
なら、鹿は何処に行く…?
花が行方不明に。住民総出で探す。
巧は思い当たる所を。高橋と黛も協力。
黛が怪我。巧の家で休ませ、巧と高橋で。
開けた平野。そこに、花が…。目の前に、鹿が…。
巧は驚きの行動を。そのままこれまた驚きの終幕になる…。
どう解釈したらいいか分からないラスト。
突然巧が高橋を羽交締めにして殺す。負傷した花を抱き抱えて森の何処へ。
巧は死に場所を求めていたのか…?
どんなに反対してもグランピングは建つ。そうなったら自分には居場所は無い。
鹿は何処に行く…? これは、自分なのだ。
そして私たちなのだ。我々は何処へ行く…?
居場所を無くした動物たち、破壊された自然。その悲しみ、怒り、憎しみは必ず人間に降り掛かる。
上の方の汚れが必ず下の方へ流れるように。自然の摂理。
巧=自然の高橋=人間への突然襲った災い。
災いの後は静寂が訪れる。無に帰すように…。
タイトルの“悪は存在しない”。
確かに本作には“悪”は存在しない。巧の行動も、住民たちの反発も、高橋や黛の言動も、会社側だって悪意は無い。
悪は存在しないが、愚かでもの哀しいだけなのだ。
…なんて解釈してみたが、全く自信ナシ。見当違いも甚だしいだろう。
3日ほど前に見たのだが、なかなか考えまとまらず。
やっと何とかまとまったのだが、そもそもこんな解釈でいいのか…?
今もふとした時に思い出す。多分これからも、印象残るラストと考えさせられる作品として、自分の中で存在し続けるだろう。
恐るべし、濱口竜介!
全員が初めて観る俳優でセリフ回しもぎこちなかった。 あえて演技経験...
物語以上の映画
何故あのラストシーンだったのか。
悪は存在しないというタイトルから単純な善と悪の二項対立ではないよというのは何となくイメージしていた。途中までは当初のイメージ通りというか、違和感なくストーリーが進んでいた。
ただ、最後のシーンとそれまでの展開の結びつきが未だに自分の中で噛み砕いて整理できていない。
悪意のない人が何故あのような仕打ちを受けたのか。1つ思うのは最後羽交い締めにするシーンに繋がる直前に手負いの鹿を見ていた。鹿は臆病だが、手負いの鹿だったら逃げられないから立ち向かうために人を襲うと映画の中で説明があった。
もしかしたら彼は、手負い鹿と自分を重ねてしまったのかもしれない。人は不合理な行動や間違いをしてしまうことはある。万人が理解出来て分かりやすい悪なんて存在しない。
会話はおもしろい
シカに取り憑かれたヒゲ男
結論からいうと1980~90年代であったら、まあまあな映画という感じでした。ホン・サンス監督作品のほぼ全てよりはマシってくらい。
衝撃のラスト!といいますが単純に明確な結末から逃げているように思えました。根底にキリスト教が屹立するブレッソン映画のようにはいかないのは、織り込み済みなのだとは思いますが。石橋英子の持ち出し企画と知ったうえで元も子もない話をしますと、あのラストシーンに情緒的なBGMは不要。あれは本当に非常にダサいです。
まず、今やアニメ・漫画の分野で例えば前時代的なメロドラマであったとしても自分たちなりの倫理観を問い詰めつつ覚悟を持って明確な結論を示す時代にあっては、この映画に関して言えばトータルの力量が足りてないように見えました(観察者目線のカメラワーク、映像処理、アングル・レイアウトも監督本人が狙っているだろう以上に実に古典的)。
申し訳ございませんが、時代遅れのスノビズムを感じずにはいられませんでした。
また、「地方山間部」「シングルファザー」「芸能事務所による政府からの補助金目当てのグランピング建設計画」という舞台・題材の比較的安易に感じるセレクトが、あくまで明日の食事に困らないような都市生活者≒ブルジョア目線であり、町長のいう「水は上から下へ」論は、よもや自己言及ならば悪趣味です。悪趣味といえば、父親が娘の帰宅時間を二度も忘れてるのは、あれは意図的でしょう。銃声と前後して思い出すのも意図的。娘をあえて危険な状態に晒している。「悪」も存在しないかもしれませんが同時に親子の「愛」も存在しない、他人と意思疎通も難しいが何故かポーズだけは上手い、まあまあサイコパスな(シカに取り憑かれた?)父親の話といったところでしょう。
普通の物語にはしたくないし、あわよくば映画史に名を残したいという鼻息と姿勢は垣間見せつつ、説明セリフを極力排すが作劇をスムーズに進めるべく、意図的に登場人物はステロタイプ化されているというアンバランスさは、あの懐かしき平成初期にあまたあった自主制作映画を思わせます。
あえてテーマを単純に読み解くならば、「社会道徳」<「個人倫理」<「自然の摂理」ということなのでしょうか。
便利な背景と小道具、雰囲気作りに成り下がっている森の樹木だって生きている。今度は、シカが樹木にヤられる続編でもあるのかな?って、ほら、くだらないでしょう?
しかし、「作劇」としては面白くなる可能性が多々あっただけに非常に残念でした。監督は「作劇」ではなく「芸術」をとったのでしょう。この「芸術」がどういうわけか世界的に認められたわけですから、次回作は思いっきりお金を使って「芸術」が出来るであろう幸運は大変喜ばしいことだとは思います。
この映画に「悪」は存在しないかもしれないが、送り手の「悪趣味」と受け手の「嫌悪感」は確実に存在しました。
最後に大きなお世話だとは思いますが、作品タイトルをストレートに「グランピング建設予定地殺人(未遂)事件」とか「シカに取り憑かれたヒゲ男」とかにすれば、見方も変わるし分かりやすいし宣伝もしやすいしで、良いことづくめだったのでは?
全252件中、1~20件目を表示