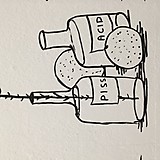アステロイド・シティのレビュー・感想・評価
全221件中、181~200件目を表示
極端な大荒れ枠になるのが確定しそうな状況…
今年294本目(合計944本目/今月(2023年9月度)4本目)。
(参考)前期214本目(合計865本目/今月(2023年6月度まで))。
まず、一言でいうと「2022年に放映された文系ネタ満載の「フレンチ・ディスパッチ」の理系バージョン」という点は言えます。理系ネタ95%といった感じです。
そしてそん「フレンチ・ディスパッチ」も文系ネタ満載「すぎて」、「眠かった」だの何だのといった投稿が多かったのですが、文系が理系に変わっただけで、結局同じ気がします。
映画として珍しく、最初に「このストーリーは架空」「1955年代を想定している」といったことが表示され、章立て形式で進んでいくという、これまた「フレンチ~」と同じような展開です。
ストーリーというストーリーが認識しづらく(日本語字幕が珍妙なほどに意味がよくわからない)、その架空の「アステロイド・シティ」に関する人々の生活を描く映画、以上の理解は普通の人には(特にアメリカ文化について学習しない一般的な日本人には)無理ではなかろうか…といったところに、理系ワード(これも、数学・物理・化学・地学・生物、と実にバラバラ過ぎる)が飛びまくる、もう「フレンチ・ディスパッチ」の理系バージョンといって差し支えないのでは…というところです。わずか5%程度文系ネタ(といっても、法律ワード)が飛んできますが、事実上理系映画という観点が極端に強く、見る方を「極端に」制限するのが結構厳しいです。
「感想を書きましょう」といっても、多くの方には感想の書きようがないのでは…という本当に極端な映画で、「フレンチ・ディスパッチ」の理系バージョンでした」という投稿が続出しそうな気がします。
予告編ではこうした点は伏せられていたため、私が見たtohoシネマズでもなんと満席になっていたのですが、多くの方が途中で帰るといった特異な自体で、これもこれでミスマッチがひどすぎるなぁ…といったところです。
正直「採点拒否レベル」になってしまう映画の分類になりそうな気がしますが、そういうわけにはいかないので…。
相当高い理系的教養を要求してくる(上記の通り、数学+理科4科目)という特異な映画で、まぁ1955年設定である以上、ITネタがでない点が「唯一の救い」と言えます。
こういった事情もあり、ストーリー展開の理解の助けとなる字幕も理系ワードが飛びすぎで何がなんだか…であり(日本では理学部であれば、数学科にせよ物理学部にせよ分岐するので、すべてに詳しいという方はいない)、本当に理解が困難だったりします。
アメリカではどういう評価を受けたのかわかりませんが、日本ではちょっとこれはないだろう…というところです。もはやクイズ大会の様相になっているため、それを想定してみるしかないというところです。
-------------------------------------------------------
(減点0.4/理系ワードの出しすぎ)
・ これだけ出ると、「眠たい」や「寝た」という投稿等も理解はでき、どうするとここまでマニアックな映画にしたのか(あるいは日本で供給したのか)が謎です。高校理系クラスでは太刀打ちができず、物理にせよ数学にせよ、学部レベルを超えて修士課程レベルの知識を問うてくるあたり、「鬼」というしかないレベルです。
(減点0.1/字幕の翻訳ミス)
・ less than は「未満」であって「以下」ではありません。
-------------------------------------------------------
(減点なし/「ゲーデル」って誰?)
オーストリア・ハンガリー二重帝国(「エリザベート1878」参照のこと)生まれの数学者で、ナチスドイツによるユダヤ人迫害を逃れてアメリカに逃れてきた人物です。
数学基礎論(数学をどのように展開していくのか、という哲学的分野に近いジャンル)や、公理的集合論(高校1年で学習する「物の集まりを集合といいます」を超えて、集合を厳密に定義するジャンル)が専攻の数学者で、後者に関しては有名な業績を残している人物です(ただし、このことも学部3年か4年の卒論レベルの知識がないとわからない)。
※ 公理的集合論を社会の実務で使うことはほぼありません(保険数学等でわずかに使う程度)。
明るいんだけど、暗い。退屈だけど、面白い。
THE シュール。
人口 87人(確か)砂漠の街アステロイド・シティの話。
解説、動画予告、劇場の部屋広め&コメディという文字を見て笑える作品と期待して観に行ったんですが、ちょっと笑えず終始眠かったです(笑)
盛り上がりがなく平坦な一本道って感じ。
何かストーリーも全然掴めなかった(笑)
何か笑わそうとしてる感じは分かるんだけど全く笑えず。
観る人選ぶのかなぁ~二席空けた隣の人はクスっと笑ってたんだけど。
唯一鮮明に覚えてるのは頭クルクルヘアーの美女のパイパイと若干ボカシのかかったアンダーヘアーぐらいだけです!(笑)
虚の中の虚の中に実はあるのか?
始まってすぐ『アステロイドシティ』は劇中劇であると明かされる。
これによって「物語」に対する興味が一気になくなってしまった。
おそらく、画面サイズが小さかったり、白黒だったりするパートが現実パートでそれ以外が劇中劇というか本編なのだろうが、その両パートの繋がり等を理解しようとするほど熱心には見られなかったし、そこまでする気になれなくなってしまった。
そもそも、全てがコントロールされた「作り物」の虚構の世界がこの監督の持ち味なので、更にその上の虚実が出てくると考えるのを辞めたくなる。
後半突然、いつものルールを破り斜めのアングル等を使って「目覚めたければ眠れ」というシュプレヒコールが行われる。
「俺は目覚めたくてウトウトしてたのではない!」と思いつつ、わざと眠くなる様な作劇をしているのか?と邪推をしながら、「そんな事する人じゃなかったでしょ」とウェス・アンダーソンに想いをはせてみるのでした。
あと、トム・ハンクスのポジションって絶対にビル・マーレイのポジションだよね。また喧嘩したのかな?ビル・マーレイならもう半分は★を足せたかな。
砂漠に青い空の背景を見た瞬間、原爆の話とわかる。
話は複雑に構成されて、
幾つものメッセージが遺されている。
1950年代のパスクアメリカーナの映画ではないことは確かだ。
わかり易くすると、
あのバーベンハイマーとの3部作と考えて観てはどうか?
日本でも早くオッペンハイマーを観たいものだ。
自分が感じた好きなメッセージは、
青少年少女達が、
爺さんや親御さんや軍隊を軽々と出し抜いていくところが頼もしくて愉快だった。
(^○^)
「グランド・ブダペスト・ホテル」のウェス・アンダーソン監督が、
砂漠の街に宇宙人が到来したことから巻き起こる大騒動を独特の世界観で描いたコメディ。
1955年、アメリカ南西部の砂漠の街アステロイド・シティ。
隕石が落下して出来た巨大なクレーターが観光名所となっているこの街に、科学賞を受賞した5人の少年少女とその家族が招待される。
子どもたちに母親が亡くなったことを言い出せない父親、映画スターのシングルマザーなど、参加者たちがそれぞれの思いを抱える中で授賞式が始まるが、
突如として宇宙人が現れ人々は大混乱に陥ってしまう。
街は封鎖され、軍が宇宙人到来の事実を隠蔽する中、子どもたちは外部へ情報を伝えようとするが……。
キャストにはジェイソン・シュワルツマン、エドワード・ノートンらアンダーソン監督作の常連俳優陣に加え、スカーレット・ヨハンソン、トム・ハンクス、マーゴット・ロビーらが参加。
2023年・第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品。
世界観を楽しむことで精一杯
目覚めたければ眠れあたりで目覚めました。
豪華キャストを探せ!
見る人を選ぶ作品だなー
豪華なキャストでワクワクしながら見始めました
しばらく見ている→全く面白くない、ガマン
もうしばらく見てみる→やはり全く面白くない、ガマン
最後にすごいオチがあるのか→全く無い(ネタバレになるか?)
こういう感じの映画、面白い人も居るのだろうけど、私は選ばれなかったようです
キャストだけで見ようと思っている方はご注意です!
なにがどう独特なのか、が問題なのだ❗️
いやぁ参りました。
どこでどう作動したのか、しっかりと眠気スイッチがオンに❗️
目覚めたければ眠れ❗️って俺のこと?
と冷や汗かきました。
独特の世界観だということは分かる。
人工的な背景やセット、いつでも晴れ、どこまでも明るくて眩しくてカラフルな街と人。
ノッポで人懐っこそうでとぼけた愛嬌のある宇宙人。
あれだけの俳優さんが参加したくなるのだから、さぞ楽しい雰囲気の現場なのだろうな。
マーゴット◦ロビー見逃さなくて良かった❗️
トム◦ハンクスがゴルフ場から電話してる時に画面の左上の方に映っていたグリーンのピンを握っていた人。何か可笑しなことをしてくれるのかと思ったら、そのままだったな。
スカーレット◦ヨハンソンはじめ、いるだけで存在感のある俳優さんのシーンは別としても、なぜか断片的に印象に残るシーン、切り取られた映像が記憶に残る。決して面白い場面ではないところも。
なんとも不思議な映画で、独特なことは分かるけど、なにがどのように独特なのか。
私にはうまく説明できません。
宇宙人かわいい
監督らしさは出たが、いかんせん平板、感情なし意図的でわかりにくい。
この監督は、細かい作り込みで楽しいけど
こと今回に至っては
アメリカ西部砂漠 と舞台劇 が結びつきが難解🧐
➕俳優も敢えて意図的に無感情だから 眠くなってきた
1955無敵のアメリカの夢はなんと無く伝わった
しかし舞台劇がそもそもサッパリ意味わからず
事実関係がわかりやすい宇宙人➕砂漠も、俳優が意図的にセリフ多いの、棒読みに近い
から無機質すぎて、私には辛かった。
あっ有料パンフは購入しましたよ
最初の方の説明でカラクリは明快にわかります【ネタバレだから言えない】
ただこの 有料パンフは 最初の数ページ以外 文字が以上に多くて流石の私も読まないなぁ
風景建物の造り込みは良し、ただし、砂漠と 暗い画面の舞台だから飽きてきた
まあ人によって理解力は違うから、評価違う方もいると思います。
ただし、通りすがりで入る作品では無く、確固とした意志で見るべき ある程度 映画ツウの人のための作品に思えた
あと、普通映画開始時刻は10分予告編・広告で時間余裕あるはずだけど
それを見込んで客席入って行ったら、すでに本編始まってた 生まれて初めての映画遅刻でございました。
ただ土曜朝に本作観にくる人々、咳😷一つ、ポップコーン🍿でガサガサなどあるはずもない
【映画鑑賞の猛者】が集う雰囲気がたまらんかった。その雰囲気は良かった
しかし、雰囲気に浸れただけで、落ちこぼれて ひねくれる映画ドシロウトジジイであった。
文字が以上に多くて →文字が異常に多くて パンフでございました。【おしまい】
「approved」
洋服で喩えるならば"デザイナーズブランド"といっていいのではと思う程のルックを全面に押し出すウェス・アンダーソン監督作品
ストーリーテリングさえも綺麗にパッケージングされているようなイメージしてしまう 計算され尽くした色彩設計やカメラワーク、スプリット等の映像処理、画角と撮影距離の絶妙さ、小説や詩のような台詞と、早口の回しに依る抑揚の制御、まるでテーマパークのような(実際の設定だがw)、セットや大小様々な道具達 結局回収されない建設途中のハイウェイや、意味げのあるロードランナー(ユニバーサル配給だから本来ならばウッドペッカーでは?w) 未だ未だこんな数ではない小ネタが仕込んであるんだろうと思うのだが、所謂"意識高い系"が喜ぶ出来映えではないだろうか
自分は努力もしてないので高みに登る事を放棄しているが、金さえ払えばこういう内容も鑑賞出来る『映画』というエンタメはとても楽で有り難い^^ 制作陣の努力の上にあぐらをかいて、澄ました顔で、スクリューボールドラマとしてのギャグやユーモア、そして無邪気で愉快な子役の演技を観れるのだからね・・・
なので、今作品を或る意味、"美術館"で絵画鑑賞するというアプローチで意識した人が愉しむことを享受できるのではないだろうかと思う
宇宙人飛来後の現場関係者への検査や尋問等シーンでの各仕切りの上に内容の札が立て掛けてある小ネタ等、こだわり抜かれたセンスを、ベタと捉えるかどうかは各観客の"自己暗示"具合に係っているだろう(苦笑
背景を知ると多少
1950年代のアメリカ
大戦が終わり冷戦と核開発に明け暮れ
宇宙開発もソ連と競争し政府が
宇宙人の存在まで本気で考え始め
子供たちも宇宙に無限の可能性を
持っていた時代
世間はテレビ放送が始まり
テレビドラマ等が開始
その中で俳優はそれまでの
やたらセリフを誇張したものでなく
その役の性格や背景を取り込み
自然に演ずる「メソッド演技」
に変わっていく・・
という背景を知っていると
多少なーるほどと感じる作品では
あったが不思議な映画であった
あたかも今敏作品のような
テレビ放送の中の中という
入れ子構造を行ったり来たり
そのためメイン画面は実写では
あるものの遠影もピント
合いっぱなしの舞台装置みたいな
不自然なビジュアル
なんか妙に見慣れてるのは
「バービー」で同じようなのを
見たからか・・最近流行りなの?
だから作中の登場人物が
舞台演技のように極端な行動を
取ったりしつつ
急に素に戻るなどの場面を
ちょくちょく入れたり
テレビ放送のナレーションの
おっさんが間違えて劇中に
入ってしまったり
そういうとこで笑いを取る
感じです
(と書いてる時点でそんなに
面白いわけではない)
作中のキャラクターを作り上げる
ごとに境目が無くなっていく
感じが面白いね!という
感じなのでしょう
難しい映画なんでしょうが
キャストが豪華で
そこは見ごたえがありました
ウィレム・デフォーまで
出てくるとは思いませんでした
1950年代のアメリカ
体制に翻弄される世間と
抗う将来性を持った子供たち
色々なメタファーあるんだと
思いますがまぁ
色調の面白い映画だったな
くらいの感想にとりあえず
しておく感じです
もー❤️!最高🎉
セット、衣装、構図、カメラワーク、カラーetc.
すごい、最高です。
本編とは別に
メイキングビデオを見られたので
ドキドキ💓
オープニングから、ワクワク😀が
Maxテンション!
一気にウェス・アンダーソン・ワールドにダイビング
アンダーソン監督は、「ヒューゴの不思議な発明」(マーティン・スコセッシ監督)の玩具店の店主(実は「月世界旅行」の製作者ジョルジュ・メリエス)を見つめるヒューゴのような子供の目をしていたのかなぁー?
あっ!そうそう
今、別の映画館で上映している
グレタ・セレスト・ガーウィグ監督「バービー」(着せ替え人形バービーの実写映画化)
と、いうのも、何かシンクロしてる!
ガーウィグ監督は、
「ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語」の監督だけど
留学生トレイシー役(声)で「犬ケ島」に出演してたんですね!
安心のパステルカラー
全221件中、181~200件目を表示