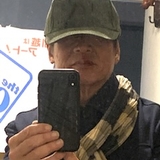ザリガニの鳴くところのレビュー・感想・評価
全444件中、201~220件目を表示
今年No.1の映画だと思います。
「ザリガニの鳴くところ」ただのミステリーではなく、ヒューマンドラマや純愛など、さまざまな側面があります。
最初はカイアが自然の中で独りで生きてきた割には、「美容院直後のようにきれいすぎる」など違和感を感じますが、「アメリカ映画特有の荒唐無稽さ」と割り切ってしまえば、映像美は随一なので、楽しめて時間を忘れさせてくれます。
あとカイアは精神的にも、学校に行かず文字も読めなかったのに、純粋な青年に少し教わっただけでラテン語の学名も覚えたり、集団生活に馴染めなかったのにこの青年と心が純粋に通いあったり、アメリカ特有の性善説を濃厚に感じます。
ただ舞台となるノースキャロライナの村のコミュニティが「部外者は疑わしきを罰す」的な態度をとるあたりに、地域コミュニティに対する信用度が落ちた、時代性を感じました。
映画の満足度が高いので、原作本を買って読書中です。
Kya〜本当の君
「 湿地の少女 」と呼ばれるカイアを演じたデイジー・エドガー=ジョーンズの凛とした眼差しとしなやかな肢体、悦び、不安、驚き、落胆、恐怖…美しい彼女の繊細な演技に魅せられた。若きデイジー・エドガー=ジョーンズにアカデミー賞主演女優賞を切望 ✨
彼女の支援者の一人となる弁護士を演じたデヴィッド・ストラザーンの表情もいい。
没頭して小説を読み進めるように、スクリーンに映し出された世界に引き込まれた。是非映画館でご覧下さい。
パンフレットが完売で入手出来ず残念。。
ー自然に善悪はない
ー裁かれるのは彼ら
映画館での鑑賞
あっという間の2時間
ずっと食い入るように観ました。
湿地で一人で暮らすカイアという女性。
カイアの行動が是か非かと問われると、、、
人間社会の面から見れば「非」なのだろう。
でも生物学的に考えると、何ら特別なことでもなく普通のことなのかもしれない。
生物たちは生き残るために、そして種を残すために、身を守る工夫をし生き残ろうとする。
時には色を変えたり形を変えたりもする。
そんな生物たちを見ながらそんな生物たちと共に湿地で育ったカイア。
弱いものが淘汰されるのも見ながら育ってきただろう。
生物という大きなくくりで考えると弱者が強者から身を守り生き残ったということになるのかな。
美しい映像と、どこか憂いを帯びたカイアがとても魅力的で惹きつけられました。
面白い作品でした。
森を疾風するカマキリ女は野生人!
原作は読んでおらず、予告編を数回見ただけで、鑑賞しました。
アメリカ中部地方の片田舎では あるある変人帰還兵お父さん なのかもしれないが
現実的には、リアリティがまるでない世界感と物語の進行が幼稚すぎて、落胆してしまう。
最後の最後でタネ明かしが有り、真犯人が誰なのかは教えてもらえたが
いかにも!と言う 赤い糸と雑貨屋さんの親切さ以外
鑑賞者に対して、ヒントを出したり、思わせぶりをしたりするきめ細かな演出がなく、本当に原作があるのか? と思える脚本には あきれるばかり。
おそらく脚本家は原作を読み込まずに、脚本を描いたのかも知れないが、僕自身が原作を読んでいないので、真偽は判らない。
1番肝心な"犯人による 無理感多彩 な殺人手法"を映画の中で、何も答えが記されず、誠に残念。
撮影・音響等無難な映画作りなので、特記事項はなく、ストーリーを追っていくだけの凡作映画でした。
「ザリガニの鳴くところ迄 避難しなさい。」の意味を考えたが、
母からの答は∞遠くにある場所、すなわち「ここにはない 家を出なさい」という意味だと思う。
お父さん、殺されたのかもね。
宮崎駿監督なら、1カットだけ そんなヒントを入れたでしょう。
この映画を観たら「ツインピークス」をまた、観たくなった。
ラストの考察
一人で鑑賞したため、誰かに話しかけたかった内容をつらつらと。
ラスト、彼女はなぜチョイスを描いたのか分かった?私はよく分かっていない。彼が湿原の一部になったから?本当に愛していたから?彼女の研究対象だったから?何か伏線はありましたっけ。
貝殻があるのはなんとなく分かっていた。多分彼女が殺している、と。でも誰も本当の彼女を見ていなかったら、見ようとしていなかったから(愛していると言っていた彼も)罪から逃げ切れたのだ。沈黙は金なり、本当に。
ラストのCarolinaが心に響く響く…彼女は自分も湿地も守り通して素晴らしい人生だったな。結局自然に善悪はないのだ。
法廷ミステリーの描き方が変わった
法廷ミステリーと言えば、従来は裁判の中でドンドン新しい証拠、あるいは違った切り口の考え方が出てきて、裁判の形勢が変わって行くというパターンが多かった。
古くは『12人の怒れる男』、最近では『コリーニ事件』など。
この作品では裁判シーンが少なく、また新事実の披瀝さえもない。
にもかかわらず時間がかかったとはいえ形勢が逆転した。
本作品では2つの事が暗示されている。
1つは陪審員制度(日本では裁判員制度)の危うさ、ひいては司法制度そのものの危うさ。
陪審員(裁判員)は目の前の事実に着目しながらも、噂・世論・差別・先入観・忖度など、最近は同調圧力と表現されている物で冤罪を引き起こす可能性を孕んでいる。
マスコミによる誤った誘導や最近ではSNSの広がりによってなおさらその傾向は強まっている。
またその逆に本来有罪であるべき者を同様の要素で無罪放免としてしまう可能性もある。
「O・J・シンプソン事件」などはその典型的な例であろう。
2つ目は主人公の女性のように小児期に家族に遺棄されても、一人で生き延び、なおかつ学者・研究者を超越する知識を有するまでになる。
そんなことが現実にあるのだろうかと思うが、決して無いとは言い切れない。
既成概念を取っ払って行かないとこれからの社会には対応できないのではないかと思わされた。
それにしても被害者は事故死なのか殺害されたのか?
どちらにしても如何にして死に至ったのか?
手がかりは本編の中にあるのだろうから、もう一度見てみたいと思う作品である。
彼女は自然に生き本能に従った
小説を図書館で借り半分から3分の2ほどを読んだところで返却期限が来てしまい、主人公の逮捕や裁判の判決、物語の結末を知らない状態での映画鑑賞でした。
鑑賞後の余韻、清濁の混じり合った感情の落としどころが分からない感じ、ハッピーエンドでスッキリ終わらない結末が心にトゲのようにいつまでも残り、もう一度映画を観るか小説を読み直すかしようと思っています。
主人公の彼女の行動原理は湿地で自然を親として育った娘として自然界の原理原則に従っていて、それは街の人たち、それは支援してくれた雑貨屋の夫婦や読み書きを教え最も長く彼女と一緒の時間をすごした彼ですら、真の姿を見ることが出来ていなかったのではないかと思った。ただ、そのことが彼女や周りの人たちを不幸にするものではなく、むしろ幻を信じた人たち、判決をくだした陪審員たちや彼女をさげすんだ街の人々や息子が死んだことで彼女を法廷でののしった遺族ですら、良心や道徳心を思い出し、差別意識に気が付いたことでその後の人生をプラスにしたとさえ思える。
終始、街の人々は湿地で育った彼女を見誤り続けた。彼女は自分からは生い立ち以外何も言わないし弁明もしない。なぜなら理解されないと思っていたし、結末を見れば誰1人として彼女を理解していなかったのだから、彼女のことを分かっていたし理解できたのは、ただ彼女自身だった。彼女は自然に生き、生存を渇望し、そして賢く生き抜いただけの事だったと感じた。
※以下ネタバレ含※
感想書き終わって他の人のレビューも見て回って来たのですが、この映画の予告で大どんでん返しがあると宣伝していたようで、そのことで期待を裏切られたとおっしゃっているレビューが高評価を得ており、やるせない気持ちになった。
その方に非はなく、そう宣伝した広報の担当者が悪い。
これってそういう話しじゃ無いですよね。
パラサイトみたいなのを期待して観にきた人は肩透かし食らって帰ったことでしょう。
裁判では無罪になったけど、本当はやったんじゃないかなって思いは自分もあったし、最後に「やっぱり彼女がやってました!っビックリしたでしょ?」をメインテーマにしていたなら、んー、、薄々そうかもなって思ってたよってなるもんね。
ただ、この映画のテーマとするところはそこじゃ無いはずなんですよね。人間社会の規範の外で生きる自然界をサバイバルして来た娘の生き様とでも言うんですか?そういうもっと深い(語彙力なくなった)テーマがあるのを感じて欲しいんだけどな。勿体無いな。
例えば、裁判終わって未来の旦那とハグする前にお腹さすったり、カマキリの描写とか、この辺見逃すと全く違う話しにみえちゃうよね。
編集者との食事でのホタルの話なんて分かりやすい伏線だったし、色々やってくれた弁護士に感謝なのか何なのかよく分からない去り際の振り返りと目線。あれも違和感があったわけで、はじめからあの弁護士おじいちゃんの優しさにつけ込んで利用するつもりだってあったんだよねー?覚えてたもんね昔会った優しい人だって。いやあの後学校で嫌な思いしたから仕返ししてやるって元から思ってた可能性すらあるわけで、って思ったら怖くないですか?
物的証拠とされた赤い繊維も、元々は未来の旦那のニット帽でしょ?ずさんな捜査のせいで、そのニット帽の元々の持ち主まで辿り着かなかったものの、現場に残ってたものがその繊維だけって、つまり彼女の狙いは、、、ってことでしょ?深読みし過ぎ??
そう思って観た人って少数なの?
せっかく想像する余地がいっぱい残された作品なのに、目に見えたストーリーにしか関心が向かないのって本当に勿体ないな。とか偉そうにごめんなさい。
とにかく、自分は本気で楽しめたしあと何回か観ます。見落としとかまだまだあるもんね絶対!
ネイチャーライティングとエンターテイメント
湿地帯の住人としての生き方
光と闇、水と緑溢れる湿地帯を舞台に
名作
ツッコミどころがたくさん🦞
主題がわかりにくいと思いながら最後まで観ました。
ツッコミどころが満載でした。結局、カイアが犯人で、捕食者を殺していたのですね。
でも、いったいどうやって?変装して深夜のバスに乗り、短時間で大の男を突き落とし、何食わぬ顔で編集者と朝食を摂り…。稀代の悪女でした😅
殺された彼の親御さんは、モヤモヤするだろうなあ。どんな悪人でも、かわいい息子には違いない。裁判の仕方も、ものすごく雑です。あのネックレスも、取る必要ないし、あんなわかりやすいところに隠して、テイトも気づかないだなんて。
結局、湿地が大好きで、町の人から疎んじられているけれど、自分からも避けていたし、うーん、何がいいたいのかがもう一つよくわからず、モヤモヤしました。湿地の泥や砂は、都合の悪いものを全て隠してくれるということでしょうか?
エンドロールの歌詞がすごい。
原作では、ツッコミどころがちゃんと説明してあるのでしょうか?半分まで読んでいるので、後半を楽しみにします。
美しい景色と濁った世間
(原題) Where the Crawdads Sing
なかなか興味深い内容の作品でした
スケールでかい。彼女の人生が一本の作品に
美しい自然には残酷さも秘めている
湿地でひとり暮らし続けている少女の話。
美しい自然を描かれた映像を観るだけでも価値がある。
その美しさとは対照的に少女の残酷な半生を描くことが印象的だった。
殺人事件の容疑者とされ、法廷での出来事からこれまでの少女の半生を描いていく様子は、とてもテンポ良く観ることができた。
自然を教科書にして育った彼女だからこその行動には納得だった。
全444件中、201~220件目を表示