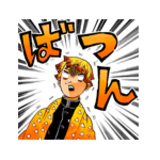とら男
劇場公開日:2022年8月6日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
本編を見るPR

解説・あらすじ
刑事歴30数年の元刑事が本人役として主演を務め、かつて自身が捜査にあたった未解決事件の真相に迫る、セミドキュメンタリータッチの異色ミステリー。
1992年に起きた金沢女性スイミングコーチ殺人事件。担当刑事のとら男は犯人の目星をつけながらも逮捕に至ることができず、未解決事件のまま2007年に時効が成立した。15年後、警察を退職したとら男は事件のことが忘れられないまま孤独に暮らしていた。ある日、とら男は東京から植物調査に来た女子大生・かや子と偶然出会う。とら男の話に興味を持った彼女は、当時の事件について調査をスタートさせる。現実とフィクションの二重構造によって、闇に葬られた事件の謎と真実を世間に問うていく。
とら男役を元・石川県警特捜刑事の西村虎男、かや子役を「海辺の映画館 キネマの玉手箱」の加藤才紀子がそれぞれ演じる。監督は「堕ちる」の村山和也。
2021年製作/98分/日本
配給:「とら男」製作委員会
劇場公開日:2022年8月6日


 堕ちる
堕ちる ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に
この世界の片隅に セッション
セッション ダンケルク
ダンケルク バケモノの子
バケモノの子