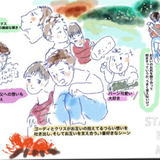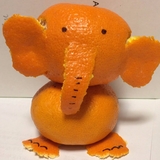CLOSE クロースのレビュー・感想・評価
全141件中、81~100件目を表示
今の時代はこういう作品が評価されるべき
ストーリーはよくある展開だし、
大どんでん返しや驚きなストーリーじゃないけど
少年の涙にここまで心が動かされるとは…
心が洗われる作品だった。
色々なやりようで、さらに涙で前が見えないくらいに感動で陥れるような展開とかがあったと思うけど、
この映画はそこがちょうどいい。
心の窓をトントンと優しく叩いて、奥に入ってきて
じんわり溶かしてくれるような作品だと思う。
誰かの心無い言葉で関係が悪くなったり、傷ついたり、
そういう人がいることがわからないお馬鹿さんがあふれているSNS時代の今こそ、こういう作品がきちんと評価されるべきだと思う。
あとは、残された人がどんなに辛いか、
周りの影響にも気付いてほしい。
今度から疲れた時におすすめの映画ある?と聞かれたら、この映画を紹介したい。
あの花は紅花油の紅花?
レミのお母さんのソフィー(エミリー・ドゥケンヌ)の表情で見せる演技がなんとも素晴らしかった。
助演女優賞あげたいです。
レオに車から降りてと言ってしまったけど、追いかけて抱き締めるシーン。うすうすわかっていながらも、よかったなぁと胸を撫で下ろしました。
いなくなったレミの悲しみを共有するふたりの物語でした。
レオがそんなに悪い訳じゃないのに、やっぱりレミのお母さんを見ると少年レオの胸は痛みます。何度も突然会いに行ってしまいます。毎日のようにお泊まりしていたので、ソフィーにとってもふたりは同じように息子だったんでしょうし、レオにとってもお母さんだったんでしょう。
ソフィーの仕事は病院の新生児室の看護師さんか小児科医師。
それだけにつらい😢
しっかりした息子がふたりいて、家族総出で仕事をしているレオの家庭が羨ましい。レミがいなくなってからのお呼ばれしての夕食も辛すぎる。旦那が泣き出して、堪らず夕闇の中に出ていった悲しい後ろ姿も印象的でした。
あの花は紅花油の紅花?
花に詳しい方、教えてくださいな。
鑑賞用の花にしては花だけ摘んだり、機械で根こそぎ刈り取ったり。
プラ容器に苗を並べて、機械にセットするような場面もあったけど。
紅花の花言葉調べてみました。
特別な人。愛する人。化粧。情熱。包容力など。
好き過ぎて喧嘩しちゃった原因のひとつがレオの虚栄心だったとしたら、化粧も関係するかななんて思ってしまいました。このくらいのことは男の子にはよくあることなのだけれど、突然先に逝かれてしまった方は堪りません。
23-094
美しさが印象に残る映画
とにかく美しさが印象に残る映画で、出てくるのは美男美女ばかり、
咲き誇る綺麗な花畑、自転車で通り過ぎるだけの草原、やわらかな陽射し、
その全てが美しい。
撮影は、監督の出身地ベルギーとゴッホの出身地オランダで行われたらしいです。
美しい映画なのでケチつけたくないんですが、後半ねむくなってしまった(笑)
でも、いい映画です♪
シリアスな映画で少し静かめだけど、暗すぎず明るすぎず、観やすい映画かと。
ベルギーやオランダって美しいなー♪と思った、美しい映画です(笑)
ベルギー、オランダ、フランス、の合作なので、言語は何だろう?と調べてみたら、
ベルギーは、オランダ語、フランス語、ドイツ語、の3ヶ国語らしく、
過去、オランダ、フランス、ドイツ、に支配されてきた事に由来するそうです。
同じベルギー人でも言葉が通じない事あるんだとか。
映画で使われてるのは何語なんだろ?
レオの美しさに圧倒✨
とにかくレオとレミの二人の透明感にやられました✨
二人ともお互いに同性愛を感じていたのははっきりとは分からないけど、レオにとってはレミが、レミにとってはレオがかけがえのない存在だったのは間違いなく、それなのにその関係はあまりにもあっけなく他人の心無い軽口によって壊れてしまう…その儚さに少年たちの繊細さを感じて切なかったです。男の子っぽさを全面に出すスポーツを敢えて始めて、レミと距離をおくレオ。もしレミが亡くならなかったら?二人はどうなってたのでしょう…ハッピーエンドになっていたでしょうか?ずっと考えてしまう、そして後から思い出しても涙が出てしまうような映画でした。
ほんのりBL
性のあわいの悲劇。
レオとレミは幼いころからの親友で、花卉農業を生業とする互いの家を行き来して長い時間を共にすごしていた。互いに深い好意を示すことに少しも疑いをはさまない暮らしの中で、夜も自然にベッドで体を寄せ合って眠るほどだった。
しかし二人のそうした濃密な関係は、彼らが小学校に入ると淫靡なからかいの的になる。レオはそれを疎ましく思い始め、レミは深く傷つき、事件が起きる。
中盤までのカメラはなかなか素敵。とりわけオープニングからしばらくの、暗がりで声を掛け合う二人が外へ飛び出して一面の花畑を駆けだしてゆくショット、オーボエを吹くレミを逆光の中からみつめるレオの幸福な視線、等々。このあたりは自らの性を明確に意識するより前の、幼い両性具有性をうまく捉えてみせたと思う。
しかし照明・カメラ・編集のいずれも表現の引き出しが少なくて、中盤以降は、同じスタイルが反復されすぎることがどうしても鼻についてくる。脚本の踏み込みの弱さがその印象に拍車をかける。
是枝裕和『怪物』にも同様のニュアンスを示唆するシーンがあるけど、あの映画の複雑さ・繊細さには到底及ばなかった。
ところで朝日新聞の本作レビューで「メロドラマの傑作」と評しているのは、メロドラマという言葉の誤用。メロドラマというのは、本作の場合なら二人が最後まで出口なしの状態で悩み続ける映画のことです。
少年たちの悲しみ
流れる空気
オーボエ、口から出す音、風音、効果的にその心象を表現する演出には敬服する 是枝監督が今作のアンサーを贈ったのではないかと勘ぐる位、その親和性を高く感じた作品である
クィアー系とはいえ、まだまだその自覚どころか、却ってミスリードさせてしまうほどのギリギリの岐路を丁寧に、しかもセンチメンタルに描いてみせた作劇、そして映像手法である あくまで主人公の顔のアップの多さで、主観をキチンと明確にしていることも好意的である
どの作品でも観賞後にあらすじを確認するためネタバレサイトを必ずチェックしている そこでの見識深い内容に、毎度感心し、自分の稚文など便所の落書き以下だと、はっきりとその能力の差違を重く受け止めてしまう事仕切りである ま、自分は対価など貰っていないのだから当然と言えばであるが・・・
そのサイトの中で、興味深い内容があった 『映像制作者向けにWHOが「自殺予防の指針」』
表現の自由に対する、公共の福祉という観点であろう、12項目から成る『望ましい、そして防止足り得る』方法の提言といった内容である そして今作はその指針が強く反映されている作りであることを解説されていて、自分は合点がいき、腑に落ちた心地なのである
今作ではハッキリとした演出や衝撃的なシーン、そして筋として核となる作劇は描かれていない なので観客がそれを推測、もしくは想像、又は先回りしたり巻き戻したりしての、もしかしたら"邪推"や"誤解"を誘発しても構わない覚悟を持った作品であることを強く感じ取れたのだ
例えば、部屋のドアノブが壊されている画は、単純にそこに縄を引っ掛けた際の損壊を想像したが、その前のシーンで、風呂から出てこないで鍵を掛けている演出があることを忘れていて、そこから鍵を親が壊して発見したと解釈し直す 重要なシーンだが、しかしこうして観客それぞれが一つの疑いない作劇上の事実でさえあやふやにしてしまう表現方法は、果して良いのであろうか?という疑問が過ぎるのである 否、勿論、だから今作を否定として捉えていることではなく、寧ろ今作の心象表現や、強い表現を回避する工夫を逃げずに努力する大事さを感じる程だ
表現の自由を損なうと簡単に切り捨てられないのは、現在のより高い人権意識への移行のとっかかりに過ぎない 自由と福祉の一見矛盾している方向が、でも何とかお互い携えて活けないモノかと叡智を産み出す作業は、これからも継続して欲しいし、映画ファンは、それをキチンと理解、応援する事を忘れてはならないと、何度も思い起こさせる思考にバージョンアップする努力が上位互換として実装することに逃げてはならない
まるで脊髄反射の様な、エンタメに支配された頭ではいつまで経っても自分はだらしないから・・・
展開が読めてしまって涙腺が緩まなかった。。。
幼馴染の少年2人、レオとレミの悲しい物語でした。2人は兄弟同様に育ち、寝る時も一緒というほどの仲良しでしたが、同じ中学校に入学して周囲から2人の関係を揶揄われるようになってからギクシャクしだし、悲劇を迎えるところで前半が終了。後半はレオの心情の変化に寄り添う形で物語が進められ、一応彼がひとつ成長したところでエンディングとなりました。
印象的にもテーマ的にも、また(カンヌ国際映画祭という)ショウレース的にも是枝監督の「怪物」と軌を一にする作品と言って良く、単なるLGBTQ物をさらに一歩進めて少年同士の話にするのが最近のヨーロッパ映画界の潮流というところなのだなと確認できる作品でした。ただ「怪物」と比較すると、容易に先が読めてしまうところがあり、悲しい物語でありながら全然泣けないところが悲しい作品でもありました。仮に同じことが現実に自分の身に起きたとしたら、立ち直るのに相当の時間をようするであろうことなのに、きっとこうなるかなと思った通りの出来事が起きるため、事前に耐性が出来てしまって涙腺が刺激されるには至りませんでした。別に泣きたくて映画を観に行った訳ではないですが、ちょっと残念な部分ではありました。
また本作の特徴は、そのカメラワークにありました。主に主人公に焦点を合わせてしかも大写しにして、さらにその背景をぼかすという映像が連続しており、他の登場人物があまり目立たないような創りになっていました。これは、彼らの心情がCLOSEしていることを表していたのか、美少年の映像を堪能してくれというメッセージなのかは分かりませんが、印象には残ったもののあまり感情を揺さぶられるような感じもありませんでした。
さらに、扱っているテーマ性から、社会に対するもっと強烈なメッセージ性とか、風刺とか訴求とかがあるのかと思っていましたが、そうしたものもあまり感じられず、ちょっと肩透かしを喰らったような形で映画館を後にしたところでした。
あと、内容とは全く関係ありませんが、「CLOSE クロース」という題名はどうなんでしょうか?先日も「Pearl パール」という作品を観ましたが、「英語+英語のカタカナ読み」という形式にするくらいなら、単純に「CLOSE」とか「Pearl」だけにしたらいいのになあ、と思わないでもありません。
そんな訳で、主人公2人の少年は、「怪物」同様にとてもかわいかったものの、物語としてはあまり揺さぶられることがなかったので、★2.5の評価とします。
丁寧な映像表現と感傷的な音楽で・・・
前に進むために、人は忘却の機能を備えていますが、大人になって、思い出したくないことでも、ふとよみがえってくることがあります。そんな心の澱を洗い流す物語です。
大人の入り口に立つ少年のイニシエーション(通過儀礼)の物語。そう表現するには、あまりにも痛切で悲劇的です。二度と取り戻せない日々だからこそ、その一瞬がまぶしく輝いても見えてくるのでした。
13歳のレオ(エデン・ダンブリン)と大親友のレミ(グスタフ・ドウ・ワエル)は何をするにも一緒。学校へ行き、放課後はともに遊び、寝るときだって互いの家を行き来し、寄り添って寝るほどの仲の良さ。2人も家族も、それが当然と思っていました。
長い夏期休暇を無邪気に過ごし新学期に。中学生となった彼らは同じクラスになります。でも、それは無邪気な時間の終わりへ。繊細で壊れやすく、手にした瞬間にその手からすり抜けてしまう「何か」のように、二人の関係に異変が待ち受けていました。
学校に行くと2人のあまりの仲の良さをいぶかしがるクラスメートが、「付き合ってるの?」と揶揄してきます。レオは「親友だから仲が良いのは当然だ」とムキになって反論するのです。
しかし、クラスメートの視線が気になったレオは、これをキッカケにレミと距離を取るようになります。なぜ自分を避けるのかわからないレミ。
一方、レオはレミをどこかで気にかけながらも、他のクラスメートと交流を深めていき男らしさを求めて、アイスホッケーのチームに加わります。一方、音楽家を目指すレミは、遠くからレオを見つめるだけ。映画の前半は、思春期の友情とも同性愛ともつかぬ感情の芽生えを、繊細に描写されます。
そして2人の友情に決定的な別れが訪れるのです。
心理学の世界で「close friendship」と呼ばれる、友情とも、愛情ともつかない少年同士の親密な感情が題材となっています。
デビュー作「Girl/ガール」で、バレリーナを目指すトランスジェンダーの少年の痛みを切なく描いたルーカス・ドン監督は、再び少年の複雑な内面に迫ります。ほとんどの場面がクローズショットで、カメラはレオと、レオが見ているものだけを映してゆくのです。レオからすれば、自分の態度や振る舞いは周囲にどう見えるのか。世間の目を気にして、社会規範からの逸脱におびえています。一方で、レミが気にかかり、その姿を無意識に目で追いかけてしまうのです。
もう一つは作者の目。物語には、アンジェロ・タイセンスと共同で脚本を手がけたドン監督の少年期の体験も反映されているそうです。大人になったレオの目とも言えるかもしれませんが、過去に失ったものをしのび、いとおしむ。そんな気配を感じさせてくれました。
映画の途中であっと驚く秘密が明かされるわけではありません。観客は家族ぐるみで付き合っているレオとレミの親密さ、関係がぎくしゃくしていく過程を全て目の当たりにしたうえで、取り返しのつかない悲劇的な状況に陥ったレオの感情に同化することになります。大人の私たちも、楽しいことだけではなかった“あの頃”の不安や孤立感が脳裏によみがえるのです。
2人が自転車に乗って登校する場面が何度か出てきます。最初は明るい陽光の中、2人は幸福感と一体感に包まれて疾走しています。しかし学校での出来事の後、硬い表情の2人は目を合わせず前方をにらんだまま。どちらの場面もセリフはなく同じ構図なのに、気まずさと戸惑いが痛いほど伝わってくるのでした。
やがて悲劇が起きて、レオは取り残されてしまいます。何が起きたのか、映画はやはり、はっきりと示しません。レオの表情と生活の断片がつなげられ、観客はそのはざまを埋めるべく想像と思索を促されるのです。
そんな状況の説明も前後の経緯も描かず瞬間だけを切り取って、本作はそこにあふれる情感をみずみずしくすくい取っていきます。
舞台はのどかな田園地帯。レオの心象を自然の風景に仮託した映像美に息をのみました。レオの実家は花卉農家。花畑が見せる季節の移り変わりは無常観を表し、慣れ親しんだ関係や価値観の崩壊も予感させるのです。花畑を駆け抜ける少年たちと並走する移動ショットのえも言われぬ美しさ。「Girl/ガール」に続いてフランク・バン・デン・エーデン撮影監督が撮った映像美が際立っています。でもただ美しいだけではありませんでした。 前半の赤い壁の自分の部屋でオーボエを吹くレミと、「お前のマネジャーとして大金を稼ぐ」というレオ。悲劇の影もない2人を、金色がかった自然光で柔らかく撮られていました。
対照的なのは、硬く冷たい人工の光で照らされた夜のスケートリンク。レオが、通路に見えたレミの母親に近寄って手すりにつかまるバストアップ。レミの母親ソフィー(エミリー・ドゥケンヌ)がリンクに向けた目を戻し「会えてうれしい」と、レオがきつい角度で切り返しを重ねます。2人ともレミの話を避け、対話感が出ないポジションの妙。ぎこちなさに、巧みさが見えました。演じている感じなのです。
レミや母親のソフィの感情表現も抑制的。過度な感傷を排し、淡々と長回しで台詞もなく描かれていく演出でも、それぞれの煩慮が痛いほど伝わってきました。
エアポケットのような虚脱を経て、再生への希望もにじみます。レオの再生のキーパーソンとなるソフィを演じたエミリー・ドゥケンヌの助演が光っていました。ふたりが奏でるラストシーンは、きっと涙がこみ上げてくることでしょう。
ところで、本作ではレオとレミ役の男の子の演技が抜群。これはひとえに監督の演技指導といいますか、信頼関係がしっかり築けている証しなのかもしれません。
しかも驚きなのが、2人とも演技は初経験であるとか。とにかく自然な演技+透明感が圧倒的です。わたしはふと一連の是枝作品に登場する素人の子役たちの自然な演技を連想しました。
演技に見えない演技とでもいうべきか、余計なことは考えずに素直に心で演じている感じなのです。口にするのは簡単ですが、なかなかどうして根気が必要な作業ですから容易ではなかったと思います。
最後に、ひと言。前に進むために、人は忘却の機能を備えていますが、大人になって、思い出したくないことでも、ふとよみがえってくることがあります。そんな心の澱を洗い流す物語です。
レオの瞳の複雑な色合いとその美しさ
本作、劇場で初めて予告編を見た途端「これはヤバいやろ(いい意味で)」と思っておりました。
違和感なく見入ってしまう美しい少年二人。前作『Girl ガール』ではトランスジェンダーの少女役にシスジェンダーの少年を配役したことで批判もあったようですが、まぁルーカス・ドン監督のキャスティングは絶妙です。
冒頭から、遊びの中での「鎧を着た兵士たち」演出や、寝付けないレミを気遣って諭す「蛇の話」など、想像力豊かで思慮深く、常に相手を想う大人びたレオに感情移入が避けられません。
学校と言うある種「特殊で狭い社会」に順応せざる負えないため、本来の思いとは裏腹に障壁を回避するための行動を取るレオですが、レオのようにやり過ごせないレミは戸惑い、そして悲劇が起こります。と、ここまでは予告からも想像できる範囲なので「ネタバレ注意」とはしませんが、まぁ、思った通り観ていてしんどいです。
アイスホッケーなどで自分を痛めつけるくらいい自分を追い込むレオ。とは言え、その細い腕をみれば、まだまだ華奢な身体に痛々しさを感じざるを得ず、レオの辛さを否が応でも想像して見もだえます。
そして、何より印象深いのはレオの眼差し。思慮深さからくる状況判断のため、常に彼の目線は観るべきものを追い続けます。そして気が付けば、レオの瞳の複雑な色合いとその美しさに見入ってしまいます。さらに最後のシーン、彼の目線の先には何が映っているのか?気づけば終始、レオ役のエデン・ダンブリンから目が離せません。
あと、何気に兄弟っていいですね。お互いを解って心赦せることや、説明の要らない「お互いを思いやりつつの言動」に劇中の当人たちと同じ思いで観ているこちらも、深く感じ入りました。
公開週のサービスデイ、ヒューマントラストシネマ有楽町の18時50分の回は5割弱の客入りでしたが、この逃げ場のない状況を体感するためにも、劇場鑑賞という選択肢もなくはないと思いますよ。
少年期はかくも美しく脆いのか
たらればを考えるのは生きてる人間の驕りなのかもしれん
落ちきった。観るべきではなかった。
美しい、だからこそ哀しい
13歳〜18歳の少年100人を対象にルーカス・ドン監督がアンケート調査した結果、13歳の頃は男友達をもっとも信頼できる大好きな存在として記されているが、成長とともに男友達との親密な関係に悩み出すようになるということ。それが「Close Friendship」(親密な友情)。
映画「CLOSE/クロース」は大人になりかけ、13歳の2人の少年に起こる関係の変化を丁寧に紡ぐ物語。
レオとレミは学校でも家でも家族ぐるみで一緒の時間を過ごす大親友。しかし、ある時2人の親密な関係をクラスメートに揶揄されたことをきっかけに「あれ?」と、自分って人から見てどんなふうに見えるのかしら?ということを意識し始める。
そして、この頃からレミとの関係に一歩引くようになってしまうレオ。気まずい雰囲気になる中で2人は些細なことから仲違いしてしまう。
親友同士の幸せな日々は永遠に続くと思っていたのに、、、、。という話。
思春期あるある!男の子あるある!
言葉にできない微妙な距離感、感覚、今にも壊れそうなガラスの感情を丁寧に掬い上げるルーカス・ドン監督の手腕が光ります。
セリフなし瞳の動きだけでここまで心のひだひだを語れるとは!
大人と子供の狭間にいる少年の感性を淡い光や美しい自然の光景に重ね合わせ見事に描き出しています!!
「怪物」の少年たちよりは少し年上だからこその悩みや考えが、どうにもできない歯がゆい気持ちが手に取るようにわかります。繊細な少年の感性、周囲にはなかなか理解し難い微妙な哀しい感覚、言葉にしにくいこんな感覚を監督は見事に映像化して、かつて少年(少女)だった者たちに突き刺してきます。
今年イチ、心に刻まれた映画です。
全141件中、81~100件目を表示