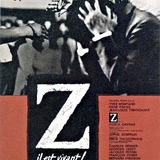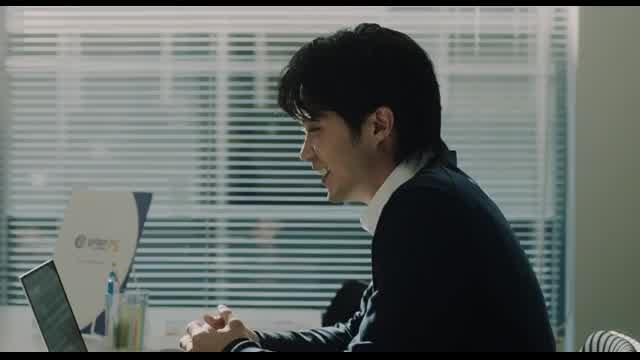PLAN 75のレビュー・感想・評価
全305件中、281~300件目を表示
タブーに踏み込んだことは評価したい
75歳を迎えた高齢者は自分の意思でその人生に幕を下ろすことができる制度「PLAN 75」。この制度が導入された近未来の日本を舞台に、78歳の寡婦、制度を推進する側の若者、制度下で必要となったある仕事を行うフィリピン人女性のそれぞれの視点から高齢化社会を描く。
突っ込みどころはたくさんある。そもそも安楽死が認められていないこの国で、どのような解釈の元にこの法律を施行するのか。75歳以上でも元気に働いている人達を死なせておきながら、認知症を患って意思を表明できない人達はどうするのか。支度金として支給されたお金をもらいながら最終段階で翻意した場合はどうするのか。彼らの遺産(プラスもマイナスも)管理はどのようにするのか。
映画はこれらの疑問に何一つ答えてくれない。劇中で起こる出来事の追及も……。おそらく監督もそんなことは百も承知だと思う。それでもこの映画が撮られた意味はあるはずだ。
9年ぶりの主演作となる倍賞千恵子さんの演技が素晴らしかった。
まさかの満席 sold out
完成度の低い残念な作品
このテーマーは昔から想定された課題であっただけに、
この映画では時代設定が甘く近未来設定なのに、
20年ほど過去に遡る単純な社会管理システムとなり、
緊張感もなく単に心情的で個人の心象風景ばかりが展開されるだけ。
そもそもが登場全員が高齢五体満足で、
このように心身健康な高齢者問題以前にもっと大きな諸問題が横たわっているのに、
この映画のPlan 75は最初からラストは、再帰、存命、縁などの希望が設定されていて、
そこに落ちていない、無理に落とした後味の悪さだけで、満席の高齢者から不満の声が漏れていた。
それにしても、
初日のこの時刻なのに沢山の高齢鑑賞者だった。
これは、賠償千恵子さんの力でしょう。
キャスティングにかなり人材を入れていたのがエンドロールで知れた。
高齢出演者全員が、
まだ20年以上も頑張れそうな元気が画面に出ている人ばかりだった。
それも作品の狙いなのかもしれない…
ありか、なしか。
自分はきっと申し込む
『十年 Ten Years』の短編から格上げ?されて長編に。
怖い話ではないけど、どこかゾクゾクするような、近未来的というか、サブカルコミック的というか。そういうベースの部分は変わってないように感じた。
この映画では、10数分の短編では描けなかった、現代の日本が抱える高齢化問題や、外国人労働者問題なども網羅してあるし、長くなった分、だいぶドラマティックな仕上がり。
ひろむ、成宮、マリアの若い3人は、国による意図的な死を間近にして、疑問を持ち、壊れていくのも無理はない。特にマリアは、まさに直後、高額賃金には訳がある。
2014年の『君がくれたグッドライフ』では、ベルギーでの安楽死を扱っていたから、全く有り得ない話でもないのかな。この先、更に年金支給額が減って、高齢者を支えていけなくなるくらいになったら、まさかね。
倍賞千恵子さん演じるミチさんが、施設での朝に髪を整えている場面。
なんだか死を処理されるような感覚のPLAN75に対して、人として死を迎えたいという誇りのようなものを感じた。
いろいろ考えながら見入ってしまった。
ひとつ不満といえば、楽しみにしていた河合優実さんの出番が少ない!
もっとミチさんといろいろ絡みがあるかと期待していたのに。
ファン歴たった1年だけど、社会人役は初めて観たから、それは新鮮。やっぱ雰囲気のある良い女優さんだなぁ。
正視できるか…?
「75歳以上が自ら生死を選択できる制度が施行された近未来の日本」っていうから寓話的なあるいはディストピアSF的なものかと思えばさにあらず。めっちゃくちゃリアルでブッ刺さりまくる。「あぁ、日本ってこうだよな〜」と腑に落ちすぎ…
この制度が制定された経緯もリアルなら、80近くなっても働かないと生きていけなかったり、変な善意から働けなくなったり、老人に死を迫ったり導いたりする仕事を若者にやらせ、死者の処理は外国人労働者にやらせ、最終的な処理は…など、そうした仕掛け作りだけは超洗練されていたり…これってまさに今の日本じゃないか。
SFという形を借りて、現代の日本の醜さを、否応なく見せてくれる傑作。しかしこれが正視できるか…?
安楽死でも尊厳死でもない
安楽死や尊厳死には肯定的である(終末期患者に対するもの)。実際に認めている国もいくつかある(まだ少ない)。しかし、PLAN75はいずれでもない。僕自身は自らの死を選ぶ権利だって認められるべきとも思っていたが、この映画で考え方が変わった。こうした権利を国が認めるような社会はディストピアである(福祉を放棄して、本来生きられる老人を死に誘導している)。国が奨励するというのはさすがにあり得ない。
この映画でPLAN75に自らの意思で手を挙げた二人の老人の現状と未来は暗い。恵まれない老人がやむなく死を選ぶことになる。"やむなく"なのである。
またPLAN75という設定は老人問題(福祉や介護など)のメタファーと考えて良いのかもしれない。
この映画は誰もが避けて通ることはできない老いや死、それに関係する社会問題、あるいは生きるということについて深く考えるきっかけになる。
最後に、主演の倍賞千恵子について。さすがでした。素晴らしかったです。
倍賞千恵子さんの声
この映画では誰も大声で話さない、叫ばない、怒鳴らない、泣き叫ばない。台詞も少ない。説明もほとんどないから日本に住んでいる人にはわかるけれど、日本を知らない人にとってはよくわからない箇所も多かったと思う。
静かに丁寧に観客に考えさせ、登場人物の思いを手渡す。映るのは背中と横顔が多かった。だから私たちも登場人物が見るもの、人、風景を彼らと一緒に見る。
倍賞千恵子がカラオケで明らかに素人の歌い方をしたことに何気ない凄さを感じて心から驚き感動した。あんなに歌が天才的に上手な人が!歌が上手い人は普通にというかあまり上手くなく歌うこともできるんだ!彼女の声の良さが映画の中で何度か言及されるけれどまさに倍賞千恵子さんのこと。
「老害」という言葉は確かにある。でも普通の地味に生きている大多数の人たちには当てはまらない。ずっと先の人生は若い人たちの将来であり夢であり希望であって欲しいと思う。
ご利用は計画的に
現在よりももう少し高齢化が進み、75歳から自身の生死の選択が出来る様になった日本の話。
78歳独身の女性と、75歳独身の伯父と20年ぶりに再会したPLAN75を担当する市役所職員を軸にみせていくストーリー。
問題提起する作品としては「十年Ten YearsJapan」のショートVer.でも充分だったけど、ドラマが深く掘られて悲哀が強くなり、エンターテインメント性は増した感じ。
まあ、ショートVer.を細かくは憶えていないけれど。
個人的にはPLAN75どころか65とか70とかでも制度としては大歓迎。
まだ、その齢には達していないけれど、もしその歳の時に独身ならば、持っている財産とか健康とか考えて、後を濁さず終わりたいし、例え家族がいても身動きできなくなったり、下の世話をして貰ったりしながら生きてもね…あくまでも個人的思想で誰かに押し付ける気もそこに共感して貰いたいとかも無いですが、それでも、恐いのは生きることか死ぬことか、幸せなのはただ生きていることなのかと考えさせられる。
そういう意味では、映画としての見せ方はわかるけれど、ラストのりんごの木の下での後どうする気なのか…とちょっと釈然としなかった。
高齢婦人らで劇場は大賑わい。
予告では、自発性姥捨て山系ディストピアものとしてアピールしている。果たしてどう裏切ってくれるか楽しみ。なぜ欧州が一定の評価をしてのか。最近の邦画「鈴木さん」や洋画では「ザ・サークル」のような、羊頭狗肉なワンアイデアに辟易しているので。
数カ国から映画助成金を集めてる。凄い組成だ。初長編だが、落ち着いた、若さが出すぎない演出もよい。クライマックスの詰めの説明が雑。伏線放置なあたりは、編集の尺詰めの問題か。音楽が素晴らしかった。外国の方だった。
主題の是非は観客にぶん投げているが、シニカルな寓話になっておらず、リアルな、検討すべき政策だとも思わせる。それほど高齢化は「映画でディストピアとして描く」というシャレにならないほど深刻。
映画に救いを求めるのは間違ってるが
よくこのテーマを扱ったと感服
75才になったら死を選ぶ事が出来る法律が施行された。
フィクションとは言え、このテーマをよく扱った、そしてかなり攻めた切り口。その点だけでも感服。
さらに死を選ぶ、死を選ぶ人に寄り添う、それぞれの人の心の動きをよく具現化したと感じた。中には施策自体に反対する人も描かれている。これは感情的な表現だけなので物足りないと思う一方、深掘りするとテーマがボケるのでこのくらいで良かったかとも思う。
そして演じるのが倍賞千恵子だ。セリフが多い訳では無いが、表情と佇まいで語る。そしてそれをちゃんと撮り作品にした監督、撮影などのスタッフも良い腕をしている。カウンセラーを演じ倍賞千恵子に対した河合優実も倍賞に引っ張られるカタチだったのか良いパフォーマンスだったと思う。
惜しかったのは最終盤の一歩手前のシーン。想像力で描かれていない内容を埋めるべきなんだろうが、ちょっと難しかった。もう少し描かれてほしかった。
とは言え、全体的には満足。
満足。。。
満足と言っていいのか、テーマの受け取り方にもよるし、結末はこの物語の結末でしか無いし、考えさせられる事の多い作品であった。
多くの人がこの作品に接して、自分なりの結末を想像してくれたらと思う。
ps.公開初日の昼前開始の回は席の半分くらいが埋まっていた。ほとんどが高齢女性。どういう感想を持ったのだろうか?
【追記】
描かれた法律について云々書いているレビューがあるが、こんな法律はあり得ない。コストのかかる高齢者だって消費者なんだから自死を選んでもイイとはならない。フィクションだから描かれているだけなのだから、その世界観を否定したら物語としてあり得ない。
なので今後観る人は「そういう世界で自分の生きている世界とは違う。けど抱える問題は同じだね。」くらいの大らかさで観た方が良いと思います。
映画館が怖かった・・・
社会問題として扱う!というよりは人情劇寄りなのだが、「楢山節考」ほどの熱いドラマもなく、たんたんとただ追い詰められてゆくストーリーで、どのように観ればいいのか迷った。
一番心が動かされたのは、昼過ぎの上映に行ったところ、観客の8〜9割が高齢者であったことだ。上映前に行った男性トイレは、高齢者や障害者用の手すりつき小便器のまわりだけ水をまいたかのようにビシャビシャだった。上映開始1時間後ぐらいの中盤に、老夫婦がやってきた。高齢の妻が足のおぼつかない夫を急かしていた。ここにくるまでに何があったのだろうかと思った。
他のレビューで見たので直接見たわけではないが、監督がインタビューでフィリピン人を出した意図を問われ「フィリピン人を出したのは、フィリピンは見知らぬ人にも手を差し伸べる人間的な温かさのある社会で、不寛容になってゆく日本と対比させたかった」といった内容を答えたらしい。
ところで東南アジアは非常に若く勢いのある国で構成されており、フィリピンの高齢者率は6%ほどだという。対して日本はおよそ5倍にものぼる28〜9%である。これを対比させるならばもう少し別の視点を入れなければならないだろうと思った。
とにかく、観客としてきた高齢者たちが、この映画から一体何を感じたのだろうか。これが一番気がかりであった。ただ不安を増大させた人も多かったのではないか。。。う〜ん?
一応若者としては、PLAN75が成立することはありえない社会に生きている実感の方が強い(倫理的にではなく、政治的な力関係から)。つまり社会問題として扱うのであればこの不寛容は明らかに政治経済の問題であるが、そこは描かれず、倫理の問題とするならばフィリピンと対比させても意味がなく、楢山節考のような家族の葛藤もなく、つまり高齢老人の貧困と孤独を描いた映画なのだろう。重いテーマだ。自分が歳をとった時に所属できるコミュニティや仕事をなんとか手に入れておかなければ、老後は暗いなぁと思う。この考え自体が「不寛容」な考えなのだろうが。。
高齢化社会への警鐘
景気は落ち込み、年金はどんどん減額され、核家族化は更に進み、高齢者には厳しい世の中が待っている。目を背けずに実現可能な対策を、早急に立てればならないという警鐘を鳴らした作品。
テーマ的に仕方ないのかもしれないが、兎に角徹頭徹尾暗い映像が更に気持ちを沈ませる。いや、それは意図的だったのかもしれない。(フランス人好み?)
俳優陣の演技はそれぞれ良かったのだが、倍賞千恵子さんが仕事を解雇されたり新しい職が見つからなかったり、家を新に借りれなかったり、友人が亡くなったりしても、不思議なほど淡々と受け入れている姿に少し違和感が。彼女が高齢で独居の寂しい老女という悲愴感を感じさせないせいなのか…。
ところどころ人間味のある話が差し込まれ、ラストも一縷の希望が見えたけれども、暗澹とした心はそのまま浮上することはできなかった。
私はまだ高齢の域ではないが、この映画を観てますます将来に不安を覚えた。劇場にはご高齢の方が沢山おられたが、どんな気持ちで家路に着いたのだろうか、ふと心配になった。
が、しかし、この社会問題をクローズアップしたことには意義があったのだと思う。
鑑賞者が考える作品
こんな愚作でカンヌ行けるとは!
面白さ、感動、共感などまったくない映画。設定に興味があり、もしもこんな未来があったらシリーズ。しかしシナリオはずさん、ツッコミどころ満載。
主人公の葛藤など全くないし感情移入出来ない。何故か?主人公に魅力がないから。こんなに頑張っているのに報われない、それでも年をとるがテーマでは。安易に今頑張ってます、友達死にました感出しても伝わらない。この主人公を男性に置き換えたら一発でわかる。女性だからその辺りは描かなくても悲しく見えるだろとあまりにも安易。
市役所青年と叔父のやり取りもなぜあそこまで関わるのかを描いてないのでただの親戚だからって、納得しないだろう。オペレーターも同じで何人抱えてるんだよ。一人一人会ってるのか?そこがご都合主義。この仕事に関わって、精神がおかしくなるオペレーターの映画のほうが興味がある。
ヘルパーも何故出したのかわからない。日本フランスの合作に近い作品なので国際化を狙ったのか?いつの時代の話してるのか出稼ぎ労働者???であれば日本人のシングルマザー設定のほうがまだ話は広がる。
取ってつけたようなような朝日のラスト。
この映画のテーマであれば夕日なのではないかと思う。希望はなくなるがそれでも生きていく事を選んだ主人公。
だからこれからも強く生きられるのでは。
是枝監督のロビー活動の賜物で息のかかった後輩カンヌに読んだが、とんだ恥なのではと強く思う。
倍賞千恵子さんの声がいいですね
全305件中、281~300件目を表示