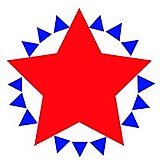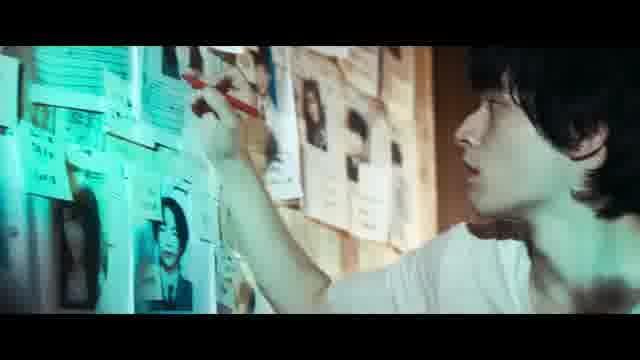死刑にいたる病のレビュー・感想・評価
全429件中、281~300件目を表示
正直、隣の隣でわっしゃわっしゃポップコーン食い荒らすDQNの男女が...
正直、隣の隣でわっしゃわっしゃポップコーン食い荒らすDQNの男女が邪魔で映画に集中できなかったけど、拷問シーンが始まった瞬間そいつらも一切動かなくなったのは愉快でした。というかカップルがめちゃくちゃ多かったけどカップルで観るような内容か?!
それは置いておいて、内容としては期待値が高かっただけに普通だな、と思いました。阿部サダヲさんの怪演が!というフレーズに引き寄せられたものの、いつもの阿部サダヲさんだなっていうように感じた。終わり方も…うーん。映画館に行くほどの内容ではなかったかなー。
消化不良だけど、満足
阿部サダオ始め、演技は良い気がするけど
サイコパスの演技としては阿部サダオハマり役って感じ。
なんていうか、「演じすぎてない感じ」とでもいうのかな?普通の所作や話し方に異常さが滲み出る絶妙さで「やっぱり演技上手いな」と。
ギャグ要素入ってる作品でしか見てなかったから少し驚きを感じるくらい。
他の演者さんもシーン毎の演技は上手いとは思うのよね。
なんだけど、結局「何をもって“死刑に至る病“なの?」ていう部分が伝わりきってない感じがする。
原作読んで無いから、その解釈部分とか見せ方が元々そうなのかの判断は出来ないけど、結局何をテーマにしたいの?てくらい半端な要素が多すぎて。
小説のト書部分を説明する様なシーンを敢えて入れずに演技で見せようとしたのかな?と勘繰るくらい伝わるものが少ないのよな。
物静かが空気…
純粋な残虐性の怖さ
先読みができてしまうストーリーなので驚きの展開はなかったです。意外性とか新しい見解を期待していた身からすると、ちょっと拍子抜けかな。そもそも動機が解明されて理解した気になるのもおかしいので、分からないままがいいのかもしれない。
虐待された子はみんなあんな風にどこか心が歪んでいるって勘違いされないか心配。原作の傾倒によるのか偏見が垣間見えた。
主人公が一つの事件の犯人探しを始めるのだけど、聞く対象がそれぞれ「殺人犯」としてでなく「榛村さん」として話してのが興味深い。
息子は母が父に「家政婦として扱われていた」といっていて、端からみると不幸なのかと思うけど、とうの母はもしかしたらそれを安心として捉えた考えをもっているのかもしれないし表面だけを捉えることがもはやできなくなった。それでいうと、虐待されていた子がみんな不幸になっているとは限らないです。
すべての子供が虐待から一番遠い生活を送っていることを願っています。
全体的に浅い、謎解きも不完全燃焼
白石監督が阿部サダヲx岡田健史という豪華食材を使ってサイコサスペンス映画が作られたのを期待を込めて観ましたが、脚本や登場人物の背景が浅く描かれており物足りなさを感じ、特に驚きの展開もなかった。
ただ、弁護士役(正しい人格者)の赤ペン瀧川さんや農夫役(気の毒な隣人)の吉澤健さんが出演していたシーンはテンションが上がり、更に傷め付けられる被害者がリアルで名演だった。ホラーより恐ろしいと思う人も多いでしょう。(私はホラーもスリラーも平気ですが)
恐らく元々の題材である原作が私好みではなかったのかな?殺人鬼の標的を選ぶ理由が不快で府に落ちず理不尽に思えた。
阿部さんは通常運転で岡田くんは新境地でもあるが、とにかく世界が狭い物語。
阿部サダヲを堪能
阿部サダヲの演技を堪能できました。
とてもすばらしかったので、彼とそれ以外の演者との力量差が大きいように感じられました。
阿部サダヲの出番を楽しみにしていなければ、最後まで観ていられなかったかもと思うところもあります。
わかりやすく描写されており、シナリオ展開に大きな驚きは感じませんでした。
犯人は誰かということよりも、何のために殺人鬼・榛村は雅也へ手紙を送ったのかにぞっとさせられます。
全体として大きな起伏はなくしずしずと進行し、それ自体は作品の不穏さが増してとてもよかったと思います。
原作小説ではどんなふうに表現されているのか気になったので、これから読んでみたいと思います。
可愛いヒロイン。
ロケ地が素晴らしい
阿部サダヲの狂気
最初から、グロさ満載のサイコ・サスペンス。櫛木里宇のタイトル同名の小説を、暴力や人の怖さを描いたらピカイチの、白石和彌監督がメガホンをとった話題作。
とにかく、サイコキラー役の阿部サダヲの演技に呑み込まれた2時間。彼は、人情モノの心を揺さぶる役から、笑いを誘うコミカルな演技、そして、今回のような、恐ろしい殺人鬼の役まで、幅広くこなし、主役でも脇役でも存在感を示す、オールマイティーな役者だ。
本作では、決して言葉を荒げたり、威嚇したりすることはなく、何処にでもいる真面目で、穏やかなパン屋の店主として微笑む姿が、その裏に潜む狂気に満ちたサイコキラーとしての怖さを倍増する。逮捕されてからの面会室での描写も、24人もの少年少女を殺してきた殺人犯とは思えないような冷静な態度で、淡々と自分を分析して語る姿は、一層の恐怖をあおる。
ストーリーは、連続殺人犯で逮捕され、拘留中の榛村大和から、三流大学生の筧井雅也の所に、「ぜひ、面会に来て欲しい」という手紙が届く。雅也は、中学生の頃から、パン屋の榛村の店も訪れて顔馴染みでもあった。面会に行くと榛村は、「23人は確かに自分が殺したが、最後の1人は自分がやったのではない」と伝え、雅也に別の犯人を突き止めて欲しいと依頼する。そして、雅也は単独で、その調査に乗り出し、新たな犯人像も見え隠れする中で、雅也自身にとったても、残酷で驚愕な事実へと繋りを見せ始める…。
本作での怖さは、榛村が、人の好い一面を見せ、次第に被害者との信頼を築いてから拉致し、爪をはぎ、骨を砕き、切り刻み、拷問によって奈落の底へと突き落とし、極限の中で惨殺されていく恐怖である。そして、巧みな話術や行動によって、榛村の術中にはまり、犠牲となっていく純真で真面目な少年少女の姿。
こうしたマインド・コントロールとも言える榛村の怖さが、面会室で筧井が榛村が対峙するシーンによく表れていた。犯罪者と犯罪者でない者を隔てる、面会室でのアクリル板。そのアクリル板に反射する榛村の姿を利用し、いかにも、筧井のすぐ横で悪魔の囁きをしたり、心身の中にまで忍び込むように、筧井と重なって榛村を映し出したりするシーンは、白石監督の巧みな映像アングルとも言える。
一件落着後もまた、狂気的な怖さを引きずるような、意味ありげなラストシーンで、エンドロールが流れた。
ただひたすらに怖い
四回くらい目を瞑った
阿部サダヲのあの目はヤバい!
17,8歳の真面目でお利口そうで爽やかな子がいいな。男・女は問わず。あ、爪はきれいでないとね。そして信頼関係を築き上げてから、相手を絶望に突き落とすことに快感を感じる榛村。「そうする事でしか人と関われないから」——!?何ですか、それ。病気と言うより、生まれながらの異常者に思えます。治癒不可能です。
阿部サダヲさんは初対面から変質者の感じが出過ぎじゃないですか。獲物を品定めするねっとりした目つきで、あんなに接近して来られたら、仲良くなる前に「あの人、キモイ」ってなりそうです。近所の人と話すときみたいに自然な感じなら良かったんですが。最初から気持ち悪っ、と感じてしまったし、豹変する場面を見せないので、ショックとか怖いとかより、ずっと不快感がありました。
爪に固執する理由のエピソードもあった方が良かったですね。
「お母さん、決められないから、雅也が選んで」と言う母親。強権的な父親にずっと支配されて来たので思考停止です。(そのお父さんが存在感が薄いので、途中まで親戚のおじさんだと思ってました)
岡田健史さんの演技は良かったと思います。面会のシーンはとても凝っていて、見ごたえがありました。
性癖というよりコレクター
生きてる事に感謝しながら観ました
阿部サダヲの狂気と岡田健史の鬱屈。綱渡りを最高に成功させたみたいな作品
観終わってからも数時間、ちょっとした興奮状態が続く。j
それほどの作品であった。
残虐なシーンも多く、心理的に追い詰められるような描写もあるのだが
そういう問題ではない。
それは、まるで観進めていくうちに、
細い木綿の糸と鋭いナイロンのテグスが絡まって、こんがらがって
どうにもこうにも全く解けなってしまうような。
それを解くために時間も忘れてぐちゃぐちゃに固まった糸の絡まりを
痛くなってくる指先でずーーーっとほぐしているような∙∙∙
少し絶望に似たような鬱屈とした世界がジワジワと広がっていく様は、さすが白石監督だと思わされた。
拘置所【榛村(阿部サダヲ)】とこちらの世界【雅也(岡田健史)】を
線引く面会の衝立のアクリルに重なり写る互いの顔の使い方、
無機質で澱んだ空気感に包まれた面会室という密室の狭い世界から
語られ、探られ、想像しては繰り広げられる
歪んだ人間たちが創り出す現実世界の広がりが恐ろしいこと極まりない。
前半で植え付けられる【榛村】の狂気と相反する普遍性に
「ひょっとして∙∙∙」という思いから
後半に回収されるさまざまな
「え?こいつが?!」
「え?まさか∙∙∙あの人も?!」
「あ!アイツなのか?!」
「え∙∙∙そういうことだったのか∙∙∙」
キリがないほど引き込まれ翻弄されるのです。
観終わった後、
なんだかグラグラの綱渡りを見事に大成功で渡り終わったような
意味不明な解放感みたいな気持ち良さが襲ってきた。
そして最後に思うのです。
なるほど。
タイトル通り『死刑にいたる病』だな。と。
素晴らしい作品でした。
何気ない日常に潜む人間の怖さ
全429件中、281~300件目を表示