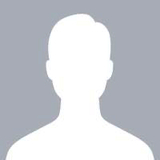さよなら、ベルリン またはファビアンの選択についてのレビュー・感想・評価
全18件を表示
タイトルなし
叙情的で不思議な映画。ラブーデの話は酷かった。そして、教授の振る舞い。ナチの影。生きる者と死ぬ者が逆。ベルリンはこういうまちだったのか。
そしてラストはドラマチックすぎる。でも人生とはこういうものかもと思う。
映画中の詩のような言葉が美しい。
「人の尊厳の時代が始まる。」
「理性では権力は得られない。」
美しい恋の物語。
優しい母親と息子。
ひどく心を揺さぶられた。
ケストナーの心象なのか、やはり当時のベルリンが本当にカオスだったのか、すごい描写だった。
ラブーデの公園での力強い演説。彼の出自。快楽に生きる父と彼の後悔。銃にのめり込むラブーデとラブーデが好きだけれどそれは受け入れられないファビアン。
こんな風に語りが寄り添う映画もNHKみたいか。
レストランから追い出される浮浪者をテーブルに呼び、タクシーから出る老婆を手伝ってチップをもらう。母との別れのハグの間にお互いにバッグにお金を入れるシーンは美しい。こういう主人公だからこそ、泳げないのに飛び込んで死ぬのだ。
友人を死に追いやった糞豚(本当に糞豚)を殴る。
その間にもナチは少しずつ忍び寄る。原作も映画も本当に素晴らしかった。
二人の浮き沈みは世相の反映か。
作中で時折はさみ込まれるモノクロの映像が、1930年代当時のベルリンの風情なのだと思いますが、先の大戦が終わってから、そう時間(年)の経っていない頃ですから、戦時中の興奮が冷めて、戦勝国から押しつけられた戦後処理の不合理さが、段々と実感されるようになった頃なのでしょうか。
社会全体に押し詰められたような頽廃感が漂う中で、作家・女優という人気によって左右される、ある意味では不安定な立場が、本作の時代背景の不安定さを象徴しているようにも思われました。評論子には。
「人生の浮き沈み」という言葉がありますが、女優として浮き上がることのできたコルネリアと、もがきつつも、文字どおりに沈んでしまったファビアン…その浮沈という厳然たる(当時のドイツ社会に漂っていた?)社会の落差を反映しているかのようで、なんとも胸に痛い一本でもありました。評論子には。
佳作であったと思います。
饒舌
ドイツのトム君が、アメリカの戦闘機のトム君より好きです❣️
178分、長い…。 でも、4年ぶりのトム・シリング。 もう、それだ...
178分、長い…。
でも、4年ぶりのトム・シリング。
もう、それだけで嬉しかったです。
『コーヒーを巡る冒険』が好きな人は、この作品だって好きになります。
1930年代のドイツを舞台に、目的を見つけられず惰性で生きているファビアンを主軸とした人間の悲喜劇。
世の中が変わっていく中でも必死に生き抜いていく様が鮮烈に描かれている。
映像は、ハンディーカメラでベルリンの地下鉄ホームを過ぎ行く風景から始まる。
地上に出ると、そこには、第一次大戦に出征し、心的外傷に苦しむファビアンの姿があった。
街には、緩やかなドイツ人の人々の営みに混じって、張り紙やら軍服兵隊の姿やら…、じわじわと不穏なナチスの影が忍び寄っていることが見て取れる。
劇中で「人間に必要なものは祖国だけだ」という風刺のセリフが印象的だった。
祖国の為に人は闘いを強要される。
敗れても帰る祖国がある者は、まだ幸せである。
毎日がどうなっていくのか…、人生は何処へ向かえばいいのか…、という不安。
気持ち次第で変えられる世界と、不条理にやってくる苦しい世界。
誰もが抱えている人生への恐怖。
それは、溺れるような息苦しさだ。
カナヅチのファビアンを比喩に、教授になれるほど賢いのに、人生を上手く泳ぐことが出来ない姿を描くことで、時代に翻弄されながらも生き続けていくことが難しいことがよく分かる。
それでもファビアンは、人間の内面的価値を大事にし、「生きるということは、1番、楽しい仕事だ」と言っていた。
その姿は、まだ何を成していなくとも気高く美しく見えた。
178分と少し長丁場ではありますが、自粛で、しばらく良い作品とは疎遠だったので、久しぶりに劇場で良いものを堪能したなぁ〜と幸せを噛み締めました。
感染対策をして是非、劇場で観て欲しい作品です。
178分!! 長いです…(泣)。 4年ぶりに見たトム・シリングは、...
178分!! 長いです…(泣)。
4年ぶりに見たトム・シリングは、良かったでした。
『コーヒーを巡る冒険』が好きな人は、この作品だって好きになります。
1930年代のドイツを舞台に、目的を見つけられず惰性で生きているファビアンを主軸とした人間の悲喜劇。
世の中が変わっていく中でも必死に生き抜いていく様が鮮烈に描かれている。
映像は、ハンディーカメラでベルリンの地下鉄ホームを過ぎ行く風景から始まる。
地上に出ると、そこには、第一次大戦に出征し、心的外傷に苦しむファビアンの姿があった。
街には、緩やかなドイツ人の人々の営みに混じって、張り紙やら軍服兵隊の姿やら…、じわじわと不穏なナチスの影が忍び寄っていることが見て取れる。
劇中で「人間に必要なものは祖国だけだ」という風刺のセリフが印象的だった。
祖国の為に人は闘いを強要される。
敗れても帰る祖国がある者は、まだ幸せである。
毎日がどうなっていくのか…、人生は何処へ向かえばいいのか…、という不安。
気持ち次第で変えられる世界と、不条理にやってくる苦しい世界。
誰もが抱えている人生への恐怖。
それは、溺れるような息苦しさだ。
カナヅチのファビアンを比喩に、教授になれるほど賢いのに、人生を上手く泳ぐことが出来ない姿を描くことで、時代に翻弄されながらも生き続けていくことが難しいことがよく分かる。
それでもファビアンは、人間の内面的価値を大事にし、「生きるということは、1番、楽しい仕事だ」と言っていた。
その姿は、まだ何を成していなくとも気高く美しく見えました。
178分と少し長丁場ではありますが、自粛で、しばらく良い作品とは疎遠だったので、久しぶりに劇場で良いものを堪能したなぁ〜と幸せを噛み締めました。
感染対策をして是非、劇場で観て欲しい作品です。
倫理的な人、ヤコブ・ファビアン
退廃的な社会に生きるヤコブ・ファビアン、32歳(Tom Schillingー実際32歳には見えないねえ、やっぱり40歳だね。トムにはこういう役は適任) ファビアンは遅刻が多くプロ意識に欠けている。1931年と最初に出るから、ナチズムの台頭時代だとわかるからありがたい。世界大恐慌の時代に、ファビアンは社会の動きを気にしているようにも思えないが、、、、、、でも、この世の中は『品位のキャパシティー』 があるかと、大家に犯罪の多い新聞記事をを読んだ後、いっている。
でも、この映画を最初の30分しかみていないが、ファビアンは危機感を感じていないように見える。 そこが現在社会でも言えることで、何も問題意識を持たないで、生きていると、危険な政治状態になっているのを見逃してしまう。戦争に一歩足を入れて気付くようになる。危険信号だと我々に伝えているようだ。
ここからこの長い映画を全部鑑賞してからこの後を書いている。
この映画はアーカイブやポスターで政治の動きを見せている。これらのポスターが、ファビアン、コルネリア(サスキア・ローゼンダール)、ラブーデ(アルブレヒト・シュッヘ)の生き方を反映していて共通性が窺える。ただ、ドイツ語がわからないので、正確には言えないが、 明らかにわかるのは、『エルンスト・テールマンに投票せよ』 と言う壁に書かれた文字である。テールマンはラブーデの思想であるようだ。テールマン率いる共産党は、選挙で負けてヒットラーが天下をとるわけだが、彼は1944年にブーヘンヴァルト強制収容所で殺害されたとネットで読んだ。
ベルリンは世界恐慌で、生活がくるしい人が大勢出ている。例えば、ファビアンが女優を夢見るガールフレンド、コルネリアと一緒にいる時、彼がレストランに招待した浮浪者ふうの人は『生活保護は10マルク、経験していないのは自殺だけ』だという。ファビアンもタバコの会社の広告コピーライターの仕事を首になり、物書きになりたく書いている。大恐慌の時代の金のないファビアンのとるこの行動こそ彼の人柄を示している。
そして、ファビアンと彼の唯一の親友であるステファン・ラブーデ(Albrecht Schuch)はGotthold Ephraim Lessingというドイツの哲学者の卒論を書いている。彼は左翼で、政治改革を考えている。弁護士の息子で、裕福であり、豪邸に住んでいる。資本主義の賜物のような家庭に育ち、彼自体、社会変革を求めているところがファビアンの道徳的な行いと共通するようだ。だから、この二人の親友は批判しながらも合っていると思った。
二人の会話で面白いところがある。大好きなシーンだ。
ラブーデはファビアンは何もしていないと。そして、誰も助けないし、誰も助からないというようなことを言う。ラブーデはヒットラーが台頭し始める中で社会を変えようとしている。
しかし、ファビアンの答えは『観察しているだけじゃダメなのか?』 情勢や人々を観察しているだけで、何もしないのはダメなのかと言う意味で、特に、ナチスの動きを気にしていない(ように見える)ファビアンだが、ラブーデは自分の頭の蠅を追っているだけではダメだといってる。
このシーンは強烈であり、社会参加に興味がないファビアンの結末はこの時代どうなるのかと案じた。
パーペン
ヒットラー
テールマン
バルト海に今晩大嵐が来るよ。
しかし、警察の取り締まりと大学の腐敗に直面したラブーデは見事に快楽主義へと落ちていってしまう。これが、まるでドイツがヒットラー、ファッシズムから道徳的に衰退していくのと同じだと思う。
ファビアンだけがラブーデを裏切らず助けていた。ラブーデの父親は教授に話して、卒論を書き直せばよかったのにと。そして、『息子がなぜ自殺したかわかれば泣くなと』。ファビアンはそこでは泣かなかった。
ファビアンだけが、最初からこの映画の最後である、ドレスデンの自宅の近くで子供を助けに川に飛び込むシーンまで、ナチスドイツに移りゆく時代に、倫理的な人間に描かれている。だから、結末に衝撃を受けるが納得がいく。
1930年代のベルリン
はい、泳げません
ケストナーは大好きな作家で、中でも「ファービアン」(※)は、児童文学の「飛ぶ教室」「五月三十五日」と並んでベスト3に入るお気に入り。二つの大戦の間のワイマール憲法下の逼迫と頽廃のドイツで、作者の分身とも言える青年の彷徨を描く。そんな諧謔と混沌に満ちた原作の映像化として、過不足ない出来(ややラブストーリーの要素が強くなっているが)。
主演のトム・シリングは「コーヒーをめぐる冒険」以来だが、良い味を出している。ダニエル・ブリュールの雰囲気にも近い気がする。
邦題は、同じ時代を描いたボブ・フォッシーの「キャバレー」の原作と期せずして同じだが、この映画のタイトルとしては的はずれで、近頃の配給会社のセンスはどうにも解せない。
途中、市民が水たまりを次々に飛び越えるシーンは、アンリ・カルティエ=ブレッソンのあの写真へのオマージュだろうか。
ラスト近く、少年が見るファービアンの手帳のメモがせつない。そして焚書の映像は、ケストナー自身の本がナチス突撃隊に燃やされた事実を想い起こさせる。
※私が持っている小松太郎訳版はこの表記。
ナチスが台頭する前のベルリンを舞台に描かれる、ドミニク・グラフ監督の日本初公開作品。
ドミニク・グラフ監督作品の日本での公開は、この映画が初めてとなるらしい。
178分の尺があるため、紆余曲折はあるが、作家志望の青年ファビアンと、女優を夢見るコルネリアの恋の行方が物語の中心となる。
しかし、あのラストシーンは何だったのだろうか?
カナヅチ?最後に仕立てられたアクシデントによって、この映画のストーリーは、完全に意味不明となる。
途中の話は享楽的な生活の話で、ファビアンの心理的な背景を描いているに過ぎない。
さすがに長いため、二度寝落ちてしまった。
きついシャレなのか?よほど、ハッピーエンドが嫌いなのか?
コルネリアは毎日午後3時にカフェに来て待ちぼうけでした…ということか。
この映画が原作どおりなのかは知らない。
ただ、ラストシーンにそれを持ってくるなら、尺は90分で十分だろう。
長い時間をかけて、しょうもない終わり方は、ちょっと時間の無駄だ。
ファビアンにとって幸せな結末だったのかもしれない
主人公ファビアンは極端なチェーンスモーカーで、のべつ幕なしにタバコを吸っている。タバコを吸っている時間は、我に返って醒めている時間だ。つまり一服するのは、現実から一歩引いて自分と対話することである。
喫煙を勧めているのではない。むしろタバコを吸うのは一種の現実逃避だと思っている。ただ、喫煙には一瞬の恍惚がある。本作品の舞台となっている1931年のミュンヘンは、連続してタバコを吸わなければならないほど、厳しい時代だったということなのかもしれない。
ファビアンを演じたトム・シリングはナチ政権下のドイツを描いた「ある画家の数奇な運命」で主演しており、その主人公クルトもまた、ファビアンと同様に自由な精神の持ち主であった。第二次大戦前後を描く映画の主人公には、自由な精神性が求められるのだろう。トム・シリングはその容貌からして、時代のパラダイムに染まらない反骨が感じられる。いい俳優だ。
1931年は世界恐慌の2年後である。景気は少しもよくならず、街は失業者で溢れかえっている。タバコを買う金にも困り、1本だけ買う。他人が吸っているタバコを通りすがりざまに奪う。そういう時代なのだ。そこへナチスの登場である。強いリーダーシップと自信に満ちた主張に、人々はなんとなく心酔してしまう。
ファビアンは時代に対して嫌な感じを持つ。それは石川啄木の「強権に確執を醸す志」に通じるものがある。強権に媚びる人間が急増するベルリンに嫌気が差したのだ。それは退職金で恋人のドレスを買う刹那主義的な生き方となる。その恋人は女優になるが、ファビアンには彼女がどんな作品に出演することになるのか、目に見えている。ナチのプロパガンダ映画だ。
ファビアンにとってこの時代には絶望しかないが、それでも恋は大事だ。親友は遠距離恋愛に失敗した。自分はどうだろう。彼女は待っていてくれるだろうか。
ラストシーンはファビアンにとって幸せな結末だったのかもしれない。童話作家の原作なら、こういった唐突な終わらせ方もありだと思う。
長い。退屈だった。
昨夜、3、4時間しか眠れなかった。そのためか映画が始まって暫くしてから、5分寝てしまった。
原作者のケストナーは名前だけ知っていて、その小説を読んでいない。ナチス政権下、禁書と認定され、目の前で梵書された体験を持つ。
チラシにはケストナーが書いた唯一の大人向けの小説で、最高傑作と謳っていた。それで鑑賞する気になったが、長すぎで退屈してしまった。主演の男優と女優の演技は良かった。いかんせん、監督が私にはつまらなかった。偉大な小説は読書にかけた時間と同じ位の上映時間が必要との考えらしい。
そうすると「カラマーゾフの兄弟」の上映時間は、半日要することになりそうだ。ミステリーの要素があるからなんとか我慢できるかもしれない。
原作を一度読んでから最終判断をしてみたい。3時間超えの作品なので、覚悟が必要だ。
シュパルテホルツで。
1931年のベルリンでタバコの広告のコピーライターをする青年ファビアンの仕事と恋と友人との話。
ドイツ共産党の影が見え隠れする不況のベルリンで、女優志望のコルネリアと出会い一目惚れし、巻き起こっていくストーリー。
仕事を失い収入が無くなりながらも変わらない二人の関係が、彼女の秘密が明らかになりすれ違っていく様や、底辺に堕ちていく金持ちの友人ラブーデの様を、主人公を取り巻くちょっと乱れた世界だったりを交えつつみせていくけれど、若者と言っても32歳ですか…どうなんでしょう。
ドロドロとした世界観とか、彼の境遇とか、ドラマとしては面白いけれど、7割方恋愛物語で、しかも超まったりテンポで、流石に178分は長過ぎて飽きてくる。
そしてこの長尺のシメが悪ふざけの様なそれですか…このオチ自体は嫌いな方ではないけれど、このダル~い感じのラストはにしてはちょっとスカシが大き過ぎた。
焚書の世界が来る前に水の中へ
いかにも30年代冒頭のベルリンだなと知らないくせに懐かしい感じがするが、決して過去でなく世界中の「今」と、そんな「今」に生きる若い人たちを映画は描いている。ベルリンの歩道の上にいきなり、その時にはまだない、ホロコーストの犠牲となったユダヤ人の名前を記した躓きのプレートが映ったりもする。二人の語り手(女と男)の声が響きあい、これから何が起きるか私達に教えてくれたりファビアンやケストナーの言葉を投げかけてくれる。出会ってすぐ、まだ恋に落ちていない寸前のコルネリアとの場面で耳にする「ハーモニカ」の歌。若々しく可愛らしい歌い方で、マレーネ・ディートリッヒとは異なる明るさがあった。
音楽、挟み込まれるモノクロの記録映像、無声映画の台詞画面、アップ、上から斜めから下からの、それから鏡から見せる映像は美しくも躍動感と不安感でいっぱい。ファビアンが大学構内で飛びかかって階段から奴を突き落としたのは当然だ。汚い醜い言葉で手紙を書いただけでなく、読み手の尊厳を奪い殺した。そして学問上は知的であってもそれ以外では無能で何が今自分に求められているのか判断できない教授にも絶望した。職業も恋愛も失った若者は絶望する、でもそんな彼らに「生きることそのものが素晴らしい仕事なんだよ」と語りかけるのが大人の役割だと思う。
泳ぎを習おう。確かに泳げた方がいい。でも泳ぐというのは水の流れに抵抗しないで身を任せることでもある。だからファビアンは泳げなくて良かったのかも知れない。ケストナーは生きてくれた。
トム・シリング、適役だった。親友の最後の手紙をレッシングの本に挟んだファビアン、水に入ってから泳げないことに気づくファビアン、普通の生活をする両親の元で育ったファビアン、母親や困った人を思いやるファビアン、美しく力強い文章を綴るファビアン。恋するファビアン。どのファビアンも誰もが自分の中に思いあたる。
本を読み切るのにかかる時間と同じだけの長さ
「偉大な文学作品をもとにした映画は、理想的には本を読む読み切るのにかかる時間と同じだけの長さで上映されるべきだ」とドミニク・グラフ監督が語るように
この物語は約3時間という少し長めの映画。
1931年のベルリン、ファビアンが悩み戸惑い心が揺れ動く様子を丁寧に描いている。
母親や親友や恋人との関係や思い、街中の人々の様子、お気に入りの小説を読んでいる時のように、いつの間にかファビアンの気持ちで見ていた。
なのでラストシーンは彼らしい行動だと思った。
ケストナーの原作『ファビアン あるモラリストの物語』を読み、もう一度観たいと思う。
それから、児童文学の『飛ぶ教室』も読みたい…(意味深)
グラフ監督の作品はこれが初だけど、とても好みだったので過去作品も見てみたい。なので特集上映が組まれるくらいヒットして欲しい!
トム・シリングさんのトークイベントもとても良かったです。
試写会ありがとうございました。
全18件を表示