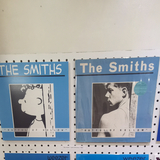サウンド・オブ・メタル 聞こえるということのレビュー・感想・評価
全114件中、21~40件目を表示
静から動への変換! ドラムの音がSeoulと共鳴し合う作品
ドラマーであるルーベンが聴覚を失い、路頭に迷うなか、ハンデを抱えながら自分の聴かせたい音楽をどうやって、人に伝えていくか
と言うストーリーでした。
日々の暮らしのなか、路頭に迷うルーベンが
恋人のルーの勧めもあり、聴覚障がい者の
コミュニティーに参加する場面は、
手話を通して自分と人とのコミュニケーション
を、少しずつしていき、自分の音楽と共鳴し合う!
自分の音楽を表現することが出来る!
ほとんど音が聞こえないなか、静寂から
音を振動で感じる、ルーベンが新しく一歩
踏み出す姿を見守っていきたい気持ちで
見ていました。
教会の鐘、街のざわめき、無音のなか
父親と再会できた喜びは人生の再出発を
嬉しく思うシーンでした。
補足、耳のインプラントの手術を初めて知りました。
映画館にて観ましたが、レビューが遅くなり
すみませんでした。
何が正解なのかを考えさせられる作品
障害を受け止めるということ
失ってようやくその恩恵に気付く 職業的な突発性難聴のお話だと思っていたのですが、もう治らないんですね そう人間(?だけじゃないだろうけど)の聴覚はスグレモノなのだ 大音量の中で人と会話しててもちゃんと会話だけ聴き取れるし(カクテルパーティー効果)、何も聞いていないようでも、気になる言葉が耳に入れば注意を向ける、無意識の内に選択的に聞けるにようなっているのだ ルーベンが人工内耳の手術を受けてからのくだりは、祖母の補聴器の話を思い出しました すぐに落ちたり、音が全部が全部大きくなってどうにも不愉快だったらしいです 聾のコミュニティの教えを受入出来なかったのが残念でしたが、最後は哀しいけど、悟ったようですね
しかし難聴になる人とならない人の差が? アルコールとドラッグ関係あり?
じわじわ食らってくるラスト
聴こえなくなったら!
ある日聴こえなくなる!
うそだろ!
ミュージシャンだけに
治す方法は?
主人公は俺に必要なのは、ガンだ!
支援センターにいき
徐々に安らぎは取り戻すが
やはり
手術する。
その代償は?
静寂の中に安らぎは見つかるのか?
障害を描き切れていない惜しい作品
アカデミー賞音響賞を受賞しただけあって、音の表現は圧巻です。主人公そのものを生きることができる作品はそう多くはありませんが、この映画はそれに成功した作品の一つでしょう。
ただし、この映画が社会に何らかの問題意識を共有したい作品である(監督自身もそれを目指している)ことを考慮すれば、主人公ルーベンやその他の聴覚障害者の苦しみが描ききれていなかったように感じます。もちろん、個人的な苦しみ(ドラマーとして聾者になること、療養中に彼女が前へと進み始めていたこと、手術を受けても生活は元通りには戻らないことなど)は繊細で洗練されたものとして多くの人の記憶に残ったでしょう。ですが、社会的な苦しみはあまり描かれることはありませんでした。それはこの社会がいかに聴覚障害者にとって生きづらい世界かという、社会のデザイン側を問う視点です。
障害学には、障害の「医学モデル」と「社会モデル」という概念が存在します。医学モデルは、障害は本人にあり、医療によってそれを治療しようとする考え方です。一方で、社会モデルは障害を社会の側に帰属させる、すなわち、様々な身体的制約のある人々の生活を拒むような障害が社会の側にあるとすると考え方です(「バリアフリー」という言葉の「バリア」はこの意味で使われています)。障害学は、医学モデルを批判し、社会モデルをその立場としています。
この映画では、「障害は治すものではない」という医学モデルの否定まではありました。ところが、「結局は当人の考え方次第」というところへ帰着してしまい、社会の側を問う描写はほとんどありませんでした。もちろん障害者に対するセラピーはとても重要ですが、そればかりにフォーカスすると障害というものを個人に背負わせてしまいます。障害者理解を広げるためならば、社会モデルもきっちりと扱うべきだったと感じます。
とはいえ以上のことが、音響のダイナミクスや役者の素晴らしい演技を否定してしまうわけではありません。鑑賞後は劇場で、騒がしいほどの静寂を楽しみました。
アカデミー賞受賞作品と聞いて…
生きるって何だろう
自分も含めて、人には色々な人生がある。
生きるということが、物心がついた頃からだんだんと当たり前になってきて、自立して仕事に追われるようになってからは"生きている"というより毎日がまるで何かルーティンで動いているような感覚におちいる。
ただし、そのルーティン化された毎日の作業工程のような人生はその動力源である身体が正常に作動していることが前提条件である。
昨日まで正常だった機械が突然故障したら?
部品交換や整備で直らなかったら?
ルーティンは何一つ欠けても成立しない。
だけど人生は続くのだ。
だとしたら、生じた不備は不備と思わず、むしろこの状態がデフォルトだと考えて、新たなルーティンを構築していく。
健康で何一つ不自由なく毎日を過ごせたら、もちろんそれに越したことはない。
しかしながら、人生何かに"つまずくこと"も少なくない。
そんな時こそ、何かを変えるという考え方を受け入れなければ先には進めないのではないだろうか。
まさにそれこそが生きると実感する瞬間なのだ。
と、肯定的に捉えるべきである。
サウンドが素晴らしい。
メタルバンドのドラムの人主人公の映画だと思っていましたが、全然違いました。
主人公がやっている音楽はハードコアです、これは苦手な人も多いと思いますが、
聴力を失う人の話です。音が聴こえなくなっていく過程が凄くリアルで引き込まれます。
音の工夫が凄く、通常の音と、難聴の人に聴こえているであろう音の表現が素晴らしい。
人間の耳は物凄い能力を持っていることに感謝してしまいました。
このタイトルは、ヘビーメタルではなく、人工内耳を付けた時の音を表現しているらしいです。主人公が、手術で人工内耳を取り付けるのですが、耳が機能している訳ではなく、脳に取り付けたインプラントが脳を錯覚させて音を認識させる方法なので、嫌な音もいっぱい聞こえる、その音がサウンドオブメタル、ということらしい。難聴者の施設の管理者の方が素晴らしかった。ラストシーンの主人公の決断も印象的。このシーンで映画をもうワンランク引き上げました。
知らない世界に触れていろいろ考えさせられました
聴覚障害者(突発性難聴の初期やインプラントをつけた後など)が感じる音とはこういうものだったのか、という驚きと衝撃。もちろん個人差があって人によって全く違うのでしょうけど。でもそのくぐもった音やキーンとするハウリングの音と普段私達に聞こえている音を何度も切り替えて対比させる音響演出の素晴らしさ。
ある日突然難聴になれば誰だって大きく動揺するし自暴自棄にもなるかもしれない。それがドラマー(ミュージシャン)ならば…。
リズ・アーメッドもオリヴィア・クックもこれまでとはまるで別人の演技でとても良かったです。
ラストシーンはとても清々しく印象的。だけど住むところも楽器等も彼女も失った彼はこれからどうやって生きていくんだろう、と野暮なことを心配してしまいました。
これからの生き方
ヘビメタ?が原因なのかわからない(結局原因もわからなかった)が、聴力を失っていく若者の苦悩。
アメリカはこういう感じなのか、あそこが特殊なのかは判断がつかないが、支援グループがあるのは心強いだろうね。
ああいうコミュニティがアメリカ全土にあるのかな?
日本ではちょっと考えられないかも。
ルーベンが手話を覚え馴染んでいくのがよかった。
とはいえ、やはり元に戻りたい気持ちが強く、全財産をつぎ込んで手術を受け、案の定うまくいかったなんて。
元の鞘には納まらなくても、この先なんとか生きていけそうな光が見えたのがよかった。
金属の音
“Deaf”という単語を知ったのは、<87分署>でだった。
飛び道具的な演出ではあるが、この内容ならコレが必然なので。POVが段々手詰まり感を覚えてきていただけに、こういう主観的な音響表現に力を入れた作品がもっと出てきてほしい。くぐもってたり歪んでたり無音になったりするの、だいすき!
呼吸音すらはばかられるような静寂は、昨今中々体感できない。同じ回を鑑賞していたお客さんがみな、わかってらっしゃる方々ばかりだったので、音響効果を余すところなく体験できた。
クリーン(clean)というのだね、ふむふむ。あのコミュニティ/学校の人はポール・レイシー以外は…?
補聴器でも、調整したり慣れるのが結構大変と聞くが、ラストシーンでちょっとだけ、「ああっ、それもいいかも。ちょっと羨ましいかも」とつい思ってしまった。
聴覚を失うことの意味を知った
全114件中、21~40件目を表示