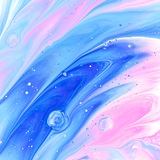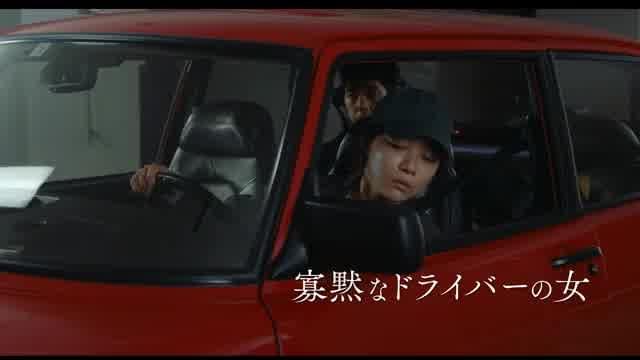ドライブ・マイ・カーのレビュー・感想・評価
全797件中、21~40件目を表示
素晴らしい!
本を読んだことはないのですが、村上春樹というので少し気が引けていたのですが、予想を超えてくるヒューマン映画。
チェーホフの物語に自分がさらけ出されてしまうということで怖がっていた主人公がみさきや高槻と過ごす時間で向き合うことができて、それがとても穏やかに描かれている。
きっと家福さんは一人で妻の死や不倫の悲しさに向き合えずにいた中で、みさきと同じ感情や罪悪感を少しずつ共有していったんだと思う。
その上でチェーホフの演劇のテキスト、ユナの静かで優しい手話にも救われていく。
そして正しく傷つく。それがとてもはっとさせられました。
私もだが、傷つくのは怖いし避けたい。関係が終わってしまう恐怖、心の痛み、誰しもきっとそんなの感じたくない。
でも正しく傷つくことができたら、乗り越えられるのかもしれない。傷つく勇気があったら自分の生きていく術になる。
見て見ぬふりは誰にでもできる。他人の心はわからないけど、自分の心は覗き込むことができる。
素敵な映画。安心して見ることのできる映画。
素晴らしい!!
注目の映画監督
このようなタイプの映画は初めて。
何か上質な文学作品を読んでいるような気持ちになる完成度の高い映画。
多言語での読み合わせ、亡き妻がカセットテープに吹き込んだ朗読を聴きながらのドライブ、美しいゴミ処理場、印象的な場面がたくさんある。
全体的に夢の中の出来事のような、不思議な心地よさを感じ、退屈することなく最後まで見ることができた。淡々とした語り口で物語がゆっくりと進む。
演出家兼俳優の家福とその運転手の寡黙な女性みさき。二人とも過去に大事な人を亡くし、家福は、自分のせいで妻を死なせてしまった、みさきもまた自分のせいで母を死なせてしまったと心に傷を負っている。
ドライブでの会話でお互いが誰にも言えなかった心の闇を告白することによりその闇が少しずつ晴れていく。
この難解で重厚な話の感想を言語化する能力が残念ながら私にはないが、世界基準の日本映画を見れたことに満足度は星5つ。
ド派手じゃ無いドライブ映画NO1
マッドマックスとかワイルドスピードの見過ぎで、車に乗る=カーアクションって勘違いする僕はよくないね
でもドライバーのみさきはマックスやドムと同じくらいの運転がうまそう
ただ作中ずっと車を走らせてたのでガソリン代が心配
セリフや会話のテンポに癖があって、登場人物がみんな一言一言噛み締めるように話すから妙に回りくどいなと思ってたら原作が村上春樹なのね
ははーん はいはいはい なるほどね
面白かった設定は音がオーガズムを感じながら脚本のアイデアを口ずさむところ
僕もピロートークで新ネタ考えようかな「どうもーお願いします!」からはじまるやつ
悲しみや葛藤によりそうようようのではなく、次のステップに登った場面転換的な効果で流す音楽がオシャレだった
「3時間が短く感じた」って感想ありつつも僕はしっかり3時間に感じた⏳
演劇が表象するものは?
独特の演出、日替わりのタイミング、セリフの多さ、役者の表情が示す感情を読みとるのは難しかった。これは、村上春樹さんの作品だからか、演出家由来のものなのかわからない。また、伏線も多いように感じた。村上春樹さんは、「エロ・生死・罪」というテーマを感じられる作品が多いのか。半分ぐらい空想のような、そうでないような、多カ国語の入り組んだ演劇が人の複雑性を示しているようにも見えた。小説でも読みたいと思った。
女性の魅力を引き出す事に成功している点は高評価
☆☆☆★★(1回目) ☆☆☆★★★(2回目) ※ 2022年3月8...
☆☆☆★★(1回目)
☆☆☆★★★(2回目)
※ 2022年3月8日 レビューを改訂しました。
それによって。折角以前にいいね!を頂いた方々の思いとは違う方向へと、レビューが変わってしまった感は否めません、、、
どうかご了承頂けるなら幸いです。
映画の主人公にあたる男は俳優兼舞台演出家。
彼は、その言葉の使い方であり。周りに対する物腰の柔らかさから察するに、一見して(人に対し)優しく性格の穏やかな人間の様に思える。
だが実際にこの男の本質が、映画が進んて行くに従って段々と露わになって行く。
曰く…自分自身への自信の強さゆえに。自分に関わってくる人間に対し、精神的に追い詰めて行く人間だとゆう事実が、徐々に炙り出されて行くのだ。
人の意見を聴いている風に見せかけて、現実には自分の思いを相手に対して刷り込ませようとする。
それが如実に現れる場面が、舞台リハーサルの際の本読みの時。
《感情を出させない》
それを相手に求める彼の狙いはズバリ【支配】だ!
若い男は自信満々の塊。
若い頃からチヤホヤされたがゆえに、その頃の記憶がどうやら抜けきれない。
自信があるからこそ、(芸能界でのしきたりや)社会に対しての反抗の姿勢を崩さない。
「自分は他の人間とは違う!」
その想いこそが彼のアイデンティティを突き動かしている。
そんな彼だったのだが。(主従関係にも見える関係性に於いて)主人公の男から厳しい【支配】を受けたことから、抑えに抑えていた想いが次第に爆発して行く。
この2人の関係性には一体何があったのか?
主人公の男には愛する妻が居た。
彼女はその昔、才能のある女優だったのだが。彼と結婚した事によって家庭内に収まり、女優の道を諦めた過去があった。
結婚生活が進むにつれて、彼女の中での彼に対する愛情が少しずつ薄れて行き、同時に悩みが増して行く。
「こんな筈では無かったのではないか?」…と。
湧き上がる想いが溢れ、彼女は脚本家としての活動を始める。
だが、そんな彼女の真の想いは彼の元には届かない。
周りに対して発する彼の【支配欲】は、彼女の小さな《策略》の前では気付く事が出来なかったのだから。
夫婦間でのセックスの時にだけ浮かぶアイデアの宝庫。
それは、決して彼に対する愛情の証しでは無かった。
それこそが、自分を閉じ込め【支配】していた彼への裏切り。
この彼女の《策略》に、彼女を【支配】していると思っていた彼は、まんまと騙されていたのだった。
【支配欲】が強かったからこそ、彼女の裏切りに気付いた彼に芽生えた想い。それは〝 憎しみ 〟と同時に〝 悔恨 、でもあった。
彼には、自分を裏切っていた妻と関係性が深かったと思える男に関する予想がある程度は出来ていた。
そして今、その男が自分の目の前に居る。
動揺をしない様に努めながら、妻の裏切りに対する【復讐】の意味を込め。この男を〝 精神的に支配 〟する事を選ぶ。
一方で、若い男にはどうしても確かめたい事実があった。
元々、自信満々な性格ゆえ。自分が心底崇拝し愛した人が、共に愛した人とはどんな男なのか?…を。
彼は薄々感じていたのだった。自分は彼女にとっては単なる《遊び相手》だったのかも知れない…とゆう屈辱。
だからこそ、どうしても面と向かっての彼の本質を〝 見抜きたい 〟との想いに突き動かされる。敢えて正面から対峙したくなったのだった。
若い彼にとって主人公の男は、はっきり言って【敵】以外の何者でもない。
現在の【主従関係】から、どうしても《争い》を仕掛ける事は叶わない。
だからこそ、この若い男は絶えず《挑発》を繰り返す。
その想いがやがて爆発を起こすのが、終盤前での車内での長い独白の場面に繋がる。
今、この若い男はハッキリと主人公に向かって【戦線布告】を表明する。
動揺を受けながらも受け流す主人公の男。
若い男に潜む闇の深さに戸惑いは隠せない。
今この瞬間、この若い男を【支配】しようとした自分の計画は失敗に及んだ事実を知るに至る。
そんな彼の元には、ふとしたきっかけで専属の運転手となった寡黙な若い女性。
彼女は自分の過去を一切語ろうとはしない。
頑なに口を閉ざす理由が彼女にはあるのだが、主人公の男にはそれが謎となって彼の脳内で少しずつ大きくなって行く。
その佇まいであり、胸の奥に何かを秘めているであろう雰囲気。現在の《主従関係》から、その謎を解こうと絶えず小さな波紋を投げかけるのだが、それでも彼女の心は凍結し続ける。
現在、主人公が抱えている仕事は、そんな彼を絶えず挑発して来る若い男を含めた多国籍な人種の舞台。
送り迎えをしてくれるのは謎を秘めた若い女性ドライバー。
この多言語を介した不思議な舞台空間。
元も子もない事を呟いてしまうのは愚の骨頂なのでしょうが。どう考えも舞台作品として果たして成立するのかどうか。
そこを、ありそうな空気感を漂わせる脚本であり演出力。
なによりも 「如何にも!」と思わせる美術設計と照明、それに撮影技術。
リハーサルの本読み部分から醸し出されるピリピリとした緊張感を始めとした、役の人達との妙に少しだけズレている…役者VS演出家との確執等。観ていても座りの悪い椅子に座らされている感覚は、監督の演出の冴えも加わって、絶妙なバランスの上に成り立っていたと思います。
そんな舞台作品での中で、一際目立つ異彩を放って居たのが韓国人夫婦の存在。
当初2人は、俳優と舞台スタッフとゆう位置付けであったのですが。若い男の度々に渡る【挑発】等もあり、(主人公の精神バランスも含んで)何度も空中分解しそうになるところを舞台作品全体に於ける《調定役》となってたのではないか?と思わせました。
〝 夫婦であっても元々は他人 〟
そんなこの夫婦の、人への接し方には全くの【棘】がない。
全てを包み込む《包容力》に溢れている。
それだけに主人公の男には、自分と亡くなった妻との関係性に想いを馳せる。
更には謎多き女性ドライバーの彼女。
この夫婦の自宅に2人が招かれる場面こそがこの作品での重要なキーワードになっていた。
この韓国人夫婦は、生活拠点を日本に移した理由を訥々と主人公の男に語り始めるのですが。その根底にあるものは、〝 お互いがお互いを尊重し、他人に寄り添う心を持つ 〟…とゆう心の奥深さにあったのを主人公の男は感じる。
そして彼以上に、この韓国人夫婦に影響を受けた人…それが寡黙なドライバーの彼女だった。
それまで頑なに心を閉じていた彼女は。この韓国人夫婦から受ける無償の愛情により、彼女の心はじっくりと解凍し始める。
そんな雰囲気を感じ取ったのか。主人公の男は、彼女に対してそれまでの《主従関係》な接し方を変え、他人を思い遣るかの様な違う接し方を試みる。
彼は彼女に賭けたのかも知れない。
彼女の心に巻き付かれ、その想いを閉ざしていた茨の鎖が解放される瞬間を見届けようと。
彼女が心を閉ざすキッカケとなった土地と、彼女そのものを【支配】していた人物に対しての彼女自身からの《告白》
その姿こそが、愛していた妻に裏切られていた自分の想いを代弁している…かの様に。
その後に起こる若い男の事件をキッカケとし、彼女のルーツ探しの旅に移行するのですが。その行程自体が、諏訪敦彦監督の『風の電話』と殆ど被る。
主要な出演者に西島秀俊が居るとゆう事も含め、とても危ういのですが。そもそもこの作品には原作が存在する。
何ゆえ原作は未読の為に、その関連性に対してハッキリと言及する事が出来ません。
そこで監督のインタビュー記事を参考として読んでみたのですが。元々の設定は韓国を舞台としていたらしく。大筋を占めていた韓国での撮影自体が、コロナ禍の為に撮影中止の憂き目に遭い、叶わなかったがゆえの応急対応だった…となれば、やむを得ない状況ではあったのでしよう。
初見の際には、漠然とした意見すら言えないくらいに困惑してしまう作品でした。
思い返してみた際に。何となくですが、作品全体で発せられている(製作者側からの)メッセージに対しては、此方の教養の無さもあり〝 それ 〟を受け止める事が出来ませんでした。
つい先頃、2回目を鑑賞。
やはり鑑賞直後は、作品からのメッセージに対して1回目ほどの困惑ではなかったものの、まだ受け止めるほどの理解力には乏しかったのでした。
ですが、日を追うごとに少しずつではあるのですが、(作品に対する)自分なりの想いが沸々と湧き上がって来ているのです。
それは大いなる勘違いの可能性はかなり大きいとも思っています。何しろ、あくまでも作品を観た此方の感想でしかないのですから。
〝 お互いがお互いの気持ちに寄り添う…その単純なる思い遣りこそが紛争を回避する最大の防御策となる 〟
現在、日韓の関係性は冷え切った冷戦状態に突入してしまったかの様な様相へと変化している。
ここまで冷え込んだ感覚を覚えるのは、過去にもない程だと思える。
そんな両国間に登場したこの作品。一応は多国籍な人達を登場させてはいるものの、主要な登場人物はやはり日本人と韓国人…と言って良いのだろうと思う。
ストーリー展開としては、日本人個人の問題であり、日本人同士のイザコザ自体に問題がある。それを韓国人夫婦が優しく包み込む状況を描いていた。
それを持って現実の日韓関係と同一として考える事は確かにあり得ない。あり得ないのだけれど、この作品に登場する韓国人夫婦の関係性で描かれる〝 お互いの気持ちに寄り添う思い遣り 〟
例え、それが韓国人夫婦を通して描かれていた事だとは言え。そんな些細な事すらも気に入らずに容認出来ないナショナリズムの強い人が居たとしても、この作品での夫婦の様に心穏やかにして包み込むんで行く事を目指して行ければと思うのだ。
それはかなり難しい問題なのは理解している。
だからこそ、この作品をキッカケとして。長年に渡っての繰り広げられている日韓の間に高く聳えている《心の壁》の氷解に繋がって貰えたならとても良い事に違いない…との想いを強く抱きながら、、、
2021年9月12日 TOHOシネマズ錦糸町オリナス/スクリーン8
2022年2月6日 キネマ旬報シアター/シアター1
終始現実がそこにあってヒリヒリさせられる映画
終始現実がそこにあってヒリヒリさせられた。
音のテキストの書き方は、村上春樹の小説の書き方と似ているように思った。
村上春樹がインタビューか何かで言っていた、真実とファクトの話を何度か思い出した
高槻と車の中で会話するシーンが一番ヒリヒリした(ここはもっと読み取れるものがあったように思う。
「私が殺した」が色々なことに通じている
生き残ったものは死んだもののことを考え続けるとか
北海道の雪の上で抱き合うシーンは結構核心をそのままに話す、自分の心を見ないふりをした、みないといけなかった
これも真実とファクトかもしれない
最後にみさきが赤のサーブ、大きな犬とともに車を走らせるシーンが素敵に前向きだ
原作を見事に昇華して巧みにディスコミュニケーションを描いた
職人芸の塊のような映画だ。
村上春樹の短編は、あくまでも原作であって、種のようなものだ。本作は、その種から見事な花を咲かせることに成功している。
この映画は、西島秀俊が演じる、俳優の家福悠介が、広島でチェーホフの「ワーニャおじさん」の舞台を作っていく過程を描いている。
彼は亡くした妻のことをひきずっている。舞台俳優はオーディションで選んだが、ワーニャ役には家福の妻の浮気相手だった高槻という俳優が選ばれる。
原作では、高槻はさほど重要人物ではない。ほぼ全編が家福と、彼のドライバーである渡利みさきの会話に終始する。物語における「現在」は、ほとんどが車の中で、舞台は東京だ。原作では、俳優は舞台でも実生活でも演じ続けると語られ、妻との関係においてもそうだった、と。家福は仕事場と自宅の往復の中間、つまり車の中でのみ本当の自分を取り戻す。
映画では、舞台は東京から広島、北海道をつなぐ。そのすべてを車で移動する。日本人の感覚だと、飛行機を使うだろうと思うが、逆にこれがこの映画の重要なポイントで、要するにこれはロードムービーなのだ。車で移動するという意味でもそうだし、家福や、他の登場人物の心の旅でもある。
登場人物はみんな棒読みだ。チェーホフの舞台、という要素があるから、この演出が生きてくる。舞台でも、実生活でも、人は演じ続けているのだ。そして、棒読みのセリフ回しの中に、感情を感じ取ることができる。西島秀俊はさほどうまい役者だとは思っていなかったが、沈黙の中で感情を表現していた。
そして高槻を演じた岡田将生。彼だけは感情豊かに演技をする。これは、棒読みの演技ができないというよりは、家福とは違う世界に生きている人間だからだろう。後半、高槻が、カメラをじっと見据えて、長いセリフを言うシーンがあるが、これは本作において、ひとつの山場だった。岡田将生がおいしいところを全部持っていってしまったように感じたほどだ。
本作が職人芸だと感じたのは、「ワーニャおじさん」の場面を切り取って、家福の心を説明しているところだ。この紐づけのやり方はうまい。一場面だけではなく、全編にわたって、延々とワーニャおじさんのシナリオが、家福の心理描写をし続けるのだ。村上春樹の短編と「ワーニャおじさん」を徹底的に解剖して再構築したような印象をうける。
この映画では、家福の住むマンションや、泊っているホテル、洋服、どれもこれも洗練されている。そして、そこに心はない。どんなに豊かな生活をしていても、人は自らの心に真摯に向き合うことでしか成長できない。そして、自らの心に向き合ったうえで、そこにはなにもないことに気づいてしまう人間もいる。
非常に重いテーマを、巧みにまとめあげた手腕がすばらしい。小生はインターナショナル版というのを観たので、日本版はどうなっているかわからない。個人的には最後のシーンは不要だと思った。
文学的で難しいな
................................................................................................
演出家兼俳優の西島は同じ舞台を長年つとめてた。
妻は自分を愛してくれたが、裏でずっと不倫してた。
その不倫相手の一人が岡田だったが、西島は見て見ぬフリを続ける。
そんなある日、西島が帰宅すると妻が病気で急死してた。
2年が経ち、西島は舞台で裏方に回り、自分の役に新たな俳優を抜擢。
それがオーディションを受けに来た岡田だった。
岡田は西島の妻を愛してたので、西島の舞台に興味があったのだった。
紆余曲折あり、岡田はついに俳優として才能を開花しかける。
ところが元々素行が悪く、町で人を殴って死なせ、逮捕。
代役は西島しかおらず、自分が出るか中止かの選択に迫られる。
この舞台の間中、西島の運転手を務めてた若い女性がいた。
その女性とは心の中に秘めた悲しみ?何か通じるものがあった。
ということで彼女の故郷である北海道へ2人で行き考えることに。
妻が死んだ朝、妻は西島に今夜話があると言ってた。
西島は別れ話を恐れ、帰る決心がつかずブラブラしてて遅くなった。
そのせいで妻の発作への対応ができず、死なせたことを告白。
一方運転手は母から虐待を受けて育ち、ある日山崩れで家が埋まった。
運転手は這い出たが、助けを呼ばず母を見殺しにしたことを告白。
やっぱり似たような者同士だった。
生き残った者は死んだ者のことばかり考えてしまう。
それでも生きてかなければならないよ、って西島は語った。
結局西島は舞台に出ることにしたようで、上演された。
................................................................................................
劇場で見た。海外の賞を取ったとのことで少し期待してたが・・・。
3時間。うーん・・・長い。また文学作品なので硬い。
色々感じることはあれど、面白いわけではない。
文学なんて全く分からん素人の感覚から言えば、
唯一、そして最も理解できたのは西島と運転手の共感の部分。
本編は舞台の練習のシーンがやたら多かったが、無駄に感じた。
実際、岡田の存在ってストーリー上あんまり重要じゃないし、
舞台の共演者達もはっきり言ってあんまり関係ない。
何度もある劇中劇のシーンも、多分何か関係あるんやと思うけど、
どうストーリーに関わってるのかよう分からんかった。
ラストシーンでは何故か運転手が韓国で1人で西島の車に乗ってた。
これは身寄りのない2人が韓国で共に生活を始めたってこと?
元気になる薬 ロジックとレトリック
全体を通して残る違和感
前情報ゼロで鑑賞
共感できない登場人物たち。
意味のわからない多言語を用いた劇?みたいなもの。
理解できない性描写と暴力性
私には合わないが
納得のいく、解釈が知りたくて感想をあさるが
何が表現したいのかやっぱりわからない
感情が伝わらないのか伝えないのか
例えば「愛情」と言う側面では、家福が心中を吐露する際、愛してるから向き合えなかった、本当のことを言うのが怖かったとある。
しかし、岡田将生演じる高槻は明らかに浮気相手として疑わしいが特に感情を見せない。
報復を考えてのミスキャストかと思えばそうでもない。
音の行為後に話す話の続きを教えて貰う場面では、浮気相手確定したも同然なのに、なんのコメントも残さないで逆に説教じみた事を言われる。
そして逮捕後は親身に心配する様子すらある。奥様も病気なのか、浮気の後ぬけぬけと愛を語る。みんな感情をオフにしてる?ってなぐらい、感情と行動が乖離してる様に感じる。
その対比なのか本能のままに生きる様な高槻が、説教じみたり、逮捕の際に落ち着いてたりと悟った様な行動を取るのが、作り手側の意識と役のキャラが混在して不可思議なものにしてるのではと感じてしまう。
そういった、推測や考察の奥行きを良作とするにしても、自分なりの解釈をした上でやっぱりわからんし、胸を動かされるものはなかった。
3時間は長いし、導入は人を選ぶ。しかし大変出来のいい映画
どうせ製作陣と一部スノッブが内輪で褒め合ってるタイプの映画なんだろうな・・・と覚悟して臨んだら、明快な筋、質の高いカット・演出、お手本のような物語構成で逆に驚かされました。すみません、名作です
この映画に好き嫌いが生じるのはわかります。「導入の性的描写が合わない」、「静的な演出が合わない」、「主人公の人間性が好きになれない」と引っ掛かりポイントが多重に存在しますからね。私も正直最初の30分間は辛かった。しかし過度に性的な描写もちゃんと意義をもって物語に回収されますし、「これは演劇を通じて亡き妻と向き合う物語なんだな」と筋を理解してからは抑制的でセンスのいい描写に感心させられていました。静謐な人間ドラマに求められる高い水準をクリアーしている作品の一つだと思います。3時間は長いですが、お薦め出来ます
俺、映画鑑賞に向いてないのかな?謎だらけで、モヤモヤしたまま終わった
他の方たちのレビューを読んで
ここにたどり着いた
以前、スカパーで見たのを思い出してのレビュー
西島秀俊演じる主人公の家福は舞台の演出家で俳優
ある日、妻の浮気現場を目撃してしまう
しばらくして妻に「今夜、話がある」言われる家福
仕事が終わって帰宅すると妻は倒れていて
そのまま他界してしまう
2年後
仕事の依頼を受け、広島を訪れる家福
そこでは、自分で車を運転することは禁じられ
専属のドライバーを紹介される
という物語
妻の浮気相手が誰かは不明のままで仕方ないけど
奥さんの作る脚本の内容とか
岡田将生演じる若手俳優の行動とか
ラストの三浦透子演じる渡利みさきが韓国にいる(?)シーンとか・・・
(乗っているサーブは家福の車?)
モヤモヤがたくさん残ってしまった
妻に先立たれた喪失感の中での広島での活動とか
みさきの過去をたどる旅とか
その辺は良い感じで見てたんだけど・・・
う~ん、
簡単に言ってしまうと
「自分には向いていなかった」
です
よく分からなかった
無意識の物語と現実の苦しみの折り合い
いろんな感じ方の人がいると思いますので、あくまで私が感じた解釈で、ネタバレを含みます。
この映画では、音の物語(無意識内容のように性的でやや残虐、実際語った後の記憶が本人に乏しいと悠介が言っている)、みさきの母の別人格さち、高槻の突然豹変したような暴力など、何らかの解離を思わせる描写が複数出てきます。背景の家族歴は違っていても、おそらく家族の苦しみを、登場人物がそれぞれ抱えているように、描かれていると思います。
途中、高槻は悠介との車中で、音の物語のその後を語ることで、自分の闇に向かい合う決意を表明して(そうとはその時は悠介にはわからないのだけど)、舞台を去っていったように、私には思えます。
終盤でみさきが母に花を手向けて「単にそういう人だったと考えることは難しいですか」と悠介に呼びかけ、悠介が「正しく傷つくべきだった、でももう取り返しはつかない」と語り、現実の苦しみを苦しいまま受け入れて、生きる決意にたどり着く。
これらを台詞だけではなく、カセットテープの音声や、車、舞台、風景を巧みに象徴として用いながら、観客に解釈を委ねている、芸術性の高い作品と感じます。
小児逆境体験がある人物としては、みさきはやや個人的な体験をしゃべりすぎてるかな、と思う面もありますが、ぶっきらぼうで挑戦的な態度など、全体に描写が納得感あるものになっていて、フィクションとして許容範囲と思います。
私は心理的に妥当性を感じさせる、個人的なストーリーを、登場人物たちが統合してゆく映画はとても好きなので、その点でこの映画は非常に優れていると感じます。ベースになっている物語が、高い象徴性を備えている、村上春樹さんの作品であるところも大きいのだろうと思います。
また、映像の美しさも素晴らしかった。私は見て良かったと感じました。
全797件中、21~40件目を表示