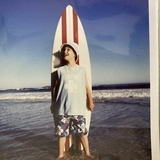ウエスト・サイド・ストーリーのレビュー・感想・評価
全339件中、121~140件目を表示
ベルナルドはジョージ・チャキリスの方が良かったかも❤️
「Tonight」「Maria」「Mambo」「I Feel Pretty」「America」次々と繰り出される永遠の名曲の数々😍40数年前、中学生の頃、リバイバルで観て大感動した時の気持ちが蘇りました〜❗️
でも、ベルナルドはやっぱジョージ・チャキリスの方が良かったな〜❤️
いまいち
懐かしさと新しさ
1961年版は昔一度くらいは観たと思うけど、その頃はミュージカルにまだ抵抗があってそれほど感動はなかった気がする。
でも、今作であらためて観ると、あ、このシーン観たことある、この曲聞いたことある、このダンスあったあったと記憶が甦ってきました。スピルバーグ監督が最新の映像技術で1950年代ニューヨークのウエストサイドを描き、最新の音響効果で迫力あるミュージカルシーンを届けてくれました。ダンスや歌に移行していくシチュエーションも自然で違和感なく観る事ができました。一部ここで歌う?ってシーンもあったけど笑
たぶん自分にミュージカルの耐性ができたのかな?ディズニー映画のおかげかも。
ラストはわかっていても泣けましたねー。ヒロイン力入ってました。
音楽はやっぱりジョン・ウィリアムズが関わってましたね。
それにしてもアンセル君走り方ダサいよ汗
ミュージカル◎❗ラスト……❌❗ネタバレあり。
旧作が好きすぎて何度も繰り返し見てきて……今回、スピルバーグ監督がリメイクしたこともあり、期待値が高かったかな。
旧作を思い出させる始まり方や、ストーリー構成、迫力のあるミュージカルシーン……これらは期待通りの素晴らしい出来でした❗
まあ…時代でしょうね。当時よりも人種差別の描かれ方はソフトになっていたことは理解できますが。
カメラワークも素晴らしかったですね❗
このあと……ネタバレですので、読みたい方だけ読んでくださいね。
ラストですよ❗❗
私が思う、ウエストサイドストーリーの核は、ラストシーンのマリアの言葉にあると思ってます。人間の憎しみが悲劇を生むんだっていう………そこが、本作からは抜け落ちてしまいました……。そのためにラストシーンがなんと物足りないものになってしまったことか……。もうね、ぜひ見てほしい❗オリジナルを❗ただのミュージカルではないことを、ただの悲しいラブストーリーではないことを知って欲しいです🥺
あと………ベルナルドのキャスティング……ダンスはめちゃ上手かったけど……ジョージチャキリスが素敵すぎましたかね😂比べちゃいけないか〜。
歌と踊りのパワーを実感!
これを2千円で観れる事は奇跡なのかも⁈
予告で散々、煽られて(ドチャクソ面白そうな予告で)大変楽しみにしていたので観てきました!!
単純に凄いです。これ映画の金額で観て良いのかと思っちゃいました笑 まず、踊りがエグいです!個人的にはプエルトリコ女性チームのダンス(あの靴であのキレ)とjetsの警察署のダンス(少し深いです+ユーモアよ)が良かったです。
後は、マリアの歌唱力よ…笑 女優さんでは無く本作初出演のインフルエンサーと知ってビックリ‼️
トムも何処かで見た事あるなーと上映中気になっていたら、まさかのベイビードライバーの子だったという!すんごい大人の男性になってました( ^ω^ )
ファッションもとても興味深く楽しめました!スタイルモンスターの方達のジーパンの似合う事よ❗️
原作がミュージカルなので、そこは留意して観て下さい!!(時間の制約もありますし、ストーリー性なども)
個人的には、字幕翻訳が少しだけ(ほんの)不満です。恐らく差別的な言葉など、昨今の雰囲気で丸くしてるのかなーと思いました。
ミュージカル系の作品にアレルギーの無い方は是非観に行って下さい、映画館でダンスシーンの迫力を!!
不寛容による悲劇の連鎖
ひとめぼれから始まる恋愛映画はミュージカルが良く似合う。
前・後半は別映画と考えた方が良い。
前半は ★無限大! しかし後半が。。。
画像の色彩感(色合い)がとても良い 細かな造作もいい 音楽・音響もいい
唄も前作よりもうまくて、素晴らしい。
登場する車もみな、前作よりもいい雰囲気だ。
前作は演劇のような固定カメラが多かったが、今回はカメラワークが素晴らしい。
特に第1カットの入り方
前作は地理的な説明だったが、今回は時代背景だ。
カメラが来ると、人物がはじめて動き出すやり方は、あまり好きではないが
昔:フィルムでは不可能だった長回しを、現代技術:デジタル撮影ならではに魅せてくれたのは、リメイクならではの好手法。
逆光やスポットライト等の少し誇張した光源を使った表現方法は舞台劇のようでもあり、素晴らしく、
多くのシーンでは"光と影"が上手く取り入れられ、どこも素晴らしい構図に成っていた。
今回は前作で印象的だった"足を上げて踊るシーン"と"指パッチン"がないのが残念。前作の代表シーンをあえて入れなかったのは監督の配慮だろう。
組みダンスが前作より少し地味になったが、それでも前作同様"完璧に揃っていない"のが逆にアメリカぽくて良い。
赤い服が好きなヒロイン:マリアは、愛しい人:トニーと出会ってからは
仕事でもプライベートでも彼と同じ青色の服を迷わず着るところがニクイ演出表現。
今回はトニーが"むしょ帰り"これは何を意味しているのか? 監督に聞いてみたい。
プエルトリコ人の話す言葉が【 】を使った日本語字幕がでていたが、その下に英語訳がでていない!
スペイン語の英語字幕が入らないのは米国版でもそうなのか? 確かめたい。
快調な前半に反して、後半にかけて「ロミオとジュリエット(シェイクスピア)」色が濃くなり
救いがない、中途半端な社会派悲劇"映画に成ってしまった。
前作は前作時の時代背景として、くそれで良かったが、
2021年にリメイクした時、同じ内容では意味がない。
今は今の"結び"を用意して、はじめて この映画をリメイクした価値がでる。
この映画は、前作の「ウエスト・サイト物語」と見比べてみるといい
細かいところと登場人物が違うが、内容も映画の質も同じである事に気づいてしまうだろう。
しかし両作とも超1級作品であることには間違いない。
映画としては素晴らしいのだけど。
良い音響を望んで、普段ほぼ使わないIMAXにて鑑賞。
流石のスピルバーグで隙が無く没入感が心地よく映画体験としては良かった。
名作なのに1961年版は見ていなかった。
ウエストサイドストーリーは名曲が多く、良く知る曲も聴いてて心弾む。
ただ、ポーリッシュ系がプエルトリコ系に対して、移民が、、と良く言っていたけどオマエも移民だろ、、
というか、アメリカ人って誰よ。
偉そうにしてるフランス系もイギリス系も自国で住んでられないから移り住んできただけだろ、、
皆んなネイティブアメリカンにひれ伏しろ。
とか考えてイライラしながら見てました。
底辺争いで自ら窮地に立つとか、アメリカンシチズンって本当馬鹿ばっか。
アメリカに住んでいた時の嫌な思い出が思い出させれて、、感動も薄れました。
映画に対する評価ではないけれど、、
人殺しをしても尚、イノセントな雰囲気漂うトニー役のアンセル・エルゴートの甘いマスクが眼福でした。
ただの古典リメイクなんかじゃないよぉ〜☝️
スピルバーグも凡作を作ることはある
チンピラのクズ同士が争っているように見える映画だ。そして実際にその通りである。クズのクズたる所以は、自分で考えないことにある。その上、無意味に高いプライドがある。だから反省がなく、うまくいかないのは全部他人のせいだという思考回路になる。
本作品は、クズたちが、社会に蔓延している民族その他の対立という固定的なパラダイムに乗じて、仲間内での地位向上や鬱憤ばらしをする物語で、その精神性は暴走族となんら変わらない。
ナタリー・ウッドが主演した作品が上映された1961年当時は、多くの問題をロミオとジュリエットに似せたストーリーでミュージカル映画にしたことで高い評価を得られたが、それは当時のアメリカ社会の問題意識があまり進んでいなかったためだと思う。だから作品が問題を明示したことの衝撃は大きかった。当時の人々は暴力に対する耐性があり、銃に対する馴染みがなかったことも、作品が受け入れられた下地となっていた。
映画には旬があるものとそうでないものがある。言い方を変えれば、時代が移ると色褪せるものと色褪せないものがある。いまは価値観が相対化されたり、新しい価値観が創造されたりする時代である。普遍的な問題に深く斬り込んだ作品だけが100年後も生き残る。残念ながら本作品は生き残る作品でも、旬の作品でもなかったようだ。
主演の女の子の歌は抜群に上手い。バーンスタインの音楽はいま聞いても新鮮である。しかしそれ以外はひたすら退屈であった。天下のスピルバーグといえども、凡作を作ることはあるのだ。
リメイクでもアニータが凄い!
正直劇場に観に行かなくてもいいかなと思っていたが口コミによる評価の高さに流され遅ればせながら鑑賞。
本作のリメイクはまさにスピルバーグにしかできないって思うほどの出来ばえでさすがだった。オープニングのカメラワークからお馴染みのスピルバーグ節が炸裂しワクワクが止まらない感じでスタート。中盤はやや中だるみ感はあったものの迫力のダンスシーンにこれまた圧倒される。そして気になるオチをスピルバーグはどう締めくくるのか。その決着の付け方はもう見事だとしか言いようがない。
リメイク映画はたいていのものはオリジナルを超えられずにいる。しかし本作はオリジナルの良さを最大限に継承しつつ、今の時代に合うようにリアルに表現し、それでいてオリジナルよりもエモーショナルな仕上がりになっており、かなりレベルの高いリメイク版になっていたのではと思った。
また画面の中の世界が今の映画とは思えない、まさに60年代の映画を観ているかのような錯覚におちいる絵作りには圧倒されっぱなしで特に瓦礫が散乱している街並みの描かれ方は本当に素晴らしい。
もはやオリジナルとどっちがいいかなんて考えるのがくだらなくなるほどだ。
他の監督が撮っていたらここまでのものが出来ていただろうか。きっと名作のクオリティに押し潰されていたにちがいないと思う。しかしスピルバーグはそのハードルの高さをものともせず、自分らしいスピルバーグバージョンを見事に世に放った。
オリジナル版と共に再びこの名作に触れる機会を与えてくれた事にも感謝したい。
そして劇中を流れる数々の楽曲が改めて素晴らしいなと痛感した。
劇場の大画面と大音響で鑑賞しておいてよかった一本だった。
スピルバーグの危機感を見る
前作は91年梅田OSのシネラマ最終上映で衝撃の初体験。原作ミュージカルはロビンス振り付けで3回観た。「シンフォニック・ダンス」は演奏機会に恵まれて、フルスコアも買った。という視点でのレビューです。
極論すれば、前作は『ミュージカル映画』、今回のリメイクは『スピルバーグが映画でミュージカルを表現した作品』という印象。冒頭でリンカーンセンター取り壊し中=前作のことはいったん忘れてください、と観客に求めているから、努めてそうするのですが、前作(と違っていると分かることが)前提の演出が随所に出てくるので、ちょっと戸惑った。
物語の大筋は、前作を踏襲しているけど、その描き方は大きく異なる。特に、登場場面が前作と異なる楽曲が多いので、その違いを楽しむのは一興。言い換えると、前作と同じ場面で流れる楽曲は、まさに作品のスタンダードなのでしょう。
個人的には「One hand, One heart」の歌詞変更と、大詰めでマリア(とトニー)が歌うナンバーの入れ替えに、大きな違和感があった。原作での 「Only death→Even death」の流れの方が、歌詞に込められた二人の決意の強さが際立つし、「Somewhere」は最後に歌われることで、初めて音楽的寓意が成就する。こうした部分を変更すると、作品のもう一つの主役である音楽の意味が大きく損なわれてしまう。
それでも製作陣は、これらの変更を大胆に導入した。さらに移民間の対立をより強く打ち出すなど、全体として味付けを濃くしたと感じる。
それはたぶん、「ここまで簡明にしないと、今の観客には伝わらない」というスピルバーグの強烈な危機感があったのだと思う。特に、アメリカを覆い尽くす分断主義者の人々には、ここまで簡明にしても彼の伝えたいことは響かないように思える。それでも彼は、手を取り合おうと訴えずにはいられなかった。その危機感が今回の作品の影の主役だと思う。
映像は流石の美しさで見惚れてしまう。だけど、前作の「ミュージカルの舞台です」という描写も捨て難く、甲乙つけ難い。個人的には「Mambo」と「America」は断然前作が好みですが、「I Feel pritty」は今作が上手い。そしてなんといってもモレノが歌う「Somewhere」の素晴らしさ。ここは、ミュージカル→前作→本作と全て歌い手が異なるのですが、本作での舞台設定変更がもっとも効果的に働いたのが、この曲だと思う。私はここで泣きました。客席のあちこちでもすすり泣きの声がした。
モレノの好演は当然として、マリア役は大熱演。トニー役はもう少し運命に振り回される感覚があってもよかったか。また、本作で一気に重要度が増したチノ役が、いい演技で期待に応えていると思う。チノの描写の深化は、ドクのドラッグストアの仕掛けと並んで、本作の大きな見どころでしょう。
81年にミュージカル全曲をレコーディングした際、作曲者のバーンスタインは
「この作品が描いたテーマがいまだに時代遅れになっていない、ということが悲しい」
という趣旨の発言をしている。それはそのまま21世紀の今に当てはまるように思える。スピルバーグの危機感の源は、たぶんここにあるんじゃなかろうか。
物語という都合
名作
大スクリーンで観てよかった! 考えてみたら旧作はDVDでしか観てなかった。
スピルバーグはどうしても21世紀版「ウエスト・サイド・ストーリー」をアーカイブしておきたかったのだと思う。極めてオーソドックスな新作として。プエルトリコ人にはちゃんとラティーナをキャスティングして。
冒頭から50年代のニューヨークを再現した空撮映像に惹きつけられた。どこまでがCGなのかわからないけど、モノクロフィルムに無理に天然色をつけたみたいなノスタルジックな色味も効果的と感じた。ダンスシーンを舐めていく低い位置からのカメラワークにも心躍った。
もちろん、「こ、ここで歌うんですか〜??」みたいな、ミュージカルならではのツッコミどころは多々あるのだけど、それはそれ、そういうルールの下で製作されたジャンルなのだ。
しかし女性の皆さん、よくあんなヒール履いてストリートで踊れますね。見ててヒヤヒヤした。
今日感じた教訓。「ピストル(核兵器)は殺し合い喧嘩(戦争)の抑止力にはなりません!」。本作の源である「ロミオとジュリエット」を残したシェイクスピアの洞察力はすごいなあ。現実的にはウクライナが心配である。
全339件中、121~140件目を表示