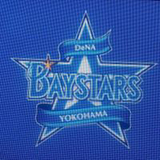罪の声のレビュー・感想・評価
全425件中、401~420件目を表示
初見的感覚感想。
原作本未読者の感想です。脚本担当の方の作品は兼ねてより拝見しており、巧みな物語の立て方に信頼を置いておりました。しかしながら前作は前作、今作は今作と、作品たちを混同してその人の描く脚本だからいい、と過大評価するのは視点ズレの色眼鏡かとおもいますのでそれら抜きのお話です。
初めから予告映像にもある、あの特徴的な子供の声を使い、開始10分ほどで物語が立ち、進展していき、進展し続け2時間20分の映画。よくある伏線を散らかすだけ散らかし、回収しない作品になることもなく、撮るべきところを撮り、伝えるべきところを伝える、大変筋の通った脚本に感じられました。
今作の出だし、巧みかつ、「最初からクライマックス」な、初見で見ても「どうなるんだろう?」と興味の湧き立つ立て方だったのではないかとおもいます。
私は後述のひとりですが、邦画特有の陰気なライティングに加え、クドイほどの尺使いなどが苦手な方にも今作はかなり見やすい作品かとおもいます。
ちょこちょこイギリスのシーンがあり、おしゃれな風景が出てきて、星野さん演じる曽根のテーラーもおしゃれです。映画全体のライティングも明るく、「冬の美しい背景」で描かれるので見やすいです。
2時間20分、知り合いに誘われ観覧しましたが、邦画としては評価できる作品だったとおもいます。
映画評価±0が★3つなら、今作は2段階評価を上げてもいい気がしました。
初の組み合わせ聖域に挑む
トイレに行きたい!でも、トイレに行けない。
なんだこの映画は。
長めの映画だったけど、気持ちが途切れることなく、最後まで駆け抜ける感じの映画だった。
こんなに気持ちを持っていかれた映画は初めてだった。
事前に小説を読んでたから、より、ぐっと気持ちが入ったかもしれない。
犯人の言い分もわかるし、一方で、その結果振り回された人たちの悲劇も切なすぎて、憎しみをどこにぶつけたらいいのか、気持ちのやりどころに困る。
それが、すごくリアリティがあって、脳が痺れる感じがした。
ただ一つ欠点があるとすれば、2時間半の映画は長くて、途中でトイレに行きたくなって、でも、画面から目を離せなくて…。多くの人が映画終了後に、トイレに駆け込んでいました。
それくらい、夢中になれる映画でした。
見応え充分
【点と点、80年代】
グリコ森永事件をモチーフにして、少しずつ真実に迫る謎解きを展開しながらも、どこかノスタルジックな感覚を覚える作品だ。
そういう意味で、80年代の雰囲気をよく伝えていると思うし、更に、子供の声を主要なファクターに据え、その子供たちの成長や運命を見つめる重厚な作品になっていたと思う。
80年代は、ある意味、混沌とした時代だった。
多くの謎を残し、この作品のモチーフになったグリコ森永事件もそうだが、70年代の学生運動の残り香もあちこちにあったような気がする。
バイトしていた都心繁華街の居酒屋の近くにあるバーのオーナーが、学生運動に傾倒した人物で、「腹腹時計」という爆弾の作り方を記載した地下雑誌を所有しているという噂を聞いたことがあった。
70年代の三菱重工ビル爆破事件の爆弾の作成工程を記したものだ。
あの居酒屋は、ビルを建て替えてまだ営業している。
今度、バーがどうなっているか探してみようと思う。
また、80年代は、金融市場が激変した時代でもあった。
為替のプラザ合意。
後半は、バブルに突き進んだ。
しかし、株式市場も、まだまだ未成熟で、仕手やインサイダーといった禁じ手に手を染める連中がいて、取り締まりも不十分な時代だった。
そして、確実に儲かる話というのもあって、株絡みのうまい話に政治家が擦り寄って来ていたというのは、リクルート事件でも明らかになったところだ。
企業がらみで言えば、佐川急便事件で、政治家の金丸信が90年代初めに逮捕起訴されたが、実際の贈賄が行われたのは80年代だった。
そんなことを考えると、この作品で、株の空売りの資金の金主が政治家と推測される場面があるが、80年代であれば、ありそうな話だとさえ思えてくる。
こうして、この作品では、時代の雰囲気を表す特徴を点と点で結び、僕達のノスタルジーが刺激されるのだ。
そして、子供の声。
僕達は、キツネ目の男の似顔絵や、人を食ったような脅迫文、次から次に標的にされる食品関連企業に注目しがちだったように思う。
でも、声を利用された子供たちの、その後の運命など考えたことはなかったのではないか。
どのように声は調達されたのか。
この劇場型とも言われる事件の闇の深さを改めて思い知る。
グリコ森永事件では、当初、録音された声の主は、30代の女性と言われていた。
しかし、再鑑定で、これは10代のものとされ、他に幼い2人ないしは3人の男の子の声があったと報じられていた。
幼い子は記憶も確かに曖昧かもしれない。
だが、10代と思われる女の子は、記憶も鮮明なはずだ。
彼女は、何を感じていたのだろうか。
今も、怯えながら生きてるのだろうか。
興味というより、胸が苦しくなる。
ストーリーは、子供たちのその後の運命にフォーカスし、時代や時代の雰囲気に翻弄された周りの人を照らしながら、声の主たち…といっても残されたのは2人だけだが、彼らを罪の意識から解放していく。
阿久津と曽根が繋がった。
そして、京都のテーラーとヨークのブックストアの店構えがとても似ていたのも、点と点が繋がるような気がした。
この作品では、事件がさまざまな事柄や人と繋がっていた。
実際のグリコ森永事件はどうなのか。
一体、社会の何とか繋がっていたのか。
改めて興味が湧く。
しかし、子供のことを考えると、実は謎のままの方が良いような気にもなる。
ただ、一方で、キツネ目の男をすんでのところで取り逃したとして左遷された警察幹部は自死を選択した。
なかには、事件が永遠に終わらない人もいるのだ。
グリコ森永事件とは一体何だったのか。
僕達は改めて考えることで、日本の社会の歪んだ暗い部分を心にに留め置くことになる。
久々に胸にズドン!と来た作品でした
公開初日の舞台あいさつ全国同時中継回を
観てきました。
映画の宣伝番組で星野源さんだったか小栗旬さんだったか、どちらが仰ってたかはハッキリ覚えてないのですが…
高田聖子さんのシーンが印象的だと言われていたのが実際に観て納得でした。
そこからが涙が止まらなくって…
私には この事件は最初のターゲットになった会社の名前が入った事件名が印象が強すぎて、他の会社の事を含め 具体的には覚えていない事も多かったのだけど、でも今回の作品を観て改めて記憶の奥底にバラバラに眠っていた記憶のピースが正に埋められた感がありました。
あくまで事実を題材にしたフィクションではあるのでしょうが、でも…
自分の知らない内に"罪の声"に使われてしまった人や その人に関わった人がこの世の何処かに存在されていて、それが原因で長い間 辛い思いをされていたのだとしら…。
その何とも言えない切ない思いが、前述の高田聖子さんのシーンから溢れてきてしまって…。
本当に舞台あいさつで星野源さんが言われていた通り、時間を感じさせない作品でした。
子どもの未来を奪うことへの作り手の怒りが伝わってきます
・自分が感銘を受けた原作のどの部分をどう掬い取りどう表現したのか。
・個人的に極めて重要だと思っている、弱い立場の子ども達への眼差しはどうか。
この二点で唸らされた作品は、私の場合、無条件に満点です。
原作は文庫で500ページを超える緻密な構成の作品です。真相は本当にこうだったかもしれない、と思わせる筋立てで圧倒された記憶があります。
映画という時間的制約のある中で、最大限に原作の厚みや深味を映像化していたように感じました。
さすがにやや急ぎ足の感はあるものの、破綻をきたさずに新聞記者の取材と真相を知りたいテイラーの二元中継で、糸を手繰り寄せていく展開。
自分の知らない新聞社という世界の雰囲気や、ちょっとしたロードムービー風の交流の中で信頼関係が深まる様は、確かに人間の付き合いってこういうこともあるよな、と感じさせる説得力。
生島の娘と息子に関しては、原作より感情移入を強めるドラマ性が付加されていたようですが、過剰な感じはなく、子どもを親の自己都合優先の事情(それは決して犯罪とは限らない)に巻き込むことは子どもの未来を奪う可能性がある、ということがストレートに伝わってきました。
2000年に制定された『児童虐待の防止等に関する法律』では、児童虐待の定義が下記の4種類に分けられています。
①身体的虐待
②性的虐待
③ネグレクト(保護の怠慢・拒否)
④心理的虐待
子どもを犯罪に巻き込むのは、結果的に①や④に繋がるわけで、紛れもなく児童虐待だと思います。
【リアルで怖い夢を見たので、忘れないうちに追記】
2020.10.31
それはこの記事が現実に報道されていて、聡一郎さんや、匿名の洋服店店主S氏が、ネット上で攻撃されていること。
曰く、
・聡一郎さんの悲惨な人生については、「バチが当たっただけじゃね?」
・Sって、○○町の△△という店らしい。
犯罪で儲けた金で作った店なんだろ❗️
などと、なんの根拠もなく決め付けて、他人まで煽るような攻撃に晒されていました。
本当に怖くて目が覚めました。
夢とは関係ないのですが、もうひとつ。
事件や事故、災害などに巻き込まれて助かった方が、亡くなった方や、自分より不幸な状況にある人を知った時に、
自分だけおめおめと生きていていいんだろうか。
みたいな罪悪感を抱くことがありますが(最近では『ホテル・ムンバイ』でも感じました)、キリスト教圏なら、告解室で懺悔したりそれなりに救われそうですが、日本だとなかなかその方面のケアが難しいように感じます。そんな時に『星の子』のような新興宗教に走ってしまうのは、また別の話ですが。
予告が1番面白いパターンのやつやん
緊張感の途切れない秀作
原作は未読である。忘れ難いグリコ森永事件をベースに、その犯人像を想像して話を展開させる手腕には感服した。非常に良くできた話であり、脅迫で持って来させた金の受け渡しに失敗しても、実は他にも金を手に入れる方法があったという点は、見ていて目から鱗だった。いかにも有りがちな話だと思った。犯人たちの目的と動機がバラバラだったというのも頷けるし、金以外の目的で参加した者たちの薄っぺらな正義感と復讐心には心底から憤りを覚えた。50 年以上前の学生運動で革命とかほざいていた連中の思慮の足りなさ、独善性を痛烈に指摘した描き方が痛快であった。
テキストの読み上げ機能など遠い未来の話だった当時、話者特定を困難にすべく、脅迫文の読み上げに3人の子供を使った犯人グループとその協力者は、その子らが後でどんな不幸を引きずるのか、全く理解も想像もしていなかった。その想像力の欠如、我が子を不幸にしてまで、社会に一矢報いたいと語る身の程知らずの行動には、非常に腹が立った。3人のうち、最年少の1人を除き、あまりに悲惨なその後の話は目を覆うばかりであり、胸が痛み、深い同情を禁じ得なかった。
上映中、途切れることのない緊張感は、子役を含む俳優陣の好演の賜物であろう。小栗旬は、原色好きの変な映画監督の太宰役で見て以来だったが、力みのない演技が別人のようで、いかにあの女監督が異常な演技を強いていたかがよく分かった。成人後の聡一郎役の俳優は、特に印象的で、悲嘆に暮れる際の血管を浮き立たせた演技の迫力には度肝を抜かれた。望役の原菜乃華さんの美しさは、物語の痛切さをいや増していた。あと、聡一郎の子役のほうが星野源に似ていたので、やや混乱した。
佐藤直紀の音楽は、登場人物たちの不幸に想いを寄せて寄り添っているようで、非常に好感が持てた。演出は非常に見事で、根っから根性の腐り切った悪人から、インテリを気取っているくせに他人の人生にまで考えが及ばない無自覚な悪人まで、良く描き分けてあった。事実が次々に明らかになる度にカタルシスが落ちる想いをし、それが連打で来るので、大変に見応えがあった。
(映像5+脚本5+役者4+音楽5+演出5)×4= 96 点。
大作ではあるがやや物足りない
予告編を見た時は殺人事件を捜査する刑事物のミステリーなのかなと思って期待していたのですが実際はグリコ森永事件をベースとした物語だったのでちょっと肩透かしを食らいました。
結局半分実話、半分フィクションな訳ですからなんか中途半端さを感じてしまいました。
もちろん本作品はかなりの大作ではあるのですが、怖さ、悲しさ、せつなさみたいなものが少し物足りないと感じました。
また、登場人物が多くて全体的に少し間延びしている感がありました。
違和感も多少ありまして、そんなに小さな頃ではないはずなのにいつ誰のお願いで録音したのか覚えていないというのはちょっと変かなと感じました。
グリコ・森永事件を知らない世代の方のほうがむしろ楽しめる映画なのかもしれませんね。
途中でアイコムのIC-232というアマチュア無線機が出てくるシーンがあったのですが、私も大昔に同じ無線機を使っていたのでめっちゃ懐かしかったです。
最後に小栗旬が若い時の原辰徳に似ているのが気になってあまり映画に集中できませんでした。
さすがの野木亜紀子脚本!
滋賀県草津市のイオンシネマ草津にて、公開初日の初回上映を鑑賞。
かつて日本中を震撼させ迷宮入りしてしまったグリコ・森永事件をモチーフにした塩田武士氏のミステリー小説を小栗旬さんと星野源さんのダブル主演により映画化。
あたかも「たぶんそうだったんじゃないか劇場」的なリアリティーをもって、この未解決事件の真犯人像と事件の真相に迫るミステリー。
物語としては、小栗旬さん演じる35年前に時効を迎えていた劇場型犯罪の真相を追う主人公の新聞記者・阿久津と、幼少期にこの事件の脅迫テープに自分の声が使われていたことを知ってしまう、星野源さん扮する、京都在住のテーラー店主・曽根俊也を軸に、35年も前に迷宮入りした事件を掘り起こして一体どんな意味があるのかと自問自答しながらも、知らぬ間に犯罪に加担させられ、ある意味、被害者でもある「声」の主たちを巻き込んで事件の真相を巡る謎解きを行っていくというヒューマンミステリー的なお話し。
あいにくとベストセラー小説の原作は未読でしたが、私自身も、グリコ・森永事件については、京都府という、あの事件の顛末に関わる地域に住んでいる土地柄から、事件の当時はすごく怖かった印象が残っていますが、一体どの様に、この事件を料理されるのか楽しみにしていましたが、さすがに野木亜紀子さんによる脚本担当の作品だけあって、見事なバディムービーとして昇華させてくれていました。
あくまでも原作者の憶測によるフィクションであるのは分かりながらも、とても重厚なストーリーに、長尺な事もつい忘れてしまうほどお話しに引き込まれてしまいました。
お話しの展開や内容が内容だけに、「グリコ・森永事件」の真相とは謳えなかったのも理解出来ましたが、劇中の事件の犯行グループの行動のあらましはあの事件そのままでしたので、未だにあの事件をよく覚えている私からすれば、よく些細についてまでも調べ上げてあって、スリル溢れる内容にもなっていて面白かったです。
小栗旬さんの自然体な演技や、星野源さんもさすがにミュージシャンだけあって音感に鋭いのか、京都弁を上手く駆使してられて素晴らしかったです。
また端役に至るまで、中高年代の昔ながらのオールド映画ファンには懐かしく嬉しい豪華キャストだったのも堪らなかったですね。
私的な評価としましては、
現実のグリコ・森永事件を知らなかった世代でも楽しめるミステリー映画になっていたことでしょうし、 勿論、あの事件を鮮明に覚えている世代にとっても楽しめる作りの映画になっていましたので、文句なしの満点評価も相応しい作品かと思いました次第です。
この国の大人たちは未来を信じている
過去の欠片を丁寧に紡いで辿り着く答え
実際の歴史的事件を下地に、あくまでフィクションとして描かれた本作ですが、造りが非常に丁寧で細部まで矛盾がなく、且つ、大袈裟になり過ぎない物語になっているため、これが真実ですと言われても信じてしまいそうなくらいです。
ミステリー的要素よりも、時効を迎えたとはいえ日本中を巻き込んだ事件の真実が明らかになるにつれて変わっていく登場人物の心理描写に重きをおいて描かれていました。
真実を知らない方が幸せだった人もいれば、知ったことで少しは傷が癒えた人もいて。動機を聞くと「そんなことで」と思うけど、それは時間が経った今だから、当事者じゃないから感じることで。
令和の時代に見るとなお、昭和という時代の異常性が際立ちます。
でもラストは、哀しみや虚しさの中に少しの希望を感じることができ救われました。
真実を追う意味
フィクションだがノンフィクションのような作り方
流転
中途半端はいけないよ
ヨークの撮影が素晴らしかった。映画を見るのはああいうシーンが見られるところだね。
もう一ついいのは、エンデイングに流れるUruさんの歌!
前半はイマイチだなぁ・・・
小栗旬が「何のために報道するのか?」みたいなところに行き始めた頃から、引き込まれていくかな・・・
学生運動闘争とか、一つ一つが物足りなくて、中途半端、事件の動機の背景を網羅したにすぎない感じがした。
まあ、星野源、小栗旬を見たい方の映画だと言っていいかな。
予告動画ではもっと緊迫感があると思ったのだけれど、少々肩透かし感が残った、残念。
もう少し言えば、大道具や小道具、美術の統一感にかけていた(私個人の感想)。
映画の楽しみはセットにもあるからね。堤幸彦監督の映画みたいな、ああいう絵は見応えがある。
脇役もいい
全425件中、401~420件目を表示