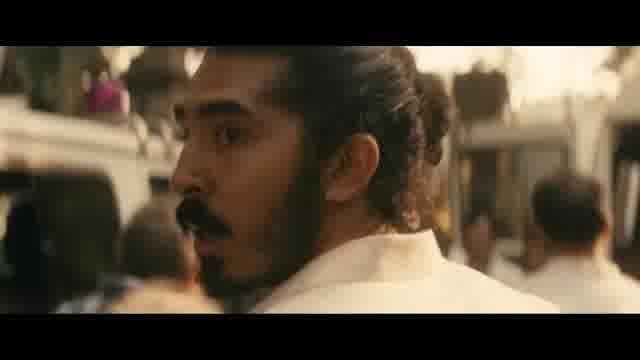ホテル・ムンバイのレビュー・感想・評価
全257件中、161~180件目を表示
靴が象徴的に扱われていたような…
冒頭、アルジュンの靴が映る。靴を履くのを忘れてサンダルで出勤してしまった。結局事務所にある小さな靴を履いてフロアに立つことになる。靴を忘れたことでルーム担当が代わり命が助かった、という意味だけなのかな?と思っていた。
いや、しかし、潜在的に足元に意識を向けるための意味があったのかもしれない。
テロリストの少年達はアメリカやイギリスは敵だ、と言っていた。でも履いている靴はvansとconverseではなかったか?
とするならば、あの少年達は本当に知識がなく、洗脳されているただの少年として描かれていることになる。
決してそこをフォーカスしたカットはない。
しかもイスラムの貧しいテロリストの少年達がそんな靴を履いているわけはない。
そこは本作の演出の1つなのだろう。
ってただ単に似てる靴ってだけだったりして。
テロ描写は容赦ないが、名も無き英雄はどこ?
つらい
開始47分くらいから泣き出して最後の方でやっとちょっとほっとした。あの電話だけで操ってるテロリストのボスなんなの。テロリストの父親もまさか使い捨てにされる為の訓練とか思ってないと思うけど。自分の子供を巻き込んだ一家自爆テロのニュースも前に見たから、こういうのどうしたらいいんだろう。友達と観たら気分が重くなって話す気分じゃ無くなりそうだからDVD鑑賞がおすすめ。料理長がしっかりして主人公や他のホテルスタッフ、地元警察が良心に基づいて行動してて良かった。
疲れるけど、観ておくべき映画
インドのホテルムンバイを舞台に、全員殺害を最終目的として占拠するテロリストと、できるだけ多くの人を逃がそうとする従業員の話。
始まって五分で占拠、終わる五分前まで続くので、123分間ほぼぶっ通しの緊張感持続。これは、疲れるよ〜。
おまけに宗教テロなので、交渉の余地なしという無力感。これがけっこうキツい。宗教ってなんだっけ、と考えざるを得ない。
テロだし実話がベースだから、たくさん人がしぬのはしょうがないのだが、群像劇だけに切なくなる。おまけに、ほとんど犬死にだ。現実は映画とは違うということを見せつけられる。それでも、いいこと(ホッとすること)が一つ二つはあってよかった。なかったら、映画の体さえなさないのではないか?
こういう不幸な事件があって、犠牲になった人も多かったが、従業員の献身で助かった人たちもいたんだ、ということを記録しておくことは、大切なことだと思う。
日本でも起こりうる
10年以上前、2008年11月26日から29日に起きたムンバイ同時多発テロ
の映画です。
ムンバイ同時多発テロを知らない人、忘れてしまった人は多いと思います。
私もすっかり忘れていました。
重武装はしていますが、わずか10人で170人以上を殺害し、230人以上に負傷
させたことには驚きました。
同時期に起きた主なニュースは、以下の通りです。
2008年11月4日、バラク・オバマは、米国大統領選挙に当選しました。
2008年11月4日、大阪地検特捜部は、小室哲哉を5億円の詐欺容疑
で逮捕し、のちに懲役3年、執行猶予5年の罪が確定しました。
時間が経つ早さを感じます。
次々と人が殺されるので、鑑賞するのは大変ですが、事件を忘れない
ために鑑賞しました。
インドの地名が色々出てくるので、事前に調べた方が物語に
入り込みやすいです。
・タージマハルホテル
・インド門
・CST駅
・レオポルド・カフェ
・カマ病院
特にタージマハルホテルとインド門が一緒に撮影されている写真を
見ておくと映画のリアリティを感じることができます。
インドで行われ、パキスタンの関与が疑われ、カシミール地方を巡る
国境問題かと思いましたが、違うようです。
テロの背景は、イスラム教、貧困、格差であり、世界中で普遍的に
存在し、広がっています。
テロリスト達が話しているのは、インドとパキスタンの国境地帯である
カシミール地域で話されているウルドゥー語です。
テロリストの1人は逮捕され、「ラシュカレ・トイバ」の構成員であると
答えてました。
「ラシュカレ・トイバ」は、カシミール地域で南アジア全域にイスラム
帝国建設を掲げ、ユダヤ教徒とキリスト教徒に対するジハードは、すべて
のイスラム教徒に与えられた義務として、テロ活動し、カシミール地方に
軍事キャンプを所有し、本部はパキスタンにあり、2000年以降数々のテロ
を行っています。
米国、英国はもちろんパキスタンからも「ラシュカレ・トイバ」はテロ組織
に指定され、資産は凍結され、活動は禁止されています。
イスラム教の聖典「クルアーン」ではイスラームにおける天国の様子が
具体的に綴られていることを悪用し、ジハードという名のテロを行っています。
イスラム教におけるジハードとは、イスラム法の支配する
ダール・アルイスラーム(イスラムの家)と、異教徒の法の支配する
ダール・アルハルブ(戦いの家)に二分されている世界を、
ダール・アルハルブを征服によって、ダール・アルイスラームにする
ことです。
首謀者は、計画的にテレビで情報を収集し、携帯電話で実行者に指示を
していたのには、驚きました。
テロ発生時の報道管制の重要さを痛感しました。
平和を祈るだけでは実現しません。
なぜ、若者がのテロリストとして、事件を起こしたのかを考えるきっかけ
になれば、良い映画です。
この事件以降もテロ事件等は減るどころか、今年に入り激増しています。
2011年7月22日、ノルウェーの首都オスロ・ウトヤ島で銃乱射事件が発生し、
1人で70人以上を殺害し、100人以上に負傷させる事件も起きました。
知らない人は「ウトヤ島、7月22日」を鑑賞すると良いでしょう。
2019年3月15日、ニュージランドの2番目の都市クライストチャーチで
銃乱射事件が発生し、1人で50人以上を殺害し、40人以上に負傷させる
事件起きました。
2019年4月23日、スリランカの最大都市コロンボで同時爆発事件が発生し、
7人で250人以上を殺害し、7人で500人以上に負傷させる事件起きました。
2019年7月30日、米国ミシシッピ州のウォルマートで、従業員が
他の従業員2名と警察官1名を銃殺する事件起きました。
2019年8月4日、米国オハイオ州デイトンで、1人で9人を殺害し、
16人に負傷させる事件起きました。
ムンバイの人口は1200万人で、インド最大の都市です。
ムンバイを日本に例えるなら、東京です。
東京を管轄する警察組織は警視庁で、職員数は4万6千人、特殊急襲部隊
(SAT)は全国で300人います。
特殊急襲部隊が、外国人工作員の襲撃を想定した警備訓練が報道機関に
公開されてはいますが、ムンバイ同時多発テロのような事件に対処した
ことはありません。
日本で起きた似たような事件としては「通り魔殺人事件」がありますが、
警察組織や特殊急襲部隊では対応できていないのが現実です。
海に囲まれている島国である日本では、重武装したテロリストを侵入
させないことは現実的ではないです。
バックパッカーで日本を旅行する若者を東京で目にすることは珍し光景
ではなく、日常的な光景で、重武装したテロリストが、日本国内を移動
することは可能です。
組織的に軍事訓練を受け、重武装したテロリストが東京を襲撃すれば
この映画のような結果になると思いました。
この映画が気に入ったら「ホテル・ルワンダ」もお勧めします。
インドとパキスタンの歴史的関係を知りたければ「歴史は勝者によって記される」
という言葉で始まる難解な映画ですが「英国総督 最後の家」を鑑賞すると良いで
しょう。
パンフレットは、よくできているので、映画を理解したい人にはお勧めできます。
撃たれる側に立たされる恐怖
五つ星ホテルに宿泊する富豪の身勝手さと、当たり前に共感できる一個人としての心情の動き。コック長の責任感とリベラルさ、リーダーシップ。アルジュンのサンダルに象徴される貧しさ。そして、彼の献身と誠実。テロリストという名の若者の、無邪気さと極貧と悲しさ。唐突に始まるテロの恐怖という言葉では表しきれない恐怖。
重層的に凝縮された、みごとな映画だと思います。
映画を見た後に、ニューズウイーク日本版の大場正明氏のコラムやその他のサイトを読むと、映画の内容・演出がよく理解できるのでお勧めしたい。なぜ、ザーラがテロリストの仲間だと疑われたのか。なぜ、アルジュンがシーク教徒なのか。このテロは、一体何だったのか。文化的・歴史的背景が理解できないと、見えてこないものがあまりに多くて、もったいない。決して、従業員の英雄奇譚で終わらせる映画ではないし、ましてやホテルへの忠誠を描く美談ではないと思う。
この映画を通して、一つ気付いたことがある。アメリカはドローンという兵器で、アメリカにいながら、「朝出勤して、殺して、夕方、妻子の待つ温かい家庭に戻る」という戦い方を発明したと言われるが、テロの若者もドローンであるということ。攻撃の主体は祖国にいながら、危険を冒さず携帯電話で指示を与え、攻撃をしかける。最貧国・最貧組織における、若者という最弱者がドローンとなる。戦いは、いつの時代も、集団の強者が弱者をして相手の弱者と殺し合わせる構図だ。このテロを計画実行させた組織やそのリーダーは、ステイタスを上げる結果につながったのだろうか。
もし、日本周辺に最貧国があったなら、きっと日本もテロの標的になっているだろう。歴史と経済格差がテロの温床だから。隣国とけんかをしても、何も良いことはない、と改めて思う。そして世界の混沌を思う。
勇気と冷静さと知恵
世界を繋ぐのは恐怖でなく優しさと敬意
2008年に発生したムンバイ同時多発テロを、
テロリストに占拠された高級ホテル、
『タージマハル・ホテル』での脱出劇
を中心に描いたサスペンス作。
開幕から終幕までとにかく物凄い緊張感の作品。
実際のテロ事件を扱っているため精神的にも重い。
...
実行犯たちがボートで上陸する冒頭からすでに
不穏な空気が漂っている。そこから駅での銃乱射、
繁華街での大混乱、ホテルでの立て籠もりから生存者
が脱出を遂げるラストまで、気を抜く暇は殆ど無い。
実行犯は未成年の少年ばかり。
だが、その淡々とした犯行の様子には背筋が凍る。
「奴らを人と思うな」という指示役の言葉通り、
実行犯たちは害虫駆除か何かのように無表情
のまま、逃げ惑う人々へ銃弾を浴びせていく。
ルームサービスのふりやロビーからの電話で
警戒を解かせるなど、巡らせてくる知恵も残忍だ。
にこやかに恋人や友人と会話をしていた数秒後に
周囲の人々が手投げ弾や銃弾で惨殺されるという
状況では、誰だって冷静などではいられない。
状況も理解できないままに人々がムンバイの街を
当てもなく逃げ惑う様子がゾッとするほどリアル。
狭く明るいホテルに舞台を移してからは益々緊張感
が高まり、廊下に出たり物陰から覗いたりといった
小さなアクションや微かな呼吸音すら恐ろしくなる。
...
そんな未曾有の恐怖に晒されてもなお、宿泊客を
1人でも多く救おうと居残り続けた従業員たち。
料理長オベロイが見せる毅然とした姿や
宿泊客への気遣い。どんな状況でも決して
焦らず怒らないアルジュンの優しさと勇気。
一刻も早く家族のもとへ戻りたいだろうに――そう
することも出来たのに――彼らは逃げ出さなかった。
それは単なる義務感だけではなかったと思う。
持って生まれた善良さだけでもなかったと思う。
宿泊客をもてなす為、様々な国籍のゲスト
ひとりひとりを理解しようと日頃から
努めていた彼らにとって、宿泊客の人々は
簡単に見捨てられるような他人ではなく
自分と同じく家族もいれば人生もある、
隣人のような存在だったんじゃないか。
家族を案じ続ける宿泊客たちの姿も印象的だ。
無謀ではあったが、家族を救うために単身
ホテルを駆け巡るデヴィッド。夫を想い、
泣きながら唄い続ける妻ザーラ。軽薄な男と
思いきや意外な男気を見せるロシア人ワシリー。
...
テロ実行犯たちの描写もしっかり。
残忍な彼らに完全に同情するのは僕には無理だが、
本作は彼らを単なる殺人鬼として描いてはいない。
テロ実行犯のひとり、イムラン。
足を撃たれた痛みにのたうち、家族に報酬が
支払われたかを心配し、父との電話で泣きじゃくる彼。
実際の報道を調べてみると、
ムンバイ同時多発テロの実行犯はパキスタン
の中でも特に貧しい地域の出身だったらしい。
貧しいが故、家族を養える大金に飛びつく。
貧しいが故、「自分達が困窮するこの状況
を生み出した者は誰なのか」と怒りを抱く。
顔を見せない指示役は、そんな彼らの
背中を少し押してやればいいだけだ。
"敵は我らの利益をむさぼる強欲な外国人どもだ、
我らの神の教えに反する強欲な異教徒どもだ。
彼らを殺せばお前もお前の家族も救われる。
神の栄光と家族の安寧を手に入れられる。"
だが当たり前の話、人を殺せば恨まれる。
恨みは報復につながり、それが新たな恨みを生む。
どちらかが根絶やしになるまで続く報復など不毛だし、
おまけに彼らのように世界中から恨みを買われる
ような真似は孤立を深めるばかりではと僕は思う。
...
人と人の心を隔てるのは、
国籍でも人種でもなく、互いへの無理解だ。
イムランの取り乱した姿を思い出す。
「奴らを人と思うな」と叩き込まれた彼が
動揺を見せたのは、ザーラの祈りの唄声に
『彼女もムスリムだ、自分と同じ人間だ』と、
それまでの教えを激しく揺さぶられたからだ。
アルジュンの真摯な姿を思い出す。
「ターバンと髭が怖い」と彼を突き放す婦人に対し、
彼は怒りを見せることも無く、自分のその身なりが
いかに自分にとって大切な物なのかを滔々と語った。
そして、それでもあなたが怖いのであれば、私は
あなたのためにそれらを取り除くと頭を下げた。
相手に自分の文化と心を理解してもらう努力。
そして同じ人間として相手に敬意を払う心。
そうして初めてお互いを、同じ人間と認め合える。
世界を繋ぐのはその粘り強い優しさだと思う。
...
最後に流れる『タージマハル・ホテル』での式典の映像。
「世界中がお前達を見ている」と、顔の見えない
テロの指示役はことあるごとに語っていたが、
世界が本当に見て、憧れて、語り継いでゆくのは、
人を殺す英雄よりも人を救う英雄の方だと言いたい。
安全圏からイスラムの大義とテレビリモコンを
振りかざす指示役には怒りが込み上げるが……
あの指示役もやはり、家族・民族・自身の宗教が
踏みにじられる怒りに駆られているのかもしれない。
きっととてつもなく怒っているのかもしれない。
だけどさ、銃や火薬を買って、何の罪もない少年達
の命を買って、彼らを殺人機械に教育するだけの
金があるなら、自分達の窮状や諸外国から受ける
不平等を世界に理解してもらための情報発信に
使った方がよっぽど効果的じゃないのか?
彼らに恨まれる側の僕らももっと、彼らの現状に
アンテナを向ける努力をしていかなければとも思うが。
窒息しそうなほどのサスペンスと同時に、
残忍なテロを生み出す今の世の中の悲しさ、
人間の尊厳や相互理解の美しさを感じさせる
素晴らしい作品だったと思います。4.5判定で。
<2019.09.28鑑賞>
.
.
.
.
余談:
先週からチマチマ書き進めていた本レビューと
昨晩書き上げた『ジョーカー』のレビュー、
どちらも激重な映画で気持ちがしんどい……。
無邪気で明るい映画が観たい……。
ホテルマンの誇り
息もつけぬ2時間半
2008年の事件だというが私も同伴者もこの事件を知らなかった。
ムンバイが一夜にして戦場と化し、誰が犯人かも分からぬまま特殊部隊の到着に時間がかかり、超一流ホテルが占領され、おびただしい人数が倒れていく様はあまりに残酷で臨場感があった。
無駄なBGMなどは一切なく、淡々とリアルを描いていく。
冒頭から息つく暇もなくそこかしこで銃が乱射され、人が倒れていくりあるパニック映画
12人?のテロリスト達はいずれもまだ少年であり、彼らの視点からも描くことで絶対懲悪になっていないところが良かった。恐らくISだが首謀者は未だに捕まっておらず、反抗中も悲鳴が聞きたいから電話を切るなとほざき少年達の最期までその通話は上がったままだった
ところに残虐性を感じる。
富裕層の人間を生け捕り人質としてころがしている部屋に怪我をした犯人の1人が見張りでいた。
一人一人殺して行き、最後に残った女がイスラム教の呪文を唱えた時彼の心が揺れたのが見えた。
耳元では殺せと囁くボス
イスラム教以外人ではないと教えられ訓練されてきたのに目の前の女はイスラム語を唱えている。
テロをした暁には家族に多額の報酬を払ってやると約束していたのにまだ入金されてすらいない
なぜ?自分のしていることは間違っているのか?
赤子を連れた財閥夫婦は恐らくフィクションだろうが少年の心を揺らがすのに必要だったのだろう。
どこを取っても残酷で目を背けたくなる映画だったがこういったことが現実に起こったということ、救いようのない状況で人と人とが助け合い、自分の命より客の命を優先して亡くなったホテル従業員の方々など、ひたむきに生きようとする人間の本性を見た気がした。
素晴らしい映画だった
辛い
わー!とか、うー!とか唸りたくなります。
泣きたくなるし(というか映画館で号泣だし、煩いし。私)考えさせられる映画でした。
元々イスラム教徒のお姉さん、彼女が存命だったから明かされることもあったんだなぁと。
えーっと、何を聞いても辛い。
うわーってなります。 別に彼らの味方をするとかじゃないけど、それこそ、洗脳されて実行していた少年たちは多分正直使い捨ての駒だったんだろう。その中で、テロ実行中に家族に電話するシーンがあったんだけど、本当に本当に彼らの味方をするわけではないんだけど、彼らには彼らの正義があったんだろうなと。この行為を肯定するつもりはないけど、トイレがウォシュレットで驚くとか、今私たちも当たり前のことが、未来の話のように語られているシーンを観て、おもうところはありますよね。と。
正直、そういう当時のうやっともやっとかついろいろな感情を持った様子を、それを伝えてくれた、イスラム教徒のお金持ちのお姉さん。
結局ご主人殺されたし、守ってくれた偉そうな(実際偉いおじさん)や、人質たちを見張る彼の発言行動なども、ご存命の方の当時の記憶とかあるんだなと思うと辛い。
正直、多分実行犯の彼ら。少年たち。家にお金もらえる。あいつら敵だしおっけーっとか言われて実行したのかな。
え、だって彼も辛いよ。家族のためにとか。
本当にこういう世の中よくない。
正直、なんで今のこの世にそういうことが起きるのだろうとおもうと、辛いです。
でも新興国はいまだにそういう考えの方も多いし、安全だと、そりゃ誤解するよね。
ニューデリーには特殊部隊いるけど、ムンバイには居ないから放置とか、知らんしそんなの、なってみて、マジか!そうなの?バカなの?頭大丈夫?って思うのは、何故か金を払ってる市民なんだよね。世知辛い。
や、特殊訓令積んでない人が言っても無駄だしわかるけど、や、でもそういうことでもないし、辛い。
15:17パリ行きは同じ実話を元にしてても、正直見所ないしよーわからんな感じでしたが、ムンバイは要所要所辛い。
逃げる事はがわるいわけじゃないけど、逃げた人、それを見守る料理長。
お客さまを売れなくて殺されるフロント従業員のお姉さんら,当時の誇りを持って働いてた方に敬意を称します。
ありがとうございました。
緊迫感半端ない
恐怖の時間を目撃
123分の上映時間があっという間。それくらい無駄のないストーリー展開、緊張とスリルに満ちた場面の連続。スクリーンに釘付けだった。
宿泊客たち、そして彼らを守ろうと決意するホテルマンたちの行動にスポットを当て、一応、テロリストの少年たちの止ん事無き事情にも触れつつ、でも許されることのない行為の行く末、恐ろしい時間をスクリーンを通じて共有させられた。
様々な国の宿泊客数十人を一堂に集めた状態で、それを統率することなんてほぼ不可能。それぞれがそれぞれの考え方を持っているし、優れた指揮者がいるわけでもなく、ホテルのスタッフの言うことについて、自分の方が正しい、自分の思うように行動したい、そういう考えを持つ人は当然出てくる。勝手な行動は見ていて歯がゆくもやむを得ない。が、それゆえ危険にさらされるリスクも。
直ちに救出される可能性も薄く希望も持てない、困難極まる状況下でも決して諦めることなく宿泊客を守ろうとするホテルマンたちの心には胸を打たれる。
それほど昔ではない2008年。インドで実際にあったこの事件は記憶になかったが、本当に恐ろしい映像体験をした。最後は涙溢れて止まらない。
悲劇すぎるが過度なヒーロー劇でなくとても響く
ものすごい緊張感
全257件中、161~180件目を表示