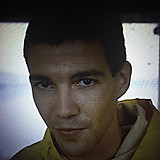赤い闇 スターリンの冷たい大地でのレビュー・感想・評価
全70件中、21~40件目を表示
恐ろしい国…
世界恐慌の中、景気が良いソ連を探るべく、単身潜り込む英国人記者ジョーンズ。同様に探った記者仲間は殺された。鍵であるのがウクライナの地と聞くと、政府高官を騙しながらも向かう精神はまさに命懸けのジャーナリズムだが、彼がその地で見たものは人為的飢饉=ホロモドールだった。強制労働で、穀物を次から次へとモスクワ行きのトラックに乗せる人々。列車の中で捨てたみかんの皮に群がる人々、兄の死骸に手を付けてしまう痩せ細った子供たち、彼自身もソ連に追われ、木の皮を食べ、飢えを凌ぐ。死体もその辺に転がっている。やがて、仲間6人と共に捕らえられるが、公言しないことを条件に彼だけ解放される。それは仲間が人質ということでもあった。紆余曲折あり、報じるも権力者によりフェイクニュースとされる。また、ここでも揺るぎない信念のもと、ライバル社に直談判し、遂に国家による虐殺を告発する。ヴァネッサ・カービーとの多少のロマンスなどの脚色はあるが、実話だけに全体的に淡々としていた。本人はその後殺されたとエンドロールではあったが、記者魂とはまさに彼のためにある言葉だ。しかし、あの国は今も昔も怖い国だ。
史実の重さと、カタルシスの大切さ
第二次大戦前のソ連の惨状を目の当たりにする外交補佐官の物語。
史実を基に創られた映画のようです。
重たく残酷な歴史を、しっかりとした演出で再現したドラマです。
ウクライナの描写が秀逸です。絢爛煌びやかなモスクワ。それに対して、ウクライナは一転してモノトーン。降り積もる雪、荒廃した家屋、生気を失った顔・・・汽車の中で唯一色彩を宿した蜜柑のオレンジ色が印象的です。
そして、幼い姉弟・・・実際に起こり得るような状況だったのでしょうね。
現地女性記者とのロマンス、尊敬する敏腕記者との関係、これらのサイドストーリーもしかっりとして好感が持てます。
非情に完成度の高い作品だと思いますが、映画としてみると、カタルシスを感じることが出来ないのが残念。史実なので仕方がないのですが、モヤモヤな気持ちが残ってしまいました。
巨大な力には勝てないのか😣
ヒトラーに取材経験のあるジョーンズは、スターリンにも取材したいとソ連に向かうが頼りにしていたジャーナリストの友人は強盗に襲われて死んでしまう。きっと強盗ではなく殺されたんだろう。ホテルにも2泊しか泊まれなかったりと圧力をかけられる。政府に取り込まれたアメリカの記者はジョーンズに取材を辞めさせようと酒と美女そしてアヘンを(男も)勧めるが、そんな誘惑にはのらず、仕事ひと筋。
なんとかウクライナ行きの汽車に乗り、北へ向かうのだが、、、人々の様子に驚く。汽車を降り、逃げ延びた村での地獄のような生活。道端に死体が転がり、それを片付けるリヤカー、母親の死体の横で泣き続ける赤ちゃんもまるでゴミのようにリヤカーに放る。歌を歌ってくれる子供達をカメラに収めようとすると、その隙をついて子供達はジョーンズの荷物を奪う。わずかながらのスープを分けてくれた兄妹、スープの中身は、、、悲惨な状況が観ていてとてもつらい。
なんとか事実を記事にしたいジョーンズだが、6人の人質となった人達のことを考えて諦める。しばらくして漸く記事を出す事ができたが、最後の解説で30歳を前にして強盗に襲われて死亡したとのこと。消されてしまったんだろう。正義を暴けば命はない。悪には勝てないのか、、、。
真のジャーナリストのあるべき姿。
ポーランド・イギリス・ウクライナ合作なのが頷ける内容でした。実話を...
スターリン政権下の内幕映画は珍しい
第二次世界大戦前後の時代は本当に映画化されるネタが無尽蔵。ついに旧ソ連時代のスターリン政権のことが映画で観れると思ってたら、スターリンは出てこない。
でも、その残酷非道ぶりは凄まじかったことを窺わせる内容だった。
ナチスに絡む映画は映画の歴史が始まって以来山ほど世に出続けている。そもそもなぜナチスばかり?やっぱり戦後にドイツが民主化されて徹底的に悲惨な過去を反省したからかな。ナチスの悲惨な歴史を映画にすることはドイツではほとんど誰も否定しないからかな。それもあるかもしれないけど、本質的にはユダヤ人がエンタメ界で活躍していることの方が大きい。ナチス絡みの映画は本当に物凄い数があって一大ジャンルにまとめられるくらいの規模だと思う。
それに比べて、旧ソ連、旧大日本帝国などのやばい時代のやばい政権のやばい出来事はネタが数え切れないほどあるはずだが…
ドイツが自国で映画にしないのであれば、他国が映画にするという流れがナチスに関連する映画にはある。そこが大きく違う。ドイツやドイツに迫害された国のたくさんのユダヤ人がいろんな国に亡命して、その子孫が映画監督や映画業界の重役になるという流れができた。とくに移民の国アメリカ。スピルバーグやポランスキー。ポランスキーはその後ある事件でアメリカから出てますが。バーホーベンはアメリカでSFのナチ映画を撮り、コケてヨーロッパに帰り、またナチ映画撮りました。タランティーノも撮りました。あの人もこの人も。
ディアスポラの歴史とユダヤ教という世界宗教をもったユダヤ人は世界中に相互扶助のネットワークをもっているから、ユダヤ人迫害の風潮が盛り上がるようなことがあれば、ある程度裕福な人たちは他国へ逃げる場所があったかもしれない。そうした人たちが、エンタメ界で活躍したからナチやその時代は映画の定番ネタになった。
一方、スターリン政権下のロシア人やウクライナ人は、ユダヤ人のように自分たちの国をもたず(当時は)、いろんな国に亡命するのは当たり前なのと違って、生まれ育った土地を離れる気持ちもお金もないし行く先もない。自国で生き延びるのに精一杯だったと思う。
自国で生き残ってその子孫がエンタメ界で活躍するようになったとしても、あの時代と今が地続きのままだから到底スターリン時代がネタにされて映画にされる機会は少なくなる。だからこの作品のようにイギリス人ジャーナリストの目線という立て付けでしか映画にできないのかもしれない。そもそもロシア映画はまともに日本に輸入されてこないので本当のところはわからないが…
そして、日本はというと、民主化されてもドイツのようにあの時代をネタにした映画はなかなか作られない。自国の悲惨な恥の歴史をわざわざ映画にする必要性を感じないからだろうか?そもそもあの時代のことがどれだけ広く一般的に反省され知られているのか?ドイツやオーストリアなどに住み、ナチスドイツに迫害されたユダヤ人は、ドイツやオーストリアを自国だという意識はなく、冷静に徹底してドイツやオーストリアの犯した戦争犯罪を批判できたと思うし、だからこそたくさん映画が作られるようになったと思うが、それが日本人やロシア人やウクライナ人にはそれができなかったということが、その時代の映画がほとんど作られない大きな理由だと思う。
エンタメの根源にあるのは、怖いもの観たさであるからこれはまだまだ本当はやれるはず。『スパイの妻』まだ観てないけど、意識してあの時代をたくさん映画にしてほしいと願うばかりだ。
歴史の暗部に光を当てた作品
ネットで作品の広告を観て興味を持ち映画館へ。自分は元々ノンフィクション系の作品が好きだが、これはまさにその王道。1917年に革命が起き、翌年にソビエト社会主義連邦が成立して10数年後から物語は始まる。壮大な20世紀の社会実験が失敗に終わったことは前世紀でご存知の通りだが、実は黎明期には西側(日本含む)にもソ連を見倣う声があった。折しもニューヨークのウォール街に端を発する大恐慌が世界経済を破壊している最中、ソ連は鉱工業・農業生産共に大躍進を遂げ、日本や米欧を凌駕する急成長を見せた。その秘密を探る為、英国人ジャーナリスト・ジョーンズが単身ソ連へ向かう。そこで秘密はウクライナにあることを知り、そこへ向かう列車から急遽途中下車し、一面冬の銀世界へ降り立つが、そこで目の当たりにしたものは…
ウクライナのホロドモール(飢餓輸出)に関しては日本ではあまり注目されることはないが、特に西側諸国に関してはソ連による「ジェノサイド」であると認識されている。主に戦争映画ではノルマンディー上陸作戦やスターリングラードの戦い、ミッドウェー海戦などが取り上げられるが、この作品は戦間期に焦点を当てている点においても評価できる。途中、英国作家ジョージ・オーウェルの「動物農場」の節が登場するが、ソ連に対する最大の皮肉になっている。
もう少し
今も変わらない話
なんか観るもんないかなと上映スケジュール漁ってるとこに
たまたま見つけて観賞
感想としては
結構淡白な内容と途中で監督変わったのか
と思うほどの不安定な描写スタイルに戸惑うも
扱うテーマは今も変わらない事過ぎて思うところは
ある映画でした
第二次大戦前の英国
政権奪取直後のヒトラーを取材した事もある
ウェールズ出身の外交顧問ガレス・ジョーンズは
世界恐慌下でも繁栄を謳うソ連のスターリンの国家運営に
疑いを持ち首相に訴えますが相手にされず
予算削減で外交顧問の任も解かれフリーランスに
なったところでソ連のことを調べはじめます
そこでヒトラーの時に世話になった記者ポールが
ちょうど今モスクワにおり会いに行きますが
その記者に会えと言われたニューヨークタイムズの
ピュリッツァー賞も取ったデュランティから
ポールは強盗に殺されたと聞き愕然とします
ガレスはヒトラーの時のようにスターリンに
取材したいと言います鼻で笑われ
1週間取ったはずのモスクワの豪華ホテルは
勝手に2泊にされているなど歓迎ムードでなく
ディランティに言われ参加した記者のパーティは
麻薬も溢れる堕落した世界でガレスは呆然とします
モスクワは確かに大都会で賑やかにやっていますが
相変わらず理由がわからないガレスはポールの同僚
エイダに委細を訪ねるとポールも同様の取材をして
殺されたのだと真相を打ち明けウクライナに
行こうとしていたと伝えます
実は母がウクライナ出身のガレスは監視をかいくぐり
ウクライナ行きの列車に乗りますがそこには食べ物を
見るだけで目の色を変える飢えた人々しかいませんでした
結局ソ連の繁栄の正体は近隣の軍事的支配地域からの
ウルトラ搾取社会でウクライナの人々は作物を全て
ソ連に奪われ何百万人と餓死者が出ていたのでした
このガレスが結構抜けた男でして
不用意にソ連のことを訪ねてはスパイとされ逃げ回ったり
○○の肉を食べちゃったときにすぐ気が付かなかったり
そもそもスターリンにすぐ取材出来ると思っていたり
コイツ大丈夫かという描写が目立ち移入しづらかったです
真実を知りたいんだろうけどポールよりいつ死んでも
おかしく無さそうです
結局ガレスはウクライナ潜入でソ連側に捕まり
実態を口外しない引換にロンドンに返されますが
「真実を公表する義務と知る権利」を守るために
結局新聞にソ連の真実を公表するのでした
観てて思ったのは
今でもソ連みたいな国はあるし
マスコミが恣意的に内容を操作してる現実は
なんら変わっていない現実に滅入るばかりです
共産主義は人民の平等と共栄を謳いますが
そんなものはどだい無理で外面ばかりよくして
中身は国民の犠牲をなんとも思わない社会です
ですが世界恐慌によって資本主義経済も大して上手く
回っていないところも現代とまるで変わってません
自助公助のバランスを取り持つのは結局
共産主義でも資本主義でも難し現実に人類社会は
未だに直面しているのです
映画としては話の展開とかテンポが不安定で
どこまでやるのかダラダラした感じで進んだり
不満もありましたがキャストは総じて雰囲気があり
ワイスピのスーパーコンボでも印象的だった
ヴァネッサ・カービーも存在感ある演技でした
あまり知られる事のなかったウクライナの悲劇
知る機会になって良いと思います
勇気ある主人公の行動は世の中にどのような影響をもたらしたんだろうか。
ウクライナにおける人為的な飢餓の事実を世に公表した勇気ある主人公の行動は、どのような影響を世の中にもたらしたんだろうかと、映画終了後に思った。
スターリンが統治方針を変更するわけないし、旧ソ連以外の国からは内政問題と片付けられただけじゃないのかなと思ったりする。
結局のところ、ジョージオーウェルの物語のきっかけになったに過ぎないとしたら、それは悲しいこと。
そして、飢饉の惨禍を隠蔽したピュリッツァー賞受賞記者が名誉を剥奪されることがないのも恥ずべきこと。
ちなみに、冒頭の豚の描写はジョージオーウェルの「動物農場」からだろうけど、この人についてうまく説明されていないから、知らないとナニコレ?となる。
主人公も最後は〇〇されちゃうし、後味はあまりよくない
ウ・ク・ラ・イ・ナ に行っちゃイヤ 💋
ホロドモールはウクライナ語で飢餓による殺害という意味。ジェノサイドということばを考えるきっかけに。
英国首相ロイド・ジョージの元私設秘書(外交顧問)であった若い優秀なジャーナリスト、ガレス・ジョーンズの実話に基づいた映画。第二次世界大戦前の1933年のお話。彼はヒトラーに独占インタビューをした経験ももつ。世界的恐慌のさなかにあって、むしろ羽振りがいい(ルーブル高維持)ソ連。ドイツが再び戦争を仕掛けてくると危惧するイギリスではソ連と同盟を組んだ方が得策であると意見するものも出てくる。急激な近代化を推し進めたスターリンにもインタビューしたいとジョーンズはニューヨークタイムズのモスクワ支局長のピューリッツァー賞受賞経験のある大物記者ウォルター・デュランティーを頼って、単身モスクワに乗り込む。しかし、デュランティーは完全にスターリンに蹂躙されていた。ジョーンズがモスクワに立つ前に電話で連絡を取った友人の記者ポール・グレブは背中に4発もの銃弾を浴びて死んでいた。グレブはジョーンズと同様にソ連繁栄の秘密を取材していた。ジョーンズはデュランティーの部下のエイダ・ブルックス(ヴァネッサ・カービー)に探りを入れる。ソ連当局から日常的に監視されているエイダの口は重かったが、ジョーンズのひたむきさにこころ動かされたエイダはジョーンズに「ウ・ク・ラ・イ・ナ」とつぶやく。ウクライナ行きの汽車に乗り込んだジョーンズは彼の行動を監視する男をうまく巻いて、途中で貨物列車に滑り込む。しかし、貨物列車には異常なほど飢えた人たちがひしめきあっていた。ジョーンズがミカンをリュックから出すと異様な視線を向けてくる。ジョーンズが急いでミカンを食べ、皮を捨てると奪い合って皮を食べた。ジョーンズの母親(元・英語教師)はかつてウクライナのスターリノでウェールズ出身の実業家の孫の家庭教師をして暮らしていた経験をもつ。母との繋がりのあるスターリノ駅で降りたジョーンズはモスクワ行きの穀物を貨車に乗せる現場に出くわす。銃を持った軍人が、痩せて力の出ない民間人に重い穀物の袋を運搬させている。ジョーンズも手伝わされるが、カメラのシャッターを切らずにいられなくなったジョーンズはスパイとみなされ、発砲される。奇跡的に追跡を逃れて、凍てつく雪原をさまよい、ゴーストタウンと化した村にたどり着く。そこは極度の飢えに苦しむ生地獄だった。飢えた子供たちが歌う童謡の歌詞がすごく気持ち悪くて怖い。ジョーンズもそのうち、木の皮を食べる。母のかつて暮らした家の幻覚を見る場面に引き続き、もっともショッキングなシーンが。
主人公のガレス・ジョーンズは英国、米国の新聞にウクライナでの見聞をリリースする。すぐさま、ウォルター・デュランティーによりニューヨークタイムズでジョーンズの記事は否定される。負けていないジョーンズはニューヨークタイムズに辛辣な反論記事を展開する。英国、米国の様々な新聞に飢饉に対する記事を載せ続けるがソ連外務大臣から英国首相のロイド・ジョージに向けてジョーンズがソ連に二度と入国させない旨の通達が送られる。ロイドは「英国の経済が破綻寸前の時に勝手が過ぎる。君は一線を越えた。」と激怒したという。1935年、30歳の誕生日の前日、29歳でジョーンズは3発の銃弾を浴びて何者かによって殺されてしまう。
一刻でも早く飢饉に苦しむ人々を救いたいという彼の信念は打算で動くものたちにとっては脅威なのだ。彼の運命は実に悲しく、絶望的。ジャーナリストにはその正義が強いほど自己犠牲がつきまとう。正義の脆弱さを補うにはジャーナリストたちの結束が必要だ。ピューリッツァー賞受賞記者に騙されてはいけない。消されかけた功績に焦点を当てたこの映画は、いかに平穏な時代に、恐ろしい怪物がいつまた我々の生活、生命を脅かすかも知れないことへの警鐘であり、この、かりそめの平穏は偉人たちの屍の上に築かれたものであることを訴えている。
ジェノサイドもその認定は主権国家ごとに違ってくるという現実。同盟国どうしは認めない。第二次世界大戦以前のジェノサイドは語られないタブー。
ガレス・ジョーンズ役のジェームス・ノートンはストーリーオブマイライフ/わたしの若草物語に出ていたらしいが、印象が弱い。
エイダ役のヴァネッサ・カービーはワイルド・スピード、ミッション・インポシッブルなどのハリウッド大作に出ているので、ちょっとバランスが悪い感じ。ヴァネッサ・カービーのプロフィール写真が隣の気の強い奥さんにちょっと似ていて、個人的には萌えませんでしたけど、監督、撮影監督、音楽監督の意気込みは大変評価します❗
ウクライナは未だに世界最貧困
全70件中、21~40件目を表示