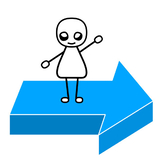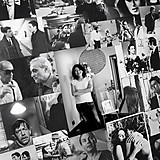風をつかまえた少年のレビュー・感想・評価
全67件中、41~60件目を表示
必要は発明の母
William Kamkwamba本人の執筆による原作を基にした作品。
彼の出身国Malawiの貧しい村Wimbeで安定した農業を営むために、ほぼ独学で風車を作ったという実話。
これを可能にしたのは、ごく短期間でも学校に通えたこと、図書室でこっそり本を借りれたこと…。
学校に行けるのは授業料を払える家の子のみ。延滞したら即刻退学という厳格ぶり。だから生徒も教師も見る見る居なくなってしまうという状況に、無償教育の貴重さを実感しました。教員の給料確保も大事なのは分かりますが、校長先生の言い方がきつ過ぎて言葉を失います。
学校に来ても学習意欲のない生徒を多く抱えている教師が観たら歯がゆいでしょう。
照明もラジオも、何なら風力原動機も、
必要なら作ってしまえと。
Williamの賢い所は、足りない物を得るにはどうしたら良いか、問題点を直視し現実的に解決策を探る能力でした。
Williamの知的好奇心を阻む教師、経済状況、生活環境を何とか乗り越えて風車製作に辿り着きますが、作品全体としてみると国民/村人の悲惨な暮らしぶりに重点が置かれており、風車自体は作り出したらいとも簡単に成功するので、重心を少しずらした方がもっと感動したように思います。
Williamが再利用した部品のひとつに消えかかった日本語表記があり、巡り巡ってこんなにも遠い国で役立っているのかと感慨深いものがありました。
油がもったいないから夜は勉強できないとか、寂れた古本屋のような図書室が知識の宝庫だとか、モノが溢れるほど豊富な日本では一昔前のような話です。駅前の放置自転車も、回収される古本も、不法投棄される電化製品も、こんな物でも良ければと全て差し上げたくなります。当時のWilliamが日本を知ったら、宝の山があちらこちらにあるような国です。
だからと言って、アフリカの国の話ねぇ…と、あまり他人事でもありません。世界149ヶ国の中でMalawiと日本の共通点は、男女平等度が低いこと…。世界経済フォーラム (WEF) が発表した”Global Gender Gap Report 2018”によれば、日本110位、Malawi112位です。
***
黒人の肌は紫外線に強い為、皺が出来にくい上に目立たないので、見た目年齢不詳になりがち。白髪の有無や体格で検討を付ける感じです(^^)。
Williamの母Agnes役が、「市場一の美人」だけあって綺麗な方でした。
大統領夫人の頭巾がミッキーマウスの耳みたいでした。
“Democracy is just like imported cassava. It rots quickly.”
観てよかったなぁ
映画館から出てスマホの電源をオンにしたとき、さっきまでスクリーン上であんなに切実だったことと全くかけ離れた話題が溢れていてちょっとクラクラした。
これがたかが20年ほど前の話だなんて…。
涙も枯れる苦難の数々、瀕死の状況にある集団心理の危うさ…かなり迫力ある描かれ方でしたが、過剰さはなく青少年にも飲み込める絶妙な匙加減が良かったと思います。
正直いくらでも悲劇色を濃くすることはできるので…。(幼い妹さんが成長して良かったし、悲しいけど相棒の犬が自然に倒れたのも優しさかも)
ライオン・キング(2019)のヴィラン、スカーの声を当てたキウェテル・イジョフォーさんが監督・脚本・出演。ここでも情けなさ愚かさもあり、そして憎めない大人の男を演じています。
超実写版ライオン・キングからはアフリカの自然の偉大さや命の尊さを感じられなかったのですが、裏表でこちらの作品に触れることができて縁があったなぁと満足しています。
全くの余談ですが、主人公ウィリアムを演じた少年のお名前がシンバなんてミラクルw
監督は蠅の羽音にこだわりがあったのでしょうか…妙に印象に残っています。
ラストの明るい光で吹き飛ばしきれないほど作品を覆う闇は濃かったですが、ライオン・キング、天気の子と本作を並べて観ることができた2019年の夏は幸運だったなと感じています。
どこの国も男ってやつは
面白いが
ぜひ、中高生に見てほしい。
学が人生を変える
一家族を焦点としながらも一国を広角に捉えてある
こまかくみればツッコミどころ多いが、アフリカの大地が、そのような見方はそぐわないと言っている。発電を成功させる筋書き自体は実にシンプルである。そこだけを追ってしまうと木を見て森を見ずの類だ。ここには何もないと繰り返し語られる、アフリカのなかでもで貧しい国マラウイ。そのマラウイの一家族の貧しい暮らしを通じて、映し出されるのは、広大で悠久たる大自然、それと対峙する人々の暮らしである。この地の世界のすべて。だからここはアフリカ大陸をわたる風に吹かれているつもりで、骨太な解釈で臨みたい。
ひたすら耕すことで立ち向かう父親。人ひとりの無力さがよく描かれていた。大地の奴隷である。対して、ラストの風車の横でほほ笑む少年。「知識は奴隷にならない人間を生み出す」という名言を、この映画に添えてみたい。
ウイリアム少年の想像力と実行力には拍手だが、もうひとつ大きな力となったものがある。図書館だ。何もないという貧しい村だが、学校があり、学校には図書館が備わっていて、一通りの本が揃っていたということ。蓄えていた知識を活用できていなかったのは教師をはじめ大人たちの不面目だが、学校と図書館を護り継いできたことは殊勲ありだ。
一家族を焦点としながらも一国を広角に捉えてある。気候風土、生活、文化、風習、政治。人間社会の構成要素がほぼ原石の姿で互いとの係わりを描きあっている。
カムクワンバ一家の、ものわかりの悪い父親が、監督も兼ねているキウェテル・イジョフォー。やり場のない苦悩にまみれたやるせなさ、そういったどう演じたらよいのかを伝えようもない役どころを、うまく演じている。さすが監督兼任。さらに調べたら、2013年作のアカデミー作品賞「それでも夜は明ける」で奴隷を主演した俳優さんだった。
創造と工夫で世界は変わる。そこを啓発される。ウイリアム少年の貧しくてもつらくてもどこか豊かさ感じさせる表情もよかった。
題材は良いが前置きが長い
良い話だ。が。
必要は発明の母 を地で行く少年の成長物語
感動する前に悲しすぎる現実に愕然とする
アフリカン ドリーム
ちょっと違うかもしれないけれど、厳しいアフリカの自然に知恵と工夫で立ち向かう、サクセスストーリー。
村や家族という小さな単位での話なので、スケール感は小さいが、その分身近に感じられた。
21世紀になっても干ばつや洪水に苦しめられている、アフリカのある農家。農家といっても、土地を人間が鍬で耕す原始的な農法だ。父親は、貧しいながらも息子を学校に行かせるが、天候のせいで収穫が減り、学費が払えなくなってしまう。実際にあった話とのことなので、こうした事実がつい20年前に存在していることを、改めて認識させられる。
映画ではそれほど悲惨なシーンは無いが、飢饉が起こり、餓死者が出てしまうほどの惨状は、酷い状態だったのだろうと想像できる。人心は荒み出し、一家も窮地に追い込まれる。
現在の状況は、改善されているでしょうか。少し気になりますね。
学習礼賛 若さが世界を変える
異なる文化圏の話は、前半がついつい眠くなってしまう。しかし、風車を作る終盤は軽快で気持ちよかった。
自転車のダイナモ(発電機)ひとつで、ポンプ動かすことができるんだね〜。ダイナモなんて、文明に毎日浸っている我々にとっては、その中のたったひとつの小さなパーツに過ぎない物なのだが。
我々は、かえってひとつひとつのパーツの凄さというか、「力」を忘れてしまっていたり、過小評価していたりするのだろうなぁ。…なんと言っても、実話なので。
印象的だったのは、冒頭と最後に描かれる、この地方の葬式。森の精霊たちが、陽気に踊りながら、死者を迎えに来る姿は、なんだか正しいような気がする。
アニミズム(原始宗教)などと呼ばれるものだが、これが人間の本来の感覚なのではないか。自然とつかず離れずの関係。
一方で、自然の脅威を克服するための科学技術が、村に入ってくる瞬間。本作ではそれが、主人公によって、風力発電による「ポンプでの水の汲み上げ」が稼働する瞬間。
本作の主題は、若さと学びによって、「大人=従来の人たちが、一生懸命やっても克服できない飢饉という大問題」の解決を果たすという、学習礼賛。
その中での葬式の描写は、自然を克服することによって、一体化するよさから少しずつ離れていくことを暗に意識させる象徴だろうか。
理不尽な状況が長い
学校の図書室で一冊の本に出会った少年が、風力発電でポンプを動かし、井戸から水を汲み上げるシステムを作り、干ばつによる飢饉から村を救った2001年の実話を基にした、ベストセラーを映画化。
少年の活躍は最後の15分くらいで、それまでは延々と「いかにこの国は文明程度が低く、貧しいのか」と「この国の政府は堕落して国民を救わない」という描写が続く。
ストレスからの解放が、快感に繋がるとはいえ、約1時間半の理不尽な否定と状況がつらかったな。
しかしわずか18年前に、アフリカの最貧民国は、農業は天候頼みで祈りで雨乞いをするレベルだったのかと思うと、我々はいかに恵まれているかと実感させられる。
この物語が2001年だという事実に驚いた。 むかしむかし、みたいな...
全67件中、41~60件目を表示