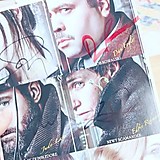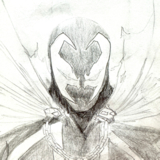グリーンブックのレビュー・感想・評価
全175件中、141~160件目を表示
確かにフィールグッド。だけど実に無頓着。
人種差別の問題があまり身近ではない日本と言う環境でこの映画を見ると「フィールグッド・ムービー」として単純にとても楽しめると思うし、実際私もこの映画を見て確かに気分が良くなるのを感じた。分かりやすくて笑い易い喜劇と、(最終的には)好感の持てる登場人物。ありふれたストーリー展開ながらも、味付けが巧く施されていて、主演俳優二人の演技にも旨味がたっぷりで卒なく美味しい。仮に監督のセクハラ問題が浮上しても、脚本家の過去の差別ツイートが露見しても、主演男優の差別発言があっても、それと作品とは別であると考えるべきだと思うし、少なくとも作品に罪はないと考えるべきだ。ただこの映画を見て、アメリカに住む有色人種(主に黒人)が違和感を覚えても不自然ではないだろうとも思う。この映画は明らかに白人至上主義的で、描かれたのがあくまで白人の目で見た黒人差別に過ぎないからだ。
この映画より前にも、人種問題を扱いながらフィールグッド・ムービーとして成功した作品はあった。「ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜」や「ドリーム」などはその好例だと思う。だから人種問題をフィールグッド・ムービーにすること自体は悪くないし、フィールグッド・ムービーの形式を取ることでより観る者の心に訴えかけることが出来るということもある。ただ「ヘルプ」も「ドリーム」も黒人が受ける差別の現実をしっかりと描写していたし、その深刻さや過酷さも直視されていた。ただこの「グリーンブック」に関しては、白人がわずか二ヶ月ほど黒人と過ごしたほんの僅か垣間見た差別にしか目を向けておらず、それだけで黒人(と同性愛者)の立場や在り方を知ったようなつもりになるのはあまりにも短絡的と言わずにいられない上に、その差別から白人である主人公が救出するという構図で徹底されている無神経さ。人種問題の現実を捉えた作品とは思えない。不条理な差別を目の当たりにしたその時その場でだけ「なんと気の毒に」と同情を覚えるばかりで、人種問題の根幹には興味を示してさえいないのだから。目を閉じれば気分はいいし、何も知らなければ気持ちのいい映画かもしれない。差別されない環境で生きる者が観ればそれこそ”フィールグッド”かもしれない。でも差別される側の立場で考えれば、些か無頓着な内容であることも否めない。
だけれども、だ。フィールグッド・ムービーとしてのツボを的確に押さえているため、見終わった後の感覚は本当に清々しいのだ。うっかり心が温まってしまうのだ。ヴィゴ・モーテンセンの陽気なイタリア系男の演技も、マハーシャラ・アリの気品ある凛とした演技も実に素晴らしくて二人のことを愛してしまう。単純に男二人の友情の物語だと思えばいいではないか、と一瞬思いが過ぎるが、しかしそれは違う。1960年代という時代背景においてあえて「差別主義の白人」と「差別を受ける黒人」を描く物語となれば人種問題は避けて通れないのだから。
とても巧く作られたフィールグッド・ムービーだと思うけれど、同時に欠点が終始目についてしまう。味はとても美味しいけれど有害な添加物たっぷりの食品を口にしたような罪悪感が付きまとう作品だった。
ハックルベリーフィンの冒険??
「黒人との旅」と聞くと真っ先に思い浮かぶのは文学的で有名な「ハックルベリーフィンの冒険。」内容は全く違うけれど、「旅、人種差別」という部分では同じ。だから「ハックルベリーフィンの冒険」を少し意識したのかなと思った。
やはりアカデミー賞作品賞を受賞してるだけあって本当に素晴らしかった。ストーリーも良いが、ドクの奏でるピアノの音から楽しさや怒りがとても伝わってきた。クラブで演奏している時は1番楽しそうだったな。。
また2人の成長の物語でもあって、互いの良いところを吸収し合う。勇気や暴力は負けだということや、諦めないよころ。最後のレストランのシーンでは互いの成長をとても感じた。ドクはいつもだったらあのように粘らないし、いつものトニーだったら金をもらって説得していた。
旅が終わり、トニーが「ニガーはやめろ。」と言った時に周りの皆はトニーがどのような旅をしてきて、どのような変化をしたのか少しは気付いたのだと思う。。だからドクを皆受け入れた。(「あのトニーがこんなことを言うなんて」)みたいな。そう考えると妻のドロレスは最初から最後まで素晴らしい人だなと思った。
最後のドクがトニーの家に来るシーン自分が監督だったらトニーが迎えに行き、そこからトニーの家でクリスマスパーティーに参加し、皆が受け入れるというシナリオにしたと思うけど、考えてみると、あのシーンでドクが自ら来た理由は自分で行動するという成長を表したかった変化を表したかったのでは?と思った。
グリーンブック
グリーンブック見ました。とても素晴らしい映画です。粗野で取っ付きにくそうな用心棒と黒人天才ピアニストのコンサートツアーの旅の道中、二人の全く噛み合わない会話、そして数々の偏見と差別。実話に基づいた作品という事でより一層悔しさや腹立たしさもあり、だからこそそれを乗り越えた後に残る二人の清々しさが感動的でした。見終わった後、とても素敵な気持ちになる、そんな作品でした。
最後のライブシーンはじーんときた。
最強のふたりの逆バージョンのような。アカデミー賞取った直後で気になって鑑賞。
これはいろいろな要素が入りすぎるくらい入っているが、ストーリーは難しくないだけに、その要素1つ1つに考えさせられる。
いくつかの分野で博士号を取り、小さい頃からクラシックピアノを習いプロにまでなった育ちの良いNY育ちのアフリカ系黒人と、
イタリア系アメリカ人で働いていたクラブが改装で2カ月ヒマになったところに、その黒人のドライバーをする話が舞い込む。
ロードムービーというスタイルを取りながら、南下していくごとに黒人差別があからさまに厳しくなっていく。
出演者というおもてなしをするべき立場なのに、黒人というだけでトイレを使わせてもらえない、演奏するレストランで規則だからと食事ができない、という扱いを受ける。
黒人、知的側面、バイORゲイという三重苦を抱えて時には立ち向かい、時にはそれを諦めとして受け入れ、そういう差別に情が深いものの鈍感なドライバーもそれを目の当たりにして感化されて立ち向かう。逆もあり、ジャンクフードの良さ、情の深さにピアニストも影響されていく。
また、イタリア系移民ということで、名前が発音しにくいのをニックネームで名乗ったりとマジョリティな部分も抱えている。
これは誰しも見方・側面によってマジョリティにもなりマイノリティにも成り得ることを示唆している。
❓%の力のレビュー🤘🏼
NASAのマーキュリー計画と人種問題を絡めた映画『ドリーム』と似た安定感のあり過ぎる本作品。
実話に基づく系ですが、結局白人がええモンになるお話だとか、アカデミー賞向け作品だという難癖もあるようですが、確かに正統派過ぎて危なかしさと面白みに欠ける面はありますね(笑えるシーンがあるというのとは別の意味で)。
お話内容は優等生ですが、人種問題の根は深く、皆こうすべきと解っていても完全解決まではまだ月日を要する事なので、まあ日にち薬というか時代薬ですので置いといて(←この先送り態度がイカンのか😓)、、
私がムズムズしたのは、たとえバ-ガ-🍔であれホットドッグであれ🌭バンズの油分ですら~そんなん付いた手でハンドル握るなんて許せ~ん!😝! フライドチキン🍗なんてもう‥異次元の極み〜😫 その手で窓を開けるシーンはあの時代でもパワ-ウインドウのワンプッシュのオ-トモ-ドが付いててまだ良かった🥴ホッ
そんなバレロンガ役は『始まりへの旅』のワイルド教官パパ役の人でしたか、そうでしたか。いつも長旅ご苦労様です。
最後のウェルカムなシーンで、‥ジッと感動しつつも、それまで散々交友を育んでおきながら、ラストで態度を翻して突き放して追い返すというあり得ない鬼畜展開を、つい一瞬チラと (皆がかしこまった冠婚葬祭の場などで、何故だか不意に常軌を逸した奇妙な展開を脳内再生し、独りで勝手にゾワッ!とソワソワする気分を味わうかのように) 想像してしまうのは私だけですかね😗❓
(他の例:心優しき純真な人から心のこもった贈り物🎁を受け取る場面で、そんな気持ちはさらさら無いのに、何故だかそれを本人の目の前で叩き落とす自分と、それで悲しい気持ちになる相手を想像してゾッ😱とするみたいな‥🙄 なんか何の問題もない平和で幸せな状況だとジッとしてられない天邪鬼みたいな小さな虫🦂が心の何処かに潜んでいるのかも🧐
幸せに慣れぬ男の幸せ恐怖症か😅饅頭怖い)
2人の演技が素晴らしい。かなり好きな映画。
【グリーンブック】観てきました。
実話です。1960年代のアメリカ。
著名な黒人ピアニストが南部への演奏旅行にドライバーとして雇ったのがヴィゴ・モーテンセン演じるイタリア系アメリカ人のトニー。粗野で、無学で、腕っぷしが強くて頼りになる。
クリスマスまでの2ヶ月に渡るツアーの道中を描いたロードムービー。
当時のアメリカは知っての通り黒人差別が酷く、特に南部は黒人蔑視が強い(昔アフリカから連れてこられた奴隷がまずは南部特産の綿花畑の作業夫に使われたため)そんな時代。
題名の[グリーンブック]とは、Mr.グリーンが毎年出していた、黒人の使えるホテルや店のガイドブック。
当時はトイレも、乗り物も、ホテルもお店も、黒人の入れない場所があったのですね。
このグリーンブックを頼りに、数々の演奏会場を車で巡りながら、2人の関係性が徐々に変わっていくというストーリーなのですが、その旅途中のエピソードそれぞれがなんとも言えない味わいで。考え方も育ちも全く違う2人は、時にぶつかり、時に笑い、ハプニングや危ない目にも遭いながら切り抜けていく。
実はトニーも最初は黒人を差別する気持ちのあった人。でも、粗暴ながら家族を大切にし、失業していてもマフィアの友人からの仕事は断わるような、信念のある心根の熱い人。
一方ピアニストのシャーリーは、黒人ながらその才能を幼少の頃に見出され、ロシアのレニングラード音楽院で英才教育を受け、幼い頃からプロのピアニストとして生きてきた教養溢れるセレブ。
まさに正反対の2人が、旅の終わりには互いの人生に大きな影響を与え、最高の笑顔になるのは、旅の間の出来事を通して互いの立場なりの心の痛みや苦労を知り、理解し合い、真の友人になれたから。
シャーリーが[あえて黒人差別の激しい南部を選んで演奏会をするということは、彼なりのチャレンジである]ということが次第にわかってきます。
警官、住民、そして時には招いてくれたホストや会場の責任者からも肌の色が違うというだけで不当な扱いを受けたり暴力を受けることがあっても、どんなにつらいことがあっても、決して声を荒らげず、静かに耐える。
彼の唯一の武器、ピアノの才能をもって、彼なりに、世界を変えようとしている。
静かに、ひとり闘っている。
それがわかったとき、涙します。
なんて勇敢な人なんだろうと。
そして、それまでの過去が滲み出た彼の孤独な眼差しに引き込まれながら、対照的なトニーの明るさ、力強さに私たちも一緒に包まれる感覚。
全力でシャーリーを守るトニーの姿に、胸が熱くなる。
雇い主だからじゃない。お給料もらってるからじゃない。
大切な友達だから。それだけ。
観終わった後、すごく余韻が残る映画です。
色んなことがあった2ヶ月間、いくつかのシーンが思い浮かぶ(私は特に手紙の書き方を教えるエピソードと、酒場で即効演奏するシーンが大好き!)。
今も、トニーの笑い声が聞こえる。
シャーリーの美しいピアノの調べが聞こえる。
人間の尊厳、本当の勇気。友情。
ラスト近く、シャーリーがやっと、心からの笑顔になれたのがわかります。
あったかい気持ちになる、本当に素敵な映画。
超おすすめ✨
白人でも黒人でもない、人間でもない!
2人の可笑しなやり取りに思わず笑ってしまったりしながら、最後にはジーンとくる、良い映画だった。
黒人ジャズピアニストとイタリア系白人の運転手兼用心棒。肌の色も違えば、性格も全く正反対に見える2人。
共通点が少ないような2人だが、最後には心通わせる親友になってしまうということは、どこかシンクロする部分があったのだろう。あるいは、自分にないものを、相手に見出したのだろうか?次第にお互いがお互いを尊重し始め、学び始める…。
タイトルは、ドクタ・シャーリーの悲痛な叫びである。
はぁ。
見終わったあとに、感想やら言葉やらを喋ったら自分の中の気持ちが全部出て行ってしまうんじゃないかと思ってしばらく息さえも慎重にしていた。
黒人差別を描いている映画に対して、「よかった」「感動した」なんて感想は不謹慎なんじゃないかと思いながら、なかなかぴったりな言葉は浮かんでこなかった。
海外の人は差別的に思っていた相手の素晴らしい面、才能、実力などを見せられた瞬間、コロッとその人を受け入れて仲間にする事が出来る。日本人にはないところだと思う。本当に素晴らしい。
少しずつ、ゆっくり個々を認め合い、寄りそう二人。信頼関係というのは一瞬では成り立たないということを教えてくれる。
一回目パトカーに捕まり拘留される。
二回目もまた捕まると思ったら、今度は助けてくれる。人生はそんな悪いことばかりではないと教えてくれる。
傑作
相当おもしろい。
ドクとトニーがうまいのがなにより。
最後の警官に止められるくだりにはやられた。
勇気と信念をもてば世界を変えられることを教えられた。
ドクとトニーの心の描写も美しい。
コメディ要素も最高。
色々な差別で楽しむ心を失っていたドク。
高貴な育ちも起因しているだろう。
それは自己肯定のために高貴な演奏会をきいてその後はニガー呼ばわりにされていると思っているところからもうかがえる。
そこで「上流貴族で俺の生活のほうがよっぽど黒人だよ」といわれてしまえばふさきこんでしまうのも当然だっただろう。
この映画を糧にトニーのように心から楽しめるようになりたいとおもうし、変な考えに縛られたくもない、自分が差別されているネガティブな意味で特別だと思い込まないようにしよう。
ただし前半のトニーのように金目的ではなくドクのように信念を持って、愛をもって行動していけるようになればよいのだとおもう。
そうすれば世界を変えられる。
古き良きアメリカ☆
アメリカ版「最高の二人」という感じかなぁ・・
始めは、お互いに理解し合えない二人がだんだん分かり合えて
むしろお互いを尊敬しあえるまでを描く物語。
ある意味、最後まで期待を裏切らずにストーリーは進みます。
ラストも、こうなると良いなみたいな終わり方。
それでも、見て良かった・・と思える映画。
主演(助演男優賞をとったのに変ですが・)の二人が
素晴らしいです。
物語を彩る音楽・歌も良くて 古き良きアメリカに入りこめ
ました。
他の方が書いているとおり、好みあっても見て良かったと
思える映画と思います。
観賞後の満足度はかなり高め!
黒人ピアニストのシャーリーとマネージャーに雇われたイタリア人トニーのアメリカ演奏ツアー。
序盤で「グリーンブック」の意味を把握。これからの展開は容易に想像出来ちゃいます。
ツアー中に起こる人種差別などの数々のトラブル。
個々のトラブルが重くも軽くもない良い塩梅。このさじ加減が絶妙。
所々に笑いやほっこりするシーンもあり良好。
作品で流れる音楽やシャーリーのピアノ演奏も凄く良い🎵
二人の絶妙なコンビのやり取りも最高。
観賞後はなぜか幸せな気分に。
最後にトニーの奥さんがシャーリーに耳打ちする一言で幸せをお裾分けされた気分になります。
観賞後、ケンタッキーフライドチキンが食べたくなるのは必然ですね( ´∀`)
とても素敵な映画でした◎
一部アカデミー賞に相応しくないと言う人もいますが、
個人的には最高な作品に出会い幸せな気分になれました。
ずっとこんな心に沁みる映画を観たいと思っていました。
トニーとドク主演二人の醸し出す空気感に癒されました。
トニーがドクに言います、
「寂しくなったときは、自分から動かないとダメだ」と、
ドクの孤独という殻にひびが入った瞬間だったと思います。
その伏線があっての最後のシーンには泣かされましたよ。
流れる曲や演奏シーンも最高です!
そして観た後、あなたも必ずやKFCを食べたくなるハズ(笑)
マハーシャラ・アリの圧倒的な演技
人種問題の根深さ、複雑さというのは本作を観ても、本作を中心とした論争(スパイク・リー監督、ドクター・シャーリーの遺族からの批判など、詳しくはWEBで!)をみても、異なる文化圏にいる私には全く想像できないほどだということがわかった。
その複雑さに苦悩するドクター・シャーリーを見事に演じたマハーシャラ・アリが素晴らしい。
文字通り品位を身にまとった姿、ピアノを弾く前には必ず指輪を外すという細かい仕草から、黒人からも白人からも白い目で見られる私はいったいなんなんだ!と感情を爆発させる表情まで、全てが胸に刺さる。彼の表情、佇まいが頭から離れない。
ピーター・ファレリー監督は今まで弟と組んで「メリーに首ったけ」や「ジム・キャリーはMr.ダマー」などのコメディを撮ってきましたが、本作では初の単独での監督作!!
で!いきなりのアカデミー作品賞受賞!弟はたまったもんじゃないだろう(笑)
全てが素晴らしく、大満足の作品でした。
グレーゾーン。
公開初日に鑑賞。アカデミー賞発表直後、映画デーかつ金曜という最高のタイミングよく映画館は満員。
アカデミー賞を受賞した黒人差別を描いた作品は「それでも夜は明ける」が記憶に新しいがあちらはリアルで見ているのが辛い。
本作はがさつな運転手と教養ある黒人のジャズピアニストという組み合わせで、コミカルな会話も随所に入りテンポよく進む。勿論理不尽な差別、綿花を摘む黒人労働者からの妬みの視線、俺は黒人より黒人を知っているというトニーのセリフに人種差別とは無縁に育ってきた身としては理解しようとしてもしきれない辛さを感じる。
最強のふたりと構想が同じだというレビューも見るけど、これが実話に基づくというところが何よりすごい。
今日のブランチでモーテンセンのインタビューがあったけど、この作品の良いところは単純に白か黒かではなく、グレーゾーンがたくさんあるところだ、と。
多民族国家のアメリカでもイタリア系は侮辱されたり、闇は深い。
そして、のだめほどではないけど音楽映画としての魅力も特筆すべきところ。スタインウェイのピアノにこだわるセリフで、この時代スタインウェイを用意するのは大変だったのかなーとか、黒人のクラシックピアニストは需要がないとか、音楽に関わる人間としては楽しめるポイントたくさん。
ボヘミアンラプソディーも良かったけど、作品の深さという点ではこちらが選ばれたのは納得。
どんな時代でも差別はなくならない。ジョージアインマイマインドのメロディが今も脳内で流れながら、そんなことを思います。
優しくなれる温かい作品
とても良かったです。
トニーとドクの距離の近づき方が自然で、ドクの孤独や黒人が受ける差別の哀しさ辛さを知っていくことでトニーの偏見も無くなっていくのが嬉しくて、ラストシーンは温かい気持ちになれました。お互いを知って認め合って、近付こうとする勇気が大事なんだと優しく教えてくれる良い作品だと思います。
ストーリー的にはめちゃくちゃ面白いわけではないし、こんなに現実は上手くいかない(実話ですが)という意見も分かりますが、映画なんだから綺麗事でもいいじゃないと。この映画を観て優しい気持ちになれる人が1人でも増えればいいなと思います。
素晴らしいの一言
米アカデミー賞作品賞も納得の一本。
差別などの表現がある映画はなかなか感想を言いづらい。
だけど、観るべき映画。
観て欲しい。
バーのシーンは
めちゃくちゃサイコーーーーーー!
泣きながら笑ってた。
トニーの「世の中は複雑だ。」
この言葉に救われる。
この2人は自分の立場を理解しようと努力している。
そして、歩み寄ろうと努力してる。
無理に急に距離を縮めようともしないし、相手に強く求めることもしない。
そこがいい。
内心は黒人を拒絶しているのに
寛容な人間だと思われたくてドクの演奏を聴きにきているこの愚か者たち。
人のふり見て我がふり直せ。
今一度思いかえそう自分の行動。
オーソドックスな良い映画
アカデミー賞作品賞にはここのところゲテ物や社会派が多かったように思うが、これはいかにもアメリカ人が家族で観て楽しめるようにできている。涙も笑いもあり、人種差別を描いてはいるが、ホテルやレストランでの扱い、人種差別で有名な都市名などアメリカなら教科書に載っているレベルの話なので、子供でも大丈夫。
そういえば新宿の映画館にも小学生が来ていたなあ。
ケネディの演説をネタにしたギャグなど、アメリカの映画館なら大笑いだっただろうね。
全175件中、141~160件目を表示