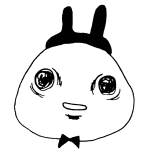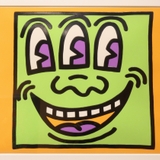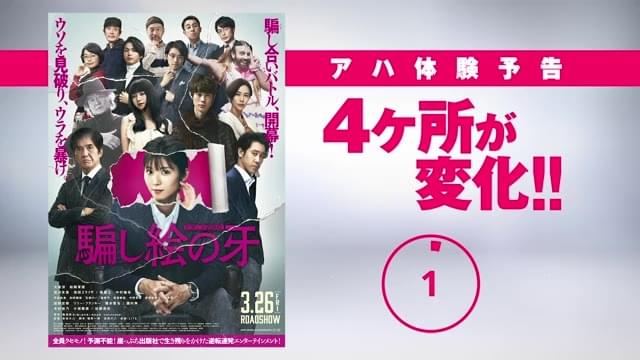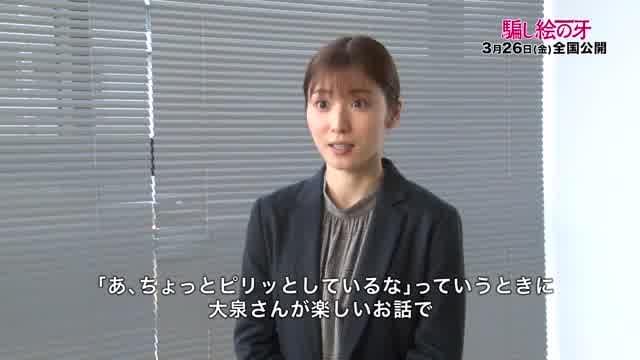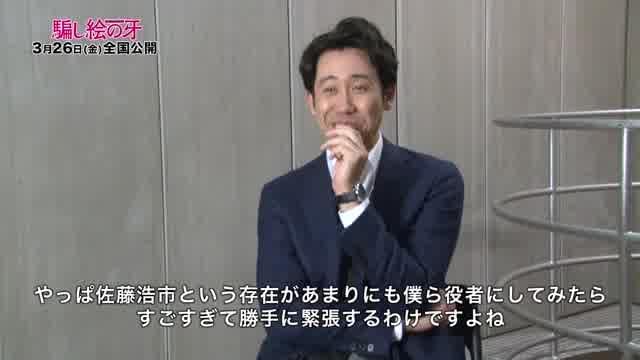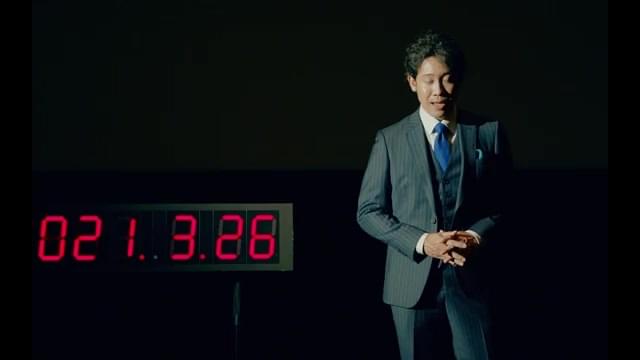騙し絵の牙のレビュー・感想・評価
全436件中、41~60件目を表示
この作品だけ
大泉洋さん出演でいいなと思えただ一つの作品です。ファンの方には申し訳ないですが、大泉洋さんは苦手でした。
自分が観たい出演者が出ているので観た作品に出てられて、なぜこの人を起用するのだろう、と思ってました。
しかし、この作品では見た目や演じ方がピッタリ合っていて、まさかのことにカッコよくさえ映ります。ただ、終盤松岡茉優に出し抜かれて屋上でコーヒーカップを蹴っていたのはいただけなかった。いつもの速水らしく動じず落ち着いて景色を見ながらゆっくりとコーヒーを飲み干す姿が見たかった。速水のカッコよさが際立ったと思う。
結局、騙し絵とは、出し抜き出し抜かれ騙し騙される過酷な出版界を描いたという事?
牙は期待させたわりに、K.IBAだったりKoとばのK、〇〇のI、〇〇のB、A‥‥この時代でローマ字の頭文字?
鋭い牙?あったかなあ。
引き込まれた
主人公は誰?
大泉洋なのか、松岡茉優なのか。
誰に感情移入すればいいのか。
騙し絵と言ってるぐらいだから、大泉洋がめちゃくちゃ胡散臭く見えて、松岡茉優がとにかく騙されていくのではないかとか、いろいろ邪推してしまう。
そしてまたしても現れる中村倫也。
何故か、おれのみる映画にかなりの頻度で出てくる。何故なのか。笑
出版業界をかき回す大泉洋。
雑誌を売り上げる為に、いろんな才能を集めてくる流れはなかなかの盛り上がりを見せて面白い。
あの有名なムキムキ女装コスプレ外国人が出てきたときは笑った。
ただ、オチがちょっと難しかった。
マネーゲーム?的な経営戦略についていけなくなってしまい、気持ちが離れてしまった。
どんでん返し的な流れなんだが、いまいち乗り切れなかった。
まあ、松岡茉優の最後の決断は、応援したくなるので良かったんだけどね。
わざとなのか
✅佐藤浩市さんのタバコで調子づくシーンが凄く良かった。
騙し絵の牙
🇯🇵東京都
大手出版業界、薫風社の社長が亡くなる。
これを機に雑誌関係者が次々に廃刊に追い込まれる中、カルチャー誌の『トリニティー』が生き残りをかけて奮闘する!
遺族、専務、常務、薫風社の編集部、カルチャー誌の編集長、外資ファンド、新人作家、連載中の大御所小説家、文芸評論家、書店主、謎男
などが複雑に絡み合う中、秘策は見つかるのか⁉️
✅佐藤浩市さんのタバコで調子づくシーンが凄く良かった。
◉70E点。
★彡普通に面白いのだが、大泉さんも佐藤浩一さんも見たことある感じのキャラでした。
松岡さんは良かったです。
★彡酔ったシーンはお気に入り!
🟡見所。
1️⃣タバコ🚬を調子に乗ってるアイテムに!⭕️
★彡この感じ凄く良いと思いました。
2️⃣騙し騙され、誰が笑って勝利するのか?🔺
★彡そんなにすげ〜ってオチではなかったかな?
3️⃣人物が多いので、ネットで相関図を見ておくと割とすんなり楽しめます。⭕️
時間の流れは思っているよりも早い、、、
業界あるある
所詮はビジネスはビジネス。人を幸せにするものではない。
舞台は落ち目の出版業界。奈落へと加速することを止められないのは古い業界人。既得権益にしがみつき権謀術策だけで乗り切ろうとする輩。そして、主人公はライブ感満載の不届きな中年おやじ。大泉洋をイメージして作られたと解説に書いてあったが、なんともはや僕のイメージとは程遠い。どうしたって緻密な計算に則って行動できる人物には思えないからだ。行動の訳を新人の女子社員に聞かれて「面白いからだ・・・」ぐらいしか言えない。さしあたって「それは偶然なだけだ・・・」ぐらいのセリフを吐けば、観察眼の賜物だと言うことの意味合いが身に沁みるのだけれど・・・似合わない役柄を狭量の役者に当て込むのは見るものをコケにししまう。
出版ビジネスが面白さを追求することでバブル期の爆発を再現できると思うのは愚か者の幻想。あの時期を忘れ去ってしまえる者だけが生き残れるのだ。
上に登っていくことが"善"ではないし、言わずもがな下っていくことが"悪"ではないはず。
楽しかった。
ラストは少し弛んだ気がしたけど、
とても楽しく観れました。
出版業界の編集と作家が軸なモノはいくつか観たけど、
出版社の社内が縦軸なのは初めて観た気がする。
政治的でとても面白かった。
ドロドロはしてるんだけど、
みんな心の奥は出版不況を乗り切る。
部数を出す!と言う同じ気持ちなので
嫌な気持ちにはならなかった。
なんとなく他の出版社とはバチバチやり合ってる
イメージだけど、
社内でも潰しあって、
作家を引き抜いたりしてて、
この会社大丈夫なのかよとは思いました。
だけど、社長が代わる、雑誌の休刊、作家を見つける
新人発掘、部数を上げる…
問題山積で見てる分にはとても楽しい映画でした。
ラストは本当にこれで大丈夫なのかな?と
ラストの続きが心配になる終わり方でした。
思ってたよりは騙していない
タイトルから騙されないぞと構えてしまったのだが、騙し合いというより駆け引き要素が強い印象だった。だが、展開は変化に富んでいて面白い。役者陣の仕事はみな見事で作品に緩徐移入しやすかった。
ただ、東松に引導を渡すシーンがいまいちぐっと来なかった。そこまでに東松へのフラストレーションを溜め込ませておいて、一気にスパッと切るべきなのに、あれ?今切った?切れたの?今ので切れるかな?と、いまいち釈然としないシーンだった。
出版社のパワーゲームの顛末
タイトルなし(ネタバレ)
変わり者編集長・速水(大泉洋)が当然、編集長と言う実働部隊から覇権争いのキーパーソンになっている所がピンとこない。新社長・東松龍司(佐藤浩市)の更迭とKIBAプロジェクトの頓挫を「社長室」で、どんでん返しをするのは、ミステリーの犯人当ての様でチープである。伊庭惟高(中村倫也)は後ろ盾も無いのに、何の権力があるのかも分からない。持ち株が多いのなら役員会議が蚊帳の外だったのもおかしい。もっと良い演出があったと思う。まだ伊庭惟高(中村倫也)に対しても速水(大泉洋)が、上から目線でしゃべっていたら、「俺はいつでも辞めてやる。面白い事がやりたいだけの放浪者」の人と言う事で納得できるが、伊庭惟高(中村倫也)に対してヘコヘコしてるから、キャラがブレブレだと思う。
たぶん原作者は、会社で責任ある仕事をしたことが無いんだと思う。
だから、権力争いの人と、実働部隊の発想がまったく違う事を知らないんだと思う。
新規制と普遍性
各登場人物の初登場の場面でそれぞれの人格を台詞・話し方・表情・行動・仕草・スタイリングを総動員して伝達してくる感じに、こんな情報量が多い作品が観たかったんだよ!ととても幸せな気持ちになりました。全編を通してプロットの意外性よりも演技アンサンブルの方が刺さった。
現実世界の構造的な課題や実際に起きている事、実際に完成したプロジェクトをコンテクストにしてるので同時代性を強調しているかと思いきや普遍性にもしっかり目配せしているのは流石。
同時多発的に今正に起きている構造転換をある分野に焦点を当てて描きつつ、それはいつの時代も常に起きている事である、つまりエンタルピーは常に増大しているという事を描いている。それに対抗する手段は普遍性と逆の特殊性を指向する事である、という事を一つの説得力を持った解を以って示している。
LITEの劇版がとても良くてサントラを買ってしまいました。
最後まで見応えのある、ちょっと活力をもらえる映画
全436件中、41~60件目を表示