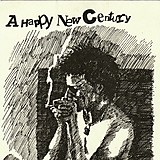止められるか、俺たちをのレビュー・感想・評価
全29件中、1~20件目を表示
「止められるか、俺たちを」という科白を聞いたのは誰か
若松孝二でも足立正生でもなく、謎の死を遂げた吉積めぐみを中心にしたことで、「映画に命を賭けた男たちの群像劇」とは違う深さが加わった。エネルギーの塊のような若松孝二、観念世界を構築する足立正夫。対して、作りたいものがわからない吉積めぐみ。悩みを打ち明けた彼女に、秋山道男(オバケ)は「目の前の課題をこなすだけだ」と答える。しかし、吉積はそれだけでは生きられなかった。
子どもを身籠ったことと、自分の方向性のジレンマに陥った吉積。ここに男性性とは異なった女性性の問題が立ち現われる。また、彼女は政治に興味が持てない、と言う。しかし、その「政治」とは、男たちが語る大文字の「政治」のことだったのではないか。実生活とはどこか遊離した「政治」の議論に違和感を感じていたのではないだろうか。
若松は「男に生まれた以上、女は拝むものだ」と語っていた。「止められるか、俺たちを」とは、若松や足立たちを含む映画に賭けた男たちからの、吉積への問いであり愛だったのではないか。
悩む事じゃない。
ともかく、私小説見たいな自然主義文学であるなら、彼独自のオリジナルは無いし、訴えかけてくる。イレギュラーな展開は無い。つまり、赤裸々を予定調和にしているだけ。
つまり、ここに出てくる人達は団塊の世代って事。
日本が如何に平和ボケしていたかって事だが、それを煽る「ウマシカ松コウジ」って事。
しかし、なんでグラサン掛けているか?
つまり、目で演技出来ないんだろうね。
存在感が物凄く薄く感じるが、僕の思い過ごしか?
ネタバレあり
翌々考えれば「視点」は亡くなってしまった主人公。
つまり、完全なフィクション。
ブラックな企業を内部告発しているに過ぎない。こんなんで映画の哲学を語って貰いたくない。
僕はダイレクトに若松は見てないが、後に名画座で10本くらい見て飽きた。
映画は私小説でもなければ日記でもない
これでも門脇麦としてはずいぶん頑張って一人の女性を体当たりで演じたと言えるだろう。事務所の方針で濡れ場も、裸も汚いセリフもイメージを損なうものはNGという女優さんがずいぶん多いなか、異彩を放つ存在感でこんな女性が実在したことを解りやすく伝えてくれる。
でも、「女は子供を産んで家を守るもの」という映画の中のセリフに敗北感を味わい、睡眠薬を飲んで自殺する描写に、「解剖したら妊娠6か月だった」という他人事のような説明セリフのエンディングに、「それはないだろう」という感想しか湧かなかった。
主人公が仕事を通じて成長し、周りを変えていく様を面白おかしく描いたドラマではない。若松孝二監督の仕事ぶりを通じて伝説的なカイ作を生み出していった伝記でももちろんない。実らない恋を成就させるラブロマンスでもない。悪人を懲らしめるアクションヒーローも出ない。
これを称賛できる人は、芸術性に娯楽性は邪魔なんだよとでも言いたいのか。それとも、映画人の日常なんてこんなものさ、ドラマなんてないんだよ。みたいなことなのか。
だったら、なんで映画にしたんだろう?
人によっては満点の映画
実在のモデルがいると言われてる助監督の女性が主人公の映画。
最後に主人公の女性が悲しい結末を迎えるのだが、実話がモデルになっているということで評価が難しい…。
これが100%フィクションなら「ハッピーエンドの方がいいな」と言ってしまえるのですが。
そこを踏まえてこの映画は人によっては満点の映画だと思う。この苦味こそが現実なのだと。苦くなければコーヒーではないという人がいるように苦くなければ現実ではないと。
映画に理屈は映らない
若松監督は存じ上げないが、映画製作映画には惹かれてしまう。
とりあえず芝居がすごい。
日常の自然な演技と、劇中劇での昭和的な演技がしっかり使い分けられている。
穏やかないい人が多い井浦新が口元をひん曲げ、口調から声の出し方、口の開け方まで変えていて見事。
門脇麦の細やかさと分かり易さの両立も異次元で、酔っぱらいのシーンは特に魅力的だった。
映画製作の舞台裏が描かれ、勿論いいことばかりではないのだが、みんな楽しそう。
議論を戦わせたり、放尿したり、プールに忍び込んだり、学生がそのまま大人になったようで、正に青春。
口は悪くも面倒見はよく、何より映画が大好きな若松監督の元には、そりゃこんな面子が集まるわ。
吉積を中心に苦悩もしっかり描かれており、青春群像として纏まっている。
撮りたい作品のために不本意な作品も撮る。
ここは、シングルでは一般受けする曲を出しつつもライヴではカップリングを中心に演った黒夢を思い出した。
生きるためには開き直りも大事だよね。(満島真之介はピュア過ぎた)
撮りたいものも見つからず、初監督の短編も認められず、妊娠の相談も出来ず亡くなった吉積が不憫。
そのためスッキリとはしないが、望んでのことではなかったと信じたい。
飾られた写真が、彼女がいかに愛されていたかを物語る。
それでも彼らは止まらないし、止められない。自分自身にすらも。
映画を好きになれそうな映画 「青春ジャック 止められるか俺たちを2」
# 映画館で観た感想
「青春ジャック 止められるか俺たちを」といういかにもマイナー感が漂うタイトルなのだが、なかなか楽しめたし、自分も今までよりも映画を好きになれるような気がした。
役者たちの演技もなかなか光っていた。
# 井上陽水× 田中邦衛
見かけは井上陽水みたいで話し方は田中邦衛みたいな映画監督が出てくる。
とにかく話し方の癖が強い。訛りが強いし田舎大将みたいな感じ。めちゃくちゃ昭和感がある。
皮肉ではなく現代の劇でよくここまで昭和感を出せたなと思った。この監督に限らず劇全体にちゃんと昭和感が出ている。
だが後半になるにつれ、癖のある話し方にも耳が慣れてきて、キャラクターの良さが分かってくるのだった。
# 名画座
監督は支配人をお膳立てして「シネマ スコーレ」という小さな映画館を開く。名画座というのは昔の映画を上映する映画館のことをそう呼ぶらしい。
今で言うとミニシアターかな。
# 映画がテーマの映画
「映画が大好き」という気持ちには自分はまだ分からない。確かに映画館にはよく行くが、過度な熱中をしているわけではない。
映画の中で映画愛について語られるというのは、なんだか自己言及的で、くさい感じがする。だがこの映画の「映画」は良かった気がする。
# 映画監督になりたい少年
映画監督を目指す少年。友達にも映画のウンチクをよく語る。口から出てくるのは数々の映画監督たちの名前。
なんだか映画が好きというよりは「映画が好きな自分が好き」というか、映画知識をコミュニケーションのマウントに使っているような感じがする。
虚勢だけでまだ中身は空っぽの少年。
# 塾講師
やけに格好良い塾講師。ナイス。こんな先生がいたら誰だってファンになる。
全共闘時代を生き抜いてきた人なので、芯があるのだ。(たぶん)
# 映画を撮りたい女
ほぼ紅一点で彼女には昭和感がない。男臭いこの映画の中でほぼ唯一の癒し要素。
彼女も映画を撮りたかったのだが自分には才能がないと諦めてしまい、映画館の受付のバイトを始める。
少年との掛け合いもあるのだが、なんかとても良かった。
# 映画監督を任される少年
色々あって若くしていきなり映画監督を任される少年。
だがもちろんうまく出来るわけがなく、だんだんとプロデューサー役であったはずの若松監督に座を奪われて行き、立場もプライドもボロボロになる。
だがそれがコメディともなっており、会場には笑いが起こっていたし、僕も笑った。
# 井浦新
エンドロールで俳優名を見ると監督役は井浦新だった。
調べると前に映画「つんドル!」のささポン役もしていた人だ。すごいキャラクターの変わりようだ。カメレオン俳優だ。
# 監督は少年だった
この映画の監督は作品に出てきた少年「井上淳一」だった。そういうことか。
「人は人生で少なくとも1本は作品を書ける。それは自分の人生を書くことだ」的な名言が作中にも出てきたが、監督はこれを体現したことになる。
# 青春ジャック1はあるのか?
「止められるか俺たちを」という第一作が公開されていた。
吉積めぐみ助監督と若松孝二監督
1970年代の映画監督と女性助監督
映画はこの女性助監督“めぐみさん”を中心に話が進んでいく。
映画を制作していくにあたり、この年代の現場は実に熱い。
映画の中で『映画の中で何をやったっていいんだ』というセリフが実に面白くて、いままで考えつかなかった思いが溢れてきた。
例えば「全裸監督」の村西とおるさんもそうなんだけど、作りたいものや出したいものに必ず制限がかかり、皆それに苦しむ姿や映画を取るために必死になってる姿が印象的だった。
それにしても、めぐみさんの最期は悲しかった…。
あの時代だと、人の死を知るのってあとになってからが多かったんだろうなぁ。
子供を育てながら監督をしてる方々っていまの時代にはいるだろうけど、あの時代は難しかっただろうし、背負いきれなかったのか…
父親のように可愛がってくださってた、若松監督に相談をすれば厳しくも受け入れてくれた予感がするが、映画の方向転換の時期だったから、誰にも相談出来なかったかったし…
堕ろすのも育てるのもどちらも選択できなかった結末だったのかな。
動き出したら止まらない姿や恐らくラストシーンは「あさま山荘への道程」の撮影へと繋がっていくのかと想像してしまう。
そして、タイムリーなのを見てしまったと思う
【若松孝二監督】についても調べたら、とあるニュースに繋がってしまった。
ニュースを読むと、足立正生さんが監督だ。
そしてもう1つ、この映画の音楽が曽我部恵一さん
革命とか政治とかが関係する「ビリーバーズ」でも音楽担当だった。
数々の偶然に驚いた。
映画界のつながりを感じた。
ちなみに私は藤原季節さんが出演していたので、観たのであって、そちら方面には興味はございません。
若松監督!
映画が好きで、でも、難しいことは分からないし、映画制作の技術や論理やその他諸々知らないことは多すぎる私が、若松監督の作品を初めて見たときものすごい衝撃をそ受けたのを今でも覚えている。(初めて鑑賞した作品はキャタピラーです)
本作品の主人公はめぐみ(門脇麦)。彼女が何者かになりたいと自問自答する中で、若松プロに入ることになり、その中でたった2年と数ヶ月の間過ごしたお話。
男だらけの映画製作チームの中でひたすらもがきながら、どやされてもひくことなく必死で食らいついているめぐみの姿は印象的だった。
それから、男性がビルの上からタッションするシーン。2度でてくるけれど、その2度ともめぐみは一緒にタッションするのを女性にとめられる。その時のなんとも残念がる表情がとても良い。
門脇麦の演技も存在感も醸し出す雰囲気、空気。どれもこれもがこの映画で輝いていて。彼女の魅力を十分味わえる。白石監督さすがですな。
めぐみの最期が自死というのはとても悲しい最期だった。死を選ばないといけなかったのかなー、、、赤ちゃんと一緒に生きる道を選んでほしかったなと思う。
この映画にレビューを残すなんて難しくて何を書けば良いのやら状態だが、とにかく若松プロダクションという場所で映画を作りたくて集まった人たちの情熱と映画愛にひたすらついていく鑑賞だった。
当時の社会情勢、世界情勢は今現在と違う部分もあるけれど、世界では恐ろしい戦争や紛争が未だ続いていたり、始まったり。若松監督がもしまだ生きていたら、今どんな映画を作りたいと思うだろうなぁ。
若松プロで映画づくりを学び経験した人たちのほんの一摘みをこの映画で拝見しただけだけれど、もっともっと若松プロの映画を観てみたくなった。(正直、そんなんばっかりみてたら心が病みそうやからほどほどにしたいけど)
あの時代だからできた破天荒な日々
昭和40年代の若松プロとそこに助監督希望で入ってきた女子の物語。とにかく熱かった。若松孝二を取り巻く仲間たちは時代を席巻した有名人などが結構いて驚いた。若松孝二監督に心酔していた寺島しのぶはスナックのママ役で出演してます。
主演の門脇麦は昭和の女よく合います。かなりの好演だったと思います。若松組はカンヌ映画祭のあとレバノンにわたり連合赤軍に合流ってあり得ませんね。だんだん政治色を強め左翼活動に傾注していった若松孝二らとのギャップに彼女は精神を崩し結局最悪の結果に至るわけですがせつない人生でした。
若松孝二をなんとなくでも知らないと乗り切れない作品のような気もします。個人的に若松孝二が作った映画館で若松プロの作品を観賞でき感慨深かったです。
映画作る側の人たち
興味深く観れました。
タイトルが格好いい!
鑑賞後、インタビュー記事と
皆さんのレビュー読んで、
なるほど! そゆこと!
勉強になりました。
めぐみさんの最後は悲しい。
誰にも止められない、俺たちを
昨年、3本の監督作を手掛けた白石和彌。
やはり最高作は『孤狼の血』だが、本作も非常に良かった!
描くのは、師・若松孝二。
若松孝二と言えば、日本映画界屈指の鬼才。
様々なバイトを転々とし、ヤクザの下っ端や刑務所にも入った事があるという異色の経歴の持ち主。
日本映画は全てクソ、警察など権力を心底嫌い、警察を殺したいから映画の世界に入ったとも。(デビュー作は警官殺しの映画)
性や暴力を通じて、常に社会や権力に対して刺激的・挑発的な作品を発表、当時の若者たちから熱狂的な支持を得る。
連合赤軍メンバーと親交もあり、2008年の『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』はキャリア最高傑作とも言える衝撃的な力作。
2012年に死去するまで、映画を武器に闘い続けた。
1965年に立ち上げた若松プロダクション。そこに集った若き映画人たち。
1969年、同プロに助監督として入った一人の女性・吉積めぐみの視点から描く。
自分は何者か、自分は何をしたいのか、日々悶々と模索していためぐみ。
知り合いを通じて若松プロに入り、若松孝二の助監督に就く。時には女性ながら、ピンク映画の助監督も。
とにかく気性の激しい若松孝二。激昂すると、「俺の視界から消えろ!」。
そんな若松にキツく振り回されながらも、元々映画好きという事もあって、活気に溢れていく。若松に影響受け、性格も若松化していく。
集った仲間たちも同じ。映画を通じて社会と抗い続け、訴え、自分自身を模索し続けていた。
ヒロインの成長とアイデンティティー、若者たちの映画と青春のグラフィティ、興味深い若松孝二と若松プロの知られざるエピソードが巧みに展開し、飽きさせない。
門脇麦がさすがの若手指折りの演技巧者!
自然体でありながら、時に大胆に、時に複雑な内面を繊細に。
彼女の代表作の一つになったとも言えよう。
他キャストには、若松孝二ゆかりの面々。
若松孝二を演じるのは、晩年の作品の常連でもあった井浦新。
若松孝二本人がどういう人物でどういう性格だったかよく知らないが、喋り方やクセなど、かなり近付けたのだろう。
若松孝二と共に映画を作った実在の人物、親交のあった著名な人物も登場。
再現される初期の作品やピンク映画の数々は、熱心な若松ファンなら堪らないだろう。
これらの作品を是非見てみたいが、ソフト化されてないのがほとんどで、見たくとも見れな~い!
主人公のめぐみも若松プロの実在の人物。
若松プロで発見された彼女が遺した助監督の記録が本作製作のきっかけだとか。
尺は30分程度のピンク映画ながら、遂にめぐみにも監督の話が。
何を作りたいか自問自答しながらも、若松孝二の下で学び培った経験を注ぎ、撮り上げる。
が、出来映えは…。
改めて知らされる、鬼才と凡人の才能の違い。
この頃若松孝二はパレスチナに赴き刺激を受け、より政治に傾倒していく。
若松プロも、映画か政治か、で分かれる。
めぐみも依然映画は好きで、若松孝二に刃を突き付けるような映画を作りたいという意欲はありながら、映画以外の道の事を…。
再び、模索し始める。
そんな時、関係を持ったカメラマンの青年の子を身籠り…。
何が決定的な原因だったのかは分からない。
自分は何者か、どんな映画を作りたいのか、答えを見出だせず、迷走したままだったのか。
無軌道な若者のこれが終着点だったのか。
映画を変える映画を作りたかったのに、結局自分もそんじょそこらの女たちと変わらぬ事に意気消沈したのか。
分からないままだろう。
しかしめぐみは、自ら命を絶ったのだ…。
映画作りに迸った熱気。
突然消えた灯火。
それでも彼らは映画を作り続けていく。
映画を通じて闘い続けていく。
止められるか、俺たちを。
誰にも止められない、俺たちを。
まるでその精神を受け継ぐかのように、映画を撮り続けている白石和彌。
去年3本、今年も3本。
その精力さには感嘆するが、傑作もあれば駄作も…。
一時期の園子温みたいにならなければいいが…。
チェ・ゲバラの顔が常に見守ってる。性と暴力そして革命
一番印象に残ってるのが、初監督を任された吉積めぐみ作品「浦島太郎?」が若松孝二監督に認められなかったときに見せた涙。最初はフーテンの自分を拾ってくれた若松プロで何気なく助監督を続けていためぐみだったが、自分の目標をやっと見つけたと思ったら、これだもん。ちょっとした青春の挫折感がいい具合に描かれていた。涙を見せるシーンは何ヵ所かあったのですが、男社会の紅一点という立場を乗り越える健気なところが素敵でした。
足立(山本浩司)からすれば、女を捨てたと思われていた吉積めぐみ(門脇麦)。しかし、映画製作にのめり込む過程で何かが変化していた。映画への情熱、大手とは違った湧き出るような創造力。ピンク映画中心ではあったが、それらはすべて資金のためであり、難解であるがため評判が良くなった若松プロ作品の奥底にある体制批判や、映画からにじみ出るエネルギーを皆が共有していたのだ。エロ目的で映画を観る人は所詮エロどまり。映画に隠されたテーマやメッセージはなかなか気づいてくれないもどかしさは現代にも通じていると思う。
時代背景からして、学生運動華やかなる時代。しかし、インターナショナルを歌わなかった若松孝二。彼は映画を通してのみ自らの思いを発する手段として使っていたことがわかる。同門の助監督たちはその意思をくみ取り、富士山を天皇と見立てたり、体制批判の精神だけは忘れなかった。しかし、助監督から監督へと道を進むにつれ、主人公めぐみの心は複雑に揺れていた。
カンヌ映画祭へと招待され、ついでにパレスチナの現状を撮ろうとする若松、足立。「パレッチナ」と発音するところが何ともユニーク。同時にその映像を映画化されてないのは、ハリウッドはユダヤ系が多いためだという現実も伝えられる。そこからは映画製作よりも活動拠点として赤バスを走らせるなど、政治的ニュアンスが強くなっていく。そんなときに思いがけない妊娠に気づいためぐみ。彼女が死を選んだ理由はよくわからなかったが、簡単には答えは見つからないような内容でした。
赤塚不二夫や大島渚といった著名人も顔を出し、三島由紀夫の自決シーンも大きな意味を持ってくる。死んでしまったらおしまいだけど、死ぬまでに何を残せるかという人間の背負った運命をも感じさせてくれた。
とてもよかった
3年我慢したら監督にしてやる、と希望を抱かせるところが憎い。そうは言ってもオレなら3年は無理な気がする。これこそ紛れもなく青春だ。団体行動を楽しんだり耐えられる根性があったらなあとつくづく思う。エンドロールで、ご本人登場で実物の写真を見せられたら泣いてしまった。まさか自殺なんてそりゃないよ、産めばいいのになあと思う。
若松映画の映画というメタシアター
門脇麦に尽きる。
ただし、破天荒な青春群像劇となり得たところが、門脇演じるめぐみをメインに据えたために、良くも悪くも物語が浄化されてしまったように思える。
だって、あの頃のポルノ映画の独立プロが、果たして、これほど「きれい」だっただろうか?
しかも監督は、「彼女がその名を知らない鳥たち」(傑作)で、あれほど汚い人たちを描き、観る者の心揺さぶった白石和彌。
おそらくはノスタルジー、そして死者を悪くは描けない、ということか。
若松孝二に私淑していた曽我部恵一が音楽を担当。彼の柔らかな声は映像にはなじむが、実際、当時聴かれていた音楽は反体制のメッセージを込めた、もっと鋭いものだったはず。こうした点を鑑みても、現実の「あの頃」との差異を感じる。
父を知らない娘(めぐみ)が、若松孝二の父性に憧れ、父の面影に惹かれて男に抱かれる。
そして彼女は映画を生むことも、子供を産むことも出来ず死を選んだ。
当時はいま以上に職業と性差の考え方がはっきりしていた。映画を生むのは男性という暗黙のルールがあったのだ。
しかも、母になれば絶対に映画は生めない。せっかく、ここ(助監督のチーフ)まで来たのに、積み上げてきたものは無になる。彼女は映画と我が子と“2人の子”を選べなかったのだ。
さて、本作は「映画の映画」である。劇中、はしばしに映画への愛が溢れている。
従って、この作品がメタシアター的になるのは当然だろう。
そもそも本作は劇中でめぐみの死を悼みながらも、と同時に作品として若松孝二へ追悼を捧げるという二重構造を持っている。
また、本作は、映画作りそのものが、「若松孝二的」だ。
映画を撮影しているシーンで、助監督のめぐみが「背景に関係ない人が映ってしまった」と指摘するシーンがあるが、若松孝二は「そんなの誰も見てねえよ」と一蹴する。
なるほど。劇中、町を歩くシーンで、どう考えても当時にはないものが映り込んでいるところがあるのだが、それは若松組の映画作りなのだな、と合点がいった。
また、何かのインタビューで井浦新が、本作の撮影期間は2週間だったと言っていたのだが、やはり、めぐみが仕切って撮影日数を短くしたというやりとりが出てくる。
本作が若松プロの再出発となるとのこと。そのことにふさわしい映画作りを志向したのだろう。
女性に観てもらいたい
言いたいことはいっぱいありますが個人的には、門脇 麦さんの演じる女性の心の揺れ動く描写に終始見入ってしまいました。
子供をおろすのはセックスに負けた事であり、子供を産むこともまためぐみにとっては負けることになるから結局『死』という悲しい選択をしてしまったのでしょうが…
その行為は浅はかではありますが死ぬことによって彼女のクリエイターとしての最期の自己主張たる『作品』として完結したのでしょう。
そう、文学者・三島由紀夫 氏のように…
19’ 11月1日 ミニシアターにて鑑賞
思考の上積みも感情の整理もできず…
1969年は確か、ウッドストックのあった年だ。
学生運動やベトナム戦争などの時代を直接経験していない自分にとっては、この映画を観ても思考の上積みも感情の整理もできなかった。
若松監督作品も知らないため、強烈なキャラクターであることはわかったが、彼が本当に撮りたかった映画がどんなものか知らない。何かを“破壊”したかったのだとは感じた。
若松映画に憧れて、監督志望のめぐみは、映画監督にはなりたいけど“何を撮りたいかはわからない。”と言っていたことが印象に残る。助監督を勤め、あんなにがんばっていたのに、どうして自死を選んでしまったのか?
映画監督の大澤渚、漫画家の赤塚不二夫、漫画家のモンキー・パンチも登場する。
当時の雰囲気、情景だけは、何となく伝わってきた。
熱量
男臭い映画は嫌いなんですけどこの映画はその熱量を感じて引き込まれて観た。女性が主人公と言うのがよかった。門脇麦ちゃんが本当に美しい。過酷な現場ながら、笑顔もたくさん。夢や希望がたくさん。でも、それは期間限定のことなのかな。何かをつかもうと自分の道を自分の意思で歩む女の子が、最後あんな形で終わってしまう悔しさ。あんまり物事を深く考えてない男子がああやってひとりの情熱を持った人間の命を危機に晒すってこと、ほんと罪深いね。女の子の自尊心が本当に低い時代だったんだなあとも思う。劇中の映画にでてくる女の人はつよいのにね。
全29件中、1~20件目を表示