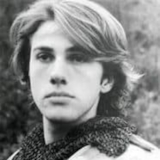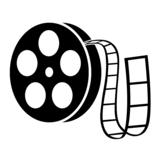焼肉ドラゴンのレビュー・感想・評価
全130件中、1~20件目を表示
掛け値なしに「小さな家族の大きな歴史」
<映画のことば>
わしらは、この先ずっと日本で暮らしていく。
そやから、日本の教育が一番や。
<映画のことば>
「留年なんかしたら、もっといじめられる。」
「この日本でわしらは闘こうていかなならん。いじめくらいでへこたれて、どうする。」
龍吉か隻手(せきしゅ)なのは、戦争の故にということのようです。戦時中は徴用工として、戦役に従事していたのでしょうか。
おそらく、もともとネイティブではない日本で生きていくためには、日本という国家に忠誠を示す必要があったからでしょう。
龍吉にとっても、この国での家族の生活の安定のため、苦渋の決断だったのだろうと、評論子は推察します。
そういう龍吉の決心は、上掲の映画のことばに色濃く滲み出ているというべきでしょう。
まったくをもって、胸が張り裂けるような痛みを禁じ得ません。
かてて加えて、世は高度成長期の景気に華やいでいるときに、人種的な差別もあり、すっかり、その趨勢(すうせい)から取り残されてしまい、家族が不幸を襲っても、ただじっと耐えながら「片手にカネ、片手に涙の在日物語」という哲夫の台詞のように、ひたすら社会の末端で生きることを余儀なくされる日々。
本作でも美花の彼氏・長谷川が妻子もちであったり、彼の生業が高度成長期を支えたいわゆるモーレツ社員の憩の場として享楽的な産業だったり、進学校といわれる学校の学校の教育に時生か馴染むことができなかったりといったということのほか、大量輸送時代の花形でもあり、作中に何度も描写される航空機の轟音は、家族が高度成長という世間の波に翻弄される様(さま)を表現して余りがあったように、評論子には思われました。
(経済の活発化やレジャー=旅行需要の増大による旅客の大量輸送時代という「正」「陽」ないしは「花形」という部分の恩恵には、あまり(ほとんど?まったく?)与ることはないのに、その騒音という「負」の部分の影響だけは大きく受けている)
「小さな家族の大きな歴史」とは、本作の予告編での表現でしたけれども。
その形容には少しの誇張もなく、観終わって、充分な佳作だったとも思います。
(追記)
龍吉の店は国有地を不法占拠しているみたいでもあるようです。
日本に居つくためには、仕方がなかったのでしょうか。
それとも、戦役にまで従事して忠誠を示したのだから(国有地に住み着くくらいは)、日本という国家から恩典を受けても責められる道理はないと、龍吉は考えていたのでしょうか。
いずれにしても、本作の半ば頃に、哲夫に対して吐き捨てるように言った「終戦後すぐに醤油屋の佐藤さんからこの土地を買ったんや。確かに買ったんや。」という龍吉の説明は、とりも直さす「言い訳」そのものなのでしょうけれども「真っ当に自分が使っていい土地なのだ」という彼の思いが込められていたことには、疑いがありません。
そして、それが「言い訳」に過ぎないことは龍吉本人も重々承知の上のようで、そのときの苦しそうな龍吉の面持ちを、評論子は忘れられそうにありません。
(追記)
本作では、真木よう子の演技が光っていたと、評論子は思いました。
幼馴染みの哲夫に対する思慕と、哲夫をめぐる妹・梨花との確執をひっそりと心の奥底に秘めながらも、終始にわたって抑制の利いた彼女の演技が、外面とは裏腹に反対に哲夫に対する思慕を浮き彫りにさせながら、両親を助けて一家を取り仕切る長女の役柄にピッタリだったように思われます。
本作は、主演という役者が存在せず、両親を始め、家族役の全員が、皆で合わせて「主役」だったような一本でしたけれども。
その全員の演技を取りまとめる「主役」が彼女であったと言っても、過言ではないと思います。
(追記)
「造反有理(ぞうはんゆうり)」という台詞は「造反にこそ理(ことわり)有り」という中国語、つまり「謀反側や反乱者こそ正義が持っていること」の謂(いい)であり、梨花との婚姻届を市役所に出しに行ったおりに、市の職員と口論になったことの、いわば哲夫の「腹いせ」として本作に登場する台詞でしたけれども。
しかし、ある意味では、作品の冒頭で哲夫が叫んでいたこのフレーズこそが、高度成長期の日本に住まっても、いろいろな意味で「日陰者」であることを強いられていた龍吉一家にとって、本作を通底する彼・彼女らのポリシーがあったのかも知れないと、評論子は思います。
(追記)
本作では、そのエッセンスとして、時生のナレーションが効いていたとも思います。
時生のナレーションで始まり、それと対を成すような時生のナレーションで締めくくられる構成も秀逸だったと思います。
(追記)
考えてみれば、高度経済成長の掛け声の下、日本中が踏ん張っている最中(さなか)、いわば「清濁併せ呑む」ような猥雑な時代背景を、本作は余すところなく描いていたとも思います。
その意味では、「昭和の猥雑さと混沌に溢れる」というレビュアーbloodtrailさんの指摘には、まったく同感です。
適切なレビューでそのことを評論子にも再認識させてくださったbloodtrailさんに、末尾ながハンドルネームを記して、お礼に代えたいと思います。
兵庫県伊丹市の在日韓国人家族を描く。 本人はその土地を買ったつもりらしいが、 結果的に伊丹空港近くの土地を不法占拠して焼肉屋を営んでいる家族6人。
動画配信で映画「焼肉ドラゴン」を見た。
2018年製作/126分/G/日本
配給:KADOKAWA、ファントム・フィルム
劇場公開日:2018年6月22日
真木よう子(静花)
井上真央(梨花)
桜庭ななみ(美花)
大泉洋(哲男)
大谷亮平(美花の男)
宇野祥平(店の常連)
根岸季衣(美花の男の妻)
李姃垠(おかあちゃん)
金相浩(おとうちゃん)
兵庫県伊丹市の在日韓国人家族を描く。
本人はその土地を買ったつもりらしいが、
結果的に伊丹空港近くの土地を不法占拠して焼肉屋を営んでいる家族6人。
長女、静花は美人で愛想が良くてにこやかで客たちにも人気がある。
脚が悪い。
びっこをひいている。
※びっこ。片方の足が不自由で、歩き方が不自然であること。
次女、梨花はいつも何かに怒っている。
ほとんど笑顔を見せない。
三女、美花は妻がいる男に夢中で他のことに興味を示さない。
店主はおとなしい男で、自己主張は控えめ。
20年以上この土地で必死に働いてきた。
店主の妻はこれは韓国人らしい特徴かもしれないがすぐに激昂し当たり散らす。
哲男も在日韓国人だが、
梨花と結婚してみたが上手く行かない。
哲男はずっと静花が好きなのだ。
梨花にもそれは判っていた。
梨花はやがて韓国人の男と恋仲になる。
梨花は結局、哲男とは別れることになる。
静花は在日韓国人の男と婚約したがその男とは結婚しなかった。
静花は哲男と一緒になった。
結局、すべては収まるべき所に収まったわけだ。
静花ほどの美人ならオレだって必死にモノにしたいと思うだろう。
在日韓国人家族の私的な物語だが、
元々は戯曲であり、
舞台で演じられていた話だ。
真木よう子や大泉洋らによって映画化されることになった。
おかあちゃん役の李姃垠は「パラサイト半地下の家族」にも出演しているらしい。
満足度は5点満点で4点☆☆☆☆です。
濃厚な家族の関係に、ふと思うこと
在日の「渡る世間は鬼ばかり」悲喜こもごも、泣かせます
戦争がなかったら...もうこんな悲しみはいらない
時代に翻弄される在日ファミリー
ちょうど日韓関係が悪くなりだした時期だけに興行成績はさほどと記憶してます。しかし焼肉ドラゴンはかなりの良作です。舞台で賞を総なめした作品らしく脚本、演出とも良かったですね。キャストも両親役の韓国俳優も好演でした。(お母さん役はパラサイトにも出演)三姉妹は体調不良後の久々の復帰の真木よう子はさておき、井上真央はこのくらいの助演がしっくりくるようになっています。なにしろ驚いたのが桜庭ななみで韓国語のセリフを無難にこなしたり、まさかのキャットファイトまで繰り広げていて2018年の私の中の助演女優賞ですね。
大阪のコリアンタウンといえば鶴橋やら桃谷など生野区は有名ですが伊丹(正式には兵庫県)にもあったのですね。
あの頃はそういう時代だったのか
途中大阪万博の話が出てきて、あー私が生まれた頃の時代舞台か〜と見てました。
飛行場近くでしょっちゅう飛行機の爆音が響く。
その下での人間模様。
皆がいつの間にか「焼き肉ドラゴン」に集っている。
帰る場所にもなってるんだな。集会場ともいう。
男たちは酒を飲んでばかりで、女が働いている姿が。
店のエリアの活気なさを表してました。
最初は母親がすべてを切りもりしていて、父親はその横で寡黙。
それがいくつかの悲しい事件があったりして。
父親が口数は少ないながらも、言う時はきっちり言う。
存在感が出てくるところが、とても頼もしく見てました。
「故郷は近いけど、ものすごく遠い」。
昭和40年代ならそうだったろうね。
娘たちとその夫や恋人の話も、ごっちゃ混ぜにひっくるめて。
大切な「家族」なのが伝わってきます。
戯曲の映画化とあって、時代背景も合わせてこじんまりわかりやすく。
思っていたより良質な作品でした。
【高度経済成長期の関西地方都市の市井の人々の姿を描いた作品、だが舞台劇の色合いが出過ぎていて映画にした意味が弱いと感じてしまった】
頑張った作品
いい映画ではありますが!
映画じゃなくて舞台の方が映える気がする
人気戯曲と知ったからという事もあるけど。
なかなかカットを切らない
独特の間
さすがに「働いた働いた」シーンは泣いた
ご返盃のシーン、真木よう子笑ってたよね!?
ホルモン最初しか焼いてない!
ほぼほぼビール飲んでるだけ
3姉妹良し
真木よう子のおっぱいに釘付け
在日
大阪
1969〜1971
バラックの屋根はいいが壁はちょっと
自殺
兵庫県
大阪
尼崎市水道局
京都グランシャトー
ご返盃ごっこする二人
高度経済成長期を迎えていた日本。大阪万博開催で沸いていた一億総中流意識の中で、その社会の歪みのうき目に遭っていた在日コリアン。金龍吉(キム・サンホ)と金英順(イ・ジョンウン)の夫婦は伊丹空港近くの集落で焼肉ドラゴンというホルモン屋を営み、互いの連れ子静香(真木よう子)、梨花(井上真央)、美花(桜庭ななみ)と夫婦の息子・時生(大江晋平)と暮らしていた。冒頭から家族の説明は時生のナレーションで始まるのだが、劇中では叫び声しかあげていない。
娘3人の恋愛事情を基軸に在日の内に秘めた思いを語っていく物語ではあるが、面白おかしく演技する中で、終盤の龍吉の告白が真に迫る。大泉洋とか亀の子タワシのおっさんも凄くいい演技。『万引き家族』の陰に隠れてしまった感もあるけど、こちらも凄い映画だった。
日本に来て働いて働いて、戦争に駆り出され日本のために戦って左腕を失った龍吉。故郷の韓国に帰ろうとも思ったが、そこで故郷済州島の虐殺事件(済州島四・三事件など)で家族・親戚・友人たちが皆殺されてしまい、家も焼かれて帰る故郷を失ってしまった。さらに朝鮮戦争勃発により、日本に永住することを決意したのだ。
そんな焼肉ドラゴンの店。実は戦後混乱期に醤油屋の佐藤さんから買った土地だと言い張るのだが、もともとは国有地であり、市役所からもはした金で撤去するよう求められていた。結局は万博が終わった1971年に家を出ることにはなるのだが、3人の娘たちが伴侶とともにバラバラになってしまう。『万引き家族』とも近いようなテーマはあるのですが、こちらの方はバラバラになっても永遠に家族なんだと主張している点が違うのです。大泉洋は北朝鮮に行きたがってるし、次女は韓国、三女は日本・・・。それでもたくましい性格の者ばかりなので、明日はきっと明るいんだと想像させてくれるところがいい。
記憶に残る台詞、大泉「その世間一般とやらを連れてこい!」、龍吉「土地を取り上げるなら、わしの腕を返せ!」など。その後の国有地は公園にされるということから、時期的にも森友問題にも繋がる面白さもあった。
全130件中、1~20件目を表示