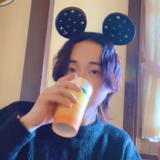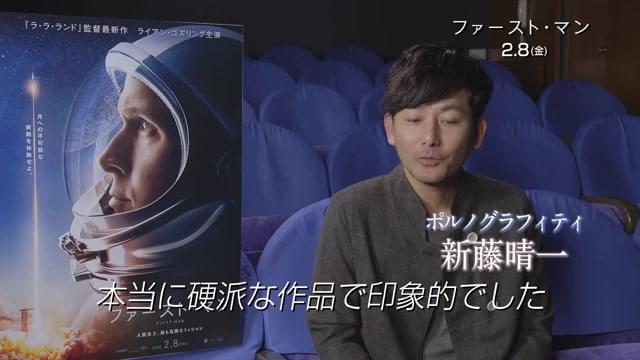ファースト・マンのレビュー・感想・評価
全372件中、101~120件目を表示
初男
日本人の誰もが知っている?
アポロ11号の人類初の月面踏査を描いた映画です。
前評判で、意外と地味な展開だと聞いていましたが
お話しの展開は淡々と進み地味です。
画面も16ミリ撮影で、クローズアップの場面が多く
IMAXで観たのですが、あまりスケール的な壮大感
は感じられませんでした。
そして、淡々と進むので、つい2、3回うとうとと。
私的には、主演のライアン・ゴズリングは、「ラ・ラ・ランド」
のイメージが強くて、ニール・アームストロングには見えません
でした。今にも踊り出しそうで。
ゴズリングの演技は非常に抑えた演技で、感情的になる場面は
ほとんどありません。幼い娘を難病で亡くした場面以外は
同僚が事故死しても動じません。
ニール・アームストロングか実際にそういう人だったと
いうことらしいですが、そうでなけば、生きて帰って
これないミッションに挑戦することはなかった?のかも
しれません。
初期のX-15航空機やジェミニ8号での実験の場面は、
機体を外から映す場面はほとんどなく、狭いコックピット内の
様子がリアルに描かれています。
このリアルさは、機体が大気の圧力で縮んでミシミシいう音や
エンジンの爆音も激しく、臨場感はありました
(4DXでも楽しめると思います。)
この点は、IMAXで観てよかったです。
ただし、閉所恐怖症のヒトには耐えられないと思います。
閉所感は堪えがたく、おすすめしません。
※この時期に、なんでアポロのお話しを敢えて作ったのか
あまりよくわかりませんでした。アメリカ万歳という
感じで作っているわけでもなく。
※実はアポロは月に行ってなく、全て映画セットで
撮影されたフェイクだという都市伝説がありましたが
現在は都市伝説は完全否定されています。
ただし、アポロ計画の初めのうちは実際に月に
行っていましたが、後半は予算不足で、映画セットで
撮影したという説も出ています。
そんな都市伝説も今回のお話しに絡めてほしかった
です。
※若い女性グループが、遊園地のアトラクション
感覚で観ていたらしく、終わった際の様子は
ポップコーンを両手にしたまま、へこんでいる
ように見えました。
※ニール・アームストロングの奥さんが
目力も含めて非常に怖かったです。
ニールがアポロ11号の船長となり、家族と
別れて基地に出発する前日に、ニールに
2人の息子に対して、今回の挑戦で戻れない可能性
があることを、パワハラ的に説明させます。
他にもニールの上司にブチキレる
場面もあります。
アメリカ~
宇宙飛行士の出征。魅力は映像美。
誰もが知る月面着陸の瞬間。歴史に残ったのは、成功したから。その成功の延長線上の未来に生きる我々には、その計画、挑戦は必然に見えるが、当時はとてつもないリスクと犠牲を覚悟しなくては成せなかったこと。
アームストロングが飛び立つ直前の妻の怒号で、それがよくよく伝わります。まるで、出陣する特攻隊員を送り出すかのような前夜。
宇宙飛行という壮大なテーマの割に、全体としては起伏がなく、娘の死も仲間の死も淡々と伝える展開はやや退屈かもしれません。史実をきっちり収めるために、ドラマ性は抑え気味、ドキュメンタリー風。そんなストーリー展開をカバーするのは、映像の魅力。無音で視覚効果を高めた静寂の月面風景は、圧巻です。どうか、その美しさを最大に享受するために、今から観る方々には是非とも携帯電源オフのダブルチェックをお願いしたいです。バイブ音でも、鳴ってしまうとあのシーンは台無し!
ニールがあることを乗り越えるために挑んだ怪物“月”への挑戦
最近まで月面着陸捏造説を信じていた・・・
1977年の『カプリコン1』を映画館で観たときから捏造説を信じるようになった。以来、飛行機は飛ばない説など、米ソ冷戦などを学ぶにつれ米国の尊厳として陰謀を企てていたという方が真実味があったようますます疑念が生じてくるほどだった。『ライト・スタッフ』や『アポロ13』などといった映画で徐々に信じるようにはなったけど、その後、月に誰も行ってないことでまた疑問が・・・。
NASAが機密扱いしていたアポロ11号との交信記録が公開され、ようやく信じる気になった。アカデミー賞の視覚効果賞を獲ったことや、13日にTBSで放映された「宇宙プロジェクト」なる番組で、この映画の宣伝みたいな内容があったので、ようやく最終日になって観る気になったのです。ちなみに1202のアラームも紹介していました。
冒頭から重低音の響くテストパイロット時代の映像。そして、幼き愛娘カレンの死。その悲しみから逃れるべくしてNASAの宇宙飛行士に応募する経緯。過酷な訓練と、友人たちの事故死。生きて帰れる保証もないし、ニールが時折見せる虚ろな表情がまた妻ジャネットの目を通して悲しくさせる。
ケネディ大統領の月面着陸するという演説も効果的に挿入され、ソ連に勝つために死に物狂いで訓練したようにも思わせながら、ニールだけは違ったのだと感じた。月に降り立ったニールが亡き娘のブレスレットをクレーターに投げ入れるシーンで彼の目的が弔いでもあったと思わせ、帰還後隔離中にガラス越しでジャネットと指を重ねるシーンで終わるところも素敵だ。
映画では扱っていませんでしたが、「一人の人間にとっては小さな一歩だが人類にとっては偉大なる一歩」という名言以外にも、ニクソン大統領から「アメリカの誇り」だと称賛されても「合衆国のみならず、平和を愛するすべての国の人々、好奇心、未来へ希望を持つ人々を代表して」と、米国第一主義には反する意見を述べたという。さらに、宇宙飛行士仲間は次々と政界に進出しているのに対し、政治家への誘いを頑なに断ったニール。後日談ではあるが、テロップ等で扱ってほしかった。
これは月面着陸の映画ではない
観る前から、どういう映画か、何となく予想は付いていた。
まずデイミアン・チャゼル監督の過去の作品を思い出してみよう。
若きミュージシャンを死ぬほどシゴいた「セッション」、夢の実現のために愛を喪わせた「ラ・ラ・ランド」。そう、本作はこれらの作品と同一線上に置くことが出来る。
つまり、徹底して主人公たちにハードワークさせる、ということだ。もう、それは容赦なく。観ているこちらが「もう、やめて」と思うほどに。
ハードワークの末、どの作品でも主人公たちは「何事かを成す」。
本作では、人類初の月面着陸という偉業。
だが。
「ここ」で予想を裏切られる。
「そこ」ではないのだ。
そう、主人公ニールの成した事は「月面着陸」ではない。
幼くして死んだ娘を弔うことなのである。
本作では、画面の情報量は少ない。
登場人物たちの感情表現は最小限に絞られていて、なぜニールが娘の形見を月に持っていったのか、その経緯も理由もわからない。
だから、ラストシーンに驚く。
本作は140分超と長い。この尺で語ってきたのは、月面着陸のサクセスストーリーと見せかけて、実は愛する娘の追悼の旅だったのである。
だから本作には、全編を死の気配が覆っているのだ。
この娘にまつわるエピソードが本当かどうか、僕は知らない。
しかし、偉業とは、こういうものなのだろう。
国の威信を賭けたソ連との宇宙開発レース、注ぎ込まれる巨額の税金に対する批判。
こうした「大きな物語」は、現実には個人の人生とは関係ないのだ、ほとんど。
お国のためになんか、こんな死と隣り合わせの挑戦なんて出来るわけがない。
もちろん、必ずしもニールは、月面着陸をするということを初めから約束されていたわけではない。
そこには偶然や運もあった。
しかし、映画が始まって早々に、彼が宇宙飛行士に応募して面接を受ける場面ではっきりとこう語っている。
「宇宙飛行士になることは、娘の死と関係がある」と。
そう、映画が始まってすぐに、彼は娘を弔う旅を始めていたのである。
彼はずっと、娘の死をどう受け入れていいか分からなかった。だから言語化できないし、ゆえに娘の話はしなかった(できなかった)。
アポロ11号に乗るためには厳しい訓練も多くあったはずだが、そのシーンは描かれない。なぜなら、これは宇宙飛行士としての挑戦ではなく、娘の死を受け入れていく旅だからだ。
そして最後に彼は月に行き着き、そこで娘のために涙を流す。そう、わざわざ月面で、である。
本作で彼が続けてきた旅は、月への旅ではない。娘を弔う旅だったのだ。
地球に戻ったニールはガラス越しに妻と向き合い、そこで映画は終わる。
しかし、僕たちは想像できる。
娘の死を乗り越えて、ここからが彼の人生だろう、と。
これは死と再生の物語なのである。
期待して観た私が悪い
全編を通して描かれていたのは「死」である。冒頭からして夢落ちを祈ったくらい宇宙は孤独と死が隣合わせの空間だ。
それを素晴らしい映像でみせた技法は評価するものの、こんな葬式を観るために、交通費1万円をかけて映画館に来たのかと
エンタメ的盛り上がりの乏しさについ愚痴を言いたくなる映画だった
ワクワクしなかった
オープニング後、すぐに、計器が映し出される。これは、回想シーンなのか、どのタイミングのシーンなのか、さっぱり分からないまま、物語は進んでいく。ただ、何となく、手に汗握らなければいけないシーンなんだろうなぁ…と。でも、いきなりそんなシーンから始まっても、気持ちがついていかない。手に汗…握れない。そうしてるうちに、いろいろ人間ドラマとしての側面が映し出されるのだけれども、これまた、言葉少ない主人公アームストロングに、イライラさせられた。女目線で…、奥様目線で見てしまったからだと思う。そういう意味で言うと、人間ドラマとしては、良い作品だったのかもしれない。でも、月へ憧れる男のロマンみたいな部分は、共感できないし、いろいろな計器が映し出されても、どれくらいピンチなのか、あまり伝わらなかった。理系、もしくは男性ウケする作品なのかも…。
月旅行は命がけ
人類で初めて月へ行ったアームストロング船長を基礎とした映画。
だが、偉人伝でもドキュメンタリーでもなく、ニールという名前の一人のパイロットが直面する、死と隣り合わせの宇宙飛行が描かれている。
制限された視界と、ほとんどBGMを使わず、風圧や機械の軋む大きな音、無音などで構成された映画のため、序盤は面食らってしまうだろう。
これによって、安全の保証がない飛行をしているという緊張感が伝わってくる。
実際に自分が機内に同行しているかのような、アトラクション性を感じた。
(ただし、楽しいアトラクションではなく、危険を伴ったもの)
月でのシーンも実際にそこに行っているかのような、感動でもあり恐れでもあるような、不思議な感覚を得た。
こういう疑似体験ができる、ちょっと変わった映画だ。
このような特殊性の他、ニールの感情表現があまりなく何を考えているかわからないところ、家族を描写したシーンは日常の切り取り方はうまいがシーンとして多くないところなど、一般受けしにくい部分は大きいかも。
危険を伴う宇宙飛行へ向かう、それを疑似体験する、というところに興味を持つなら気にいるかもしれない。
音が重要な映画なので、他の観客のマナーによっても評価が左右される。
あのおじさんおばさんがいなければ、星4くらいつけたのかもしれないが。
魂を月に運ぶ物語
ニール・アームストロングの半生と言われて、苦難を乗り越えて最後に偉業を成し遂げる“英雄譚”を想像していた。実際は多くの人の死を背負って、魂を昇天させるために取り憑かれた男の悲愴で狂気すら感じる“冥界探訪譚”だった。
・アームストロングの娘の死で始まる物語(娘は一度幻覚として現れすらする)
・ロケット搭乗中などに度々起こる状況の理解が不可能なくらい激しく回転したりブレたりする一人称のカット
・真っ暗な夜空に浮かぶ青白い月と陰影が強調される暗いシーンの多さ
・悲愴感漂うBGM
・妙に人間味に欠ける無表情のライアン・ゴズリング
この辺の要素が重なって、前半はホラーかというくらい陰がある。後半は後半で同僚の死が重なり月到達以外のことが考えられなくなっている。あの世に片足突っ込んだかのような男にも元々家庭があったが、狂気と平穏のギャップに苦しむのはむしろ妻だったりして、やつれっぷりが酷い。
暗闇と荒涼とした大地が続き、音はないという月のロケーションはまさに冥界だった。有名な「一人の人間にとっては小さな一歩だが……」も勿論出てくるが、あまりに取ってつけたような感じがして物凄く浮いている。人類の進歩とか歴史とか、ましてや国際情勢とかのために月を目指したようには、少なくともこの物語では見えない。
生と死
事実なのでしょうが。。。
難しいミッションで失敗を繰り返し、不安と大義と犠牲者への思いなど、いろいろあるのはわかります。
わかりますが、見づらい。そして、行くのはあんなに大変。帰ってくるのも大変だと思うのにそこは無しなの⁉️戻る方がもっと大変だったと思うのに、そこほしかった‼️
ドキュメンタリーとしては
良かった。
幾多の失敗と犠牲があったからこその月面着陸なんですね…
どんなシーンから始まるのかなぁ? きっと回想シーンからさと思っていた自分の予想を裏切って、かなり緊迫した飛行シーンから始まって、すぐに物語の世界に引き込まれた。ニールは冷静で技術もあり、優れた飛行士だった。幼い娘のカレンの死を抱えながら、懸命に仕事に励んでいた。だが、その死について、他人やまして妻にさえも語ることができず、一人月を見ることで慰めていたように思う。私は、内に秘めずにもっと語り合えばよかったのにと思った。ニールももちろんすてきだったが、私は奥さんのジャネットがすばらしい人だと思った。特にいいなぁと思ったシーンは3つ。1つ目は、ジェミニ計画の時、ミッションが危うくなって自宅で聞いていた通信を切られた時。基地に怒鳴り込んで、再開するよう迫ったシーン。家族の不安を理解してもらおうと必死だった。2つ目は、同僚の奥さんと本当はもっと普通の生活を送りたかったと自分の本心を話したシーン。マスコミが詰めかけたりしない静かな生活を送りたかっただろうなぁと思った。3つ目は、アポロ11号の出発前に子どもたちに、失敗の可能性もあることを説明するよう懇願したシーン。同僚の中には亡くなった人もいて、自分たちもそうなるかもしれない。それを夫の口から話してもらいたいという気持ちは痛いほど伝わってきた。毅然とした人だけど、それらのシーンにさまざまな気持ちが含まれていて、すばらしかった。はやぶさ2号のリュウグウ到達で沸く日本で、こんなに力強くて感動的な作品が話題にならなかったのは残念だ。
孤独な映画
宇宙という壮大なテーマに対し、とても静かで淡々とした映画だった。本当に静かで、そして淡々としている。ただ、セッション・ララランドに活きていたチャゼル監督の音楽のセンスは今作からも十二分に伝わってきた。うるさくない程度だが効果的な音楽と、まったくの無音の対比にゾクゾクした。
個人的に一番印象に残ったのが、月に向かう主人公たちが亡くなった場合のスピーチを読み上げる場面。これ以前に地上での火災事故で主人公の友人が亡くなったことが描かれていた。宇宙に行くことがどれだけ困難で苦難に満ちたことなのか、ということが伝わるシーンなのだが、ここで使われた「水葬」という言葉にハッとした。当たり前のことだが、宇宙で死ねば死体は残らない。柩に死体を入れて水に流す水葬は、宇宙を流れるロケットのイメージに重なるように思う。
そして、帰りを待つ妻の元へは「計画は失敗した」という結果のみがかえってくるのだ。
結果的にニールアームストロングは人類初の月面着陸という栄光を成し遂げるのだが、彼が立った月にあったのは静と孤独と死だったのかと思うと、「 First Man」というタイトルには暗い影が滲むように感じられた。
全372件中、101~120件目を表示