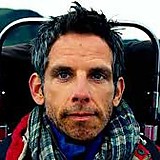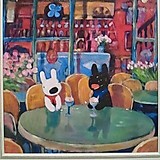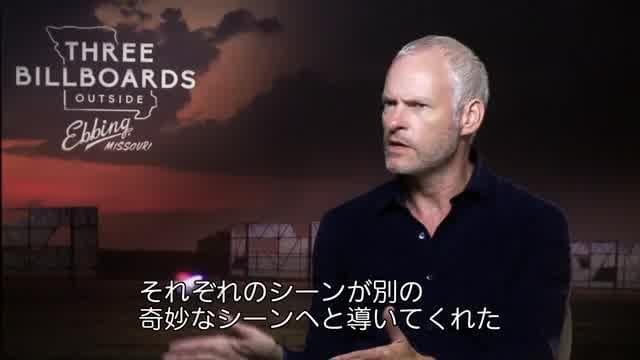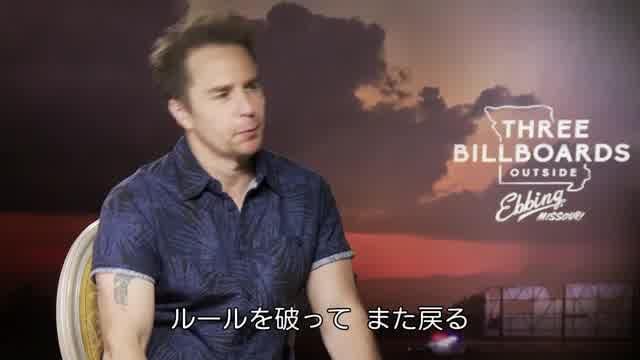スリー・ビルボードのレビュー・感想・評価
全501件中、41~60件目を表示
怒りではなんも解決しないってことを言いたかったのか?
予備知識0で観賞。警察不審を正す正義物かと思っていたら、娘の死にいくぶんからむ自責の念を晴らすために人のせいだと転換し、周囲の人たちをとにかく不幸にしていく胸糞物。一方、対照的だったのが広告代理店の元警官に対する罪を憎んで人を憎まず的なシーン。主人公の心の着地点が描かれていないので想像するしかないけど、要するに、怒りという感情は誰の得にもならないっていうことや、人のせいにしたところで自分のわだかまりは消えませんよっていうことをさとすための映画で、見ているあなたはこんな主人公のようになっていませんかっていう警鐘を諭すためのものなのか。そんなふうにとらえ、子を持つ親として気をつけようと思うことにしよう。
スリー・ビルボード
怒りの連鎖は時に関係のない人を巻き込んだり、後から後悔することになる。
作品全体は暗くて遅い印象たが、署長の自殺や看板の焼失等によって良いテンポ感に。
常に復讐心に燃える女性の演技が素晴らしい。だからこそ最後の笑顔が印象的だったし、良かった。
炎が怒りのメタファーに?
怒りの連鎖には暗闇の中光る炎があった。火事はもちろん、ライターの炎も。
署長の自殺は怒りとは無関係だったから炎が無かった。
最後、ディクソンは火事を起こした主人公を許したような感じ。ここで怒りの連鎖は終了か。あの後、レイプ魔を殺しにいってまだ怒りの連鎖が終わらないのか、殺しにいくのをやめて怒りの連鎖が終わるのか、どちらともとれる。スッキリとはしなくともベストな終わり方。作品としては綺麗にクローズした。
タイトルなし
一言で言い表せない、怒り、赦し、笑い様々な要素が入り交じる。娘を殺された母フランシス・マクドーマンドが捜査が遅々として進まない警察に怒り、ガンで余命間もない署長ウッディ・ハレルソンと対決するだけかと思いきや、署長は自殺してしまい、そこから複雑にストーリーが急展開していく。どうしょうもない差別的暴力警官サム・ロックウェルが暴走→クビ→火傷→改心赦しへと変化していく。ラスト単なる犯人探しだけで終わらず、結局犯人ではなく残念な気もするが、これはこれで良いのかも。
傑作に出会えた
まず、傑作と呼べる作品に出会えた事に喜びを感じる。
一つの事件と三枚の看板を基に数珠繋がりに絡み合っていくマーティン・マクドナー監督・脚本の完成度の高さをまず称賛したい。
その上でフランシス・マクドーナンドの熟練の演技が更に味を出している。
ちょうど本作の鑑賞前に「FARGO」を観ていたのだが、同一人物とは気づけないほどに雰囲気から何から変えられていた。ここには20年近い歳月だけでなく演技の幅の広がりを感じずにはいられない。
そして本作で最も輝いていた役者はサム・ロックウェルであろう。
登場の際の印象と、観賞後の印象でここまで振り幅を感じたのは初めてかもしれない。
次はサム・ロックウェル目当てで「リチャードジュエル」でも鑑賞してみようか。そう思わせるほどの存在感であった。
内容に触れていないが、良い作品というのは簡単な言葉で表現できず、けれど心に残る、そのようなものでありここでは書かないこととする。
未鑑賞でこちらを読まれた方には、まずは是非作品を見ていただきたい。
チェス盤の四方向から4人が勝負すると、どうなる? こうなる。
「戦いに関してはアマチュア」だが「怒りに関してはプロ中のプロ」である主人公が、惨殺された娘のために、戦いを挑み始めるお話です。
ただ、そもそも敵は誰で、どこに潜んでいるのか、皆目わからない。
とりあえず目の前の敵とおぼしき相手に片端から戦いを挑み始めるので、周囲のほとんど全員が彼女の敵になり、それぞれが思いがけない動きを見せ、なんだかチェスか将棋なのに4人で盤を囲んで四方八方から順番無関係に手が伸びて駒が意表を突いて動きまわる……みたいな、ストーリーの意外性を楽しむ映画なのかなと思いました。
くだくだしい説明を一切省略して、メインテーマに、いきなり観客を引きずり込む手腕はなかなかのもの。
絶対的権力を握るものが、批判されない立場にあると、どうなるか?
その絶望的な閉塞した気持ちは理解できるのですが、心を動かされるためには、ちょっとストーリーの作り込みが浅いかなと感じたのも事実です。
一例ですが、結末部分で、テーマの一番大切な部分を描かずに(描けずに)エンドロールに逃げ込んでしまったシナリオの腕。
かなり落胆しました。
暴れん坊母ちゃん
もがき苦しんだその先に・・・
この映画について事前に知っていたのは、母親ミルドレッドが、レイプされて殺された娘の事件の捜査が進まないことに業を煮やし、町はずれの道路に3枚の看板広告を立てる、という事だけです。娘の為に精力的に行動する母の愛、というシンプルなテーマかと思っていたら少し違いました。
アメリカ南部の寂れた、一見のどかに見える町には色々問題があり、人種差別、偏見、偽善者の事なかれ主義、人々は問題から目を逸らしていた。
「ここの警察は黒人だけを殴るんじゃないのか」というようなセリフがあります。また、神父に母親が「少年がどんなに犯されてもあなたは見ないふり」と言うセリフ。娘が犯されたのに敢えて少年、と言ったのは、「スポットライト世紀のスクープ」という映画で観た、実際にあった聖職者による子供への性的虐待事件を想起させ、この映画はアメリカが抱える様々の問題を描いていると思います。
一方、ミルドレッドにも問題があり、娘に最後にひどい言葉を投げかけた事に苦しんでいた。(しかし、あの道、夜は真っ暗で、徒歩なんて考えられない。私が娘なら友達に迎えに来てもらうか、出かけるのを止めますが)母親の警察への怒りは、そのまま自分への怒りでもありました。警察署長を始め一部の人間は心を寄せてくれるものの、町の人達や娘の父親である元夫にさえ中々理解してもらえず、母親は孤立していき、互いに傷つけ合う・・・その対極の無垢な存在が、馬や、寄せ植えの花や、若い雌鹿でしょうか。
予想したより複雑で、重い部分もありましたが、ミルドレッドの過激な行動は(犯罪だけど)痛快で、観て良かったなと思えます。
人生は過ちと後悔の繰り返し、でも悪いことばかりでもないです。
悪いやつはいない
話が終わる前に映画が終わった
あなたが動けば人は変わる!
凄まじいほどのB級作品でした・・・
まずタイトルにもなっている3つの看板ですが、
これが後々なにかの暗喩として役立ってくるのだと思っていましたが
特に何もなし。
それでも娘を凄惨な事件で亡くした母親の存在感はそこそこあります。
例えて言えばエイリアンのシガニー・ウィーバーや
ターミネイターのリンダ・ハミルトンみたいな
逞しく戦う女性の佇まいを持っています。
なのでこの母親が困難な道を切り開いてゆくものだと思って
鑑賞を進めていくのですが
この女性、実はただの悲しいばかりの脳筋なのです。
じゃあ誰が娘を殺した犯人を追い詰めてくれるのだと思い見てゆくと
登場時は酷いキャラクターとして存在していた人なのですが
その酷い性格の人が改心するきっかけがとても浅くつまらない物でした。
こんなに酷い性格の人間がたった一つの物や事で生まれ変わるとは到底思えない。
この人物に限らず全ての登場人物の性格付けがとても曖昧で作り込みも浅いので
誰にも感情移入できません。
それでも点数を2.5にしたのは時折母親や周りの登場人物が見せる
皮肉めいたやりきれない感のあるユーモアがクスッときたからです。
とにかくこの作品はミステリー要素もほぼ皆無。
何かを成し得る爽快感も皆無。
見終わった後のカタルシスも皆無。
ただただ行きありばったりでつまらない
B級ホラー映画を見た時のモヤモヤした疲れと
無駄に費やした時間の感覚だけが残りました。
唯一良心的解釈をすればこの作品が伝えたかったことは
人は見かけじゃない、無敵なヒーローなんかいない
きっかけさえあれば人は変わることができる
そんな事を言いたかったのかなぁとかなりいい方に解釈すればですが
そう思いました。
とにかく時間の無駄でした。
よく幾つかの賞をもらえたものだと驚きます。
ミズーリの湿り気のある雰囲気とともに
オレンジジュース
この映画を見たとき、伊坂幸太郎の小説「PK」に出てくる言葉を思い出した。
「臆病は伝染する。そして、勇気も伝染する」
この映画を表すとしたら、以下のようになるだろう。
「怒りは伝染する。そして、優しさも伝染する」
はじめ、登場人物たちはそれぞれが怒りを抱えていた。けれど、署長のディクソンを見守る優しさ、広告屋の青年のオレンジジュースを差し出す優しさが、徐々に皆に伝染していったのだと思う。最後、ディクソンとミルドレッドは優しい顔をしていた。この映画は悲劇だし、ハッピーエンドでもない。でも、不思議と、後味の悪くない映画だった。
母の強さ。そして母の弱さ。
事前知識が全く無い状態で鑑賞しました。タイトルだけ聞いたことがあったので、レンタルDVDの棚にあったのを見かけて借りてみました。
結論から言うと、非常に楽しめました。映画の序盤だけを見ると「娘を殺された母親の復讐劇かな」と思ってしまいそうですが、よくあるリベンジものの映画とは異なり、復讐は達成されないまま映画が終わります。でも、これ以上は無いくらい綺麗で爽快感のあるエンディングです。私は大好きです。
・・・あらすじ・・・・・・・・・・・・・・・・・
アメリカ・ミズーリ州の人気の無い田舎道で凄惨な少女殺人事件が発生する。事件から7ヶ月経過しても一向に解決の兆しを見せない捜査に抗議するため、少女の母親であるミルドレッドは町外れに警察署長を批難する三枚の広告看板を設置した。地元警察や地元住民はこれを快く思わず、ミルドレッドとの間には深い溝が生まれてしまう。そしてこの三枚の広告看板をきっかけに、事件は思わぬ方向に動いていくのだった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
娘を殺した犯人を突き止めたい、母親。
自分たちを批判する看板を撤去させたい警察官。
姉の死を思い出したくも無い弟。
事件解決の証拠が無くもどかしさを感じる警察署長。
娘の死についてミルドレッドを責める元亭主。
様々な人のそれぞれの思惑が交錯し、物語は思わぬ方向へ転がっていきます。
それぞれのキャラクターの考え方や会話がとにかく素晴らしく、アメリカ的な軽妙な会話シーンも楽しいですし、シリアスで重いシーンも引き込まれるような魅力があります。
キョーレツな怒りを表しています。
フランシス•マクドーマンドが「ファーゴ」に続いて2度目のオスカーを獲得しました。
始めのシーンで、神父が親身なフリをして訪れたのを彼女が叩き出しますが、
「見て見ぬフリをするのは罪に加担していることと同じ」という
ミルドレッドの怒りを吐き出しています。
以降、この怒りに突き動かされるように話は進んでいきます。
やがて、自身にもあった差別の意識に気付かされることになるのですが。
アメリカ南部の片田舎の閉鎖的な町で次々と起こる事件、
息を飲む展開です。
この映画では、特にラストが面白くて、公開時に見た時、
へぇ〜、アメリカもちょっとは変わったかな、と感じました。
未だに銃社会ですが。
怒りを胸に、どう向き合っていったらいいか考えさせてくれる作品です。
それぞれの「正義」
・・・。
自分の映画を鑑賞する眼、人間としての感性の未熟さを痛感しました。鑑賞後、これみよがしに語れるような感じたこと、考えさせられたことは、正直に言うとなにもなかった・・・。
ウィロビー署長の生き様に心打たれまり、ディクソンの正義感の目覚めに感心したりはしたものの、この映画の本質はこんなものじゃないんだろうと感じます。
どの人も主人公らしくない善の行動と悪の行動を繰り返し、レイプ犯の正体もボードの放火犯の正体も、なにも解決することなく、誰にも感情移入させることなく、ものがたりが終わった。。「なんのために映画を観るのか。」ということを改めて考えさせられました。他の方々の感じたこと、思ったこともいつも以上にじっくり見てみたいと思います。
今はこの感想が紛れもない僕の現在位置。時が経って振り返った時に「オマエ、なんにも分かってねぇなぁ(笑)」と思えるのだろうか。。
愛と暴力
全501件中、41~60件目を表示