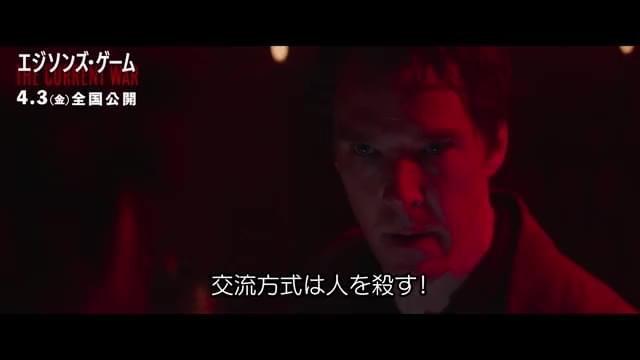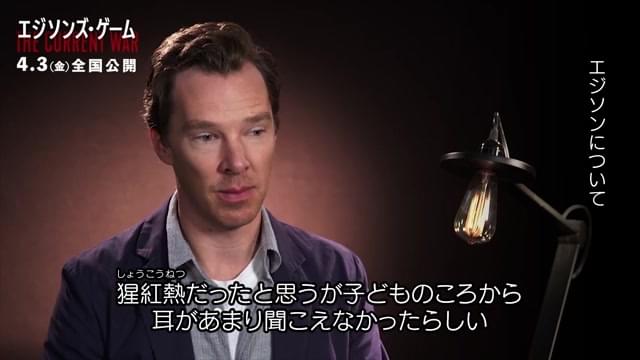エジソンズ・ゲームのレビュー・感想・評価
全120件中、1~20件目を表示
主人公エジソンが嫌な奴という珍しい物語構成
エジソンのイメージは、さほど詳しくない人なら発明王、天才、偉人といったところではないだろうか。そんな印象のままベネディクト・カンバーバッチ主演の本作を観ると、傲慢で尊大な性格、実業家ウェスティングハウスを見下した言動、若き天才科学者ニコラ・テスラの芽を潰す仕打ちなど、“嫌な奴”エピソードの数々に驚かされるはず。
もちろん、妻への愛情など人間的な面も描かれてはいる。それでも、本作の主題である電流戦争に関しては、直流方式を推すエジソンが名声と資金力に物を言わせ、ウェスティングハウス+テスラ陣営のより優れた交流方式をあの手この手で潰しにかかる姿が実に憎らしい。ニコラス・ホルト演じるテスラが不憫だ。史実に基づくドラマなので仕方ないが、テスラがもし出会いに恵まれ、若い頃から存分に発明の数々を実用化できていたら、今の世界も相当違っただろうにと思わずにはいられない。
大好物の天才モノのはずだが、楽しめる要素やアガる要素を見つけられなかった。
テクノロジーに関するバックグラウンド知識も特に解説してくれてないし(解説を読んでやっとしっくりくるレベルだし)ゴリゴリ理系の小生でもdon't think. feelに陥ったのでこの点はなかなかに不親切だっただろう。
その点を譲って漢同士の覇権争いを素直に楽しめたかというとそこもイマイチ。ウェスティングハウスの心に火が着くのが遅すぎた印象。
中盤までエジソンの一方的な遺恨のようなトーンで描かれていたなあ。突破策も論理的なものでは全くなく要は姑息なネガキャンでなにこれってなった笑
テスラの立ち位置も中盤の事業失敗などほぼ他人みたいな時間があったために、いざ寝返ったときの印象も薄いし。
映画館で眠くなったけど悔しくなかった作品。
不完全燃焼感
キャサリン・ウォーターストン
君の不正は掴んだ
過去に、レンタルで観ました💿
ベネディクト・カンバーバッチ演じるエジソンと、マイケル・シャノン演じるウェスティングハウスの電流戦争がメイン。
2人の演技合戦もさることながら、トム・ホランドもエジソンの右腕インサルを演じます🙂
そしてテスラにはニコラス・ホルト😀
映画なので脚色されてるでしょうが、繰り広げられる駆け引きは見応えありました🤔
ラストは哀愁漂うもので、これはこれで一つの物語として楽しめます🫡
カンバーバッチとシャノンの対決が観たい方はおすすめです❗
エジソンってこんな人だったの…
発明家達の戦い 〜 直流か交流か
発明王トーマス・アルバ・エジソンをベネディクト・カンバーバッチが演じる。
エジソン、理論家の発明家ニコラ・テスラ( ニコラス・ホルト )、実業家ジョージ・ウェスティングハウス( マイケル・シャノン )、発明家達がしのぎを削る様、19世紀の生活スタイルが興味深い。
時間を忘れ研究に没頭していたとされるエジソンと、妻や子供達との関係性に救われた。
BS-TBSを録画にて鑑賞 (吹替阪)
金には興味が無かったエジソン
二兎を追ってはいけなかった。
正直言って偉人エジソンのイメージが壊れました。
期待ほどには面白くも楽しくもない・・が、正直な感想です。
2019年(アメリカ)
原題は「電流戦争」です。
発明王エジソン(ベネディクト・カンバーバッチ)とカリスマ実業家ウェスティングハウス
(マイケル・シャノン)の間で起こった電流戦争。
それを中心に描いた地味な映画で、心躍るシーンもなく、これと言って楽しい映画ではありませんでした。
1880年。
発明王として名声を欲しいままにしていたエジソンだが、アメリカ大陸の西部に、
電力の送電システムを広げる競争が勃発する。
送電の費用の安い上に遠くまで電気を送れるウェスティングハウスの交流送電と、
対するエジソンの直流送電は遅い上に費用がかかる・・・。
そして巻き起こる「電流戦争」の行方?
その戦いにエジソンが「交流電流は危険だ!!」とする、ネガティブ・キャンペーンを繰り広げる。
このあたりからエジソンの発明王の偉人伝から、大きく逸れてしまって、
なんだかなあ・・・と、ガッカリしました。
「発明は金なり」と思えて来ます。
生涯に13000もの発明をしたエジソンは、それはそれは勤勉な人だったのは確かです。
そして今、私たちは電気の恩恵を、それこそ数え切れないほどの恩恵を受けていますね。
照明、電気製品、インターネットそして人工知能まで、電気がなくては生きていけないのは、2018年の胆振東部地震でたった45時間停電しただけなのに、
テレビ、電話、冷蔵庫、インターネット(Wi-Fi)を使えないだけで、生きる限界を感じてしまいました。(心底、有り難さが、身に染みました)
そのエジソンさんですが、彼は他にも、蓄音器、映写機、カメラ、などなどを発明。
今では「映画の祖」と呼ばれ、映画の分野には大きな功績のある人でした。
つくづくと発明の複雑さ・・・決してエジソンひとりの発明品と言い切れない側面、
・・・特許権と、そして訴訟王とも呼ばれたエジソンの裏の顔など。
(電気椅子のエピソードなど・・・も、)
やや複雑で詰め込み過ぎの感もあります。
(ただし無数の白熱電球が、駅舎を照らすシーンは、感動ものでした)
ラストに華々しい点灯式を持って来たら、感動出来たかも知れませんね。
傲慢なエジソンの実態
トーマス・エジソンと言えば、1800年代後半に、白熱電球や蓄音機など、多くの発明品を世に生み出した発明家のイメージを誰もが持っているだろう。本作では、その発明家としての実績の裏に隠され、あまり知られていない、起業家としての苦悩や敗北を史実に基づいて描いている。
発明家としては天才的な気質を示したエジソンだが、金には執着することなく、大統領からの命令にも応じないという、その傲慢な態度故に、敵も多かったことが覗える。本作では、電力システムの違いからの、直流送電を中心としたエジソンと交流送電を中心としたウェスティング・ハウスとの『電流戦争』を取りあげている。
最終的には、シカゴ博覧会を境に、ウェスティング・ハウスの交流送信が、勝利をおさめていくのだが、そこまでに、エジソンが抱いたウェスティング・ハウスへの敵対心は、凄まじいものがあった。交流送信に反対するプロパガンダを煽動したり、交流送電を使用して、多くの動物を使っての殺処分や死刑執行の手段として試みて、その危険性をアピールした。決して子供用の伝記では語られないような、エジソンの高いプライドからくる傲慢さと醜悪な態度がうかがえた。
また、そこに最初はエジソンの元で働いていた、技師の二コラ・テスラ(現在の電気自動車メーカーの名前の元にもなった)がもエジソンのやり方に反旗を翻し、ウェスティング・ハウスに寝返って、共に交流送電に勝利に貢献したのも面白い。
こうして観てくると、電流送信に関しては、エジソンより、ウェスティング・ハウスの方が功績は大きいように思う。しかし、恥ずかしながらこの作品を観るまで、彼の名前を知らなかったというのは.偉大な発明家としてのエジソンに、歴史は軍配を上げたのかもしれない…。
出演は、偏屈で傲慢なエジソンに、ベネディクト・カンバーバッチ。敵対するウェスティング・ハウスには、マイケル・シャノン。意外だったのがエジソンの助手役に『スパイダーマン』のトム・ホランドやウェスティング・ハウスの強気な妻役に、『ファンタスティック・ビースト』のキャサリン・ウォーターストンが出演していたこと。なかなかの人気俳優が、脇を固めていているのも楽しめる。
前評判はなんだったのか
ちょっと地味な作品
電気に詳しかったらもっと楽しめたかもしれませんが前半は眠くなるほど退屈に思ってしまいました
ストーリーが進むにつれて、エジソンって嫌な人だったん…で、小学生の時から天才発明家であって偉人のイメージしかなかったらちょっと驚きでした
「人々や街に灯りを」の思いではなく、自己顕示欲が強いエゴイストにしか思えませんでした
ライバルのウェスティングハウスの方がよっぽど懐の深い人でした
ウェスティングハウスの「フェンスを作らなければ庭は2倍の広さ」、良い言葉です
発明だけでなく、人との付き合い方も今の国際情勢もこういう気持ちが大切なのではないかとつくづく思います
テスラは天才でありながら人に恵まれなかったのか可哀想な人のようでした
その役のニコラス・ホルトは相変わらずステキでした
イメージが変わった・・・
発明王エジソンの伝記は幼い頃に読んだがその頃は小学校を退学になって母親の教えで育ったことの方に驚きをもっていた。子供のころから商売熱心で列車で手作りの新聞を売っていたり15歳の頃には駅で働くようになり電信を学んで定時電信機を作ったりしていた。もっともこれは夜勤で寝てもいいようなさぼりの為の発明だったらしく御咎めを受けて駅員を止めている。発明の知識は図書館通いで独学で習得しているのだから名言にあるように努力の天才ですね。22歳の時に改良発明した株価電信印刷機ストックティッカーの特許で4万弗の莫大な利益を上げ発明に一層邁進する。
映画はエジソンの伝記ではなく長じてから、JPモルガンの資金援助で電灯会社を立ち上げるようになりウェスティング・ハウスとの電流戦争(原題のThe Current War)を繰り広げる様を綴っている。
まさか電気椅子に関わっていたとは驚いた、どこまでが真実かは分からないが余りにも独善的で偏屈な人物に描かれているのでこれまでのイメージが壊れてしまったのは残念。
天才テスラをないがしろにしたのは大失敗だと思うが部下には後に自動車で大成したフォードもいたのだから人を観る目が全く無かったわけでもあるまい。
うがった見方をすれば映画業界はエジソンの特許料徴収や訴訟などで疲弊した歴史から辛辣なビジネスマンとしての側面も描きたかったのかも知れませんね。本作はトロント映画祭に出品されたハーヴェイ・ワインスタインのバイアスがかかった作品から追加撮影や再編集されたディレクターズカット版のクレジットがついています、トロント版は不明ですが悪名高いワインスタインの描いたエジソン像がどうだったのかちょっと気になります。
高校の時に電気科に居た自分でも
全120件中、1~20件目を表示