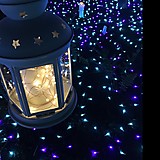夜明けの祈りのレビュー・感想・評価
全38件中、21~38件目を表示
祈りがもたらす希望よりも大きなもの
1945年12月、雪の積もったポーランドの修道院。
マリアというひとりの修道女(アガタ・ブゼク)が医者を探していた。
しかし、医者はロシア人でもポーランド人でもダメだという。
辿り着いたのはフランス人たちによる赤十字。
マチルドという女性医師(ルー・ドゥ・ラージュ)に頼み込んで、修道院に来てもらうが、マチルドが目にしたは臨月に苦しむ若い修道女の姿だった・・・
というところから始まる物語で、第二次世界大戦末期、ナチス・ドイツの占領はソ連軍により解放されたが、その際、修道女の多くはソ連兵に凌辱され、何人もが妊娠してしまったという。
実話に基づくというのだから驚きだ。
ドイツとロシアに挟まれたポーランド。
隣国に蹂躙され続けた歴史は、アンジェイ・ワイダの映画の中でも観ることはできるが、ここまで衝撃的な題材はなかったように思う。
修道院の閉鎖や近隣からの侮蔑の眼を恐れる修道院長は、修道女の多くが妊娠していることを世間に知られたくない。
そしてまた、神の前の純潔を誓った修道女の多くも、現状を世間に知られたくない。
そんな中で、出産が近づいてくる・・・というサスペンスが醸し出されていく。
修道女の多くは神に縋ろうとするが、当然のことながら、神は手を差し伸べてはくれない。
こんな状況を救うのは、やはり「ひと」なのだが、「ひと」には縋れない。
なんともジレンマなこと。
その中でシスター・マリアがいう言葉が興味深い。
「わたしたちの暮らしのうち、24時間は疑問です。しかし、1分の希望を得るために神に祈っているのです」
1分の希望。
ただただ、そんなわずかな希望のために祈ること。
それが、信仰というものなのか。
よくわからない。
しかし、祈ることで得られる希望は、たぶん、現実のものとはならない。
この映画でも、最後の最後に苦しんでいた修道女たちを救ったのは、女性医師マチルドの勇気と機転のある行動だった。
そして、修道女たちにもたらされたのは、実現可能な希望。
衝撃の実話
愛の光
尊厳と信仰、一瞬の希望
戒律とか主義主張の前に、人として、どうあるべきか、問われている気がします。信仰が、人を強くするかと思いきや、道を誤らせてしまう件は、観て辛かった。それでも24時間の疑問のうちに、1分に満たない僅かな希望があるとすれば、やはり信仰は人の支えになるのでしょう。
ラストの神々しさ、ほとんど反則技ですね。赦しの心と、未来を生きる新たな希望。手助けするか、見て見ぬふりするかは、私達に委ねられたのかも。本作は、単なる昔話では、ないはずです。
本作に、何か思うものある方は「サラエボの花」をお勧めします。失われた尊厳と、その先にある日常…。この問題は、解決するどころか、深刻になっているようです。映画観たところで、世界は変わりません。それでも観てほしい、そして、知ってほしい。戦争と暴力は、セットでやってくることを…。
一切捨てショットが無い
幸せは、誰にも分からない
考えさせられる。修道女である彼女たちは、イエスを拠り所にして生きている。本編中でも、「信仰とは、最初は子どものようなもの」だと言う。信じているのにも関わらず、理不尽にも突然その拠り所を失う時があり、そこで道に迷うのである。
彼女らはその時、どのようにして生きてゆけば良いのだろう?
信じていたものに突如にして見放される。不条理な困難に襲われる。そこで信心を失いかける彼女らはどう生きるのか。
熱心な信仰によるプライド・正義心と、理不尽性とがもつれ合い、視野が狭まり道を違う者もいる。そしてそれによって負の連鎖が起こり、さらに信仰を疑うことになる。
また、強い信仰心を持ちつつ、その中でも自らが正しいと思う道を進む者もいる。彼女は厳しい戒律に反してでも、何が一番大切なのかを客観的に捉え、生きるのである。
そう、本編中でも言っていたように「何が幸せかは誰にも分からない」のである。それが強い信仰心を持ち、自らの貞節を守り、神の下に生きることなのか、どういう形であれ新たな命に対して母親として子供と肌身を晒して生きることなのか。それとも全てを捨てて自由に生きることなのか。それは人それぞれである。
この物語のラストに、彼女らは、彼女らなりの幸せの解の1つを見つけることができたのだと思う。マチルダに会えたことは、思い返してみれば確かに神の救いかもしれないが、そこから先は彼女らとマチルダらの奮闘による、非偶然的なものであろう。
ストーリーとしてヴィルヌーヴっぽさもあったが、最後に良い結末になってよかったと個人的には思った。ヴィルヌーヴよりはストーリーに鮮やかな色合いがある。それにしても、これが実話に基づいているということは衝撃的である。
神はそこまで狭量だろうか
ソ連兵の暴行で神の花嫁たる身を汚され、身ごもったことで悩む女性達。でも生まれた赤ちゃんを抱く姿は聖母マリアと同じだと私が思うのは、冒涜だろうか。女性たちが受けた暴力とその結果を神は罰するだろうか?神は全てを受け入れて、慈しみ愛してくれるのではないだろうか。ラストシーン近くの子ども達が走り回り赤ちゃんが笑う修道院こそ、神が愛する場所だと思う。
医学的見地
淡々とし過ぎていて…。
女性の脆さと強さと美しさ
白と黒の美しさ
静かに考える映画
闇に葬りかけた史実に灯をあてた秀作
作品が始まって直ぐ「この作品は史実に基づいています。」というテロップがでます。最近、史実に基づいた…と謳う作品に遇います。何かこれが私自身の色んなレビューを書く「壁」になっています。「これは、事実なんで」と言わんばかり。何処までが事実なんだろうと思ってしまいます。
過去に起こり得たことは、闇に葬るのではなく、真正面から向かい合わなけれならないであろう。
今回の作品、邦題が極めて美しい情景のイメージを受けましたが、その内容は物凄く惨く悲しい作品であった。作品を見終わって、修道院の院長マザーオレスカという女性。かなり憎みました。日ごろから、神への愛や信仰の祈りはなんであったのか。
女性が「子供を産む」ということが、いかに魂の救済であり、「神からの授かりもの」ではないのか。しかし、彼女だけを恨むのは全く間違ったことであると感じた。一番に恨むことは、人間がいかに醜い争いをしたこと。過去の人間の悪行が愚かであったことを未来に向けての平和ある秩序ある地球、世界にすることが我々の使命であることを訴えかける(多少気分が悪くなる内容ではあったが、此処も史実らしい。)作品であった。
やはりズシリと来る作品ではあったのだが、疑問に残る所はある。フランス赤十字に働くマチルドが上の者に事実を述べ、修道院に起こった出来事を訴え、助けることを進言しなかったのかということである。サミュエルも同じ。
閉鎖的であった修道院が、ラストあまりにも開放的で眩い修道院になったことへの場面は、落差が大きく過剰演出ではないかとも思った。(これも史実に基づいたことなのか。)
無残にも亡くなってしまった神の子が、ただただ希望の灯を浴びていることを祈るばかりである。
誰も語ろうとしない戦争の犠牲者たち
信仰と命
修道女が雪道を走るシーンの美しさからはじまる。
舞台は第二次世界大戦後の混沌としたポーランド。若きフランス人女医がソ連兵からの蛮行によって身ごもってしまった修道女たちを救った実話をもとにした作品である。
線引きをする、という行為は誰でも無意識にしている。例えば国境、性別、宗教、、などだ。修道女たちは度々、神の秩序のためにその身に宿った命を頑なに隠そうとする。信仰か、命か、その選択を迫られた時、女医のマチルドは国境という線引きを越え、命を救うために冷静に力強く行動した姿は逞しく偉大だった。
救い とは何であるのか。救いを求めての信仰は、本当の意味での 救済 であるのか。度々考えさせられた。
フランス映画祭2017のトークで、このような事件が今も続いているということを忘れてはならない、と監督が語っていたのが印象的。
全38件中、21~38件目を表示