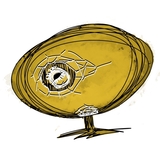サーミの血のレビュー・感想・評価
全45件中、1~20件目を表示
自由を求めるヒロインのたくましさに魅せられる
1930年代。厳しい自然に囲まれた北欧、ラップランド。この物語は、先住民族サーミ人が受けていた差別の歴史を描いた物語でもある。寄宿学校での教育や教師から発せられる言葉、人々がサーミ人へ投げかける冷たい視線などは身を切るほど辛いものがある。が、それでも本作が一向に魅力を失わないのは、ひとえにヒロインの逞しい存在感があるからだろう。彼女が日常の中で何を考え、どのような思いを発露させ、やがてどんな決断を下すのかに主軸を置いて、その心の流れを丁寧に描き出すのである。
当時、多くのサーミ人たちが故郷を捨て二度と戻ることはなかったという。本作は故郷に残った者、故郷を捨てた者のどちらの正当性を訴えるのでもなく、あくまで少女の視点に特化することで“感情”を描き出してみせる。こうした演出ゆえに決して昔話に陥ることなく、現代に生きる我々でもダイレクトに享受できる豊かな心象模様がもたらされたように思えるのだ。
人種差別
サーミ人とは、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドの北部とロシアのコラ半島でトナカイを飼い暮らし、フィンランド語に近い独自の言語を持つ先住民族。映画の主な舞台となる1930年代、スウェーデンのサーミ人は他の人種より劣った民族として差別された。(公式HPより)
主人公となる少女エレ・マリャ(レーネ・セシリア・スパルロク)は寄宿学校で優秀な成績をおさめていた。学校ではサーミ語を使わずにスウェーデン語を使わなければならないが、言葉も両方流暢に使いこなしている。帰り道では白人の青年たちから差別的な言葉を投げられ、いつも悔しい思いをするのです。そんな彼女も進学を希望するが、優しい先生から厳しい言葉が発せられる。「サーミ人の脳では文明に適応できない」と。
ある日、エレはスウェーデン人になりすまして忍び込んだ夏祭りで、クリスティーナと名乗り、都会的な青年ニクラスと出会い恋に落ちる。彼を頼ってウプサラという街に出たエレは彼の家に強引に泊まる。ニクラスの母親は「あの子ラップ人でしょ?」と言われ、長居もできなくなってしまう。そんなエレが学校の図書館に入り、本を読んでいると高校の教師から誘われたのだ。これでスウェーデン人に溶け込める・・・と思ったのも束の間、授業料を請求されたのだ。
差別的な扱いを受けても初等教育だけは受けられる。幸か不幸か頭が良かったためにスウェーデン人になりたかったエレの人生。エレには妹ニェンナもいるが、ごく普通の子であったため生涯をサーミ人として過ごし、姉の分までトナカイを育てていたことが告げられる。老婆となったエレがニェンナの葬儀に参列するため故郷に一旦帰るのだが、サーミ人の仲間から逃げた身には辛いものがあった。子どもの頃に白人から受けたイジメとは逆に、逃げたサーミ人として白い目で見られてしまうのだ。
イジメを受けるシーンになぜだか臨場感があり、教師から決定的な言葉を投げかけられたときのショックも手に取るように伝わってきました。なんとかスウェーデン人に溶け込めるようにと祈りながらの鑑賞。しかし、波乱万丈の人生だったろうなぁ・・・
どう向き合うか?
【”民族間に優劣などない!”サーミ人の娘エレ・マリャが、スェーデンの女教師、クリスティーナの名前を終生名乗っていた哀しき理由・・。】
ー 今作を観て、日本人であれば、即座に倭人と、アイヌ民族との哀しき関係性を想起するであろう。人によっては、沖縄の人と、ウチナンチュウとの関係性を想起するかもしれない。
歴史的に観れば、第二次世界大戦前に、ゲルマン民族至上主義に走った男に追従した国民と、犠牲になったユダヤ民族や、近年で言えばウィグル自治区に居住させられているウィグル民族と、漢民族との関係性や、ミャンマー政府から虐げられているロヒンンギャの人々との関係性も想起させられる作品である。ー
◆感想<Caution! 内容に触れています。>
・冒頭、クリスティーナを名乗っているサーミ人の年老いたエレ・マリャの沈痛な姿が映し出させる。
・その後、物語は1930年代(当時の資料より)のサーミ人の若きエレ・マリャと妹ニェンナが、スェーデン人と思われる若者達から、”臭い”などと言われるシーンに移る。
このシーンだけで、当時、ラップランド地方でトナカイを買い暮らしていたサーミ人の立ち位置が分かる。
この後、度々映される、サーミ人の自然の精霊に対して、畏敬の念を払うヨイクの音色がとても、魅力的なのに・・。
・更に、スェーデン人の女教師クリスティーナから”サーミ語は禁止。スェーデン語で話しなさい・・”と学校で、サーミ人の子供達が言われるシーンや、エレ・マリャ達が”身体検査”と称した骨格検査や、裸体での写真撮影を強要されるシーンも映し出される。
ー スェーデン人達にとってはごく普通の”生体調査”だが、若きサーミ人達にとっては、屈辱でしかないであろう・・。ー
・エレ・マリャはスェーデン人のふりをして忍び込んだ夏祭りで、スェーデン人のニクラスと出会い、恋に落ちる。
だが・・。
<そして、頭脳明晰なエレ・マリャは、哀しき決断をする。
”サーミ人として生きていては、この国では真面に扱われない・・。”
最後半、クリスティーナを名乗っている年老いたエレ・マリャは、故郷に戻り、棺の中で永遠に眠る妹ニェンナに頬を寄せ、涙を流すのである。
民族に優劣などない。
何時になったら、民族間抗争、もしくは一方的な弾圧は無くなるのであろうか・・。>
<2017年10月 京都シネマにて鑑賞>
<2021年8月3日 別媒体にて再鑑賞>
偏見は、血だけではない。
「血」という、実は誰にとっても身近で深いテーマです。生まれは自分では選べません。だから、出自を蔑んだり誇っても意味がないことなのに、単に「異なってるね!」だけでは終わらない。なぜか上下や優劣の評価をしたがる。人間の哀しいサガなのか。
偏見は、私たちが生きていく中で、そこら中にあります。血だけではない、家柄、学歴、経歴、性別、親の職業、容姿... なんでも縦の評価軸で捉えたい人間は、相変わらずたくさんいます。
主人公はサーミ出身、蔑まれる側ですが、一方で部族に従順な妹に対しては「自分の将来も考えられないバカ」と辛辣な言葉で蔑みます。
主人公は成績優秀、スウェーデン語もペラペラ、先生のお気に入りなのです。私、頑張ればスウェーデン社会でもやっていけるんじゃ?努力次第で。そう思うのは当然のなりゆき。
単なる無鉄砲ではない。
自信があるからこそ、いわれもない見下しに、矛盾と抵抗と正当な怒りを感じてしまう。
変な身体検査までされて、怒らない方がおかしい。
人間じゃなく、動物扱い。
そうです、本人が言うように、
バカならそこまで怒らない。
知性があるからこその怒り。
そして突き抜けていく。
想像以上の荒野へ。
偏見って非合理的なのに、社会がいったん誰かの感覚によって歪められた枠組みを設定してしまうと、歪みが常識となり、もはや己れの歪みにも気付けなくなってしまう。
でもその枠の外にいる者から見ると。
その枠型は絶対なものではなく、歪みを自慢する優生側の方こそむしろ知性が低いのではと感じる。
偏見はそういうフシギなものだと思います。
実際に本作で出てくるサーミの人たちは、民族衣装も子供達も、日本人である私から見れば素敵だし、とても愛らしい。
でもスウェーデン人は侮蔑的に見ているらしい。私は、スウェーデンは男女同権が進んだ、偏見や差別を克服した国、羨ましいとずっと思っていました。
でもどうやらそれは光の部分。
光があれば、影もある。
偏見を減らすってやはり簡単ではないのですね。
どんな社会でも、
生きにくさを感じながらも自分が今いる集団の中で、死ぬまで守られて生きる人生もあれば、
成長と共に集団のガラスの天井に頭がついてしまって、突き破って抜けていかざるを得ない人もいる。
たとえ外の世界が荒野であっても。
映画は、とにかく居心地の悪さ、いたたまれなさが延々と続きます。
主人公は突き破って荒野へ出ました。
勇気も能力もある少女。
が、終始、何か影がつきまとう。
どこへ行っても。
家族を捨てても、
名前を捨てても、
憧れの教職についても、
故郷に戻っても。
何か自分を偽っている感じ。
外向けの自分を大きくすればするほど、
隠している自分が、影を作り出すのか。
今のSNS社会とも通じるでしょうか。
サーミであることはなんら恥ではない。
けれども、スウェーデン側の教育によってサーミは劣っているという偏見を刷り込まれ、サーミである自分を認められない。
むしろ差別する側に自分も同化して、必死で見下されないようにしている。母親の「このスウェーデンかぶれが!」と娘を罵る言葉が、痛い。
主人公自身にも差別意識が芽生えた臭いに、母が鋭く反応します。
でも主人公が進学したいという気持ちは本物。
賢く、好奇心が強い。
数々の偽りも、スウェーデン社会に受け入れてもらうため、自力で生きていくための必死さゆえです。
でも、いじらしいという言葉は相応しくない。
他人がどうこう言えるような、そんな甘っちょろい道のりではなかったと思う。
映画は多くを語りません。
老婆となった主人公が映るだけ。
これで良かったのだろうか。
その問いはまだ終わっていない。
私は主人公の姉妹愛が、唯一救われどころでした。
妹も、お姉ちゃんが集団からはみ出して、みんなから疎まれているとわかっている。お姉ちゃん嫌われてるよ!と責めたりもするのですが、いかんせんまだ幼さの残る二人、無邪気に水遊びする。よくなついている妹。
お姉ちゃんも理屈じゃなく、妹のこと好きなんですね。
だから何十年も経て、妹の葬儀に帰ってきた。
主人公の寂しさに、人間らしい、血の温かさを感じました。
1930年代の設定だと!
この物語の何箇所かは監督の祖母の話だと後で読んだ。今でも少数民族に対する差別は根深く残っていると思うが、これがいつの時代か気になって調べてみると 1930年代の話だ。14歳ごろサーミの土地を離れ、60年ぐらいたって、妹の葬儀が理由でサーミの土地に戻ってきた祖母の話。
偏見や差別、嫌いな文化から逃れるため、自分を偽ってきた。人々に蔑まれ、何ひとつ、希望を与えてもらわず、それに、頼ればそれが間違いだったと気付かされ人生を生きてきたと思う。エレ・マリャのいくつかの人を利用する行為は同意しないけど、これだけ自分の血や育ちを嫌っていきた彼女の最後のシーンの姿。血は争えないというより、60年もラップランドのサーミの土地と家族に対する謝罪と郷愁に駆られて、妹に誤り、山を登ってあがったと思う。
学校の先生『あなたはスウェーデンの子供たちと同じスキルをもっていない。エレ・マリャ、あなたはかしこい。でも家族を手伝わなきゃ。あなたたちだけが、必要なスキルがこの村にある。』
エレ・マリャ『もしここにいたくなければどうしたらいい?』
も
学校の先生『それにかんしては私は何もできないよ。』
エレ・マリャ『じゃああ誰が決めるの?』
学校の先生『統計が証明しているの。あなたたちは街に行って他の人と交わることができないって。あなたたちはここに住むの。そして、死んでいくの。ここで、』
この学校の先生の言葉はエレ・マリャを失望させた。こういう考えじゃ、このサーミの生徒たちを教えることができない。ただの仕事として教職についているだけなんだなあと。なんて思うけど1930年代のラップランド。しかし、この主人公、たくましいが、全く笑いがない。心に余裕がない人だったね。いや、彼女の人生がそうさせたと思う。
それに、サーミの住んでいる土地でのスウェーデンの子供達ののいじめも強烈だった。トナカイのように『耳を傷つける』て印を残す。数をあげればキリないが、Yoikingを( Yoik of the Wind これをコピペして聞いて。自然と一体になるような音楽の文化)ニクラスの誕生パーティーで人類学を学んでいる人に無理やりハミングさせられるシーンがあるが、今流に言えば、マイグロアグレッションの典型だ。最悪。
遊牧民という身体性
差別はなくならない?
血は繋がってるけど、家族ではいられなかった私達
・「血は繋がってないけど、私たちは家族です」というようなテーマの物語やドキュメンタリーはよく観るけど、今作はその逆
・「血は繋がっているのに、家族ではいられなかった物語」
・観る前は、遠い国の民族的なテーマで感情移入できるか心配だった
・観てみたらスーパー感情移入できるやん
・強烈な迫害の雰囲気というのは、スウェーデンならではだと思うけど、家族や地元の世界が窮屈に感じて自由を求めるのは、どこの国でもある普遍的なこと
・だから遠く離れた日本の人が観ても、がっつり感情移入できる
・例えば、方言の訛りがすごくて、東京に出てくるときに、恥ずかしい想いをしたくないから必死で標準語を練習するという人だって、日本にはたくさんいるはず
・それは、ダンスパーティに繰り出す前に、体臭を気にして湖で洗うエレの姿と重なる部分がある
・遠く離れている国の人でも共感できる部分がとても多い
・そういうところに、日本で今作が公開された意味がある
・そういった普遍的なテーマに加え、ヨイクのシンプルな旋律のようにシンプルな暮らしを営むラップランドの美しい原風景が、映画としての力を宿してる
・撮影は「影を撮る」と書くけど、まさに光を使って影を映すというような画の連続で、ひたすら映像が美しい。
(エレの心の翳りの描写が非常に巧み)
・直感的に「怖い!」と思わせる、カメラのシャッター音の音作りがすごい。
・自分の望む場所で生きていくために、どんな手を使っても男を味方につけようとするサーミの色気がすさまじい。
・エレに全否定された時の妹の、「ブワァッ」っと出る涙、すごい。
・老いたエレに漂う家族に対する罪悪意識の負のオーラがはんぱない
・実家が窮屈だとしても、自分が罪悪感を感じない程度に、適度な距離を持って接したほうがいいんだなぁと、個人的には学びました。
・ダンスフロアの中にいる老いたエレと、息子と娘がヘリに乗ってトナカイ狩りに向かう対比がゴイスー
・自分の生き方は正しいのかと、老いてもなお葛藤しつづけているエレ
・冒頭とラストを、老いたエレのシーンで挟む構成が非常に効いてる
・差別というものは、人の一生に影響を与え、家族の仲も引き裂いてしまう恐ろしいものだと見せつけられました
・エレの孫が、かつての偽名と同じクリスティーンなのは、偶然か必然か
・自分より若い世代には、差別に負い目を感じないで幸せになってほしいという願いを込めて、孫の女の子をクリスティーンと名付けたのではないか
・世間的に差別はなくならなくても、自分の家族だけはと、自分の代で差別を断ち切ろうとするエレ
・だからいまでも、サーミ人であることを隠しているのではないか
・かつては自分のために血を否定したけど、老いた今では、自分の家族のためにも血を否定するという、エレの切なさ
知らない世界を知る、それが映画!
映画評論家の町山智弘さんや、社会学者の宮台真司さんなど良い、良いと言っているのは聞いていたけれど、重そうで二の足を踏んでいた「サーミの血」。
良かった。
家で見ると散漫になってトイレに行ったり、お茶入れたりしてしまうんだが、見始めたら立てなくなってしまった。
スウェーデンの少数民族、サーミ人の少女エレ・マニャは1930年代にサーミ語を禁じられた寄宿学校に入っていた。
教育の名の下に研究材料にされたり、スウェーデン人からの差別に晒されて生きていた。
寄宿舎から抜け出した彼女に何が起こるのか…
サーミ人、は昔ラップランド(今では差別用語)と呼ばれる土地に住んでいた。
ラップランドと言われると、大島弓子の「いちご物語」でイノセントな存在として描かれていたのを思い出す。
大島弓子は牧歌的な少女漫画世界の中に、文化の違いの歪みを描いた。
けれど、この映画はもっとヒリヒリとした産毛が逆立つような無意識の差別の嫌さを描いている。
かと言ってサーミ人がイノセントに描かれているかと言うと彼等も自分達の様式美に囚われている。
その中でエレ・マニャは1人の人間として認められたいと静かに、けれど強い意志で逆風に立ち向かう。
全く馴染みの無い土地、知らない言語、知らないけれど普遍的で凡庸な差別、それを教えて体験させてくれる。
久しぶりに映画的な感動のある映画だった。
ちなみに町山さん情報によると「アナと雪の女王2」はサーミ人をモデルに作った映画らしい。
#サーミの血 #ペロの映画狂人日記
彼我の岸
先進的福祉国家として名高く、異民族にも寛容なスゥェーデンで起きてる矛盾
サーミ人はスゥェーデン、フィンランド、ロシアコラ半島に住んでいる先住民族である。
物語は主人公の老婆の少女期1930年代のこと。
スゥェーデン人は同じ国に暮らすサーミ人を酷く毛嫌いしていた。サーミ人は不潔、知能が劣ってる、文化的には暮らせない。サーミの人々は代々テントに暮らしてトナカイの放牧をして暮らしているしかなかった。
サーミ人の少年少女は同じ寄宿舎で教育を受けるのだが、そこでは間違いを犯したら打ったり、スゥェーデン人のアイデンティティを一方的に教え込む教育。更には生態検査としてサーミ人の子供たちを裸にさせて写真を撮る人権無視。
サーミとしてテントで生きるよりも、自由に生きたいと願う主人公の全力の足掻きとそれを阻む虚しさ。
同じサーミ人との確執やスゥェーデン人に未だ残るサーミ人に対する不快感など。
映画にしなければきっとスポットライトすら当てられなかったスゥェーデンで起きていた人種差別。
この映画が多くの人達に周知のされたらと願うほどの良作だと思う
民族差別
見るべき映画
文明の発展の影で破壊されているもの
スウェーデンと言うと、幸福度ランキング上位の常連、かつ、高学歴インテリの多い国として有名であるが、こんな歴史があったのか、初めて知った。
1930年代。民族によって知能の優劣があるということが本当に信じられていた。約100年前の話だ。信じられないが、事実だ。多くの現代日本人は、宗教や思想・哲学の類を下らないと思っているみたいであるが、高度な文明社会・科学も同じぐらい下らないものであることを自覚すべきである。
民族文化の存在意義とは何か?という視点で、この映画は結構身につまされるところがあった。
巨大な都市文明が急速に発展すると、伝統的な少数民族の文化や故郷は壊されちゃう。これは近代以降の人間社会の悲しい宿命だ。
劇中、主人公の少女は都市文明に適用して裕福に生きられている(優秀!)ように撮られているのと同時に、帰る故郷が存在しない(or帰れない)辛さも描かれている。
僕は少数民族ではないが、この辛さは結構わかる。僕の世代は祖母や祖父から昭和時代の伝統的な文化の名残りを享受していたのだが、ここ数十年(?)で、それが本当に無くなってしまった。ある意味、故郷が無くなってしまったと言える。
だから我々でも、他の民族の文化を簡単に壊しちゃダメ、ということは理解できるはず。
青春は自分以外に敵なしの時代であってほしい。
エレマリャは出自を捨てないままでは、当時のスウェーデン社会に受け入れられないと知って、大事なものを捨てたんですよね。
棄てたことを老いたいまも罰しているし、正当化もしているから、柔らかな気持ちで故郷と向き合えないんですよね。
悲しいです。でも、世界の片隅の方々で見られるマイノリティたちのよくある悲しみですから、人ごとではないと感じました。
自分の属する多数派の暴力性をもっと自覚しないと、エレマリャを傷つける側に回ってしまうし、逆に自分が属する少数派が多勢に立ち向かう術をもっと磨かなくてはいけない。
そういう気持ちでみました。
少数派であるサーミ人が、多数派を占めるスウェーデン人にどう扱われたかということから自分を見つめ直すという行為でした。
本当は青春時代はコントロールできない自分だけにあっぷあっぷしてパニクってるのがいいと思うんです。でもマイノリティだからそうさせてもらえない。それが一番嫌かもと思いました。
少女時代のエレマリャの先生役の人は、キングスマンでエグジーとつきあうスウェーデンの王女様やってた人ですね。
エレマリャと妹ちゃんが可愛かったです。
そういう差別があること自体知らなかった
1930年代のスウェーデンで差別を受けていた遊牧民族の少女の映画。
差別という大きなテーマの映画というより、
差別を受けている少女が被差別から抜け出して生き抜くワンシーンを描いた映画という感じ。
差別と真っ向から戦うという映画じゃない。
あくまで個人が差別を受ける環境で、
その状況を抜け出すためにとても現実的に、
時には犯罪を犯してでも行動している映画。暗い。
どうにかして差別されるという状況から抜け出し、将来の道を切り開こうと一人で社会へ飛び込む様子は、
希望を背負うたくましさより痛々しく寒そうなたくましさが目立つ。
彼女が受ける暴言や暴力のシーンも痛々しいが、出自を尋ねられヨイクを歌っているときの周りの視線、空気のシーンが
この様こそ差別だと訴えかけてくる。
でもこの誕生日パーティの場に来るまでに、
主人公は相当な無茶をして来てるんだよね。
それでもこのざまで見世物と何ら変わらない。
まあ差別してる割に、
民族衣装を脱いでワンピース着てお化粧してたら見分けつくの?って感じだけど。
進学も無理だと言われ、民族衣装を着て見世物のように写真を撮られる。
研究結果という言葉は始め聞いたときは正直ゾッとした。
彼女に向けられる一斉の奇異の視線は気色悪い。
外へ出ても何処にも拠り所はなく、
帰る家にも自分の恐れる未来しかない。
浅ましく男の家で雇って欲しいという時の彼女の寒そうな目と、
彼女を通り過ぎて開けられる玄関のドアが印象深かった。
銀のベルトを売って進学しただろう彼女は、
最初のシーンの老婆になるまでにどんな人生を生きてきたんだろう?
冒頭の自分と同じ民族の人々を指していう差別的な言葉は聞いててキツい。
本人がこう言われてきたのでは?と推測してしまう。
1930年なんて、2000年現代のほうが医療も科学も人類学の調査の際のモラル領分でもずっと進歩しているはずだ。
そんな時代でも人間を民族単位で研究して結果を出せたらしい。
100年後の未来では今現在はどうはかられるのだろう。
全45件中、1~20件目を表示