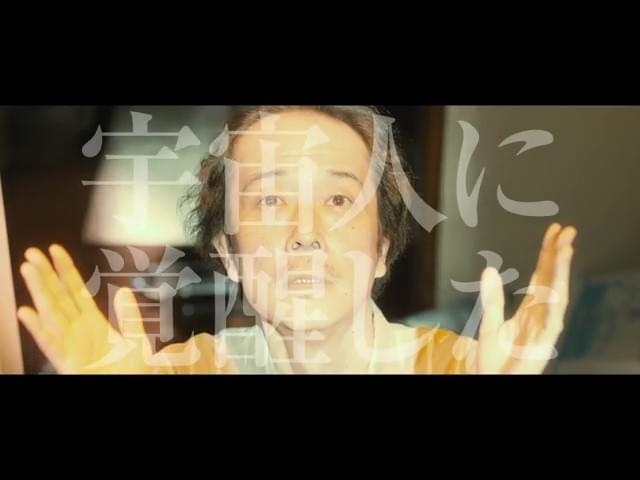美しい星 : 映画評論・批評
2017年5月23日更新
2017年5月26日よりTOHOシネマズ新宿ほかにてロードショー
原作に真っ向から対峙しつつ巧みに脚色。吉田大八の永年の夢は見事に成就した
三島由紀夫のSF小説「美しい星」は、ある種の映画人、クリエイターにとっては永年の夢の企画であった。たとえば大島渚が撮れば、〈政治の季節〉にふさわしく、クライマックスでは、主人公大杉重一郎と宇宙人との人類の運命に関する「日本の夜と霧」ばりのポリティカルなディスカッションドラマが展開されたに違いない。大友克洋の初期の短篇「宇宙パトロールシゲマ」も1970年代のシラケ世代らしいナンセンスな換骨奪胎ぶりが鮮やかだった。
30年構想を温めていたという吉田大八は、そうした変化球ではなく真っ向から三島の原作に対峙している。むろん、21世紀の現代に見合った近未来風の巧みな脚色はなされている。原作の背景をなす東西冷戦下の核への恐怖と不安や切迫した危機感は、地球温暖化と異常気象によるゆるやかな終末感に置き換えられ、白鳥座から到来した三人組は、謎めいた議員秘書に集約される。

重一郎(リリー・フランキーが怪演!)が浮世離れした高等遊民から、軽佻浮薄なお天気キャスターに、木星人の妻伊余子が地球人に代わっているのも注目される。冒頭の冷え冷えとしたレストランでの食事シーンでこの家族の崩壊が明示されるが、このバラバラに破損した家族の再生というテーマと、地球の危機を救うという大風呂敷の壮大なヴィジョンをいかに融和させるかが、吉田大八の密かな野心であったはずだ。
一家がそれぞれ異星人として覚醒する瞬間から、映画は一挙にドライブ感にスイッチが入る。とくに超越的な美を誇る大学生暁子・橋本愛が海辺で、重一郎がテレビ局の屋上でそれぞれUFOと交信するシーンは、荒唐無稽なドタバタと超越的なヴィジョンが入り混じった秀逸なイメージが生まれている。
死に瀕した重一郎の〈末期の眼〉がとらえた盛り場のネオンの夜景や、突然、山道に出現する牛の不可解な美しさに導かれながら、ラスト、この出来損ないの〈聖家族〉が超俯瞰で映し出されるとき、吉田大八の永年の夢は見事に成就したように思う。
(高崎俊夫)