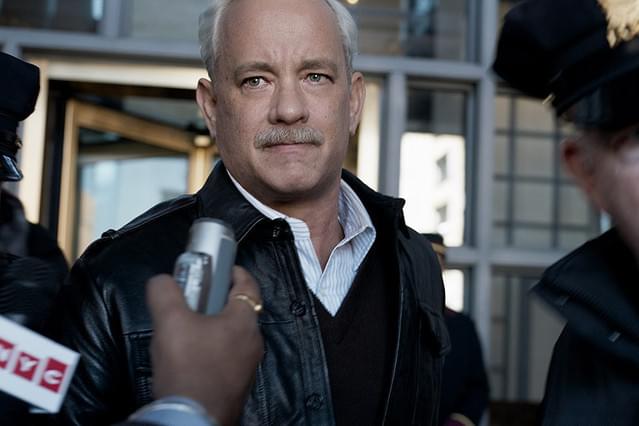ハドソン川の奇跡のレビュー・感想・評価
全495件中、1~20件目を表示
声と静寂が作る「奇跡」の重厚感。
〇作品全体
対面、電話、無線…本作は様々なダイアログ、人の声で紡がれる物語だ。英雄視されるサリーが中心にいて「奇跡」を創り上げたのは間違いないが、その「奇跡」は人の声で形作られている。
無線での管制塔とのやり取りはそれぞれが最良の策を提案しあい、それでもハドソン川という選択肢しかなかったという「奇跡」への大きな布石になっているし、サリーと連携する副機長・ジェフとは緊迫した空間で横並びとなって機体の状況を声に出して報告する。これも「奇跡」への棋譜といえる。着水後はどうだろう。飛行機の添乗員やフェリーの乗組員の的確な指示出しや励ましの声がなければ155人が生存していたかはわからない。着水後は飛行機から脱出し、翼上で待つという少ないアクションしかない中で、緊張感を作り続けていたのは乗客の声だった。
こうした「奇跡」に至るまでのそれぞれの声を誇張せずに朴訥と紡いでいるからこそ、たどり着いた「奇跡」の真価が心にすんなり入ってくるようで、とても良かった。
物語終盤の公聴会で「Xファクターは関わったすべての人だ」というサリーのセリフがある。正直、このセリフだけを聞いてしまえばごくありふれたセリフのように感じる。「みなさんのおかげです」は現代社会ではありきたりな常套句の一つでしかない。ただ、ここまで実直に様々な声を映し、積み上げていった本作においては、これ以上ない表現方法だと感じた。
本作が素晴らしいのはこれだけではない。それは「声」を彩る「静寂」の演出だ。
本作では劇伴がほとんど流れない。最初に「奇跡」をサリーが回想するシークエンスでは飛行機内では一切劇伴がなく、最初に劇伴が流れるのは病院で上司から155人全員が助かったと聞かされる場面。サリーの緊張の解れに呼応する劇伴が良いし、なにより飛行機内の緊迫感を無音で演出する真っ向勝負な感じが素晴らしい。飛行機内では環境音としてあたりまえに存在するエンジン音。これが止まって聞こえなくなったときの違和感、異常さは無音でなければ伝わらない。この「静寂」という引き算的演出の大胆さがたまらない。
飛行機内での緊迫感をオーケストラで彩るのではなく、華美な装飾から切り離された「静寂」で重厚感を演出する。この演出に痺れる。
本作を見て改めて思った。目をくぎ付けにする、作品の世界に引き込んでくれる作品は音の塩梅が絶妙なのだと。映画は静かすぎても退屈だし、騒がしすぎてもしらけてしまう。本作はその点が「絶妙」であり、作品内にある声と静寂の重たさに浸ることができる重厚な作品だった。
〇カメラワーク
・冒頭のシーン、NTSBからの聞き取りを受けるシーンはカットバック演出が光る。このシーンのほぼすべてのカットにおいてNTSB側とサリー側を同じカメラに収めず、カットバックで対立を表現している。サリー側は不快感を示したりはしているが、会話に互いの状況を打開する決定打はなく、どちらかが声を荒げたりすることもないため、一見対立構造は大きく変わっていないようにみえる。しかし、このカットバックを何度も繰り返すことで、会話が続けば続くほど両側の感情の溝を深めるカット割りになっていた。
NTSB側が席を立つカットは部屋を少し俯瞰気味で映したことでサリー側も映りこんでいるのだが、サリーがすぐにNTSB側から体を背け、ジェフのほうを向く。そうすることでカメラにサリーが背を向ける格好となり、サリーをカメラの外に追いやるような構図になるよう工夫されているのも面白い。
・公聴会でフライトシュミレーターに従事するパイロットを映すカットは、ほぼ全てパイロットの背中側から、カメラを動かさずFIXで撮っている。後ろから撮っているからパイロットたちの表情が見えないうえ、業務上のやり取りしかしないため、ロボットのように映る。カメラが固定されているのもロボット感に拍車をかける。
この演出はちゃんと仕掛けになっていて、その後にあるパイロットの思案時間を考慮した状況でのシミュレーションシーンで発揮される。このシーンで初めてカメラは機長役のパイロットを横から(しかも目元は見えないように口から下を)映す。機長役は「低すぎる」とつぶやく。これにより「低すぎる」というセリフが機長役のパイロット個人から出た感想であること、そして目元を映さないからこそ匿名性が上がり、「一般のパイロットが思う感想であること」を強調することができる。同状況で空港に戻ることが不可能であることをシミュレーションの結果だけでなく、一般的なパイロットから見た視点でも語ることで説得力を増幅させている。伏線的な映像演出が魅せる意味付けの強化…すごく面白くて、上手だなと思ったシーンだった。
〇その他
・副機長のジェフが最初のシーンで半袖のYシャツを着ているのがすごく良いな、と感じる。これはうまく言葉にできないのだけど、サリーが長袖を着ていて、かつ真正面を向いて腰かけている大人な印象を受けるのに対して、半袖で少し姿勢を楽にして座っているジェフからは若さがあふれているように見える。単刀直入に言ってしまえば、その印象が違う様子にサリーとジェフが対立しているのではないか、と感じた。でも実際はそうじゃないとこの後わかるのだけど、その「実際は違っていて、信頼関係がある」ということに喜びというか、温かい気持ちになって、それが良いなと思ったのであった。
会社の朝礼のネタに使える!社会人必見の「オトナ」の映画。
実際の事件という意味では、確かに奇跡的な出来事だし、映画向き。しかも映画の作りとしては、実に大人の映画である。
「ハドソン川の奇跡」
本作はそのサレンバーガー機長を人間味ある「ヒーロー」としてある程度描いているのは、これまでのイーストウッド監督のかつての作品の流れとして一貫しているので、当然のことだが、前作「アメリカンスナイパー」に続いての本作、とみるともう少し奥が深くなる。
前作の主人公はイラク戦争にて、「従来の強い良きアメリカ人」の「そこでしか自分を発揮できない」、アメリカの闇、アメリカのヒーローの「悲劇」を描いたものだったのに対し、本作の主人公は、まさにそれを受けて、そんな「闇」を背負ってきた、それでもなお存在する「従来の強い良きアメリカ人」のヒーローとしてサリンバーガー機長を描いている。
映画の出来をオレは、けちょんけちょんにけなした「アメリカン・スナイパー」だが、本作と比較すると、「古き良きアメリカ人の悲劇」と「仕事と家庭を大事にする強い精神力のアメリカ人の勇気をたたえた物語」という、ある意味正反対だが、実は「おなじヒーロー」として両作品を見ることができる。
これは映画のシーンでもわかるが、ここに登場する人物はすべて「あの悲劇」を想起しつつも、「今それを起こすわけにはいかない」という確固たる信念と、日々の日常を強くたくましく生活しているアメリカ人の「強さ」「優しさ」が浮き上がってくる作りはとても誠実で優しい。
国家運輸安全委員会の厳しい追及の描写が、若干単純な「敵」として見えがちだが、そっちの描き方は、あえての演出。機長と副機長の「オトナな対応」をより強調するためのやや誇張した描き方にしてある。
めんどくさい委員会の口撃も、キレることなく、さらりといなす。それは弁が立つ、とかではなく、「自分の行ったことに対して、自信があるかどうか」である。
だがそんな機長もやはり揺れる。
そんな、仕事にプロフェッショナルで、家族も大事にする、そんな強い男が揺れる。
それがあの、9.11の悲劇がもたらしたものなのである。
イーストウッドは、それでも、いや、だからこそ、オトナに描く。
普通の日本人の、ボンクラなオレはやはり、そこまでの彼らの心情はリアルに実感できない。
だが、イーストウッドの、オトナな視点のおかげで、これは、「アメリカのヒーロー」の映画だが、と同時に「オレたち」の映画でもあるのだな、と思った。
その理由は、そんな機長と副機長の委員会に対する「オトナな対応」がかっこよかった他ならない。
事故発生時に、パニックにならず、冷静に考える。副機長は「ルールとしてやるべきこととして」マニュアルを広げる。
そもそもあの委員会のシミュレーション検証内容ははっきり言ってゆるゆるだし、かつ「悪意のある検証結果」である。
だが、機長、副機長が、「やることをやっていているからこそ」、機長の証言が生きてくるのである。
感動的な実話だし、映像も迫力ある。少し単純な「敵」としての委員会の描き方も意味がある。十分素晴らしい映画だ。
が、それよりも、サラリーマンのオレとしては、何と言ってもその「オトナ」な姿に感動した。
これこそ、今オトナとして学ぶべき映画。家族を思い、無事着地する、という「仕事」を全うし、155人全員無事に家に帰し、そして「9.11」後の社会を思う。
これこそ社会人として見習うべき姿だと思う。
追記
会社などで、ワントピックを話すような朝礼があるようなところだと、ぜひこの映画を話題にし、勧めるといい。
追記2
ラストの副機長の一言は、「155人全員無事だった」という結果によるものである。仕事をするうえで、こんなジョークを吐いてみたいと思いつつ、オレは日々頑張るのである。
アウトサイダー的視点、ここでも健在
前作に続いて英雄と呼ばれた男の心理面を映像に刻んだイーストウッド。96分という上映時間は彼の監督作として最短である。とはいえ、終わりなき地獄を描いた前作とは全く違ったやり方で、今回は一瞬の閃光をあまりに鮮やかな手腕で捉えてみせる。そこには英雄礼賛を持ち出すのではなく、イーストウッドならではのアウトサイダーとしての視点が絶妙な具合に浮かび上がってくる。
“サリー”が闘う相手は調査委員会ではない。最終的に対峙すべきは自分自身であること、自分の中にこそ答えがあることを彼は十分に知っている。映画のかなりの部分を割いて繰り返される飛行シーンで、彼は自分が間違っていなかったか、他に何か方法はなかったのか寝ても覚めても検証し続ける。決して自己弁護に陥らず、自らに対してもアウトサイダー的視点で引き金を引き、答えを求めようとするその姿にこそ、イーストウッド作品の主役に通底する戦い方、孤高の生き方がある。
達人ならではの一筆書き
「過不足なく」というのはこの映画のことを言うのだろう。物語の核はコレだと見極め、余計なものに目をくれず一直線にゴールを見据えて作る。やりたいこと伝えたいことが明確で迷いがない。達人イーストウッドならではのみごとさだと思う。
ただ「なすべきときになすべきことを成した人々の矜持」という美談以上の膨らみが感じられない、と言うとワガママだろうか。
さすがですら!と感心しつつも、ムダな脇道や得体の知れないこだわりが漏れ出た映画の方が記憶や心に残ったりする。物語も演技も演出も立派なだがなにか物足りない。そんな贅沢な葛藤を呼び起こす時間でもあった。
いや、同じ事件に着想を得て、本当にどうしようもない男のどうしようもなさを突き付けるフィクション『フライト』の方が好みというだけかも知れません。96分でこれだけの作品が観られるのだから損はないと思いますが、こんな感想もあるということで。
ホントに奇跡的な話
滑走河
エンジンが止まった飛行機が、ニューヨークのハドソン川に着水して、乗客乗員全員無事だったという実話を基にした映画。美談のはずなのに、国家安全運輸調査委員会から、なぜ空港に引き返さず、危険な着水をしたのか、と機長は追及されてしまう。コンピューターのシミュレーションは、操縦歴40年のベテランの直感に、ノーを突きつける。状況を冷静に判断したつもりだが、機長は揺れ始める…。
報道の過熱ぶりには恐怖を感じた。ほんと、メディアの餌食にはなりたくないなあ。機長の家族も大変だっただろう。飛行機事故が起こる確率は低いというが、事故になったら死ぬ確率はかなり高いわけで、死人ゼロはすごいことなのだ。なのに、外野にあーだこーだ言われるなんて…。
珍しくトム・ハンクスが、硬い顔ばかりで、ほとんど表情を変えない。生真面目で一徹な人物を、まじめに表現していた。機内の隅々まで、何度もチェックしていた機長の、真剣かつ不安げな顔が忘れられない。
BS-TBSの放送を録画で視聴。
シミュレーションでできなかったこと
実際の航空事故を題材とした作品です。
末尾に特典映像としてサリー機長本人のトークが30分程度収録されていました。
もう、あらすじそのもののシンプルな内容なのですが、
それでも事故発生から不時着までの緊迫感、乗客救助のドキドキ感は半端ありません。
誰もが人命救助のことだけを考えた24分間には目が釘付けになりました。
そして本作のもう一つの山場。フライトシミュレーションに基づく公聴会。サリー機長がフライトレコーダーの確認に先立ちシミュレーション映像の視聴を求めた理由が鮮やかに明かされます。
2008年に起きた事故においてもこのようなシミュレーションがまかり通っていたことが驚きでした。
いかにビッグデータを活用しようとも、パラメーターに先入観やご都合主義が反映されていると全く逆の結果を示しかねない危険性に警鐘を鳴らす部分だと思います。
古い作品ですが、鑑賞して良かったです。
奇跡の川に生きた勇気
「ハドソン川の奇跡」は実話を元にした、緊迫したフライトと人間ドラマがすごく心に響く映画だった。鳥の群れに飛行機がぶつかってしまって、ハドソン川に不時着するという大事故。調査やシミュレーションのところは専門的でちょっと難しいけど、乗客みんなが無事だったのは本当にすごいと思う。厳しく問い詰める人たちにはびっくりしたけど、彼らも責任を感じてるんだなと伝わってきた。空港に戻る選択肢もあったかもしれないけど、結果的にみんな助かって、その奇跡こそが一番の感動だった。専門的なことがわからなくても、命の大切さや勇気を感じられる作品。
そこにハドソン川があった・・・それが、もう一つの奇跡‼️
航空機は自動車よりずっと安全だと良く聞きますが、
航空機事故に遭遇して無事帰還できたら、
もう幸運以外の何物でもありませんね。
2016年。クリント・イーストウッド監督作品。
2009年に実際に起きた航空機事故の映画化です。
ドキュメンタリータッチの緊迫感溢れる映画でした。
乗員・乗客155人を乗せた航空機が突然コントロールを失う。
サレンバーガー機長の咄嗟の判断は、ハドソン川に着水することでした。
この判断が正しかったか?否?
公聴会で責められるのですが、機長と管制官との会話の録音テープから、
機長の咄嗟の判断は正しかったと証明されます。
それにしても155人もの人命を預かる仕事の重責が滲んでいました。
ラストの実際のニュース映像を見ると、沿岸警備隊も、近くにいて
救助に駆けつけた船も、何から何までまるっきりそっくりでした。
サレンバーガー機長と奥様も絵に描いたように美しくて、
機長の白髪はトム・ハンクスと同じ(・・・似せたのですね)
副操縦士のアーロン・エッカートの、
「次の機会があるならば、7月に‼️」
155人全員無事だったからこそ言えるジョークですね。
(体感温度ははマイナスという寒さのハドソン川。1月15日でした)
副操縦士もええ奴
機長と副機長の強い信頼感を感じられた。
副機長は控えめでしかし感情的にならず淡々と受け答えする姿勢はある意味、機長以上に頼もしく見えた。
もちろん機長はトム・ハンクスが演じており演技力から来る説得感は完璧で事故調査委員会は、「こりゃまた一本取られた」である。
機長たちをまるで悪人のように扱う小憎たらしい事故調査委員会のメンバーだったが
最後に副機長が「スカイルズ副操縦士、何か加えることはありますか。何か…違う方法でやりますか…もしおなじことが起きたら。」と聞かれて「やるなら7月に」と答えるシーンは最高ににスカッとした。
エンドロールの時に本物の機長や多分乗客たちと思うが出てくるがあれは事故当日に撮ったのだろうか?
ハドソン川に着陸し、水面に羽をを広げ浮かんでいる飛行機を見てなぜかモスラを思い出した。
高所恐怖症で飛行機が苦手な私は飛行機墜落の映画は本来、見たらあかん映画かも知れないがレビューの高評価とトム・ハンクス主演ということで思わず見てしまった。でも、見て良かったと思わせる映画でした。
心に響く映画
イケオジアーロン・エッカートさん
実話に基づく、緊張と感動のストーリー!
ありえないほど正確な判断で着水を成功させた機長と、それをサポートし...
面白いんですが一般市民の機長に対する対応に疑問
あらためてプロ意識を教えてくれる作品
個人的にはクリント・イーストウッド監督作品はあまり積極的には観ていないので、本作もずいぶん遅れて鑑賞。
観終えて正直な感想、サリー機長のプロ意識の高さに心が揺さぶられ熱く泣けた。本作は全てのビジネスマンへプロとしての心意気までも教えてくれているように思う。まさに社会人向け自己啓発映画ともいえるだろう。
ラストシーンでの、「あなたを計算式から外したら成立しない」からの「全員が力を尽くし~」の回答もプロ中のプロならではでとても感動的だし、「やるなら7月に」のナイスジョークなコメントもサクッと決まり、爽やかな後味を残してくれた。
本作は、私がイメージしているクリント・イーストウッド監督風がほとんど感じられず、個人的にはとても良い意味で新たな一面を観れた気がした。
機長の凄み
飛行機のトラブルに際して機転を利かせて不時着し、乗客を守ってハッピーエンドという単純な話なのかと思っていた。しかしどちらかと言うと、調査会社に事故時の対応について問責される機長の苦悩に重点を置いて描かれている。最善を尽くしたのにもかかわらず、問責される彼の心情は察するに余りある。大衆には英雄扱いされるが当人は裏で苦悩するというテーマは、『父親たちの星条旗』のイーストウッド監督らしい。
飛行機のトラブルから脱出までの描写も迫力がある。短い時間でどのように対処するか決断を下さねばならない。また、ハドソン川に着水後も、機内への浸水により溺死する恐怖があって油断できない。そのようなトラブル時など普通は頭が真っ白になるはずだが、状況を冷静に認識して的確な判断を下す機長の凄みが伝わってくる。
助かって良かった
2009年1月、NY。
鳥の大群であんなに簡単にエンジンが壊れて
しまうなら、その予防手段に必死に取り組む
必要があるのでは、と感じた。
機長と副機長の冷静沈着な判断によって、
機体トラブルの為、ハドソン河に不時着しつつも
乗客乗員155名全員の命が助かった、という
タイトル通り奇跡のような実話、を元にした
作品。
初めは、全員助けて英雄だー、と持て囃しつつ
時間が経てば、
最寄りの飛行場の滑走路に着陸できた筈だ、
1月の冷たい川に着水して落ちて溺れたり、
寒さ冷たさによる低体温症で命の危険があったり、命のことを考えなかったのか、と。
手のひら返しのように叩いて来て、
事故調査委員会とかで、調べていくとか。
コンピューターによるシュミレーションでは
最初二つの飛行場に着陸成功。
ここで機長たちが物申す。
検討タイム35秒いる。その時間をプラスして、
再度シュミレーション、
二つとも、着陸不可能やぶつかって失敗。
いかに瞬時の判断が素晴らしく、
技能面も申し分なかったか。
機長が脱出誘導の指揮を執り、最後の一人が
機内に残っていないかとしつこく点検して
最後に機体を離れる姿には尊敬するばかり。
また、沿岸警備隊やさまざまな機関が、
時間ロスを無くし急いで、
船やヘリコプターで駆けつける様子も感動。
連絡入って24分で全員救助❗️素晴らしい❗️
ただ、乗客の身になって考えると、普通に、
目的地に着いて当たり前であり、
つくづく飛行機には乗りたくないな、と。
しかし、本事件の9年前、恐ろしい出来事が
起こり、あの際の乗客乗員の気持ちや
ビルで働いていた人々や救助の人々を考えると
尊い命がなんてもったいないことかとも。
改めて考えさせられた。
トム•ハンクスさん、エンドロールに出て来られた機長ご本人によく似ておられた。
安心の名演技。
全495件中、1~20件目を表示