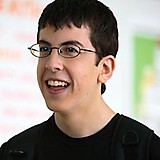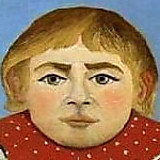スポットライト 世紀のスクープのレビュー・感想・評価
全369件中、321~340件目を表示
ウルヴァリン(ローガン)をめちゃめちゃに痛めつけた兄(ビクター)がボストン・グローブ紙の局長でナオミ・ワッツの夫!
ウルヴァリン(ローガン)をめちゃめちゃに痛めつけた兄(ビクター)がボストン・グローブ紙の局長でナオミ・ワッツの夫!
TOHOシネマズ 伊丹で映画「スポットライト 世紀のスクープ」(Spotlight)を見た。
第88回アカデミー賞で作品賞と脚本賞で受賞を果たした。
実話を基に描かれた作品。
月曜日午前10時からの上映だが、客入りは客席の2-3割だろうか。
出演はレイチェル・マクアダムス
「アバウト・タイム 愛おしい時間について」は2014年の作品
「きみに読む物語」を見たのはもう11年前の2005年である。
2009年公開の「ウルヴァリン:X-MEN ZERO」でさんざんヒュー・ジャックマン(ローガン)を痛めつけた、なんてひどい男なんだと思ったウルヴァリンの兄(ビクター)役のリーブ・シュレイバー 。
このリーブ・シュレイバーが実生活ではナオミ・ワッツの夫だったとは知らなかった。
マーク・ラファロは「ハルク」で、
マイケル・キートンは「バットマン」シリーズで有名な俳優だ。
マイケル・キートンの主演作は昨年「バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)」を見た。
マーク・ラファロとマイケル・キートンは好きな役者。
2人ともその柔らかい雰囲気が好き。
カトリック教会は、ローマ教皇を中心として全世界に12億人以上の信徒を有するキリスト教最大の教派。
その中心をローマの司教座に置くことからローマ教会、ローマ・カトリック教会とも呼ばれる。
欧米では強大であろうその権威は日本に住む我々一般庶民には知りようがないのであるが、そこの神父たちのおよそ6%にも及ぶ者たち、ボストン地区においてはおよそ90人が教会に通う子供たちに対して性的暴行をしていたという。
その教会や神父たちやそれらに雇われた弁護士たちに切り込むボストン・グローブ紙の新聞記者たちが奮闘する物語。
レイチェル・マクアダムス、リーブ・シュレイバー、マーク・ラファロとマイケル・キートンの演技が全部いい。
原作と主題に恵まれたのだろうがオスカーの賞を受けるに十分に値する作品だと思う。
上映時間は128分。
長さは感じない。
満足度は5点満点で5点☆☆☆☆☆です。
とても満足です。
土曜日の朝っぱらから深く深く考えさせられた
カトリック教会の話なぞ、無宗派の日本人に受け入れられるのかという
不安は無用、立派なエンターテインメントに仕上げられており、
置いてきぼり感は全くありません。
とはいえ、上手い役者と秀逸な脚本のおかげか胸に迫る重厚感、緊迫感あり、
非常にバランス良く作られています。
そもそも、人間がよりよく生きるために生まれたのが宗教なのに、
膨れ上がってしまった組織は権力、金、人間の欲望でいかようにも
利用できる。そしてこれほどの大国で、その事実がまかり通っていると
いうことがまずショック。
自分が絶対だと信じていた人間に辱められた被害者は勿論、
教会を拠り所としていた信者たちは、生きていく指針を失ったも同然。
気持ちのを支えていた支柱を木っ端微塵に破壊された彼らの心は
一体これから何を信じればよいのだろう?
罪人達はロクに罰を受けることもなく、新天地にてまた涼しい顔をして
同じ悪行を繰り返す。
本来ならば悩める人間を導くために存在する人間が、道徳心のかけらもない
行為を繰り返して多くの人間の人生をぶち壊し、その事実は無きものにされる…。
カトリック教会の犯した罪の重さは計り知れないし、今でもどこかで続いているかもしれない。
世界各地で混沌となっているこの世の中、人間は宗教や民族で
カテゴリ分けされてレッテルを貼られてバッシングされて攻撃される。
この連鎖の頂点にあるともいえるカトリック教会の白人教職者達の
悪行、このタイミングにてこの映画が公開されたことは、
アメリカ、カトリック信者以外の世界中の人間にいろんな意味での
大きな影響を及ぼすと思われます。
また全く異なる視点からの感想ですが、スポットライトチームの仕事。
自分がこれまで仕事に必死になったことがないため、大切な物を
犠牲にして仕事に身を投じる彼らにこころ動かされてしまったらしく、
これまでの「お金がもらえればいい」という信念が曲がりそうです。
ともすれば自身や家族の身に危険が及ぶような際どいネタに、
心身すり減らし尽力する彼らを突き動かすものって一体何なんだろう?
決して楽ではない仕事ですが、ここまで追い求められるものが
あるということが羨ましく感じました。
朝イチの回で観ましたが、おかげで久しぶりに人生の深い部分について
1日考えさせられました。
本当に秀逸なエンターテインメント。
予告通りそのままの内容
う~ん。
内容は予告そのまんまで、特別な驚きも無く終わってしまった感じかな。
期待してただけに残念な作品でした。
あんまりおもしろくなかった。
なぜ人は悪を見て目と口を閉じるのか
シナリオがよくできている
事実を映画化したとはいえ
映像化するには労がいる
この悪の事実は多くの人が知っていたり感づいていたり
何百年も続いていたのだろう
時に暴露されるが
またはびこる
現代の日本でも
大学の教授(男)が教授になりたい女子学生に性的関係を強要する
というのは知る人ぞ知る悪習だ
マクドナルドの店長がなぜ重労働に耐えれるか?
マクドナルドのアルバイトはほとんどが若い女性である
男としておいしい職場だからやめられない
あなたがその場にいたのなら
あなたは告発する勇気を持ちなさい
子供が犯されて殺された両親が
「二度とこのようなことがないよう、わが子が最後の犠牲者でありますように」と訴えた
あなたの勇気があなたの後の世代を救い
やがて社会全体が健康になっていく
教会とは…
見応えあり
面白かったです。アカデミー賞も納得です。
もっと劇的な演出もできただろうけれど、あえてそうしていないのだと思います。一つ一つの描写の積み重ねと役者の演技力で十分に伝わってくるものがあり、2時間があっという間でした。
他の方も言っているように、カトリック教会の存在というものは日本では確かにピンとこない面はあると思います。しかし、支配的な体制や価値観の下で理不尽に虐げられた者が声をあげることもできず抱え込まなければならなかった絶望感や孤独感は文化の違いを超えて理解できるのではないでしょうか。またそういった大きなものに対し異議を唱えることの難しさというのも普遍的です。
あと思ったのが、被害者役の人たちのキャスティングが良かったです。トラウマをずっと抱え人生を狂わされて生きてきた様子がリアルに感じられました。
low&order svuのよう
結論から言えば、Blu-rayを待ってもよかったかなという感想。ケーブルテレビでオンエアしてる「low&order svu」のような作り、内容。正直な話、low~のほうがあの手の話をうまく見せてくれるし、中だるみせずに見られるなと思った。
スキャンダラスなネタを扱っているわりには、前編通してなんか「のんびり」して見える。いや、あくまでノンフィクションなんだからそこは仕方ないのかもしれない。でも、さんざん伏線として「教会にバレたらただじゃすまないぞ」と言い含めてきたのなら、せめて何か起きてくれよ(笑)。なにも起きないまま、「他の新聞社にすっぱぬかれないように慎重にやれよ」ってだけじゃ、観てる方としては、「特大スクープを物にした新聞社の物語」として見ていいのか、「首や身の危険を省みないジャーナリストの生きざま」として見た方がいいのか、はたまた両方なのか(それだと大分物語の軸が定まらない気がするが)分からず仕舞いだった。
ほかにもいろいろ突っ込みたい部分はあるが、そこはノンフィクションとして、目を背けよう。
最後に、記事を見た被害者から多数の電話がかかってきたという事実だけ、ほんとうにそれだけが救いになった。
地味ながらいい作品だった。
カトリック教会が隠蔽している、多数の神父による児童への性的虐待という醜聞を白日ものとに晒すために、ひたすら取材を重ねていきゴールにたどり着くはなし。ストーリーとしては大きな盛り上がりもなく地味ではあるものの、逆に無駄な演出もなく、記者たちの情熱が現れていてよくできた映画だった。
カトリック教会の組織的な側面や、地域社会とカトリック教会とのかかわりなどがハードルになっていたけれど、自分のようなカトリック教会とは何の縁もない立場でなく、実際のカトリックの信者などがこのスクープ記事によって受けた衝撃はどれほどのものだったか。
最後に同様の事件があったことが判明した地域の一覧が出てくるけれど、その量の多さが衝撃。ただ、その後のボストン・グローブ紙ではこの件について600本ほどの記事が掲載されたらしいものの、そのあたりは物語には描かれてなく、初報に対する思いがけない社会の反響があった、ところで終わってしまっていたのはちょと物足りなさを感じた。
知っておくべきカトリック教会に纏わる真実
文句なしの作品賞
もうこれは賞を取らせないという選択肢はない、という出来栄え。
というよりも、元ネタの社会的意義がとても高い。
神父による子供の性的虐待を 教会中枢が隠蔽し続けてきたという構造問題をボストン・グローブ紙が丹念な調査に基づいて長期連載した、その過程を描いている。
映画化にあたって派手な演出は控えられ、地道な調査と関係者の小さな勇気が重ねられていった様子が描かれているのが良い。
さて、なぜ、これまで、長きにわたる教会の構造的問題が表沙汰にならずにきたのか?
教会の規律の前時代性、被害者がメディアに出たがらない、関係者による告発の不調、情報をもらったジャーナリストの迂闊、どれも悪意によるものではない。
その根底には欧米人にとってカトリック教会というものの存在感がある。
日本人の感覚にたとえていうなら、いったい何に相当するのだろうか?あの信頼感はいったいなんなのか? 弱い者の立場にたつ機関であるということだろうか?
その感覚はわからない、別世界のものだなぁと感じずにはいられない。
ただ、わからないながらも、教会の暗部をあばくことに対するためらいは十二分に伝わってくる。
だからこそ、報道機関は書くべきなんだ、という”よそ者ユダヤ人”局長の台詞が主題そのものであった。
Spotlight (2015) Quotes
Marty Baron: Sometimes it's easy to forget that we spend most of our time stumbling around the dark. Suddenly, a light gets turned on and there's a fair share of blame to go around. I can't speak to what happened before I arrived, but all of you have done some very good reporting here. Reporting that I believe is going to have an immediate and considerable impact on our readers. For me, this kind of story is why we do this.
権力と闘うジャーナリズム
期待通り
見応えのある作品
地味ながらも骨太な銘品
まず、ボストン・グローブの記者たちとボストンという街そのものの活気が本作の屋台骨になっていると思います。神父たちによる児童性虐待という重いテーマを掲げながらも、最初から最後まで躍動的なエネルギーがこの作品には溢れています。
想像するに、実際の記者たちの取材活動は、それこそ地味で心が蝕まれていくような道のりだったに違いありません。
この映画は、被害者たちの心情を描くでもなく、神父たちの罪を裁くでもなく、記者たちのガッツを賞賛するものでもありません。ハッピーエンドが待っているわけでもありません。
終盤にゆくにつれ、我々はなぜ目の前の問題から目を逸らし続けるのか、という問いかけがのしかかってきます。教会の問題を浮かび上がらせるだけでなく、記者たち自身がこの教会の暗部に背を向けてきたという、もう一つの事実が明らかにされます。
苦いドラマではありますが、その分深みが生まれていて良かったと思います。
とはいえ、記者たちの活躍は目を見張るものがあり、映画とはいえ彼らに畏敬の念を払いたくなります。
何度も事件の当事者の元へ足を運び、信頼関係を築きながら真実が解明されていく場面は、まさにジャーナリストの本領を見ているようでした。
今で言えば、パナマ文書問題が明るみに出たのも世界のジャーナリストのおかげなのかなとも思いました。
事件柄、たくさんの人物が複雑に登場してくるので、追うのが大変でしたが、徐々に増えていく被害者、加害者の数字がこの事件の深刻さを物語っていて、この辺の脚色は上手いな、と感じました。
記者たちを演じた俳優陣の熱演は見事でした。
昨年の「バードマン」と比べれば地味な印象の今作ですが、(MMFRが獲れなくて悔しいけど)オスカー作品賞も納得のいく、本当に骨太な作品でした。
実直な映画
地味な映画かもしれない。奇を衒わない演出で、ものすごく「普通」の映画と言ってもいい。だけど「普通」だからこそ響いてくることもある。「実直」だからこそ心動かされることもある。
—
加害者が一番悪いし、それを意図的に隠蔽しようとした教会も勿論ものすごく悪い。
ただ、それ以外の人たちがみな清廉潔白かというとそうでもなく。
地域・コミュニティに波風たてたくない…そんな消極的理由で事件をスルーする地元民。アッパークラスになればなるほど失うものも大きいから慎重になる。告発する奴は空気よめないバカだ的な雰囲気。そんな長年の積み重ねが、事件の温床となる。私もその場に居たら、長いものに巻かれるだろう、そう思うと怖い。
記者たちが暴くのは加害者や権力だけではない。自ら属する共同体の弱点も暴かざるをえない。
そして事件が暴かれる何年も前から、新聞社には断片的な証拠は届いていた。大きな記事にすることもなくベタ記事だった。私は、意図があって隠蔽していたのだろう、教会か誰かに頼まれたのだろう、その悪徳記者は誰だ?と思いながら観ていたのだが…。
終盤明かされる結論はそうでは無かった。意図的な隠蔽というよりも、記者の「無関心」がきっとそうさせたのだ。自覚なく空気を読んでしまったのだ。普通の人の悪気のない行動。そのことへの深い自省、苦さが、ものすごく胸に響く映画だった。
「遠い海の向こうの怖い話」ではなく、私ら自身も知らずして陥っているかもしれない苦さ。その苦さを乗り越えるからこそ一条の光が射す。「権力に屈せず事件を暴いたジャーナリストはエラい」というだけではない映画だった。文章に纏めるとものすごく説教くさいが、映画は淡々と淡々とそのラストに至るので、素直に心動かされる。とても実直な映画だったと思う。
作品賞???
それなりに難しくそれなりに震える
キリスト教にゆかりの深い国・地域に身をおく者ならば、深い感情が生まれるように感じた。自分は信仰は持たない身であるから、衝撃度は低かったと勝手に想像する。しかし、聖職者の児童虐待という衝撃は、信仰云々関係なく、ショッキングなもの。これを隠蔽しようとする理由や隠蔽可能な力学的なところはなかなか理解に苦しむ。それは信仰に大いに関係してしまうと思ってしまう。
それでも、社会の腐敗を追及しようとしたジャーナリズムと、戦い続ける被害者とその弁護士の思いもよく理解できる内容だった。
アカデミー賞作品賞というのは理解しかねるが、アメリカ人(のセレブ)が好きそうな内容だったと思う。まぁアカデミー賞もアメリカの賞レースだから外国人の自分などが文句を言ってもねぇー。
確かに衝撃のスクープだが、そんなことがあったことさえ分からなかったし、今も変わらずカトリックの組織が世の中にはびこっている現実に愕然としてしまう。
全369件中、321~340件目を表示