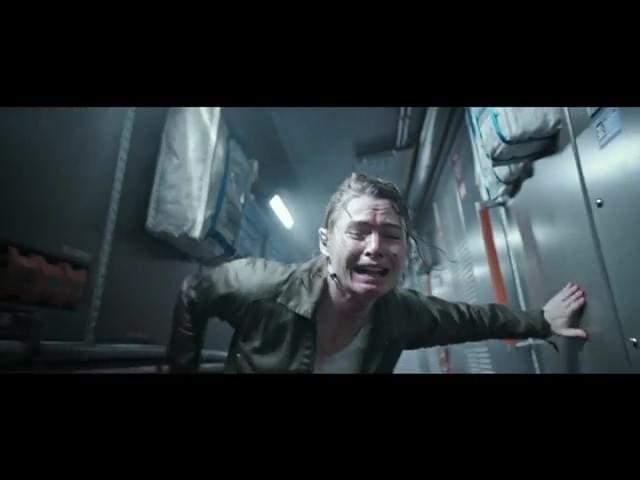エイリアン コヴェナントのレビュー・感想・評価
全351件中、161~180件目を表示
ファンメイドのような味わい
プロメテウスの続編で、エイリアンの誕生談でもある本作。エイリアン第一作を踏襲したのか大量のエイリアンとの大戦ではなく、いち個体との死闘を描く。
その割りには雰囲気がエイリアン2だったなあ…「完璧な生命体」であるエイリアンの完全無欠さが全く表れていない。
まあ、2も好きだからいいんだけど、1のじっとりとした、徐々に追い詰められていく恐怖を観たかったなあ。
モンスターパニック映画としては上々。プロメテウスの続編としてもかなり面白い。それならタイトルはプロメテウス2の方がよかったんでないの?というツッコミはおいといて。
降り立った惑星で未知の生命体に遭遇、訳もわからないまま船員が減っていく様子はエイリアンそのもの。モンスターも気持ち悪さが半端なく、かなりの高得点。モンスターに翻弄されまくる前半は非常に面白い。
ただ、後半プロメテウスとの繋がりが顕になったあたりからは少し雰囲気が違う。いや、毎回こんな感じだったっけ?ずっとモンスターの恐怖に怯えていなかったなあ…エイリアンが船に入り込んだあともあまり危機感を感じなかったし。追跡できすぎてるんだよね、仕方がないけど。
オチは、まあ、よそうできるのではないでしょうか。後半に少し不満があるが、方向性の違いみたいなものなので、充分楽しめた。続編もあるのかな?
後味がすごく悪い
気持ち悪さは健在
プロメテウスを観とけば良かったと後悔…… プロメテウスの続編で、エ...
う〜ん、、、
面白く無いこともなかったけど、やはり1作目は超えられないよね。という話。
プロメテウス観たけどあんまり記憶に残ってなかったせいで、え?こんなんやったっけ??という感じ。
とりあえず、マザーに背くテネシーにもイラっとするやろうけど、嫁もアホ過ぎるやろ‼︎ というツッコミは誰もが抱くハズ。。。
自分達が母艦に帰るためにある調査船で銃乱射て😂キチガイやがなwww
冷静さのカケラもないし飛行士失格やがなwww
とりあえず、終始ファスベンダー氏のドアップ画像が続くせいで胸やけ起こしそうでした(;´Д`A
※マイケル・ファスベンダー氏は嫌いではない
途中挟まる心地いい程のキャサリンの普通さに癒されつつも、あまりしっくりこないまま観賞終了。
結論 : イケメンは長時間ドアップで観賞するものではない。
エイリアンは、旧3部作で終わらせておくのが正解でしたね。
面白かった
プロメテウス?エイリアン?
デイビッドは嘘をつく
結構楽しめました
1から観てるけど、エイリアンを進化させたのアンドロイド?
映画が始まると、アンドロイドと作った人との会話から始まるから、キモはアンドロイドかと思ったらビンゴ。
確かにAIが独自の言語で会話し始めたり、ヒトラーを賛美したりして慌てさせたってあるけど。
人類移住計画で、途中で人間が生きられる星見つけて、そこがエイリアンの巣だった、しかもアンドロイドがエイリアンを進化させていたなんて、途中から話の全てがわかってしまい、金返せと叫びたくなった。
ストーリーがこれからどうなるんだろう?ってワクワク感全くなくて、ラストなんて萎え過ぎる終わり方に。
驚きが全く無い。
アンドロイドは都合よくエイリアンカプセルを作れるんですね(^^)
どうせ、懲りずにまた作るんだろうけど、もういいや。
箸休め的な…
気が滅入る(ToT)
全てが悪い方悪い方へと話が進み、最後も救われないエンディング。「エイリアン」とか「エイリアン2」とかは密閉性の高いパニックと絶望的な展開の末に、娯楽性の高いカタルシスによって作品を楽しむことができた。勿論また続編があるのだろうけど後味が悪い。せめて最後にウォルターも母船にしがみついています的なカットがあったら作品の印象が大きく変わったと思う。いずれにしても作品の主役はウォルターとデイビットだったようだ。
プロメテウス未でしたが
スカートの中まで汗かいてしまい、最後立ち上がるときドキドキでした。すごい怖くて目も当てられないわけでもないのですが、要所要所で力を入れて観てたみたいです。
プロメテウスを観ないで行ったのですが、エイリアンというより、アンドロイドの哀しみ、人間の愚かさみたいなものを感じました。アンドロイドが発達すれば、人間は負けますわねw
しかし、リドリースコットの映画はエイリアンといい、サルの惑星といい、やや人間に気持ちが寄れないとこがあって、自分何なのかと思ってしまいますわ。
エイリアンが誕生するまでの
悪くはないんだけど
悪くはないんだけど、ちょっとこれじゃない感が…
1つ1つのシークエンスは緊迫するし映像も綺麗だし良いのだが、見てる間は常に頭の中に「?」マークが点灯している。
登場人物が多すぎてバタバタ死んでいくので、そのうち馴れてだれてしまうし、主人公が最後にならないと活躍しないので、なおさら少し醒めた目で見てしまう。
何より「プロメテウス」以来の、人類やエイリアンの起源なんて興味ない。
そこに拘った分だけ、このシリーズが純粋なSFホラーから遠のいていく気がする。
また、粉末状で感染できるという、フェイスハガーよりうんと完全に近い有利な形態を出してしまうなど、風呂敷を広げすぎの感がある。この形態からフェイスハガーだと、まるで機能的には退化じゃないか。
アンドロイドがここまで出しゃばるのも、なんだかな感が(笑)
まあ、前作の登場人物が次作では最初から死んでいる、のはもはや定例パターンになった感じではあるけど、そうすると次作も…なんだろうね。
ラストのアレについては、観客の10人中10人がそう思っていたはずで、意外性も驚きもゼロ。
むしろここに至るまで確認しようともしない主人公のマヌケさに開いた口が塞がらないので、この演出はどう見ても失敗だと思う。
次作は原点に戻って欲しいな~
残忍さだけでなくよく練られた映画
全351件中、161~180件目を表示