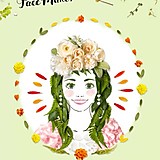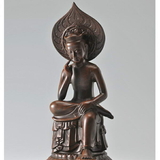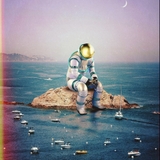映画 聲の形のレビュー・感想・評価
全578件中、61~80件目を表示
Talkin’ ‘bout all generations. これは、新しい青春映画の形。
過去の過ちに苛まれる青年・将也と、酷いいじめを受けていた聾者の少女・硝子。5年ぶりに再会した2人の交流と救済を描いた青春アニメーション。
監督は『けいおん!』シリーズや『たまこまーけっと』シリーズの山田尚子。
小学生時代の将也を演じるのは『桐島、部活やめるってよ』『悪の教典』の松岡茉優。
原作は「週刊少年マガジン」に連載されていた同名漫画らしいのだが、これは未読。
まず一つだけ言わせてくれ!
OPにTHE WHOの「マイ・ジェネレーション」を使うのであれば、EDは「俺達はしないよ(シー・ミー・フィール・ミー)」だろぉ〜〜っ!!
"I hope I die before I get old"というフレーズがあるからマイジェネを採用したのかも知れないけど、この曲だけだと正直映画の内容とはマッチしていない。
オチに「シー・ミー・フィール・ミー」を配置すれば、クソガキ時代から孤独と贖罪の時代、そして苦難を乗り越えた末の救済までの道程をTHE WHOによって表現することが出来たのに…。
ロックンロールファンとして、そこは残念に思います🌀
エンドロールで"See me〜,Feel me〜,Touch me〜,Heal me〜♪"なんて流れたら号泣必至だったね。
と、余談(しかし一番言いたかったこと)はここまでにして。ここから本題。
鑑賞前は「高校生のキラキラ恋愛もの〜?興味ねぇ〜…。しかも障害者を売り物にした感動ポルノっぽいし。なんか絵柄もオタクっぽいし〜。興味ねぇ〜…。」なんて思っていたが、やはり先入観はよくない!
いざ鑑賞してみると、そういう映画では全くなかった。
物語の主題となるのはディスコミュニケーション。
過去の出来事により心を閉ざした青年と、発話でのやりとりをする事が出来ない聾者の少女。
これだけでも十分に物語を膨らませる事ができそうなものなのだが、本作ではここにさらにいじめの加害者/被害者という要素をも盛り込むことによって、観る者の心をぐちゃぐちゃにかき混ぜる一筋縄ではいかないハードなものへと作品を昇華している。
物語は将也の主観に沿って紡がれていく。
そのため、作中で描かれる硝子の人物像は、あくまでも将也を立脚点にして作り上げられたものでしかない。
そのことで観客はついつい油断してしまい、「あぁ、硝子ちゃんって素直で健気な強い女の子なんだな😌」と思い込んでしまう。
観客に硝子を天使の様な少女だと思い込ませる。このミスリードが、中盤の展開の衝撃度を格段に高めている。
硝子の自殺未遂により、将也は自分の考えの甘さを文字通り痛感し、硝子もまた、将也を巻き込んでしまったことを契機にして、本当の意味で他人と向き合うようになる。
最後の最後、クライマックスになって初めて、人と人とが分かり合える可能性のようなものが提示されるという、ただのゲロ甘青春ラブストーリーとは明らかに一線を画す、実にウェルメイドな筋立てである。
本当にこれほどレベルの高い文学的作品が少年マガジンに載ってたの?今の少年漫画って、自分が思っている以上に進んでいるのかも。
原作の単行本は全7巻。本作はその内容を2時間強にまとめたものである。
こういう場合、物語を詰め込みすぎてごちゃごちゃした映画になってしまうか、エピソードをすっ飛ばし過ぎたせいで意味不明なストーリーの映画になってしまうか、このどちらかになりがち。
しかし、本作は長編映画用に書かれたオリジナル脚本と言われても信じてしまいそうなほどに綺麗にまとまっている。
これは、元々の原作の構成が巧みだというのもあるのだろうが、やはり脚本家・吉田玲子さんと山田尚子監督の力が確かだということなんだろう。
吉田玲子さんはアニメファンならその名を知らぬ者はいないベテラン脚本家だが、山田尚子監督と原作者・大今良時先生はいずれも1980年代生まれ。
新たなジェネレーションが確実に業界の中心に踊り出ようとしており、その溢れる若さの脈動にこちらの心まで奮い立ちそうですっ!
…いやしかし、本作の雛形になった読み切り漫画を大今良時先生が執筆したのはなんと19歳の時らしいじゃないですか。マジかよっ💦
これだけの才能を見せつけられたら、自分が同世代の漫画家志望だったら確実に筆を折ってるわね。うーん、紛れもない天才だ。
とまぁ作劇的には絶賛せざるを得ないクオリティだったんですけど、気になるところがないわけではない。
まず、全体のテンポ感が均一すぎる。硝子の自殺未遂シーンをグッと山場にするため、あえてそれまでを平坦にしたのかも知れんけど、ずっーーとリズムがおんなじ感じなので結構退屈してしまった。
橋の上での公開裁判とか、結構あっさりしていて拍子抜け。耳を塞ぎたくなるようなイヤ〜〜な見せ場を期待したのだが…。もっと人間の暗部をドロドロと描いても良かったのでは?
もう一個気になるのは、ところどころに挿入されるザ・ラブコメ漫画的なやり取り。
「スキ」と「月」を聞き間違えたりね。そんな訳あるかい。こういう難聴系すれ違いって、いかにも作り物って感じがして萎えちゃう。
思わせぶりに顔を隠し続ける将也の姉とか、あれになんの意味があんの?お姉さんの旦那さんが黒人だったことをあんなに引っ張って隠し続けた意味は?
心理描写にリアリティを追求した作品であるからこそ、こういう普通のアニメならあまり気にならないような点が無性に気になる。
あと個人的に嫌なのは昏睡状態から目覚めた将也が、管とかを取っ払ってすぐさま硝子に会いにいくとこ。こういうのはアニメにありがちなんだけどすっごく嫌い。怪我を舐めんじゃねえ!『カリオストロ』のルパンだって、ドカ食い&爆睡で怪我を治したんだぞっ!!
こういう細かいところのリアリティラインは、もっと詰めて描いてほしかったなぁ😮💨
まぁ色々書いたけど、一番気になることはやっぱり将也&硝子以外の同級生たちの描き方。
原作ではどうなのか知らないけど、この映画を観ただけだと植野とか川井はただのクズにしかみえない。特に川井!!この…クソメガネは本当にどうしようもねぇな💢
川井の横にいる真柴とかいうニヤケ面も何のためにいるのかよくわかんなかった。
元いじめっ子の島田も、あれだけの出番じゃこいつがなんなのかよくわかんない。
2時間強のランタイムでは、これだけのサブキャラたちを捌くことは不可能。原作を改変してでも、もう少し登場人物は厳選した方が良かったのではないだろうか?
永束と佐原以外の同級生がクズにしか見えないせいで、ハッピーエンド的な終わり方が全然ハッピーに見えない。少なくともあのクソメガネにはグーパンした方が良い👊💥
全て丸く収まりました、的な物語の収束には不満が残るものの、映画としての完成度はやはり高い。
本作の公開年は2016年。この年は新海誠の『君の名は。』、庵野秀明の『シン・ゴジラ』、片渕須直の『この世界の片隅に』といったアニメ(特撮)作品の傑作が公開されているが、本作はこの並びに加えてもなんら遜色のない名作だと思う。やっぱり2016年はアニメ界奇跡の一年だ!
30代前半でこれだけの作品を作り上げた山田尚子監督の才能は素晴らしい✨山田監督の今後の作品にも期待したい。
マイ・ジェネレーションと言わず、オール・ジェネレーションズに鑑賞して貰いたい、新時代の青春映画です!
【”ディスコミュニケーションから、届けコミュニケーションへ・・。”聾唖者への悪戯により疎外された少年の聾唖者への理解の過程を切ない描写を含めて描いた作品。作中の斬新な心理描写が素晴しき作品。】
ー 今作を鑑賞したのは、2018年頃であったかと思う。
作品が発信するメッセージ”友達って何だ”が強く心に響いた。
その後、京都アニメーションを襲った忌まわしき出来事に呆然とし、京都に行った際には自分なりに出来る事をした事を思い出す・・。ー
◆感想
ー 多くの方がレビューを挙げられているので、久方振りに鑑賞した感想のみをシンプルに記す。ー
・主人公の石田が、小学生時代に、引っ越して来た聴覚障碍者の西宮に対する悪戯。だが、彼のみがやっている訳ではないのに、いつの間にか、彼が一人で責任を負う姿。
だが、彼はその罪を一人被る。
ー これは、今でも年代を問わず行われている事ではないか・・。だが、石田は西宮を苛めているようであるが、彼女を大切に思っているシーンが随所で描かれている。濡れたノート・・。-
・中学時代の石田は暗黒の生活を送る。一人も友達が居ない日々の生活・・。
西宮を苛めた故の自身の境遇を甘受する姿は、初見時にはやや苛立ったモノである。
苛めに加担していた生徒達の言い逃れする姿。
ー これは、現代でもあるのではないか・・。-
■この作品の価値を高めているのは、石田とディスコミュニケーション状態にある生徒たちの顔に”×”が付いている描写であろう。
そんな中、ナガツカが彼の友となり、”×”が消え去る描写。
そして、高校に進学した石田の境遇は余り変わらないが、徐々に”×”の数が少なくなっていく。
石田は、自らが過去に犯した(と言っても、小学生である。)過ちを悔い、西宮とコミュニケーションを取るために手話を密やかに学ぶ姿。
彼が、人としてキチンとした人物になっている事が、容易に伺える。
・高校になって、久しぶりに出会った石田と西宮。彼らはぎこちないながらも再び関係性を築いていく。だが、自分の存在が石田を傷つけていると勘違いした西宮の哀しき行動。
ー 美しい花火大会を、石田と一緒に観た西宮は”自分の想いが聾唖者故、伝わらなかった事で・・。
”好きと月・・。”
命を断とうと思ったのであろう。
だが、それをいち早く察した石田の身を呈して、西宮を助けようとした崇高な姿。ー
・そして、学校に復帰した石田の学友たちの顔から、”×”が次々に落ちて行くシーンは、可なり沁みる。
<初見時に、”こんなにすごいアニメーション映画を作る集団って、どんな人たちなんだ!”と思い、その後「リズと青い鳥」「ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン」を見て、その感を強くした。
哀しすぎる出来事の後、京都に行った際に陰ながらお参りをした。
だが、この素晴らしき映画製作会社は、亡き人たちの想いを込めて、素晴らしき映画を届けてくれる筈、と信じている遅れてきた京都アニメーションの作品に魅了された男の一人ごとである。>
人が人である限り、健常者、障がい者問わず他者を理解するのは難しい
オープニングがとてもカッコよく
一気に引き込まれました
そして
エンディングのaikoさんの歌まで
あっという間に時間が過ぎました
本作品
西宮さん以外の健常者がたくさん出てきますが
皆それぞれが衝突し合います
健常者同士でもコミュニケーションが難しいのに
ましてや障がい者となると
接し方が難しいのは必然…
実生活でも
障がい者だから優しくしてあげるべきなのか
障がい者だけど健常者と同等に接してあげるべきなのか
考えさせられる場面たくさんあります
やはり
その人の障がいの有無は関係なく
人が人である限り個性は十人十色であり
その人に合わせた対応の仕方が求められるのではないか…
この映画はその感覚を見事に映画化してくれてる作品と感じました
心を抉る。とにかく「生々しい」
公開からしばらく、強烈に賛否両論があったと記憶しています。
特に「(いじめ)加害者を美化してる」といったマイナス批評が多く目に付きましたが、トラウマを喚起されてしまった当事者でないならば、表層的でもったいない見方だと思います。
物語の軸は、完全に硝子と将也の関係性に置かれています。
一見主題にも思える「いじめ問題」や「聴覚障害」は全く主題ではなく、大きめの舞台装置に過ぎません。
この作品が描く主題は、「人間の不完全さ」「コミュニケーションの難しさ」だと思います。
登場人物が全て見事に欠点を晒していて、通常のドラマ作品には必要ないまでに「脚色され尽くした生々しさ」があります。
虚勢から手痛い失敗をする繊細な小心者。
真っ直ぐ過ぎる故、不器用に周囲を傷つける者。
強烈な自己愛と、自覚すらない歪んだ邪悪。
未熟で無責任な教職者…
遠慮なく言ってしまえば、「○○性人格障害」のテンプレートのような登場人物の群像劇に仕上がっている。
そういった不快感が漂う世界観と相関関係の中で、硝子と将也の関係性が絶妙に付いては離れてはで転がる。
不完全な人たちの不完全なコミュニケーションは少しずつ噛み合い、最後には小さな希望を感じさせながら、深い余韻が残る。
「重苦しい恋愛映画」のようでもあって、やはりそうではない。
「こんな関係もある」という、そんな一例を描いた作品だと思います。
心理をゲームや記号などの独特の映像で表現したり、硝子視点での聾唖者の音のこもる表現など、京都アニメーションが放つ圧倒的なクオリティも最大のポイントです。
最高のアニメーション映画
非常に静かな映画
誰かの心の傷を理解しようとする姿勢を説く作品。
アニメだからこそ、誰が見ても伝わる形で可視化され、内容の重さを受け止められる作品。
アニメだと、ファンタジー要素が入りメッセージ性は明確でという作品が多い中で、とてもリアルで、見た人に多角的に考えさせる作品。必ず見た方が良い作品だと思った。
いじめがテーマでもあるが、それ以上に、誰しも何かしら抱える心の傷を、関わる物が理解しようと向き合う時の難しさが伝わってきた。
公立の普通学級に、補聴器で少し声が聴こえるくらいの女の子、西宮しょうこが転校してきたところから展開していく。しょうこは筆談か、一生懸命話すぎこちない発話か、手話がコミュニケーション手段だが、小6の子供達にとって、しょうこの会話手段を読み取るのは難しく、どう思っているのか感じ取るのは更に難しい。
最初はサポートしてくれていたクラスメイトの植野も、しょうこによりクラスメイト同士の関係性が変わっていくことを恨めしく思ってしまう。
更には、小6男子の年ごろゆえ、気になる女の子の気を引くために嫌がることをしてしまう石田将也は、本心はしょうこともっと話したいだけなのに関わり方がわからず、大切な補聴器がどれだけ高価かもわからず何度も投げたり、怪我をさせたり暴言を吐いたり、いわゆるいじめの行いをしてしまう。
植野は元々仲が良かった佐原さんも石田もしょうこに取られた気がしてしまい、しょうこに冷たくあたり、しょうこと仲良くなろうとした佐原さんは植野にからかわれるようになり、転校。
担任の先生が石田を首謀者として名指しし、石田はかえっていじめられる側となり、学級のバランスは崩れたまま小学校は終了。それぞれ高校生となる。
高校にあがっても孤立している石田は、過去の後悔と罪悪感に苛まれ、手話を習っていると偶然しょうこに遭遇。しょうこの希望で佐原さんにも再会し、学校でも輪に入れぬ者同士親しくなれたりして、偶然植野にも遭遇。再び新たな人間関係が出来上がってきたところで、小学校も高校も石田と同じ、川井さんが口を開く。元々石田くんはいじめをしていたんだよ、と。しかも、川井さんはおそらく高校の同級生の真柴くんを好きで、真柴くんの前でよく振る舞うためにも、ことさらに私は悪くないと高校の同級生たちの前で大きな声で主張する。
築いた新たな交友関係でも再び浮く石田。
物語を追っていけば、石田にしょうこへの嫌悪感や強い悪意があったわけではないのがわかるが、やっていたことはいじめ。
川井さんが悪口も言わず、主張の強い植野を嗜めたり、しょうこにも優しくしてきたのは事実で、いじめっこと一緒にされたくない気持ちや石田を嫌な気持ちが消えずにいるのは仕方がない。
しょうこ本人は、耳のハンディに甘んじず、声でも伝えようとずっとしていて、それがなかなか伝わらず、進展しない人間関係に密かに孤独を深めていく。
周りはしょうこの本心を知りたいが、本人はどんな嫌なことをされても、自分の会話手段のせいだと思っているため、本気ですぐに謝るし、その癖がついている。
物語が進む中で、しょうこの耳の症状も進んでいく。片耳は聴力を失ったようで、補聴器をする必要もなくなる。
成長して人間関係が開けてきて、恋もし、一番楽しいはずのタイミングで選ぼうとした、自死。
「私といると不幸になる」この思考が染み付いてしまっているから。そのきっかけはもしかしたら小6の時のいじめの影響も大きいのかもしれない。石田と再会した瞬間、逃げ出したことからも、当時を良い思い出としていないのは確かだが、手話を学んで態度を改めた石田に驚き、石田を好きにさえなることができていたのに。
元々石田は、やっていることは最悪だが、本音でしょうこと接していたことをしょうこ自身もわかっていたからこそ、小6当時に取っ組み合いの喧嘩をしたこともあったし、再会後に好きとも思えたのかもしれない。
でも、幸せを感じるほどに、関わる人間を幸せのままにしたいがゆえ、自分の存在が害だと感じるのだろう。
わだかまりを抱えたまま成長してきた登場人物達が、小6当時はそれぞれが自身のどういう感情ゆえそういう態度だったか無自覚だったのかもしれないが、高校生になると、それぞれの当時の心境を吐露しはじめる。全員正直な気持ちを述べていて、見るものにより賛否はあれど、誰が間違っているというのはないのかもしれない。
これがこの作品のポイントだと思う。
加害者側被害者側とはっきり分かれている作品は沢山あるが、後から振り返る形でそれぞれに視点があたっていることで、考えさせられる。
では、しょうことどのように関われば良かったのか。
物語に登場すらしない、クラスで遠巻きに見ていた者達なら、しょうこと親しくもならないが、問題にはならなかっただろう。
川井さんは小6当時も高校生になっても誰に対しても優しい態度だが、しょうこを深く知ることはできていないし、石田の指摘の通り自分が責められたり傷ついたりしない予防策なだけなのかもしれない。
しょうこの本心を知ろうとした、石田や植野は、会話手段をしょうこに合わせることなく、自分が楽な健常者の口頭での会話で接したため、しょうことの会話を読み取れないことにやきもき、イライラを感じ、やりすぎてしまう。しょうこの意見を聞きたかっただけなのに。
しょうこを知ろうと手話にも興味を示した佐原さんは、成長後もしょうこを気にかけていたが、立場が危うくなると自分を守るため逃げるしかなくなった。
それぞれの関わり方こそ個性であり、成長してもまだ思春期の彼らはそれぞれに思うところがあり、どれが正解というものでもない。だからこそ難しい。
妹の結弦は、自身の生活ほったらかしでしょうこと常に一緒にいて、しょうこの気持ちをよく理解しているが、それでも、目の前にしょうこがいてもメールを使ったりもしている。
例え全員が健常者でも、誰かが日本語話者でなくても、価値観はバラバラで、同様にそれぞれの気持ちの交錯は起こるのだろう。でも、共通の会話手段を持つ重要性をひしひしと感じる。
しょうこ自身は、声で伝えられればと切に願い、思うようには発音が難しくても恥を捨てて話そうとしている。
周りもしょうこを知りたければ、手段を持たなければ。
手話が、聲の形となるのかもしれない。
石田もしょうこもニックネームはしょうちゃんで、元々通じ合いそうで通じ合わないギリギリの関係性がずっと続くところがもどかしい。
「ともだち」「これでもがんばってる」「すき」都度全力でしょうこは伝えているが、なかなか伝わらず、しょうこに死にたいとまで感じさせた石田が、今度は自殺を考えるまで追い込まれて、お互いに人を大切に想う気持ちを知っていく。
しょうこの母親から見たら、何度もしつこく接触をはかってくるいじめっ子そのものであり、他人には理解し難い関係性。
しょうこの母親はしょうこを守るため強く生きてきたのだろう、言葉の強さと裏腹に、明らかに心身とも疲れている。妹もしょうこに付きっきりだが、おそらく性同一性障害を抱えている。そんな家族をありのまま受け入れ温かく接する祖母いとの死。
しょうこが死にたいと思わないように、動物の遺体の写真を見つけては撮り壁に貼っていた妹の結弦の努力も虚しく、しょうこは死を選ぼうとする。
気持ちは本当によくわかる。いても誰かに嫌な思いをさせたりし、いなくなることすら、周りを悲しませるとしたら、もうどうしたら良いのか。
「誰だってそうでしょ」という川井さんの言葉が響く。
生きていて人に迷惑をかけない人などいないのだから、できる限り自分の事は自分でした上で、少し厚かましく、助けが必要なら声をあげ頼り、感謝して生きる。そのかわり、困っている人がいたら全力で助ける。
人間関係で好き嫌いが出てきてしまうのは仕方ないが、誰しも自分より内面ですぐれた部分を持っているもの。そこに目を向けて取り入れれば、そんなに腹は立たない。
個人的には、担任の先生の対応は最悪だと思うし、お世話する感覚でしょうこを見る川井の他人行儀な丁寧さも、植野の身勝手な思考回路も苦手である。
石田が程度をわきまえて素直に接していたら、とても良い結果になったのではないか。
そのために5ヶ月も放置せず早いうちに担任が動けていたら。佐原を守れていたら。そう感じさせられる。
それを体現するかのように、石田と高校生になってから友達になった永束くんの存在がある。過去を知っているわけではないが、大切な友達を信じて、見捨てない。
「ともだち」ってなんなんだろう。
心を開けるだけでなく、例え違う意見でも、対等に声をあげ合えること。助け合おうとできること。
そうある難しさがリアルに描かれている。
石田が過去の過ちの重さを身をもって深く理解し、10年越しに当時の関係者に謝罪するまでに至る難しさ、一度してしまったことを真剣に反省すればするほど、自身を許す難しさ、周りから許される難しさも描かれている。
作中、重々しい内容に刺激をつけるためなのか、わざと女の子の下着が見えそうだったり、ひさびさに会ってすぐに胸のサイズの話をしたり、女性の監督でありながら不快な描写も多い。こういうやり方でしか、男性は真剣な内容の作品を見られないと思われているのだとしたら、それも一種の差別だなと感じた。
作中の一筋の希望は、石田の母。
自業自得な石田以上に、悲しく辛い思いをしたのはしょうこの周りを除けば石田の母だろう。常に優しく気丈に振る舞うが、大切な息子が、他のおうちの大切な娘を傷つけてしまった悲しみはいかばかりかと思う。石田がしょうこの自死を防ぎ、石田自身が死の淵を彷徨ったことでやっと、しょうこの母から会話して貰える存在になった。そして、立場ゆえ孤立しがちなしょうこの母の髪を切ったり、息抜きの場、話し相手となることができそうだし、おそらくひとり親で、娘の結婚相手も外国人だったりと、多様性への理解がある。今後もしも石田としょうこの関係性が進んだとしても、きっと大丈夫だろう。そう思わせてくれる存在。
心の声が聞こえる
×点さん、ごめんなさい
「しょうこ」と打つと一発で変換できないので「ガラス」と打ちながら、硝子の心の奥底を感じ取ろうと努力してみました。だけど、やっぱり将也の心の方が痛いほど伝わってくる。高3で心を解き放ったのは本当に良かった。
いじめっ子が逆に孤立していじめられる側になるのはよくあること。周囲の子どもたちだって、良くないことだとわかりながらも同調してしまう社会の構図。子どもは大人の鏡とはよく言ったもので、成長する彼らの変化が面白いほどに胸に突き刺さってくる作品でした。
誰が悪い、誰が嫌い・・・そんな気持ちを払拭させてくれる高校時代。闇を抱えて一人悩むよりも人と話し合ったほうがいいに決まってる。素直にならなければ老人になるまでずっとしこりとなって残るはずだ。ろうあ者を中心に添えた設定も、心がうまく伝えられないもどかしさをも端的に表すことのモチーフだろう。
自分の気持ちが伝わった瞬間。至高の喜び。“ともだち”になったと思えるときなど、幼き頃を思い出しても世界が変わったひとときだった気がします。というか、この映画がそうだったんだよと教えてくれたのかもしれません。
登場人物のそれぞれの性格が見事に描かれ、嫌な奴だと思っていても次第に優しさがにじみ出てくるストーリー。みんな人付き合いが苦手なんだよ!声が届いた瞬間は絶妙だったし、心が伝わったことに涙した。あぁ、高校時代に戻りたい・・・
人と・自分と向き合うという事
原作未読です。中高生向けのアニメかと思って軽い気持ちで観ていたのですが、泣けました。こんなに感動するとは思っていませんでした。
人の心ってこんなにも柔らかくて繊細で、危うくて残酷でもあるのだなと改めて思いました。
小学生の硝子が将也に馬乗りになって掴みかかり喚く場面が印象的でした。何をされても静かに笑ったり、自分は悪くないのにごめんねと謝るばかりだった硝子が、ある意味初めて自分の感情を人にぶつけた瞬間だと思いました。
将也に酷い事をされても‘友達だよ’と伝えていたのは硝子が将也の中にある優しさを感じ取っていたからだと思います。だから周囲から孤立し、いじめられても何もしないでいる将也を見ているのが辛かったし悔しかったし、自分の姿と重なるようでもあり、腹が立ったのかなと思いました。
‘周りの人を不幸にしている’、‘自分が嫌い’。命まで絶とうとした硝子の気持ちを簡単にわかるとは言えませんが、重みは伝わってきます。硝子の心はまだ癒えていませんが、将也と共にこれから時間をかけてゆっくりと前に進んでいくのだと思います。
ラスト、文化祭で将也が大粒の涙を流す場面も感動しました。
やんちゃ坊主だった将也が、一瞬で周囲から孤立するあの感じ、怖かったです。子供だからすぐに仲直りするという事も無く、それはその後の中学高校生活でもずっと続きます。
‘自分への罰なのだ’と将也はそれを受け入れますが、周囲の目に常に怯えています。
心を閉ざす事でしか自分も守れなくなった将也。それは辛すぎます。命を絶とうとする前に硝子に会いに行きますが、彼女との再会がきっかけで、彼の心の中で何かが動き始めます。自ら人と関わり、少しずつ向き合えるようになっていきます。でも、上手くいかなくなるとまたすぐに心を閉ざします。まだ完全には心を開けていない将也ですが、ベランダから落ちていく硝子の手を掴んだ時、彼は自分が今まで心を閉ざす事で色々な事から逃げていた事に気付きました。
文化祭の人混みの中で涙を流す将也。自分の殻から完全に外に出て一歩を踏み出した瞬間の喜び・不安・勇気、、、色々な感情が伝わってきて感動しました。
親の視点から見た
全578件中、61~80件目を表示