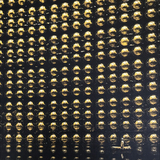マネー・ショート 華麗なる大逆転のレビュー・感想・評価
全321件中、41~60件目を表示
重すぎて、華麗なる大逆転とは…
厄介なのは知らないことじゃない。
知らないのに知ってると思い込むことだ。
マーク・トウェイン
リーマンショック、知ってるけど、理屈を理解してない。
映画の内容の専門用語、聞いた事あるけど、詳しくは知らない。
そんな感じ。
とりあえず無知な自分は搾取されてるんだなぁ、と。
今作の主要人物の成功は、自分を含む情弱無知な持たざる大衆の不幸。
それを理解しつつ、喜ぶ者、苦悩する者。
悪しき仕組みを作り上げてる元凶にはダメージが無い。
リーマンショックの影響を喰らって無い(と思ってるけど…)、自分でさえも重過ぎて、「華麗なる大逆転」って副題のセンス…
そして、主要人物にビッグネーム揃えてたけど、内容的にはアンビリの再現ドラマで充分だったなぁ。
巨悪に対する告発状
アメリカの住宅ローンの仕組みとデリバティブ(金融派生)商品のオプション取引を多少とも知らないと理解が難しい作品。
本作品に対する評価は
①取り上げたテーマは良かった。
事実に基づいていてもいなくてもリーマンショックの裏側を扱った映画は皆無なのだから。
②邦題は完全に的外れ。
原題は"The Big Short" 直訳すれば”大いなる空売り”
日本語で”マネーがショート”と言えば資金が不足することを指す。
ましてやサブタイトルの”華麗なる大逆転”は完全にチョンボ。
まったく”華麗”ではないのだから。
③余計なシーンが散見される。
マイケルの少年時代のフットボールの場面、マークの少年時代にユダヤ教のレビが訪問するシーン、ジャレッドが劇中でストーリーを解説する場面など。
後のストーリー展開にさほど意味をなさないものが多い。
これでアカデミー脚色賞?
そんな無駄なシーンを探すのも楽しみの1つとは言えるけど。
④クリスチャン・ベールとスティーブ・カレルは熱演していたけど、ライアン・ゴズリングはイマイチ。
”スーパーチューズデー”でもそうなのだけど、彼は・・・・ (個人的な好みかも)
⑤これだけ世界的な恐慌を引き起こした関係者が誰も訴追されなかったことをもっと怒りを込めて訴えて欲しかった。
リーマン・ブラザーズ経営陣だけではなく、SEC(証券取引委員会)、FRB(連邦準備制度理事会)議長、格付け会社(ムーディーズ、S&P社)トップ など。
アメリカでは横領、脱税などの不正だけではなく、企業を倒産させた経営者が訴追、収監されることはよくある。ましてや今回のサブプライムローンに端を発した世界恐慌は犯罪そのものである。
リーマン・ブラザーズ以上にMBS、CDOを発行していたAIGをアメリカ政府は(世界的な影響が大きすぎて)救済したので彼らを訴追出来なかったのか。
非常に勉強になった
もう10年程前になるリーマンショック
その裏にいた実在の人物達の2005年3月からリーマンショックまでの実際の物語です
リーマンショックはまさにアメリカで起きた壮大なマネーゲームだったのだと分りやすく、一般人からの目線を交えてで作られているので、あの時にアメリカで起きた事の裏側がとてもよ〜くわかりました
合成CDO等のわかり易い例え話等もかなかなか笑えますよね
正確には、もう一度みないとCDSの空売りで利益の出る仕組みについて完全には理解出来てないですが、、
最終的に弱者が泣きをみるだけという現実
そして格付け会社の話あたりは今でも、あのスタイルのままなのか?とか気になりますよね
最初は日本語吹き替えで観たのですがマイケルとローレンスおじさんの関係の説明がないので、マイケルが社長なのかローレンスの会社の社員なのかがわからないのが困りました
2回観て出資者だと気づきました
家だと一生懸命観ないのでだめですね
それにしてもホントに色々とっても非常に勉強になる映画でした
2021年自宅鑑賞10
大逆転とタイトルにあるが、あまり爽快感はなく後味の悪い本作品。専門...
AI企業の減価償却会計に疑念を示し、再び空売りに動き出したことで話...
AI企業の減価償却会計に疑念を示し、再び空売りに動き出したことで話題の “世紀の空売り王”マイケル・バーリ。
その実在の天才投資家が、2007–2008年のサブプライム崩壊を唯一正確に予測し、巨大金融システムに挑んだ実話を描いた作品。
金融用語・デリバティブ・MBS・CDOなど、難しいテーマをポップに、そして痛烈に描ききっているのが本作のすごさ。
投資の本質、リスク管理、群集心理の怖さ、そして“市場は合理性ではなく愚かさで崩壊する”という現実が詰まっている。
株式投資をしている人は、全員観るべき作品。
投資の怖さと本質がエンタメとして一気に理解できる。
投資家としての視点があるほど、
痛みと興奮がリアルに刺さる一本。
一般人には見抜けないよ、あんなトリック…
世の中には頭のいい人たちがいたもんだ(つまり、途中細かいところ理解できなかった)。
小難しいんだけど、それを軽快なタッチで、途中にうまい解説混ぜつつ、よくここまで描き切った!
世の中の常識(たいてい大した根拠はない)を無視して自分の頭を信じられるか。
経済ゲームを制して手にする大金は善か悪か。
喉元過ぎれば~的に、あのサブプライムローン問題を引き起こしたのと同じような商品がまた売り出されているという最後の指摘にもぐっと来た。
Covid-19 状況下で
削らなくても良かったシーン
金融知識がなくても教訓を得られる
転職考えてる人は見るといいよ。
リーマンショックを予見して一儲けしようと人生大1番のかけに出た男たちの話。
.
この映画の一番最初に「厄介なのは知らないけとではなく、知らないことを知ってると思い込むことだ」ってでくるから、劇中、サブプライムローンとか当時の住宅ローンの仕組み金融用語をすごく丁寧に説明してくれる。
.
だからなんとなくは分かるんだけど、ただそのわかりやすく説明してくれてるユーモアがアメリカ的すぎて逆にわからないとこもあったり(笑)特にお前と俺を足せばチェリーになるけどお前だけだとサンデーのままだみたいなところはマジで訳が分からなかった(笑).
.
当たり前に安全だと思っていることを疑って、ちゃんと自分の目で耳で確かめて行動を起こす、それって転職に似てるなと思った。
.
この映画の良いところは、ちゃんと自分で確信を持てるまで調べあげること(人生をかけた大1番に挑もうとしてるんだから当たり前ではあるけど)。誰かの言うことだけじゃなくて自分で見極めて自分の未来を切り開くことが大事だと。
経済というたわごと
リーマンショックのことは知らない。
が、わたしは世界経済の趨勢について、誠実なひとたちが誠実に運用している──と思ったことはない。
不誠実なひとたちが不誠実にやっているのだろうと思っている。新自由主義のミルトンフリードマンがノーベル賞とるくらいだから根本的にデタラメなもの──だとは思っている。このばあいデタラメとは富者の味方である──という意味だ。いまさら、そんなことを驚きはしない。
ただ、リーマンのとき感じた格付け会社の不誠実さってのは、度肝をぬくものだった。
わたしは大卒でもなくホワイトカラーの仕事もやったことがない。ずっと労働者でやってきたので、事務系職というものが、なにをしているのか、想像がつかない。ほどの世間知らずである。
しかし、この恐慌があったとき思ったのは格付け会社というものの存在意義である。格付け会社とは、会社の財政の健全度を、評価する会社だと思われる。すると、かれらは、何百、何千、何万人の職員がいるのか知らないが、日夜、会社の格を調査したり算定したり推量したり再評定したり、している──はずである。実地調査と議論とコンピュータが、日夜AかAAかBかBBか、について格闘している──はずである。
であるなら、格付け会社は、無教養なわたしが順当にかんがえても、暴落やデフォルトのバロメーターとして機能しなければならない。
ところがどうだろう。
とんでもない不誠実さに加えてとんでもない不透明さ。
そもそも付した格の根拠を説明できない格付けとはなんなのか。飲食店に、A定食やAA定食やB定食やBB定食があって、なんですかとたずねたらわかりませんと言われてしまった──みたいなもんである。
おそらくあの巨大なビルには、AやBやAAやBBなどが記された円形の的があって、それをぐるぐると回転させているところへ、職員たちが矢を射て、会社のAやBを決めている──としても、不思議はない。
それがビジネスとしてなりたち、巨大企業として存在するという不思議さは、労働者にはとうてい理解不能である。だいたい、会社や債券の格を付けて、どうやってお金を稼いでいるのか、かいもく検討もつかない。
しかもリーマンで格の信憑性を追及されると、格はあくまで主観的な意見ですから──と言って逃げたわけである。食中毒をおこした飲食店が、食べたのはあんたの判断でしょ──と言ってるようなもんである。
ひとは大きなお金を動かしていると感覚が麻痺する。ゆえに、ウォール街周辺のひとびとは、概して感覚の変調があるだろう──とは思う。ただしこの映画でサブプライムローンのからくりを見抜いた複数の主人公らは、意外に庶民的に感じられた。とりわけスティーヴカレルの演じたキャラクターはずっと怒っている。しごくまっとうな反応だと思った。
演出は編集に尽きる。中心人物を変えるとき、場面転換するとき、回想するとき、おびただしいカット割りを挿入する。しかも見たこともないほど早く割る。そこに使われているすさまじい量の情景やイメージ。
仕掛けは主にふたつ。登場人物がカメラ目線で観衆に話しかけること、金融プロパーではない有名人が概説すること。いずれも群像劇のさなかにスルリと移行する。思い切った演出だが違和感はなく面白い。
再現性が高いドラマとドキュメンタリーのように腰の据わらないカメラと厖大なイメージ。ぐいぐい引き込まれてあっという間に終わる。
生々し過ぎて...悲しい
金融商品は数理的・技術的に構築され、表面上見えない複雑さの中で均衡を保つ。その均衡はピサの斜塔のようでもある。保たれるはずが、我慢できなくなると。そして、年金や自己資金で将来設計をした市民が一番の被害者。近過去の出来事で生々しく悪夢を見るようだ。
そんな下でも、勝ち組はいる。映画はそんな人たちを中心に小気味よく展開されるが、結果が分かっているだけに、悲しくなってきて見ていられない。
万人受けはしないと思うが、すごい出来映えでした。
レストランのオヒョウと、ベガスのブラックジャック勝負が一番わかりやすい。
アメリカの金融業界のシステムが難しいのですが、例え話が最も伝わってくる。4人の男たちの焦りもひしひし伝わってくるのですが、最後にはこの世は詐欺で出来ているという痛烈な言葉が響いてくる。
クリスチャン・ベール。義眼でヘビメタを愛する孤高の投資家マイケル・ベーリ。いち早く「空売り」にて予見していたようだが、空売りの担保も増えてきて瀬戸際に立たされる。株価大暴落が起きなければ真っ先に破綻してた男なのだろう。
スティーブ・カレル演ずるマーク・バウムは顧客のことも考えるが、批判精神も旺盛。講演会にて質問攻めにするところは胸がすく思いになりました。その他ライアン・ゴズリングもブラッド・ピットも粛々とした雰囲気がとても良かった。
MBS(モーゲージ債)、CDOとCDSなど勉強させてもらった(多分すぐ忘れる)が、70年代における銀行家が住宅ローンの固定金利をまとめて証券化してしまったことが発端。資本主義を違ったものに変えてしまったのだ。
昔の麻雀劇画の中に「ほっかいどー」というのがありましたけど、4人の面子が麻雀してる後ろで誰が勝つか賭けるというもの。この映画のベガスシーンがそのまんまでした。会社の業績を中心に予測して株を買うとか、そんなのは古典に過ぎなかったのですね。最も腹立たしいのが格付け会社で、90%が安定のAAAにするというほぼ詐欺みたいなことを平気でやっていたことだ。日本においても、このコロナ禍で国民の年金が使われ操作されてることが今後どのような結果になるのか心配だ。もはや短期的運用ではないのだから・・・
リーマンショックの全貌をシリアス、コミカルに描いたのは評価されるべきですが、過去のことなんだと満足するだけでなく、未来のことまで考えるよう警鐘を鳴らしている作品だと思います。最後に、マーゴット・ロビーをもっと見たかった・・・
ある程度の投資の知識は必須
私はよく映画レビュー語る時には「事前知識の有無」を言うんです。何故なら事前知識の有無は映画の評価に大きく関わると思うからです。ただし、この映画を語る場合は「投資の知識」についても語る必要があると思います。
株式投資などについての知識がないと分からない場面が多々あったので、それが分かるかどうかで面白さが変わると思います。実際、「難しくて分からない」というレビューも多く見掛けます。
私は3年前から投資を行っていてある程度投資の知識があると自負しておりましたが、それでも分かりにくい場面がいくつかありました。
でも、「分からない」で終わらせてしまうのは勿体ない魅力がこの映画にはあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
サブプライムローン問題を発端とするリーマンショックを予見し、アメリカ経済の破綻に賭けた4人の男たちの物語。住宅バブル崩壊を予見し、周りの反対を押し切りながらもCDS(クレジットデフォルトスワップ)によって一世一代の賭けに挑む。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
難しい金融用語やサブプライムローン問題に関する用語が特に説明も無くポンポン出てくるので、ある程度知識があることは前提になっています。日本以上にアメリカ本土での影響の大きい問題でしたので、アメリカのニュースとかで大きく取り上げられていたでしょうし、だからこその知識があること前提の構成なんだと思います。金融やリーマンショックに関する知識がある人なら良いのですが、知らない人からすると完全に置いてけぼりのストーリー構成です。
「CDS(クレジットデフォルトスワップ)」とか「モーゲージ」とか「サブプライムローン」とか、「S&P(実在する会社名)」「ムーディーズ(実在する会社名)」「ゴールドマンサックス(実在する会社名)」とか、何の説明も無くポンポン出てきます。企業名に関してはアメリカでは有名な超大手企業なので知っている人も多いでしょうが、投資用語に関しては大抵の人は分からないんじゃないかと・・・。一応申し訳程度に解説が挟まりますが、イマイチ分かりづらい例え話で説明されるので、やっぱりある程度の事前知識が無いと完全には理解できません。
また、「華麗なる大逆転」とかいう日本映画界の悪習ともいえる糞みたいな副題を付けてしまったせいで、「爽快な一発逆転劇」をイメージして鑑賞してしまった人からは概ね不評なのがレビュー見れば伝わってきます。世紀の空売りによって大博打を仕掛けた4人の登場人物たちですが、彼ら博打に勝つことはつまりアメリカ経済の破綻を意味します。自分たちが大金を手に入れたとしても心から喜べない社会状況なので、大逆転による爽快感は一切感じられません。そこがこの作品の魅力であると私個人は思っていますが、「華麗なる大逆転」を期待していた人にとっては「期待はずれ」と言わざるを得ないでしょう。
リーマンショックのあらましを理解した上で観ると本当に面白いので、面倒かもしれませんがリーマンショックについて軽く調べてから鑑賞することをオススメします。絶対に値下がりしない安全な投資先として誰もが疑わなかったアメリカの土地信仰・顧客を食い物にして私腹を肥やしていた悪徳銀行員たち・競合他社に仕事を奪われまいと本来の機能を失い形骸化した格付け会社。アメリカ経済の破綻を予見し、アメリカ金融界の闇と戦った熱い男たちの物語です。
全321件中、41~60件目を表示